西沢橋梁は終わりじゃなかった
到達! 西沢橋梁

三富村が設置した「通行不能」の看板を過ぎてすぐ、ここまで我々を誘ってくれたレールが谷底へと落ちるように消えていった。
そのまま、主を失った軌道敷きは真っ直ぐ続いていたが、それもいくらも続かない。
「通行不能」を真とする、ここまでで最悪レベルの崩壊地が目の前に現れた。
岩だらけの川原へと、万一足を滑らせたならば必ず墜落することになる。
現実離れしない高度感が、むしろ墜落の傷みをリアルに想像させ、余計恐かった。
こんな崩壊地が長く続くなら、どこかで見切りをつけ、一度川原に降りて軌道跡を迂回しつつ下から追跡する方が良いと思ったが、その提案が口にされることは遂に無かった。
先に終わりが来たのだ。
それは、唐突だった。

12:37 【現在地:西沢橋梁 東詰】
断続的な平場を拾い集め、どうにかこうにか進んでいた我々のつま先に、今度こそ迂回不可能、正対するようにして西沢の本流が現れた。
残念ながら、そこにあった筈の橋は跡形もなくなっていた。
足元や対岸に有ってしかるべき橋台も、その存在を感じない。
全て流出してしまったのか…。
だが、地形的に見て、ここが渡河地点でないとは考えられない。
車を出発して5時間半。軌道跡に出会ってからも2km強を3時間かけて歩いた。
……これが、我々の目指した地である。
これで終宴 … か。

地形図によれば、西沢橋梁の対岸には車道の林道が来ているようだ。
実は、その林道も西沢林鉄の跡を利用していると思われるのだが、今日は時間的に考えて、林道との出会いを確かめたら撤収だ。
もし先ほどの時点で、対岸に明らかに林道が見て取れたなら、橋詰めにて引き返しても良かったが、思ったよりも谷が広いこともあって目視出来なかった。
それに、せっかくここまで来たのに、ただ橋が落ちていることを確かめて帰るだけというのは、ちょっと悔しい。
我々は、当初の目的地だった橋詰めでは一服もせず、すぐに立て札の辺りまで軌道跡を戻ると、橋のない西沢を渡ってこの目で林道を確かめるべく、川原へと降りた。


適当な斜面を見付けると、今回の探索では初めて軌道敷きを離れて西沢へ降りた。
左の写真は、一番上の写真で見下ろしていた川原で、墜落してきたレールが一本に繋がったまま、まるでそこに敷かれていたかのようにあった。
驚いたのは右の写真の標識で、川原に生える立木に取り付けられていた。
我々は別に踏み跡をなぞった憶えはなかったのだが、どうやら登山道として利用されていた時期のものらしい。
前回紹介した小屋の中の落書きを踏まえれば、昭和61年頃までは盛んに人が訪れていたのだろうか。
いずれにしても、当時から橋は既に渡れなかったのだろう。


落ちたレールに従って川原を進んでいくと、やはり先ほど我々が撤退した崖下に出た。
左の写真は、分かりにくいと思うが、先ほど引き返した地点を見上げている。(画像にカーソルを合わせるとガイドが表示される)
ただの岩場みたいだが、以前はここから大きな橋が対岸へ架かっていたはずだ。橋台が見あたらないのは、岩盤を代用していたのだろう。それにしても杭打ちの孔も見えないが…。
一方、右の写真は橋の跡地から上流を撮影。
先ほどまで歩いていた軌道の高さに迂回困難な白い岩盤が迫り出しており、やはり右岸伝いではこれより上流へ軌道を延ばすことは出来ないだろう。
我々も、橋の跡をたどって対岸へ歩みを進める。


だが、この沢を渡るのには多少の覚悟を要した。
源流に近いとはいえまだかなりの水量があり、しかも赤っぽい苔のせいで濡れた岩場は非常に良く滑る。
飛び石伝いに跳ねて越えるのは難しく、腹をくくり膝上深の川を渡るより無いのだが、代わりの靴を持ってきているメンバーは無く、以後濡れた靴と探索を供にせざるを得なくなる。
ここまで5時間を要しているし、帰りもそれなりの時間がかかるに違いない。
濡れた靴を供に長距離歩くのは、誰だって大きな負担だ。
とはいえ…、対岸には崩れかけた橋脚が我々を待っているのだから、行くより無いだろう。
すぐそこまで林道が来ていたとしても、本望だ…。


左岸の川原に残された、崩れかけの橋脚。
上部は草が生え、その高さは分かりにくくなっているが、明らかに両岸の軌道の高さより低いように思われる。
だが、一本のレールがその出自を物語るものとして、橋脚に引っかかるように残されていた。
右の写真は橋脚下部の様子。
流水に抉られたらしく、上流側にあたる面だけが著しく破壊され、芯であるコンクリートが露出している。
川原の石をそのまま使ったような骨材が、コンクリとしての質の悪さを現している。
外形を作っていた石垣だが、よく見ると、更にその表面をコーティングするように薄いモルタルの層のあったことが、原形を留める上部の状況から判明した。


沢を渡り終えたのが12時42分で、それから54分まで川原で休息した。
おそらく、この先の前進出来る量は少ないだろう。
手持ちの地形図では、林道がこのすぐ上手まで来ていることになっている。
それを確認したら、撤収だ。
これまでネット上で遭遇報告の無かった西沢橋梁の、残念な姿ではあったが、その現状を確定し得た。
一応我々の目的は達せられたと言える。
…なにか最後にもう一騒ぎしたいという気持ちはあったけど…
そんなご都合主義都合よろしく 遺構は現れないよな…。
謎の縦穴遺跡と、失われたライン

12:54 【現在地:西沢橋梁 西詰め】
川原にある橋脚は一基だけで、それも下半分の石造部分だけが現存するに過ぎなかった。
しかし、左岸の橋台はしっかりとした石垣のものが存在した。
問題は、軌道の築堤よりも一段下に築かれた、大量の石垣である。
果たしてこれは何なのか。
地図は何も教えてくれない。

謎の石垣が川原から一段高くなった場所に存在している。
橋台はさらにその上にある。
だが、橋台は結構高く、取り付きは藪ばかりで、上に登るのは容易ではない。
それよりも、今は周囲の石垣の正体が気になる。

橋台の下にはなぜか、「足もと注意」と書かれた札が取り付けられていた。
ここは崖の上というわけでもないのに、なぜ?

あ、穴だ…
こいつは、確かに足元注意だ。
石垣の上は一見平らな苔むした地面だが、ただの凹凸では片付けられない垂直な落とし穴が、幾つも口を開けている。
それは、遠目では地面と区別が付かないので、気づかず穴に落ちる危険もあるし、或いはまだ堆積物に隠されたままの穴が残っている可能性がある。

先ほど自分たちが無造作に橋台へと歩いてきた場所にも、よく見ると、穴が隠れていそうな窪地や陥没痕が見て取れて、我々は急に慎重になった。
幾つかある穴の中で、もっとも大きく口を開けていたのが、この写真の縦穴だ。
ライトを照らすと、3mほど下に平らな地面が見え、周囲を取り囲むように荒積みされた石垣がある。
しかも、三方は壁だが、川へ向かう方向だけはさらに奥行きがありそうだ。風はない。
開口部が狭く、これ以上奥を知るには中に入るより無いが、周囲をかなり念入りに捜索したにもかかわらず、この穴へ普通に入る口は無かった。
それにしても、一度落ちたら最後だろう。這い上がる術がない。
覗き込んでいても、いつ足元が崩れるのではないかと非常に恐かった。

穴の少し上流側数メートルの位置には、川に面してこれだけ大規模な石垣の構造物があった。
軌道とは直接関連しなさそうだ。軌道は一段高い所にある。
使われているのは石垣だけで、建物があったような痕跡やコンクリート、金属片などは全く見えない。木材さえ消えている。
いったい、どれだけ古い遺構なのか… まさか、信玄公の隠し金山跡?!
確かに、この西沢の南に聳える黒金山や源流である鶏冠山などは、甲州に幾つもあった古い金鉱地の一つといわれる。
現時点で、この巨大な遺跡の正体は不明である。
我々も時間が無かったことに加え、足場が悪く(どこに落とし穴が有るか分からない!)十分に捜索できなかった。
流石に金鉱ではないだろうが、沢へ向けて伸びる穴は特に気になる存在だ。

さて、肝心の軌道跡だ。
西沢左岸へ移った軌道だが、どのようにして林道へ合流していったのか。
実はこの部分、地形図にも記載がなければ、今までは想像でものを語るより無かった。
だが、林道の終点として描かれている地点と、この西沢谷底とでは、水平距離にして100mほどだが、高低差が50mもある。
これではすんなりと接続しているわけがない。
巨視的に見れば「対岸に林道が来ている」という当初認識も誤りではなかったが、実際的にここを辿るとなれば、俄然面白みを増してくる。
この高低差を、いかにして克服したのか!
索道やインクラインの利用が適切そうだが、実際には一本のレールで繋がっていた!
今度の探索の本当のハイライトは、
実はここからだったのだ!
上の写真は、橋台の先の軌道跡。
…いや、軌道跡の埋まっている崩壊現場といった方がしっくり来るだろう。
写真は橋台上より林道方向を見上げて撮影したのであるが、全ては45°を越える斜面に呑み込まれ、どこから登って良いのか見当が付かない状態だった。
普段なら、ここが終点だったと断定していたとしても不思議はない光景。
だが、10mほど上の岩場に赤テープが巻かれている立木を発見。
そこに何かを感じ取った我々は、最後の登攀を開始した!

13:09
赤テープは偉大なる先人の恵み。
やはり、失われた軌道跡へと我々を誘うものであった。
行き止まりから15mほど斜面をよじ登ると、そこには斜面に呑み込まれかけた平場と、崖下から甦ってきた二本のレールがあった。
ここからレールを追いかける旅が再開出来る。私が胸をときめかせたのは言うまでもない。
だが、復活した軌道は林道のある方向へは向かわず、むしろ下流方向へ向いている。
ちょうど、西沢橋梁をヘアピンカーブの頂点にして進路を180°変えたようだ。
だが、おかしいこともある。
眼下の橋詰めとこことでは10m近い高低差があり、水平距離10m程度という短距離で両者を結ぶ線形は特殊なもので有らざる得ない。
すなわち、かなり大がかりなヘアピンカーブをこの急斜面に想定するより無いのだが、我々の背後は一面苔むした瓦礫斜面であって、崩落で失われた区間が100mくらいにも亘って存在したようなのだ。
そう考えなければ繋がらない。
この部分を1/5000の地図で示すと次のようになる。
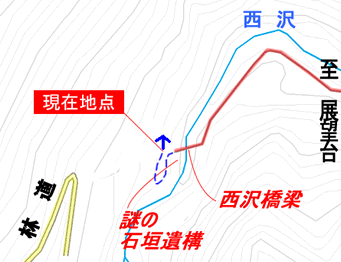
赤い実線はこれまで辿ってきた明確な軌道跡。
そして青い矢印が現在地から見る軌道の進行方向だ。
その間を結ぶ青い破線は、現地では痕跡を確認できなかったが、存在しなければならないヘアピンの想定線形である。
目指す林道との間には、まだかなりの高低差が残されており、しかも進行方向は逆という状況。
果たして、本当に林道へ出られるのか。
歓声響く軌道跡

13:13
レールが復活した軌道跡だが、地山全体が動いているのではないかと思えるほど荒廃が進んでおり、レールは殆ど地上に接することなく浮いている。
足場の悪いところを、慎重に辿っていく。
道は緩やかに登っており、沢の音が徐々に遠ざかっていくのが分かる。
沢を離れるにつれて、荒廃の度合いは収まっていった。
ここまで来る人はほとんど無いらしく、赤いテープも一度見たきりだし、空き缶なども全く見あたらなかった。

と、ここに来て、山側に巨大な石垣が現れた。
自然石を切り出した石積の隙間にモルタルが使われており、重厚で堅牢な印象を受ける。
この高い石垣に象徴されるとおり、一帯の傾斜は非常に険しいものがある。このさらに上に林道が有るはずだが、どのようにしてこの足元のレールは登ろうというのか。
我々の注目はその一点に注がれた。

久々に平静を取り戻した軌道跡。
既に右側に水面は見えなくなっており、あたりは静かな森の気配に包まれていた。
相変わらず北へ一直線に向かっているのが気になるが、とりあえず、辿る気持ちの良さは抜群だ。

左カーブ!!
キタ───!
これを待っていた!
これを待っていたんだ!!
西沢林鉄、最後まで私の期待感を裏切らないヤツ!
左カーブで進路反転の強力な予感だ!!

レールを根本に咥えたまま立派に生長した木。
レールが大人しくしていたからって、森の木々がもうやりたい放題である。
軌道廃止より前から小さな芽は出ていたのかも知れないが、たかだか40年で随分と育ったものだ。

ヘヤーピンカーブ出現!
一同、ここで歓声を上げる。
私、特に舞い上がって喜んでしまった。
だってさ、今までも何度か軌道跡でこんなアグレッシブに山に立ち向かう線形を見たし、
その都度、萌えてはいたんだけど…
いかんせん今までは…
レールが現存しなかった!


「山の鉄道」に有るべき光景が、そこにはあった。
等高線に対峙し、これを克服すべく、
か細い鉄の軌条は、
挑んだのだ!
一同!
先人の英知と努力に敬服し、感涙!
トロッコが速度を付けて曲がり得るものとして、おそらく限界まで小さなカーブがあった。
険しい斜面にカーブのスペースを確保すべく、膨大な土砂が掘り返された痕跡があった。
信じられない冷気が、その掘り割りとなったカーブを満たしていた。
我々は、その気持ちよさに至福の声を上げた。
「 涼しい 涼しい 」の大合唱!
これは、“風洞”という現象が起きているに違いなかった。
明らかに異質な涼しさと、まるで地面が呼吸しているような空気の微かな流れが感じられた。
これは、掘り返されたために隙間の多く生じた岩盤に、
冬や夜間の冷気が保持されることで発生する現象。
各地に「風穴」などとして同じような天然の低温貯蔵庫が知られているが、これは人工的なものだ。
それも、図らずに生じたものだ。
この涼しさ、現役当時もきっとここにあったに違いない。
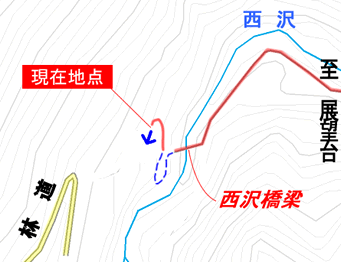

このウルトラCカーブによって、現在地と進行方向はご覧のように変わった。
林道までの残り高低差は30m。
行って行けない高さではなくなった!
ヘアピンカーブには、林鉄の“本気”を見せつけられた思いだ。
こうなれば、この先にもさらなるヘアピンカーブを連ねて登る可能性が高い!!
こいつは熱い!
ヘアピンカーブを越え、進路を反転させた軌道。
当然そこにあるのは、先ほど見上げた石垣の上の景色…。
… と い う こ と は …

喜多─!