信じ難き災害の爪痕
ジャングルになった国道…
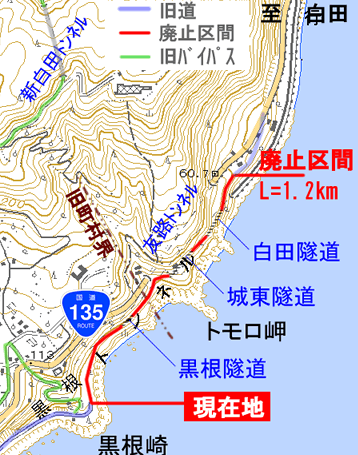
現在地黒根崎より北側約1.2kmは、国道135号の旧道であるが、既に廃道となっている。
それは外見上という意味ではなく、県によって道路としての認定を解除された、いわば「本物の」廃道である。
したがって、地形図にもこの道は描かれていない。
とはいえ、昭和53年までは普通に利用される現役の国道だった。

上の写真は、黒根崎から見たトモロ岬方向の眺め。
そこに道路があったようには見えないのだが、一昔前の地形図によれば上の地図のように道は通じていた。
途中には南から順に「黒根隧道」「城東隧道」「白田隧道」の3本のトンネルがあって、昭和42年に調査された『道路トンネル大鑑』巻末資料の「トンネルリスト」にも記載がある。
ここからだと、まずは300mほど先の黒根隧道がファーストターゲットとなる。

されどこの道…
「通行止め」などと言う 生やさしいものではない。
わたし道路だけど、危ないから通らないでね。
→通行止
もうわたし道路じゃないから。 …ご勝手に。
→道ならざるもの 「真・廃道」
この“小公園”と化した廃道区間の入り口を見た瞬間、真の廃道と言うべき存在の凄みを、私は早くも感じた。

05:34
肉厚の巨大な葉っぱを身に付けた得体の知れない植物を両腕で払いのけ、平坦ではない廃道へと進入開始。
酷い藪は、旧道を隠すために人工的に造成したものだろうと思ったが、入ってすぐにそれは間違いだったと気づかされた。
5mほど進んだところには巨大な土砂崩れの跡があって、そこには軽トラサイズの巨石が、周囲の舗装に大きな亀裂を広げながら鎮座していた。
あくまで自然の状況がこの荒廃なのだと、そう理解させるに十分な光景だった。

釣り人が通るらしく、少量のゴミと共に踏み跡が続いている。
路面を這う大量の蔦や木の根、そして落石・崩土の類によって、殆ど舗装は見えなくなっている。
所々では路盤さえも無事ではなく、極端に道幅の狭い場所もある。
しかし、かつてここが自動車も通る道だったことは、藪と土に埋もれながらも残るガードレールが証明する。
しかしこの緑の濃さ。
これでは先ほど海岸沿いを遠望したときに道形が見えなかったのも道理である。

しかしこの藪…
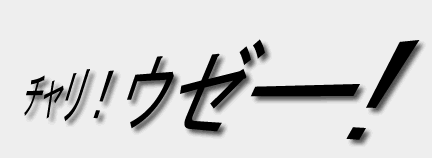
勝手に連れてきてこういう事を言うのは、チャリにとっては非常に心外ではあろうが、もうチャリは連れて行けない。
写真だとスケールが分かりにくいから、こ穴のような道も通り易そうだが、本当は人が屈んで通れる隙間しかないから、チャリを通そうとすると至る所が引っかかって思うように進めない。
両側のハンドルにペダルにサドルに…、チャリは本当に藪と仲良くしたがる。

で、
悪いけど捨てた。
この日の気温は朝から25℃、ジャングルの中は無風。黙っていても額に汗が浮く。
立ち止まればもの凄い勢いで集ってくる羽虫…耳元でプーンという高い羽音、白黒縞模様…みんな藪蚊だー。
逃げるように前へ進めば今度は警戒色のでかい蜘蛛や粘着ウェブの連続攻撃。
そんな中、チャリは藪に絡まれ思うように進まない。行っては戻って、引っ張っては担いで、蔦を千切っては投げ千切っては投げ。
滝のような汗。余計に藪蚊たちが私を大絶賛!
藪へ入って5分、たった50mで、私の我慢は限界に達してしまった!
このままチャリと一緒に進んでも、もし最後まで通り抜け出来なかったとしたら、世を儚んで海へ飛び込みそうだ。
50mで5分もかかる藪だぜ。今日一日がここで終わりかねないペースだろ。これは。
無念だが、チャリは諦めた。
待ってろ。後で必ず迎えに来るからな……。
【藪のほっとステーション】 山行がが使っている防虫グッズを紹介 【MOWSON】
夏場になるとよく質問が来るのですが、私の探索時の防虫対策についてご紹介しましょう。
廃道歩きはもちろん、登山やキャンプなどアウトドア全般について役立つと思うので、気になる方はお読み下さい。
ずばり、廃道は藪蚊や虻といった害虫(不快虫)の宝庫で、暑いからと言って半袖半ズボンかつ無対策では際限なく食われます。現場で不快なのが一番ですが、帰宅後も延々と痒くて、きっと後悔することになるでしょう。
私も、かつて幾度となく眠れぬ夜を過ごしました。
しかし、私はコンビニ店員だった男。当然お客の前で腕をさらしレジを叩くわけで、余り酷い虫刺されを見せるわけにはいきません。
そこで、山行がの装備強化および近代化に尽力してくださったパタリン氏によって、次の二つの道具が示され、以来はこの二つを使い分けています。
1. 米軍御用達!(←同一成分品) 最強の虫除け塗布薬 「ULTRATHON」
海外から通販で購入した薬剤で、これはものすごく強力です。虻や蚊が飛乱する場所へ地肌を晒しても、まずカラダにとまりません。つまり刺されない。(でも、殺虫スプレーではないので近くには寄ってきます)
とにかく害虫にはオールマイティーに効き、今回レポートの激藪でも、結果的に1カ所しか食われませんでした。
廃道にはイイ薬だと思うのですが、日本国内では未認可であるうえ、人体やプラスチック製品に悪影響があるため、今は米軍でも使われなくなったそうです。だから、皆様にもお勧めしません。
→現在の米軍仕様防虫薬 CHIGG AWAY(チグ アウェイ)
こちらは国内で購入可能。効果は前掲品と同程度で、しかも副作用の心配が少ないそうです。私も今ある分を使い切ったらこれに切り替えます。
2. ハッカ油 (10ml×3本)
ぜひ東北や北海道のオブローダーにオススメしたいのが、ハッカ油です。
なにやら巷ではダイエット商材として売られ、実際に風呂に数滴垂らして入ると痩せるような話ですが、オブローダーに軟弱なダイエットなど無用!
これを100円ショップで手にはいるような小さなスプレーに移し、体や(目以外)の顔にちょっとかけると、強烈な匂いで大概の虫はもう寄りつかない。
特に、東北や北海道では春から夏まで爆発的に増える虻に対しては、市販の防虫剤では殆ど効果がありませんが、これはよく効きます。
大きな副作用もないので(ただし妊婦の方は使わないでください、また目には入れないように)、オススメします。
つうか、虫は嫌うけど人間の場合普通にいい匂いだし気持ちいい。ほんの少しの風さえあればすーすーするので、清涼効果も抜群です。
値段は結構しますが、スプレーとして使うのでなかなか減りません。(気持ちいいからと使いまくるとすぐ無くなるけど…)

思い切ってチャリを捨てた私が、身軽になって周囲を見回すと…
な に こ れ …
と言っても、写真では分からないだろう。
私にも分からない。
写真じゃなくて生で見ても、なんだかよく分からなかった。
酷い藪に覆われた道の山側、本来法面があるはずの場所に、それまでの石垣の代わりに現れた横穴?
コンクリートで坑口が造られているが、目指す隧道でないことは位置からもサイズからも明らかだ。
ナニコレー…
不気味な横穴の正体は…

05:39 《現在地》
それは、法面に口を開けた横穴のようだ。
しかし、路上の藪が深すぎてこれ以上カメラを引けないので、坑口の全体を捉えることは出来ない。
緑色の蔦がカーテンか簾のように坑口に垂れ下がっており、異様な雰囲気を醸し出している。
かつては坑口を塞ぐ鉄製の扉があったようだが、完全に腐食してその残骸が倒れている。
内側からは微かに冷気が流れ出しており、近づいた私の頬を、怪しく、撫でるのだった。

壁は白く、まだ外気に晒されるようになって、それほどの年月を経ていないような印象だ。
ザラザラした手触り(石英分多め)の大きなコンクリートブロックは、高貴な雰囲気を漂わせ、まるで名のある王の荘厳な墳墓のようである。
一匹のコウモリがポツンと、奥の天井に下がり、こちらを見てカラダを小刻みに震わせていた。
なぜコウモリは一つの穴に一匹というケースが多いのだろう。前から不思議である。(まるで留守番をしているようにも見える)
穴は、入り口から真っ直ぐ3mほどで壁に行き着くが、そこからはさらに同じ幅で右下方へ階段が折れている。地下水が壁に湿っており、外光も殆ど届かなくなる。
気持ちの悪い場所だが、もう少し進んでみたい。

下りの階段は僅か3段ほどで、すぐ小部屋が現れた。
床が2m四方、高さ3mほどの小さな空間で、床の大部分がコンクリートの蓋をされた四角い函になっている。その上に立つと天井までは2.5mほどだ。
そして、ここで終わりではなく、さらに写真の窓が、奥へ向け口を開けている。
この景色を見てピンと来るものはあったのだが、正体はしっかりと壁に刻まれていた。

第四集水地
やっぱり水関係の施設だった。
しかし、銘板が右書き。昭和30年以前の工作物と推定される。
どこからどう集水し、どこへ配水していたのか。それらは不明ながら、廃止されて久しいことは明らかだ。
産業遺構独特の空虚なムードに包まれている。

そして、銘板の下の50cm四方くらいの窓を潜り、さらに奥の部屋へ進んでみた。
そこも前の部屋と同程度の床面積だが、床が1mほど低くなっている。
だから、元の部屋へ戻る窓を通るための足場として、コの字型の鉄製のバーが窓の下の壁に3本設置されているのだが、なんとこれ、私が最初に足を乗せた段階(部屋に入るとき)で一番上の一本がヘニャっと折れてしまった。元もと腐りきっていたのだ。
幸い、残りの二本は体重を支えてくれたので、転落もしなかったし、戻ることも出来たのだが、足場が全部折れていたら、戻れないまでは行かなくても、怖い思いをしたと思われる。
この部屋は、金属の菅が壁から出ていたりするので、貯水槽だったと思われる。

この貯水槽らしき部屋からは、またも奥側に窓があり、その向こうにはここよりも狭い部屋が。そして、そこからさらに狭い通路が、真っ直ぐ続いているのだ。
もう、奥行き不明…。
左の写真が、その狭い通路の入り口。
ご覧の通り、写真は靄がかかっていない。つまり、どこかへ風が抜けている可能性がある。
しかし、私はこれ以上入ろうとは思わなかった。
進むには這い蹲らねばならないし、その床はびしょ濡れ。
涼しいのは嬉しいが、間違いなく水路であることが判明した今、モチベーションも維持できなくなっていた。
それよりも、私は地上に残してきた廃道のほうが、何倍も気になる。
撤収だ。
復旧されずに廃道

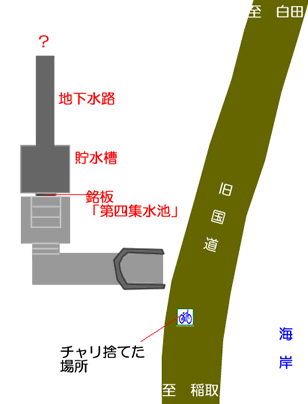
05:47
朽ちた扉を踏みながら、外界へ復帰。
出口へ近づくと、温い空気がモワッと顔に当たって、嫌な気持ちがムクムクと甦ってくる。
…もう、うんざりだよ。
オマケに、この地下集水池のマップを添付しておこう。
まあ、余程のマニアでもない限り、わざわざ訪問するほどのものではないだろう。

地上の旧道へ戻り、再び前進を再開する。
チャリを捨てたことで一挙に身軽になり、今までと同程度の酷い藪道であっても、さしてストレスを感じずに進めるようになった。
まあ、チャリを捨てたということは、仮に上手く突破できたとしても回収に戻ってこなければならないわけで、はっきり言って面倒くさい。
こんな事になるのがあらかじめ分かっていたら、チャリも連れてこないわけだが、まあ後悔しても仕方がない。
あと、初めのうちは釣人の踏跡が小道となって続いていたのだが、途中で崖下の海岸へ降りていく小道と分かれた途端、それは一気に頼りのないものに変わった。
釣人に対しオブローダー人口の如何に微少なるかを物語る事実なのか。

この写真は、間違いなくかつての路盤を撮影したものである。
しかし、膨大な量の土砂が法面と路面を完全に埋め、さらに崖下へと雪崩れ込むようにして、ほぼ45°の一様な斜面を成している。
そして、年月と温暖湿潤な気候が林を育てている。こんな状況が、50m近くも延々と続く。
普通に考えたら、この手前で道が行き止まりだったようにしか見えない。
しかしこれが、私が生まれる翌年、昭和53年までは現役だった国道の、その現状なのである。
何故、このような景色になったのか。
帰宅後、少し調べたらすぐに分かった。
それが、昭和53年1月14日に伊豆地方を襲ったマグニチュード6.8の大地震、「伊豆大島沖地震」なのだった。
この地震では、東伊豆町内だけで10名の尊い命が失われたが、断層が方々にあって地質の軟弱な沿岸地区の被害が特に甚大であった。
中でも、同地震で現役国道が被った最大の被害箇所が、この稲取〜白田間の国道135号であった。

地震の被害を伝える資料として『東伊豆町誌』の一文をここに紹介しよう。
「稲取黒根地区の海岸沿い急斜面が崩壊し、国道135号線の3本のトンネルを含めて延長1120mにわたって被災し、その一部では道路が山腹もろとも大崩壊し殆ど原形をとどめない状態となった。」
1120mと言えば、今回踏査している黒根崎からトモロ岬の先までの、ちょうど全線に相当する長さである。
被害は、この全体に及んでいたのだ。
そして、
震災後、旧道は一度も復旧されずに、現在へ至る。

この事実を図書館で知ったとき、私は震えた。
あまりに突然の 死 を、受け入れざる得なかった道……。
これだけの大崩落に逢いながら、この旧道の崩壊で死者は出なかったという。
(ただし、平行する有料道路でも落石が発生し、1名が生き埋めとなり亡くなっている)
決して安い感動に走りたいわけではないが、これだけは素直な気持ちとして、言ってあげたい。
どうぞ安らかに…。


廃道区間の入り口から200mほどの場所に、道路標識を発見!
上の写真を含め、この3枚の写真は全て同じ標識だ。
とても道路跡とは思えない場所に立っていることがお分かり頂けると思うが、これは路肩側にあった標識だ。
特に左の写真では、向かって右側が路面のはずなのだが…。
表面はまだ辛うじて塗料が残っており、「落石注意」と読み取れた。
皮肉にも、道は未曾有の“落石”によって完全に消え去ったのにも関わらず、この標識だけは、傾きながらも残ったのである。
右の写真は、支柱部分の拡大。
「静岡県」の文字が残っており、国道の名残といえる。

相変わらず酷い藪道ではあるが、予期せぬ道路標識の出現に元気を回復させた私だった。
しかし、そのすぐ先にて、イバラが道が塞ぐ呪われたようなエリアが出現!
剪定ばさみでもあれば楽なのだろうが、もちろんそんな物は持ち合わせていない。
爆弾処理班のような、慎重に慎重を重ねたムーブにて、どうにか無傷でここを通り抜けた。

総じて道は本来の平坦な路面を失っており、膨大な崩壊土砂によって斜度30°〜45°程度の斜面となっている。
全てが直接の地震の被害ではないだろうが、地震で緩んだ地盤がその後の放置によって、積み木崩しのように崩れたものと思われる。
いままで、人為的に廃道化されたものを除けば、これほど長距離にわたって斜面と化した舗装路を見たことがない。
それでもどうにか歩けるのは、地面が土っぽいことと、豊富な手掛かり(木の幹や根)があるためだ。
また、随所にガードレールが残っている安心感も無視できない。

標識から50mほど進むと、いよいよ前方右手に岬の姿が近づいてくる。
写真では、明るく見えるのが路肩の向こうの景色で、下には海岸線と青い海がある。
遠くに白みがかった山の斜面が見える思うが、そこが半島部分だ。
これは、黒根崎とトモロ岬の間にある無名の小さな岬で、その基部に近い場所に「黒根隧道」があるはずだ。
いよいよ、最初の隧道が近い!
果たして、このような状況下で無事に残っているだろうか。

くわー!
ここで、頭上に影を作っていた林が一旦途切れ、猛烈なクズの藪が現れた。
このような状況が、最も前進困難である。
もし無理を重ねてチャリをここまで連れてきたとしても、この突破はほぼ不可能だったろう。(草刈り作業をすれば或いはとも思うが、私は草刈りの道具を持ち歩いていない)
平泳ぎのような格好で、私は躊躇うことなく藪へと邁進!

そして、この叢(くさむら)を突破すると、再び元のような斜面の林となる。
その始まりのあたりで、斜面(道)を横断してチョロチョロと水が流れているのに遭遇。
ちょうどすぐ上の斜面から滲み出るようにして流れ出していた。
ここ最近はずっと晴天続きにもかかわらず、幅10cmくらいの透き通った水流が出来ている。
とはいえ、沢のように凹んでもいない場所だけに、昔なら流れていたとは思えない。
よく、土砂崩れの前触れとして「山から水が出てきたら要注意」と言われるが、何となく気持ちの悪い水流だった。

いつ、隧道が現れてもおかしくない位置に来ていると思われる。
道は、さきほど前方に見えた無名の小半島のフトコロへと突き刺さろうとしている。
だが、一向に路面は再開されず、そこに平坦な場所は皆無。
地表を覆う藪は濃く深く、地面の細かな変化を観察することは極めて困難。
…やばい。 隧道が埋まっていた場合、その痕跡を見逃してしまうかも知れない…。
わたしは、そのことに非常に強い危機感を持った。
ここまで来て、痛恨の見逃しは勘弁して欲しい!
しかし、だからといって片っ端から地面の草を毟るわけにもいかず、ただ、隧道の現存を祈るような気持ちで、前に進むのだった。

わ──!!
みっ、見えてた(笑)。
少し前から、視界には入っていたはずのこの景色。
だが、それが隧道だと気づいたのは、かなり近づいてから(この写真)だった。
猛烈な藪の向こうに、隧道の上半分のシルエットが、はっきりと確認できる。
そして、貫通している!

06:06
黒根崎から30分余りを要し、遂に一本目の隧道である「黒根隧道」に到達!
黒根隧道
全長40m 昭和3年竣工
隧道はほぼ形をとどめ、ちゃんと貫通していた!
洞床には、綺麗なアスファルト舗装が見えている。
それはまさしく、「死」の直前まで車を通していた旧道の、奇跡的に保存された貴重な空間なのだった。
そして、 この残された隧道で私は
震災の記憶を生々しく伝える“あるモノ”との
衝撃的な遭遇を果たす!!