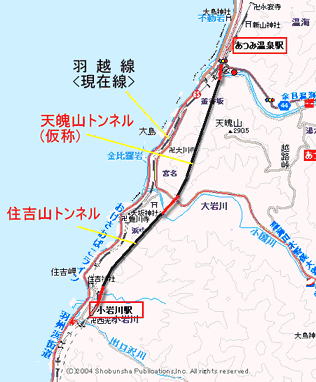
羽越線あつみ温泉・小岩川駅間に存在する、未供用トンネルは二つ。
いずれも、1kmを優に超える長大な複線断面トンネルで、将来の羽越新幹線開業を目論んで着工されたという噂もあるが、計画は凍結しているようでもある。
前回は、天魄山トンネルを攻略したので、今回は残るもう一本を、お伝えしよう。
なんか、結果が見えている気がする?
まあ、そんなこと言わずに見ておくれよ…。

退屈の極みといっても差し支えがないだろう、これまでに体験したことのない、不毛な隧道探索をしてしまった。
真新しいトンネルがそれほど面白いものではないことを、改めて実感した。
トンネルとは、単に機能であり、そこに面白みを感じさせる味付けが必要なのだ。
それは、時に廃棄されたという背景であり、廃棄にまつわる経緯であり、その姿が醸し出す情感である。
本未成線トンネルは、背景に一定の面白みはあるものの…謎が多すぎて、いまいち萌えられない。

檻のような天魄山トンネル南口柵を再びよじ登り、脱出をはかる。
その途中、坑口の先に広がる田んぼにくっきりと浮かび上がった鉄道用地が目に付いた。
次のトンネルも、その暗い坑口を見せている。
トンネル間の明かり区間は、目測で200m程度。
途中には、県道一本と、小国川の流れがあり、どのような完成形を目論んでいたのか、想像してみるのも楽しい。
高架か、盛り土か。
景観的には、高架が似合いそうだけど。

さて、チャリにまたがり、一旦大岩川集落まで戻る。
そこで旧国道の古びた橋を渡り、今度は小国川左岸の、住吉山トンネル北口を目指す。
ここには道はなく、大体の当たりを付けて河岸を強引に歩いたが、一応踏み跡はあるものの、かなりの隘路だ。
むろん、チャリは置いてきた。
また、ここへ入る前には、ある民間の庭を通ることになるので、私はたまたま住人に挨拶をして通れたが、無用なトラブルを起こさぬようにしてほしい。
危険な踏み跡を200mほど辿ると、いよいよ人工物が見えてくる。

おっつ!
みえてきたぞぞ!!
なんか、今度は、
いいムード?!
坑口の前は、見事に急な斜面になっており、よじ登る羽目に。
ここさえ凌げば、やっと坑門に到達である。

このトンネルには、銘板が設置されており、正式な名前が「住吉山トンネル」と判明した。
この名は、海沿いに平行する現在線のトンネルにもある。
銘板は、この後で詳しく見ていくことにする。
まずは、坑門の概要であるが、見ての通り、完全にネット封鎖されている。
遠目には、フェンスだけで塞がれているように見えたが、実際には、天井までびっしりと塞がれており、どうあがいても、立ち入れなかった。
無念。

坑口には平坦な場所は狭く、そのままコンクリート製の橋台となって川面に落ちている。
いかにも新幹線の高架っぽい…イメージでものを言っているが…何となくそんなイメージの、橋台が、苔むしている。
将来的には、ここから高架で小国川と田んぼと、県道を渡って、そのまま先ほどの天魄山トンネルに続くのかも知れない。
距離は短いが、まだまだ工費が多くかかりそうな内容ではある。
かといって、工事が中断されたままになっている理由としては、弱い気もしないでもない。
 フェンスには扉が設置されているが、チェーンでギチギチに固められた上で、大きめの南京錠でしっかり施錠されていた。
フェンスには扉が設置されているが、チェーンでギチギチに固められた上で、大きめの南京錠でしっかり施錠されていた。これでは、くじ氏をかつて驚かせた、鋼鉄の肉体による●●●で●を●●●●してしまう私でも、どうしょうもなかった。
潜りこむ隙は、全くないのである。
何故に、ここまでぎっちりとガードしているのかは、不明であるが、集落に近いことから、教育・防犯上の要求があったのかも知れない。
また、扉の一部には、カナ鋸のようなもので切断された南京錠が一つ残っており、何者かが強引に侵入した結果として、このような強固な守りとなったとも、考えられる。
安心してほしい。
不法侵入だけでも、ヤバイのに、器物破損まですれば、さすがに手が後ろに回ること明白なり。
ここは素直に、引き下がる私であった。

住吉山トンネル
形式:複線交流方
延長:1K395M00
設計:信濃川工事局
施工:西松建設株式会社
着手:昭和53年7月
竣工:昭和59年3月
ここでの注目は、その建設時期である。
1kmを越えるトンネルとはいえ、6年近くもかけて建設している。
そして、既に完成から20年以上を経過してしまった。
かなり古い時期から、この区間の新線計画はまったりと、進められてきたきらいがある。
 どうあがいても、入るのは無理。
どうあがいても、入るのは無理。むぬーーーー。

フェンス越しにのぞく内部の様子。
作りは、さっきの天魄山トンネルと同じであるが、そこそこ年季が入っている。
建設後は、ほとんど、あるいは全く?!手入れされていないようである。
1,4km先の出口は、やはり見えない。
内部は緩くカーブしているようである。
入れないとなれば、急に後ろ髪を引かれる気持ちになったが、とりあえず、どうしょうもない。
撤収だ。
予想外に、強固なガードであった。

さて、国道に戻り、現在線と仲良く海岸線をゆく。
まあ何ともいえない旅感たっぷりの景色が、ずうっと続く。
個人的に、温海から村上までの海岸線の景色は、何度走っても飽きない、極上の道である。
いつも冬場ばかりに来ているから、今度はガンガンに日の照りつける日にも、是非来てみたい。

国道からは、一段高い位置にあるから気が付きにくいが、現在線の住吉山隧道が、これである。
住吉岬と地図に示された、岬と言うほどのことはない小さな崎を、越えている長さ250mほどのものだ。
この隧道を抜ければ、もうそこは小岩川駅にほど近い。
大正12年の竣工で、単線のまま未だ現役である。
新線が開通すれば間違いなく廃止されてしまうだろう現在線には、ほかにも同時代の二つの隧道が存在している。
 小岩川集落にはいると、再び現国道は海上をショートカットしてしまう。
小岩川集落にはいると、再び現国道は海上をショートカットしてしまう。ここでも、内陸へのアプローチは旧道の役目であり、そして、この旧道上にあるのが、以前もミニレポで紹介した「巌橋」である。
この、幻の大正国道「國道十號線」の銘板が現存する巌橋を渡ると、間もなく小岩川駅が、左にある。
駅は、山際の丘陵上に位置している。

駅の付近から、北を見渡すと、間もなく一つのトンネルが目にとまる。
これぞ、未供用の住吉山トンネル、その南口である。
旧国道にチャリを捨て、民家の隙間をすり抜け線路上を横断。
田畑を横切って、直線坑門を目指す。
線路を横断する部分には、耕作者の踏み跡があるが、現在線住吉山隧道坑口傍で、列車の接近に気づきにくそうだから、気を付けたい。
 線路越しに、住吉山トンネル南口を望む。
線路越しに、住吉山トンネル南口を望む。現在線との位置関係が、分かるだろう。
なお、背景の丘陵状の山が、おそらく住吉山だが、地形図にはその名はない。
古い鉄道隧道の命名においては、実際に存在しない山の名前を名称にする(地名に山を付けて命名するなど)ケースがあったと聞くので、これもその類であるかも知れない。

すぐに接近することが出来た。
南口は、開かれた景色の中にあり、日当たりも良好なおかげで、まだそれほど古びた印象はない。
だが、銘板を見れば、竣工後20余年を経過していることがはっきりと示されており、それが公共事業にありがちな牛歩だとしても、きわめて公共性の高い幹線鉄道という事業における、“時の経過による経済的損失”は、計り知れぬ気もする。
もう、この坑口から小岩川駅までは、200m程度の距離しかなく、土を盛ってレールを敷いて、小さな橋を一つ架ければ、開通しそうである。
ここまでで、一応新線の全容を見てきたことになるが、いったいどこに、工事停止の原因があるのかは、分からぬままであった。
何か情報をご存じの方がおられたら、是非ご教示願いたい。
 坑門前には、わずかに路盤用地があり、例に漏れず立入禁止となっている。
坑門前には、わずかに路盤用地があり、例に漏れず立入禁止となっている。不思議なのは、ちょうどその域内にご覧の、祠が納められていることだ。
これでは、誰一人お参りすることは出来ないではないか。
コンクリート製の簡素な祠は、水音のするコンクリの板を押さえるように安置されており、これは私の想像だが、板の下には、トンネルの排水溝があるのではないか。
祠は、水の神様を奉ったものと、想像できる。

何とも寂しげな祠の後ろ姿。
ここで線路用地は消え去り、その先は蛇行する河川に落ちている。
奥の盛り土は、現在線で、その左には、かすかに小岩川駅が見えている。
 なんと、こちらの坑口は、ほとんどノーガードであった。
なんと、こちらの坑口は、ほとんどノーガードであった。正確には、天魄山トンネルのそれと全く同じ、木の柵が設置されているだけだった。
ますます、北側坑口の、異様に厳重なガードが何だったのか気になるところであるが、結局洞内は普通に、至って普通に通じており、その真意は分からぬままである。

坑口付近には、ニャンニャンのニクキュウ痕が、無数に残されていた。
どうやら、このトンネルもまた、彼らの集会場となっているようだ。
これまでの私の長年の研究によると、
人が寄りつかない隧道の、おおよそ12%程度の割合で、ニャーのニクキュウ痕が確認されている。
これは、 かなりの高確率であると言って、差し支えないだろう。
廃隧道におけるニャーとの遭遇の期待値は、数字上は近所の一人暮らしのおばあちゃんの家の軒先に匹敵するものだが(独自調査)、残念ながら現時点では、リアルな遭遇はない。
これは、ニャーが、私を避けている可能性を示唆する。

隧道レポなのに、洞内は写真一枚で、終わりです。
だって、なーんにも無いんだもの。
ただ、繋がっているだけでした。はい。
こちらは、路盤も完全に舗装されており、完成しているとみて、間違いないと思う。
このまま使われないままにしておくくらいなら、いっそ、国道のバイパスにでもしちゃえばー。無責任発言失礼。
完