ここを2002年春、山チャリがてらの内部調査を行った。
今回は、そのレポートである。

今回の探索のスタートは、この二井山集落である。
この地にかつて二井山駅があったが、廃止されて40年近く経過した現在では、そのことを伝えるのは、一本の立て札のみだ。
二井山集落を離れると、すぐにのぼりが始まる。
ここから長い山間部の道なりとなる。
かつての鉄路は、現在の車道(県道48号線)に沿って存在したようだが、その痕跡は見つけられなかった。
結構な勾配であり、SLや気動車では、速度は出なかっただろうなー。

1Km程で、車道は、直角のカーブで進路が変化する。
一応青看があるが、正面に道の表示は無く、事情がわからない人には、何のための青看なのか分からないことだろう。
このときは雪が残り、なおさらそうだったのかもしれないが、もはや正面に道あるとは思えないほど、廃線跡は自然に還ってしまっていた。
しかし、わたしの目はごまかせないぞ(笑)。

この切り通しが、廃線跡である。
今回は雪も残り、目的の二井山隧道はすぐ近くであることから、チャリはここにおいて徒歩での探索となった。
5年位前に来た時には、「通行止め」の表示があったりしたはずだが、現在では、もはやそれらも消滅していた。
この先の隧道は完全に、忘れ去られようとしているようだ。
県道48号線でもあるのに…。

切り通しには雪がいっぱい。
しかし、この雪のおかげで、通行(徒歩)はたやすかった。
たぶん夏場は…、身の丈もあるほどの雑草に覆われているのでは…?

ついに、異様な穴が見えてきた。
廃線跡には、水がたまり、雪解けのこの時期、小川のようになっていた。
スニーカー履きの私は、この期に及んでぬれるのをためらい、なかなか進行するのに難儀した。

いよいよ、入り口に接近。
ガードレールが道をふさいでいたが、もはや要を成さなくなっていた。
よく見ると、入り口両脇の崖は石組みになっているのが認められた。
それでは、いざ、内部へ!!

入り口から、内部を撮影。
なんとも不気味な様相。
壁と言う壁には、なにやら石灰質の染み出したような、まだら模様が広がり、内部からは、水の落ちる音が絶え間なく反響してくる。
以前、反対側から進入を図った際は、20mほど入ったところで、出口側の明かりが見えないことから、突破は断念した。
やはり、こちら側からも、出口は見えない。
まさか、崩壊し埋没しているのか?


今回、懐中電灯を準備して望んだ。
入り口から20mほどで、自然光はほとんど届かず、真っ暗であった。
ここでスイッチオン!!
意外に、心もとないな…。 この灯かり。
やはり、老朽化は限界まで進んでいるようで、あたり一面瓦礫の山である。
もし、チャリでは…、担ぎプレーだな。
不安になって振り返ると(写真右)、いやに、入り口が遠くに見えた。


さらに挫けず進むと(30mばかりすすんだだろうか、入り口からは50mくらい)、先にわずかな明かりが見えてきた!
出口は依然見えなかったが、そこから入り込んでいる光が壁に反射しているようだった。
で、それはうれしかったが、問題は足元…。
なんと、水浸し!!
右の写真の状況であった。(水面に懐中電灯の明かりが反射しているのがお分かりだろうか?)
もともと、ここは線路があったのだから、砂利が敷かれていたはずなのだが、泥が深く積もっており、ここに足を踏み入れると、大変そうだった。
別に、水に落ちても、足がぬれるだけだろうが、それでも、まだまだ旅の先は長かったし、それは避けたかった。

何とかかんとか、壁際のわずかな水没していない部分をつたって、出口から入り込んでくる明かりで懐中電灯がいらないくらいの場所まで進行。
こちら側の内壁のひどい崩れ方は、前年夏の調査時に印象に残っている部分だ。
いよいよ、通り抜けできた喜びが実感されてくる。
ひどく崩れた壁からは、大量の土砂が進入してきていた。

そして遂に、主要地方道48号線不通区間二井山トンネル延長190mの踏破に成功した。
やはり緊張していたらしく、日光の下に出たら自然と深呼吸してしまった。
しかしやっぱ人は日向に生きるものだなぁ、なんて、実感。
このような出口の見えない廃トンネルを踏破したのは初めてのことであったから、喜びも達成感もひとしお。
ちなみに、この写真の場所は、夏場来るとこんな⇒
 場所である。
場所である。まったく印象が違うのに驚いた。

出口側の造形がこれ。
さすがに年季の入った朽ち振りといえよう。
如何にも遺構と言った面持ちである。
さて、チャリを置いてきてしまったので、これ以上進んでも仕方が無い。
再びこの暗闇に戻ることにする。

損傷が激しい出口側(西側)。
さすがに危険であると言うことが、素人目にも分かるが、かといって、流石に生き埋めになるほどの崩落に巻き込まれる可能性は天文学的に低いと思っているので、崩れてくるような怖さは、少なくても私は感じない。
ただ、内部で大きな物音を立てようとは思わないが。
余りの朽ち振りに、見とれてしまう。
つくづく私は廃道が好きなんだと、実感してしまった。
(この写真を人に見せたら、「うへぇー、気持ちわりー!」と言う感じのリアクションをされた。っていうか、それが普通のリアクションなのだろう。)

引き返しながら、だいぶ気持ちに余裕ができていたので、周囲をよく観察してみた。
そして見つけたのが、一箇所の横穴である。
横穴といっても、奥行きは人一人は入れるくらい。
むしろ、くぼみといった程度のものである。
はじめこれがなんなのか、大変に悩んだのだが、どうやらこれは、待避所らしい。
保線作業員などが、トンネル内で車両に追い詰められてしまったりした時にやり過ごすためのものだろう。
初めはもっと、なぞめいたものを連想したのだが…。
と、今回のレポートはこれで終了である。
このあとは、無事にチャリに戻り、旅をつづけることができた。
(どういうわけか、この後に撮ったはずの写真3枚ほどが、メモリ上からすっかり消滅していたが…いまだに原因不明…)
とにかく、県内に後いくつあるか分からない、廃隧道であるが、そのうちの一つを踏破することができ、感無量である。
このレポートをご覧になって、侵入を試みようとする人がいたら、「楽しいからオススメする」けど、くれぐれも自己責任でね。
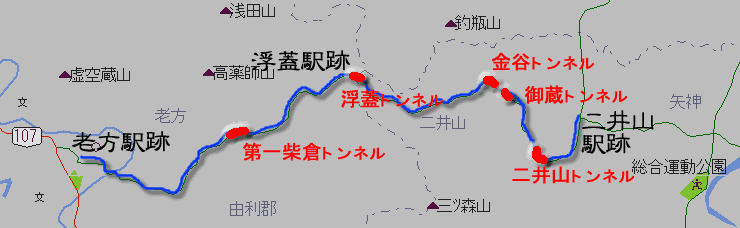










 果たして、真実は…?
果たして、真実は…?