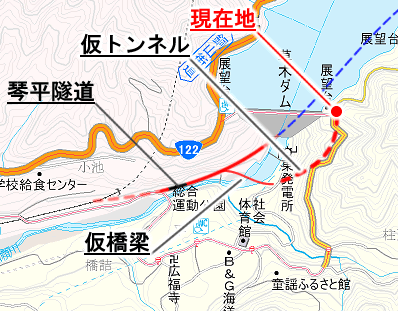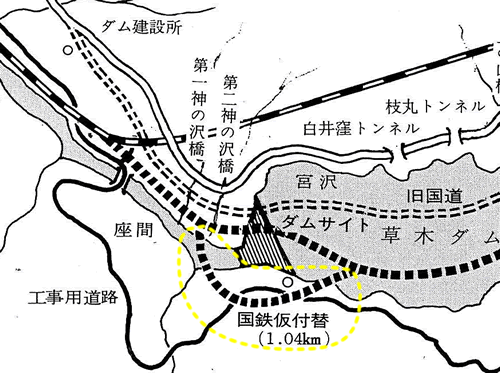�܂��͑��i�K�˔j�ƌ����ׂ����B
���̂悤�ȁu���̂Ȃ��v�p詓��ɂ����āA������ŏ����猩����͈͂ɑ����u�ǁv�������ƌ������Ƃ������B
����������B
�R���N���[�g�̓��ǂƖ������O�����Ղ��N���Ɏc�铴�����A�łɌ����Ȃ��Ȃ�܂ł����Ƒ����Ă����B
�@�u�悵�I�v�@�@�������������ł������B

�����ɂ͗₽����������C������Ă���B
���͖����̂ŁA����ł������C��������ΐ����C�̂��߃t���b�V���B�e���o���Ȃ��ƂȂ��Ă����͂��ł���B
�d���͂���Ă��Ȃ���������ː��͂Ȃ����A�ʐM���炵���z�����ǖʂ���ė����ē������Ă���B
�����̃o���X�g�͊p�̂Ȃ��썻���g�p�̂悤�ł���B
���ǂ̓R���N���[�g�̏ꏊ�ł��ŁA���̎d�グ�͊��ɐ����Ă���B
���ʂ̓S���g���l�����烌�[���Ɩ������O���������̏�Ԃŕ��u����Ă���A��ɉ����ɓ]�p���ꂽ�l�q�͂Ȃ��B
�p�~��35�N�ɂ���Ԏ��̌o�߂́A���قNJ������Ȃ��B

�r���A�Ҕ��B�͏�Ɍ������ĉE�̕ǂɌ��ꂽ�B
�Ҕ��B����ɉE���̕ǂɂ����Ɍ��ꂽ���R�́A詓�����ɍ����փJ�[�u�������Ă��邩�炾�����B
���̕ǂɂ͂Ƃ�����Ԃ��y���L�̐��������ꂽ�B
���\�ȏ����̕����������Ӗ����Ă���̂��B
�C�^�Y���Ƃ��v���Ȃ��̂ŁA�����炭���������Ă����B������̋������낤�B�i���r���[�Ȑ����Ȃ͓̂�j

詓��͒Z���Ȃ������B�����炭����200m���ĕ����Ă����B
���X�ƃJ�[�u���Ă���A�U��Ԃ��Ă������̌��͕ǂɋ͂��ɔ��˂��Ă���̂݁B
���R�̂悤�ɏo���͌����Ȃ��B
���{�݂Ƃ������������Ă������A�z�����Ă������������Ԃ��B
����ɁA���̂܂ܐi�߂��������Ȃ��_���T�C�g��˂������ČΒ�ɐi�ނ��ƂɂȂ邾�낤�B
�₽���ǂ̌������ɁA�_�������ߍ�����Ȑ�����A�z���鎖���~�߂��Ȃ��B
���炩�ɋْ����Ă���������������B
����ł��ق��ĕ����Ă����ƁA��킾���������ɁA�ŏ��ٕ̈ς��c�B
�E���i�R���j�̕ǖʁA�X�v�����O���C���i�A�[�`�̉��[�j�ɉ����Ă̑�ʏo�����B

�ǖʂ���тƂȂ�A�����I�ɂ͐����ƂȂ蓴���֗N�o�����n�����́A��n�ł���Ҕ��B�̏������S�ɒ��߂�قǂł������B
���C�g�������Ȃ���Ή������̐��E�B
�����ɂ��킵�Ȃ��g�ł��ʂ�����̂͊���Ȃ��B
�_���ƊW�Ȃ��Ƃ͎v�����A�ꌩ���ԂȂǖ��������Ɍ�����R���N���[�g�ǂ���̑�ʏo���ɂ́A�Ȃ��A�u���Ă͂Ȃ�Ȃ����m�v�����Ă��܂����S�����������B
�����āA
���̏����Ȉٕς́A���傫�ȕʂٕ̈ς̎n�܂�ɉ߂��Ȃ������B
���ǂ��c�B

���ǂ��c�@�l�b�g���B
���S�Ȃ����i�q�̗��q���Ɍ�������p詓��ŁA�S���f�x���Ƃ������̂��������Ƃ͂Ȃ��B
�����A���ǃR���N���[�g�̕��H�������I�ł���A���̂悤�ɒn�R���`���Ă����́A����I�ȏ��ł͂��邪���������Ă����B
���̑����͑����m�푈�̍Œ�����ŏ����̍H���ɂ�������̂ŁA�R���N���[�g�̐ߖ��H���Z�k��ړI�Ƃ������̂Ǝv����B
�������{詓��͏��a40�N�㒆�Ղɗ��p���ꂽ���̂ł���A�O��Ƃ͎���قȂ�B
�Ԃ����Ⴏ�A�u���v�����炱�̒��x�ŏ\�����Ɣ��f���ꂽ�̂��낤�B
�����@���ɕ����̂��A�ǂ��l�b�g�̑��݂ł���B

�l�b�g�͔�������I
���S�͎d�������J�Ȃ��ƂŒm���Ă���A����͂��̍H�앨�S�ʂɂ��Ă������邱�Ƃł���B
�펞���ɍ��ꂽ�����I�ɑf�x���c��詓��ł����Ă��A����͒n�R�̈��萫���\�������āA���s���̗�Ԃɗ�����������悤�Ȏ��̂��N����Ȃ����Ƃ��A�����Ɗ�ɂ���Ċm���߂���ł̍ŏ����x�̑Ë��Ȃ̂ł���B
�����炱���A�f�x�����Ɋ����āu�l�b�g�v�������Ē��r���[�ȗ��Ζh��������悤�ȗ���������Ƃ͂Ȃ��B�i�������Ƃ��Ȃ������ŁA���݂��Ȃ��Ƃ͂����Ȃ����j
�������A����詓��́u���v�䂦�ɂ��Ȃ藐�\�ȍ������Ă���B
�����āA�l�b�g�̌������Ɍ����Ă���ǂ͑S�R���肵�Ă��Ȃ��I
���Ƀ{���{���ƕ���Ă���̂��B
�f�l�ڂɂ��ǂ͔��ɕ������Ă���A���s���̏Ռ��ŗ����N����\���͍������Ɍ�����B

���܂��v���I�ȕ���͋N���Ă��Ȃ��悤�����A��������Ԃ̖��Ǝv����B
�₪�ė����������Ȃ��Ȃ����l�b�g�͔j��A�����͊��I�̊C�ƂȂ邾�낤�B
�ڂׂ̍��ȍ��͊��Ɉ��Ă��Ă���B
���ꂱ���A�R�N�ɖ����Ȃ����Ԃ����g����Ώ\���������u���g���l���v�̓���Ȏ�����ے�����i�F���낤�B

���S�̃C���[�W���炩�����ꂽ�A���̏ꂵ�̂��̍\�����B
�O����͌����Ȃ����n�ɂ������Ďn�܂������ǂ̊ȈՎ{�H�i�蔲���Ƃ͌����܂��j�B
����́A�g�Ō�h�܂ł����Ƒ����Ă����B
�����Ă���Ƃ����A�J�[�u�������������B
�������Ĉȗ��A���X�ƍ��J�[�u�������Ă���B
�W�X�ƃJ�[�u���������ߕ������͂߂Ȃ����A��������60�����炢�͓]�i���Ă���̂ł͂Ȃ����B
��������A����400���B
�܂��I���͌����Ȃ��B

�l�b�g������Ă���́A��_�ɂ����ǂ̔����ȏオ�f�x�ƂȂ����B
�������A����Ȉٗl�ȏɂȂ��Ă��Ă��A�Ȃ����̍d���g���S�炵���h�i���_����͎����l����C���[�W�ɉ߂��Ȃ����j�͎����Ă��Ȃ������B
�킴�킴�A�R���N���[�g�̊������ĕ����ɑҔ��B��ݒu���Ă���B
�l�b�g�̕����͊����Ă̂Ȃ����A�\���Ҕ��B����ɂȂ�قǍL���ɂ�������炸�B
�����āA�R���N���[�g�̊������ĕ���I��ŁA�����炭�͈�x���g���Ă��Ȃ��悤�Ȕ����Ҕ��B���c�B

�����I
���߂Č��ꂽ�A����詓��������ł��������Ƃ̏B
�����܂ł́A�Ȃ��u�������v�̔p�g���l��������Ă���悤�Ȋ������Ă����B
�������̋N�_�A�i�q���ѐ��ƕ��鉺�V�c�A��������̃L���|�X�g�B
�u26�v�Ɓu1�^2�v�L�����[�g���ł���B
�����Ɏc���ꂽ�A�����炭�B��̃L���|�X�g���B
�s����ɏo���ł͂Ȃ��ʂ̂��̂�����������B
����̓}�O���C�g�̓���ɂƂ�����A�i�C�t�̂悤�ȗ₽�����˂�Ԃ��Ă����B