
 接近! 最奥隧道2004.9.23 9:36
接近! 最奥隧道2004.9.23 9:36-

粒様二又から様ノ沢を遡りはじめ、30分を経過したとき、突如眼前に滝が出現した。
気が付けば、もう両岸に川原など無かった。
昨日に比べれば、遙かに上流にいたこともあって、断然水量が少なく感じられていたから、もう、何も我々の行く手を邪魔する物はないとさえ思っていた。
強いて言うならば、最奥隧道は断崖に口を開けていることが分かっていたから、その最終アプローチに懸念が残る程度であった。
だが、最奥隧道を目にする前に、我々は危険な谷へと足を踏み入れていた。
少し、油断していた。

ここで初めて、沢靴にのみ全てを賭けて歩いた。
滑らかな濡れた斜面が、下がるほど傾斜を直角に近づけつつ激流に接していた。
流れから少しでも離れる安全な進路を探したが、沢底から手がかりとなる木々までは相当離れており登ることは相当に難しい、手の届く範囲にも一見手がかりとなりそうな草があったが、それは岩盤上の薄い土に生えているだけで、体重をかけると程なく剥がれ落ちた。
我々には、直接流れに身を沈めて滝を遡行する道具も技術も覚悟もないので、慎重に慎重に、沢靴のグリップ力に全体重を賭けることになった。
滑り落ちても溺死はすまいが、滝壺は底なしに蒼い …恐すぎる。

この小さな滝を皮切りにして、沢の様子は豹変した。
連続する滑らかな淵。
川原はなくなり、代わりに水際まで稜線より直接落ちるスラブが接する。
この段階で、両岸ともに森は消失し、そこに軌道敷きなどあろう筈もないと感じた。
先ほどまで確かに燦々と太陽に照らし出されていた、我々の心地よい道は、消えた。
今眼前にあるのは、冷たく、暗く蒼い、崖と瀞の水路のような沢である。
不安な気持ちは、一気に増した。
「何とかなるだろう」という楽観は、先ほどのごくごく小さな滝越えで、木っ端微塵に吹き飛ばされていた。
そして、正直言って、こんな場所に隧道が有ろう筈もないと、この時から思った。
私の中には、この先に隧道などない方が、決定的な挫折を味あわないで済むのではないかという、嫌な予感。
恥ずかしくも、大変に後ろ向きな気持ちが生まれた。

右岸に落ちる滝。
稜線がそのまま滝の落ち口になっており、雨天時や、今日のような雨の後、ごく短い時間だけ落ちる、落差200mの滝である。
360度をお見せできないのが残念だが、左右共にこんな有様である。
多くの木々がスラブにへばり付いているが、とても素人が無装備で往来できる雰囲気ではない。
突破口がどこかにあるとしても、それを見つけるまでには決定的な滑落に見舞われそうだ。
当初、左岸のスラブと稜線を挟んで、僅か2kmまで接近しているノロ川上流の林道を、アプローチルートとして利用する案もあった。
だが、その案を選ばなくて良かったと、この時思った。
おそらく、無事に降りることは出来なかっただろう。

午前9時44分。
左岸に僅かな川原が現れ、我々の濡れた羽を休めさせた。
もう、私のデジカメは、この日のスタート時点で湿り気を内部まで浸透させており、不調だった。
沈胴式のレンズが迫り上がらなくなることがしばしばで、その都度、指で引っ張って引き出していた。
そんな末期的なデジカメは、もう正常にホワイトバランスを調整することが出来ず、空は全て白飛びしている。
しかし、不思議と今その“遺写”達を見ると、この谷を良く描写していると思う。
後ほど見て頂くHAMAMI氏の正常なカメラの画像が、客観的な景色としては正解である。
だが、薄暗い谷底から見上げる空は、まぶしさで白く見えたし、けっして辿り着けぬような断崖の上は、まるで存在自体がないかのような違和感があった。
街で見ているいつもの空と同じ空なのに、谷底は余りにも空から遠い気がしたのである。


それぞれ、上流に向かって歩く我々から左側(右岸)と、右側(左岸)の景色である。
右岸は日陰であり、未だ大量の水がスラブを滑り落ちて合流している。
一つ一つの滝が、今まで見たこともないような巨瀑である。
対して左岸は、早くも乾き始めている。
そのスラブの圧倒的な高さは右岸に勝り、稜線の向こうには比較的穏やかな穏やかなノロ川高原が広がるはずだが、隔絶している。
もし、最奥隧道が、森林軌道の隧道なのだとしたら、この両岸のいずれかに、軌道が通っていたことになる。
あり得るのか? そんなことが。
私には、不可能だと思った。
しかし、実際がどうかは、隧道に入らねば、恐らく分からないだろうと思った。
だから、前進したいと願った。

 遭遇! 最奥隧道9:53
遭遇! 最奥隧道9:53-

狭い川原を越えると、再び細い水路となった。
幸いに流れは淀むほどに遅く、さして深さもなかった。
ここは、見た目とは裏腹に容易に谷底を前進できた。
そして、この隙間をすり抜けた我々の眼前に、穏やかな砂の中州が現れた。
まるでホールのように、谷底に開けて広い。
その先は、再び狭い淵だったが、飛沫が淵の間を吹き抜けているのが、煙るようであった。
轟音もホールに轟いている。
一つ一つの事象を文章にすれば、恐らく私が力尽きるほどに長くなる。
我々の前に現れた景色は、複雑怪奇な、ものだった。
そして、それこそが、最奥隧道として追い求めてきたモノの、在る場所であった。

どこに隧道があるのか、
見つけられただろうか?

これが最奥隧道だ!
お分かりだろうか。
…皆様にストレスを与えるのも悪いので、私のカメラにはここで引退願って、HAMAMI氏のカメラの鮮明な映像をお伝えしよう。

我々は、発見した瞬間に叫んだ。
「あったぞ!」と。
その興奮たるや、おちゃらけ抜きで、脳内のアドレナリンが垂れ流しとなる程であったが、その収束は異常に早かった。
私など、恐らく二人もそうだったと思うが、見た数秒後には、或いは1秒以内で、
無理っぽい
と、直感した。
私は、こと沢歩きや山歩きについて素人に過ぎないが、それでも、廃道攻略などの目的で、様々な地形を歩いた経験がある。
大概は一人きりであったから、己の感覚だけで、行くか退くかを決めてきた経験がある。
そして、少し自慢だが、そうしてこれまでの山チャリ生活を無事に過ごしてきた経験がある。
その経験則と言うべき勘が、見た瞬間に「無理」の二文字を計算し、私の顔面に出力した。
結果、私の顔面は喜びの口元のまま、目は曇っていたはずだ。
表情は、堅かったに違いない。
直感的に無理だと思った場所は、おそらくよほど発想の転換がない限り、無理だろうという自負がある。
そして、私は隧道の直下まで辿り着けたとしても、あの垂直に近い断崖を登ることが出来ないことを知っていた。
試したわけではないが、己の力量は見極めているつもりだ。
私の、「ランドエクスプローラー」としての踏破力を、完全に勝る極悪地形である。
少なくとも、私には、この地形は攻略できない。
そう、この段階で半ば確信してしまった。
結果から言おう。
この後、我々は撤退した。
やはり、無理だった。
以下では、我々がやろうとしたことを、簡潔に述べるに留める。
非常に悔しい思いを、我々はした。
特に、くじ氏と私は、この隧道を、ルートファインダーの矜恃に賭けて素手で攻略しようと意気込んでいたから、その落胆は大きすぎた。
だから、余り多くを語らないことを、どうか許して欲しいのだ。
我々は、2005年の夏に、リベンジを決めている。
- 敗者の格闘
-
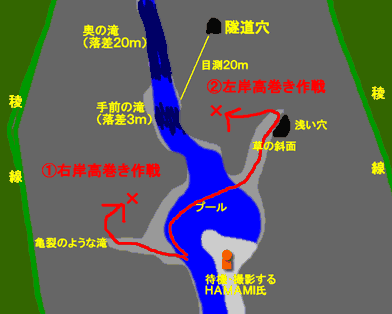
われわれは、この未曾有の難所に対し、隧道へと接近できる手だてを企てた。
現地の地形だが、概容としては右の通りである。
三人がたどり着いたプールは、一部が陸となっており、安定した休憩点であった。
しかし、ここからは前方にクランク状になった淵が見えており、この淵の奥から飛沫と轟音が吹き出している。
淵はまさに水路と言うべきもので、エメラルドブルーに見える水深が如何ほどなのかは、体を沈めてみるまでもない。
仮に泳いで進むことが出来ても、陸に上がる手だてはなく、その先に続く3m程度の滝(複数が存在する可能性もある)を遡行して隧道直下へ至れる希望は薄い。
というか、技術的にも我々には不可能なコースだった。
そうなると、このプールから始まる地形を高巻きする以外に手はなく、まずは右岸の高巻きを実施に移した。

そして、この右岸の高巻きには失敗し、撤収した。
斜面にへばり付く姿を誰も撮影しておらず、私自身、それどころでない斜面で、結局一切画像の残らない試行となった。
おおよそ10分間、退いたり進んだりを、プール直上10m程度の薄く木々がへばり付くスラブで行ったものの、登った私とくじ氏が共に断念を宣言したため、この高巻きは終了した。
ザイルなど、適宜体を支持できる安定があれば、まだ進むべき余地はあったと思うが、靴裏にフェルト総張りでスパイクの付いていない沢靴では、土が薄く載った斜面での安定が悪すぎて、命綱無しでは余りにも危険というか、落ちることが目に見えていたし、第一の滝を越えても隧道へ至れる希望も薄く、リスクが高すぎると判断した。
ぶっちゃけ、恐すぎて戻ったと言って差し支えなし。

次に狙ったのは、隧道が見えているのと同じ左岸の高巻きである。
旨く辿り着けるルートが見つけられれば、隧道へと直接接近できる期待があった。
しかし、左岸へ至るには、まずはこのプールを渡らねばならなかった。
そこが、最初の大きな難所となる。
プールは流れのある部分が深くなっており、左岸に行くにはどうしても、エメラルドブルーの場所を、3m程度は渡らねばならなかった。
我々は泳ぎが達者なわけではなく、取材道具を持った状態では尚更、胸よりも深い水深は恐ろしく感じる。
しかし、そこに見えている隧道へと辿り着きたいという欲求もまた、そう易々と再来できぬことも分かっていたし、大きなものであった。
結局、私は命の次に大切な取材道具であるカメラを“秘密兵器”である海外製のビニールパックに入れて、腰へと結わき、くじ氏と共にプールへ進んだ。
写真は、深くなっていく足元に戸惑う我々の姿。
すでに、私の腰では防水パックがカメラを入れたまま、水に浮かんでいる。

そしてこれが、今回の撮影で唯一、隧道直下の連滝を撮すことに成功した一枚である。
胸までの水深に耐えて、くじ氏が撮影している。
写真を見ると、滝は二つだけではなく、少なくとも3つ在ることが分かる。
そして、淵の両岸は滑らかで手がかりの全くないゴルジュになっており、我々素人にはどうすることも出来ない領域であると痛感した。
水際から2m程度の位置には豊富に植生もあるが、これらは手がかりになるほど強くはなく、足が完全に支持できぬ状況では移動には使えない。
そもそも、水中に足がかりが無いと、草地まで手を伸ばすことも容易でなかった。
顔に吹き付ける飛沫を含む突風が、我々を嘲るように、非情な現実を知らしめる。

左の写真は、「アクアパック」という腰の防水袋から取り出した、愛機FinePixF401が遺した最期の写真である。
水没直前に、満身創痍、瀕死のデジカメが、滴るほどに水を受けながら、それでも撮した一枚だ。
この撮影を終えた後、突如電源が入らなくなってしまう。
それを見届けた後、サブ機と共に、アクアパックに仕舞い、さらなる深みへと進んだ。
乾きさえすれば、またいつものように、復活するの踏んでのことだったのだが…。
この初代FinePixF401は、2002年8月の阿仁行きでデビュー以来、2年強の間、ほぼ唯一の撮影道具として、約70回の山チャリに参戦した。
まさに「山行が」と共にあったカメラといって良い。
70回の後半には、本体の物理的不調は深くなり、何度かサブ機の力を借りたこともあったが、最期まで良く勤め上げた。
道具には余り愛着を持たない私をして、この死は、悼まれて仕方がなかった。
現在は、2代目の同機を使っている。

プールは、足が着くが、着かないが、本当にギリギリくらいの水深だった。
私は、深みにはまってしまい、約3mほど、そのまま泳いでしまった。
その必要が在ったわけではないのだが、どうせ全身濡れていたり、寒くはあったが日光は心地よかったので、ちょっと羽目を外してしまった。
数年ぶりにほんの少しだが泳ぎをして、めちゃくちゃ下手くそになっていて悲しかった。
多分、もう25mも泳げないな。
写真では、くじさんが深いところに差し掛かっている。
私は、泳ぎ終えて震えていた。
このあと、二人で正面の草むらを登ることが出来た。

草むらの先は、再び垂直に近いスラブに阻まれ、進路を完全に絶たれた。
こちらは、先に行った右岸よりも遙かに、打つ手無しという実感だった。
その上、少しは隧道が近くに見えるかと期待したが、張り出したオーバーハングが邪魔で、全く見えなかった。
代わりに、脇の岩肌と草むらの境に、奥行き1m、幅2mほどの穴が空いていたが、もちろん隧道とは関連がない。
自然に出来たものだろう。
実際、帰宅後に聞いた、この沢を遡行した方の話では、ここを超えるには、最初に断念した右岸しかあり得ないとのことであった。
まだまだ、我々には… 修行が足りなかった!

HAMAMI氏の10倍ズームレンズで捉えた、不到の隧道。
はたして、これは自然の地形なのか、それとも…。
林鉄の遺構であるという線は、極めて少ないと言わざるを得ない。
根拠としては、隧道直前の数百メートルに亘り、両岸とも猛烈な懸崖であり、そこを軌道が通う余地はないこと。
かりに延長100mを超える長大な桟橋を組んでいたにしても、沢底にレールや遺物が一切無いのは不自然であること、などである。
また、記録には粒様線の延長が10296mとあり、これは我々が遡った距離と同程度あるが、おそらく粒様二又より粒沢に入っていたのではないかと推測する。
すなわち、我々は二又直前でレールを見失ったが、あのまま粒沢へと続いていったのではないかという想像だ。
次回の調査では、この点も判明できればと思う。
それにしても、見れば見るほど、人工物っぽい坑門をしている。
見える深さは数メートルあり岩の凹みではないだろうし、甌穴などが発生する場所でもない。
マタギの避難場所?
営林署の作業道?
集材用の通路?
悔しいが、今回我々が持ち帰ることを許された情報は、以上である。
午前10時43分、撤収。

この谷底には、
まだ我々の与り知らぬ、多くの秘密か隠されているに違いない。
神の谷とよばれし聖域。
山行がを、いとも容易く弾き返した
通称「魚止めの滝」。
その上部を知る者は限られるが、
恐ろしい深さの淵の先には、
天を突く、滝があるという。
人はそれを、九階の滝と呼んでいる。
