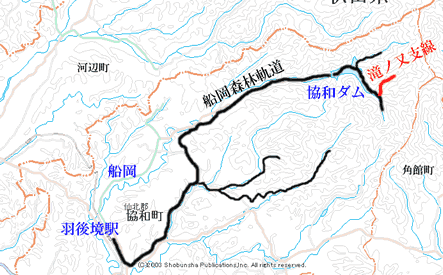
今回紹介するのは、船岡森林軌道滝ノ又支線という路線だ。
県都秋田市から東方25kmに役場を置く仙北郡協和町の山中が舞台である。
地図をご覧頂ければお分かりのように、この滝ノ又支線というのは、船岡林鉄のもっとも奥にあった支線である。
本来ならば、羽後境駅付近から始まる長い長いレポの最後に到達する、最終章と言うべき部分なのだろう。
さて、この短い支線の歴史を簡単に紹介しよう。
大正3年頃に羽後境駅から宮田又沢へと開設された宮田又森林軌道が、昭和8年に山越えで船岡川流域に伸び、これを船岡支線と称した。
船岡支線はその後も徐々に延伸し、現在の協和ダムの上流、角館町との境を成す朝日又沢上端の主稜線近くまで伸びていった。
さらに、支線も幾つか開設されたが、朝日又沢の支流である滝又沢沿いに、昭和33年、2.1kmの延長をもって開設された路線が、この滝ノ又支線である。
特にその経路上に集落はなく、純粋な伐採用作業支線であったが、特筆すべきは、その開設年度の遅さだ。
林鉄は、全国的に昭和30年代より順次トラック道などへ転用されはじめ、いわば終焉の時代に入っていた。
その趨勢のなか、新たな開設路線もほとんど無くなっていく。
昭和33年、そして34年が、事実上新規開設の最終年度だったと言って良い。
本路線の開設年度は、昭和33年。
そして、廃止は昭和43年だ。
僅か、10年間の道だった。
 秋田県仙北郡協和町 朝日又沢口2004.4.29 9:45
秋田県仙北郡協和町 朝日又沢口2004.4.29 9:45

そもそも、この支線の探索計画は、私の中になかった。
存在は、「JTBキャンブックス刊全国森林鉄道」の巻末資料によって知ってはいたが、延長2.1kmの行き止まり路線。
しかも、協和町中心地から東北東20kmという、不用意には近づけない奥地立地である。
そのうえ、船岡林鉄自体の探索も、この時点では起点から10km程の一部を確認していただけだった。
いきなり未知の終点付近の、さらに支線などと言う、“ヘタ”の部分に行こうとするわけもなかった。
写真は、協和ダムの上流にある、一般県道316号唐松宇津野線の終点だ。
この分岐点の正面が、さらに奥地へと向かう朝日又沢林道。
右は、県道とはダム湖対岸を通ってダムサイトへ戻る、美山湖林道だ。


この日の探索の原因となったのは、森吉林鉄の活動ではもうお馴染みの、パタリン氏である。
彼が、興奮気味なメールを私の山行がポストに叩き込んだのは、この約1週間前だった。
どうやら、彼は釣り仲間と一緒に、これから向かう滝又沢へと渓流釣りに行ったらしいのだ。
そして、そこで林鉄跡を「ハケーン!(←本人談)」したとのこと。
しかも、その林鉄跡が、とにかく、もう、ものすごく、「最高ですかー!」「最高でーす!(←いずれも本人談)」だったらしいのだ。
「ロケーション最高!(←本…以下略)」だそうなのだ。
彼のメールの最後は、こう結んでいた。
ただし、行くとなったら人数を呼んでいって下さい。
…それって、私に死んでこいと言っているようなもんなんじゃ…。
なぜ?って
その支流は地元の人でも行かない(熊が良くでる場所だそうです)
こんなに勧めておいて、一人で行くなとは…。
私の性格を知ってるくせに。
いくさ、一人でも。 行きたい時に、行くのだよ!

しかし、それにしても彼のメールは詳細情報が満載であった。
しかも、「ミニにはなり得ないレポートが出来上がる」などと、山行がの更新をも考えてくれてもいた。
アプローチの場所も、詳細に教えてくれた。
隧道はないと言うことも記されていた。
私は、この言葉に弱かった。
正直、「えー。隧道ね−のー。」である。
私の、貴重な休みを割いてまで行く価値があるのかと、率直に言いますと、まだ半信半疑であった。
しかも、この一帯は何年か前も走っていて、ほんと、林鉄のためだけに、こんな山奥までチャリでえっちらおっちらと来るのは、抵抗もあった。
気分的に乗らないのが、本音であったのだ。
でもなー、「ロケーション最高」らしいし、な…。
なお、写真は朝日又沢林道に入って300mほどの地点、道の脇に立つ「盛秋幹線(鉄塔だ)NO127 NO128」の表示である。

彼が林鉄に遭遇したのは、そもそも釣りの最中の偶然だったわけで、元より軌道跡を辿って歩いたわけではなかった。
彼が私に教えてくれたアプローチは、上の写真の看板の場所を目印に、脇を流れる朝日又沢を渡渉して、鉄塔保守歩道を上っていくと行き着く、というものであった。
なるほど、そういう行き方もあるだろうが、私の目的はあくまで軌道。
途中からではなくて、この支線の起点から攻めていきたい。
どこに入り口があるのかはまだ分からないが、まずは先へと進んでみよう。
地形的に見てここまでの軌道は、いま走っている林道と重なっているはずだ。
どこで、分岐するのか。
写真の部分を渡渉することはやめ、林道を上流へ向け進むことにした。

林道入り口から約1km。
ここで林道は急な登りでやや谷底から離れて、このすぐ先の大倉沢橋に向かう。
明らかに、この勾配は林鉄には無理だ。
となると、丁度登りの始まりの地点で左に降りていく、この脇道が、めちゃめちゃ怪しい。
轍の薄い脇道へ入る。

30mほどで、この道は消滅していた。
朝日又沢と、大倉沢の二つの波濤が、道路を削り取っており、これ以上は無い。
と、対岸になにやら木の構造物がある。
炭のような色をしたそれは、どうも橋台にように見える。
木製の橋台など聞いたことがないが、地形的にここで対岸に渡っていたのだと考えれば、こちらの岸にこれ以上道が無いことも頷ける。
船岡林鉄本線も、目指す支線も、ここで対岸に行ってしまうようだ。
しかし、チャリは置いていくとしても、単身でもこの激流は危険だ。
もう少し、まともな渡渉地点を探すことにしよう。
とりあえず、大倉沢(写真手前の沢)の水量が多いようなので、本流をもう少し上流へ行けば、水量も減るだろう。
 朝日又沢の終点
朝日又沢の終点
-

林道へと戻り、大倉沢橋の手前の、最も高度が上がった場所で、先ほど対岸に見た橋台らしき地形を撮影。
その背後には、妙に広い広場がある。
なんかキャンプ場のようでもあるが、そこへ行く橋も道もなく、そんな筈もない。
ズリ山のような雰囲気もあるが、この辺に操業した鉱山の話も聞かない。
また、橋台の裏に期待された林鉄の痕跡は見あたらないが、とりあえず、この対岸へ向かうことが必要だろう。

対岸へ渡るつもりが、惰性で林道本線を続走していた。
馬鹿だな。おれ。
しかも、この道の嫌すぎる顛末は、忘れた訳じゃないし。
もしや復活?と言う期待は甘くて、やっぱ数年前と同じに、大倉沢橋の先は間もなく荒れてきた。

冬の傷跡を含めても、この朝日又沢林道の終点付近は、いっつもこんな感じだ。
精々、めちゃ荒れてる区間が長いか、凄く長いかくらいの違いだ。
カーブミラーなどが設置されており、一応は車道として開設されているし、地図上ももう少し上流まで続いているのだが、結局は行き止まりだ。
それなのに、なぜか来てしまった。
この林道って、もの凄く古い地図では角館まで続いている。
それが、どうしても気になってしまう。
実際は、かつて人が往来する事はあったようだが、車道など無い。
分かっていても、来てしまう場所。

さて、途切れ途切れになった林道はもう引き返すとして、折角だから、朝日又沢沿いにあったはずの船岡林鉄本線の終点を確定してしまいたい。
それは地形的に見て、この写真のあたりだと思う。
この上流は、一気に傾斜がきつくなり、沢も狭まる。
しかも、高巻きしているような痕跡もない。
このあたりが終点だろうと言う結論に至った。
大倉沢橋からは約500mほどの地点だ。

大倉沢橋付近に新しい渡渉点を求め引き返す。
下りながら見えるのは、まだ春らしさの薄い茶色の山肌。
この時期の山って、どこまでも行けるんじゃないか、って気にさせる。
実際にそんな訳はないのだけど。
稜線の木の一本一本、その地肌の微妙な起伏まで見通せると、山に対して、少しだけ気持ちが大きくなる。
あぶない。 危ないよ、その油断。

さて、大倉沢橋傍のここにチャリを置いて、いよいよ林鉄へと向かう。
林道の為に盛り土されたらしい斜面の下に、細い朝日又沢の清流がある。
藪は深いが距離は短く、体重で押しながら無理矢理突破。
こうして、沢べりに降りた。

 滝ノ又支線のはじまり。10:15
滝ノ又支線のはじまり。10:15-

確かに、期待通りに沢は狭かった。
しかし、狭い分流れは速かった。
そして、深い。
手間こそ掛かるが、靴と靴下を脱いで裸足で渡るならば、もっと幅が広くて緩やかな場所を選んだ方がよいだろうか・
しかし、この幅ならば、一発勝負の「Aボタン」もチャレンジする価値がある。
「Bダッシュ」するスペースがないので、立ち幅跳びだ。
面倒くさがり屋の私、ここで一発ジャンプに、失敗。
正確には、対岸に届きはしたが、着地と同時に後ろへ転倒しケツから水へドボンと言う、一歩間違えれば笑えない、でも大笑いの大失態。
やってもうた。
とりあえず、渡れはしたが…。
尻つめてー。

さて、ここがさっき対岸に見た荒れ地だ。
方向的には、向かって左(南側)に朝日又沢と大倉沢の合流点を一挙に渡っていたと思われる橋の橋台が。
正面は目指す支線の入り口。
右が、終点近い軌道の本線だ。
まずは、この広場の正体が知りたいと、あたりを探索。

これが、荒れ地の南側、沢に面した橋台の付け根部分だ。
もとの地形は鉄砲水などで破壊されているのか、あったかも知れない築堤などは見られない。
荒れ地上にも、建築物があったような形跡は無く、ますます謎の荒れ地だ。
広さは、普通の体育館くらいだ。

荒れ地の一角には、写真のような真っ黒い石片が多数落ちていた。
明らかに、熱で一旦溶けたものだ。
たき火でこうまでなるだろうか?
あるいは、これは石炭なのか?
分からない。
下流のダムが出来る以前にも、ここまで奥地に集落があったという話は聞かず、ますます分からない。
山火事でもあったか?

写真は、本流沿いを上流に向かう、本線軌道の跡と思われる部分。
林道とは朝日又沢を挟んで、さらに500m程度はこの様な軌道跡が続いていることを、林道より確認済みだ。
本線ではなく、「ロケーション最高」という、支線へと私は向かう。
この荒れ地の広場が、分岐点だった。
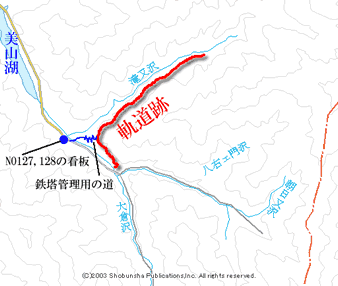
現地の地図。
これから向かう軌道は、ここから約2kmほど、滝又沢沿いに伸びる。
まずは朝日又沢に沿って500mほど戻るが、この部分で高度を稼ぐのだ。
滝又沢は、その名の通り滝の多い急な沢で、素直に谷底に軌道を引いたのでは勾配が持たなかったのだろう。
あえて、図のような遠回りをして、滝又沢奥地を目指している。
この線形、今後の林鉄探索の一例として良い勉強になった。

広場の一画、期待した場所から、期待したとおりの道が始まっていた。
最初は乗り気でなかった私も、ここに来て俄然やる気が湧いてきた。
なんといっても、早速多数の枕木が半ば埋もれつつも、整然と並んで待っていたのには、萌えざるを得なかった。
さあ! 熊対策のラジオ(何年も前に買って、道中の暇つぶしに使っていた携帯ラジオを久々に持ってきていたのだ。)を取り出して…。
あ、 あれ。
ない、 ないよ。らじおない。
もしや、さっきすっころんだ時に??
今度ばかりは、私の命綱になりそうなラジオだ。
無いではすまされない。落としたでは許されない。
だが、無情にもラジオは無かった。
転んだ場所にも、無かった。
熊たんの、胸の鼓動が、脳裏に浮かぶ。
嫌な汗が、出てきた…。
 独りで山に入るのは危険なので、慎みましょう10:19
独りで山に入るのは危険なので、慎みましょう10:19-

ここまで来て引き返すのも癪だ。
熊のことは、自分が唄うことでフォローしよう。
なーに、いつも独りでも出会わないじゃないか。
そういや…、パタ氏が、昨日電話で念を押してたっけ。
「2・3日前にも、その辺で猟友会の人が熊に襲われて怪我しているから…」
… … 。
…今度ばかりは、熊たんの顔が脳裏を離れない。
必要以上に意識しないで行こうとしても、林道も見えない奥沢に向かうのだという事実は、私の強気をもひしゃげさせる。
負けるな、負けるな私の運の良さ。
運が良ければ、熊になんて会わないさ。
運が良ければ…。

さて、こうして立ち止まっている方が危険だ。
身の安全を考えて、早々に探索を終えよう。
行くぞ、一気に行っくぞ。
早速にして、登りが始まる。
斜面に築かれた切り取りに、幅2m、平均勾配3%くらいの道が続いている。
廃止後は一切転用されなかったようで、枕木はほぼ全て存置。
軌道敷上からは姿を消しているものの、レールすら斜面に幾つも落ちている。

犬釘なお黒光りし、しっかりと固定されている枕木。
しょっぱなからの、この保存状態の良さ。
パタリン氏の「ロケーション最高」が、何か現実感を伴って、迫ってきた気がする。
熊たんの荒い息遣いも、なーんか迫っているような気がして、何度も振り返ってしまう臆病者の私。

点々と枕木の埋まった軌道跡の細道。
まだ、左の下に流れるは朝日又沢だ。
しかし、進むほどその水面までの距離は遠ざかっていく。
間もなく、雑木林の中に流れの気配は消えていった。
路面は、軌道敷きとしてしっかり固められていたお陰で、未だ藪化せずに持っている。

人の気配のない森にあって、久々に見つけた人の痕跡。
といっても、ゴミである。
それは、ファンタグレープの250ml細缶だった。
廃道と言えば、まずはジョージアオリジナルと相場が決まっているが、次いでよく見るのが、このファンタグレープだ。
なぜだ。昔はそれしか飲み物がなかったのか?!
昔語りのように、コンビニ業界にも伝わる話 「昔はジョージアオリジナルが、毎日100本以上売れていた」は、事実だったのかも知れない。
いまは、精々一日5本くらいだが。

高度を上げれば、ますます沢から離れていくはずなのに、進むほどに轟くような水音が近づいてきた。
これが、いよいよ滝又沢に近づいている何よりの証拠だった。
廃道であるが、極めて歩きやすく、まるで登山道か何かのような道。
パタ氏達のように釣りや、或いは山菜採りなどに入山する者が好んで歩いているのだろう。(地形図にもない道だが)
進むほどに、気持ちが高揚してくるのが分かる。
林鉄好きならば、もうここまででも、「ロケーションかなり良し」と言う印象を持つのではないだろうか。
まだ少し早いかも知れないが、この段階で私はもう、「パタさんありがとう!」と思った。

と、突然真新しい人工物が現れた。
ここが、パタ氏達が軌道に合流したという地点だろう。
滝又沢と朝日又沢との出合いから九十九折りで登ってくる鉄塔保守歩道が、ここで軌道敷きを十字に切り、さらに上部、稜線上にある鉄塔を目指して続いている。
電力会社のCMって最近はとんと見ないが、CMで感じた保守員達の「かっこいいな」と言う印象は、山歩きを好む人にとっては真かもしれない。
登山道よりも険しい場所も少なくないだろう保守歩道を年中歩いている彼らは、確かに格好いい。

ここまで、広場から400mほど。
時間にして10分間の徒歩だった。
いよいよ、パタ氏が「ロケーション最高」と感じた区間だ。
あと、1.7kmほどの道のりに、何が待ち受けているのだろうか。
春になりかけの森は、風通しも、陽当たりも格別。
それでいて、冬ではないこの暖かさ。
寝っ転がったら、気持ちいいだろな。
熊たんに見つからない保証があるなら、この辺でゴロゴロするのも悪く無さそうだ。
気持ちいいよー。

!
すっ、すごい。
木橋だ。
木橋が、木橋が原型留めてる。
太い太い、豪快な木橋だ。
この遭遇をなど、はじまりに過ぎなかった、だが、そのことをまだ知らない私は、はしゃいだ。
ろっ、ロケーション最高!!
後編へ
| 当サイトは、皆様からの情報提供、資料提供をお待ちしております。 →情報・資料提供窓口 | |
|
このレポートの最終回ないし最新の回の「この位置」に、レポートへのご感想など自由にコメントを入力していただける欄と、いただいたコメントの紹介ページを用意しております。あなたの評価、感想、体験談など、ぜひお寄せください。 【トップページに戻る】 |
|