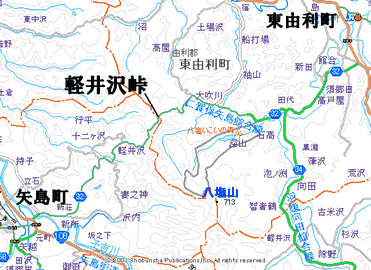
秋田県主要地方道32号「仁賀保矢島舘合線」は、日本海に面した由利郡仁賀保町平沢から鳥海山北麓の高原地帯を縦断し、同郡矢島町元町を経由し、八塩山北稜線を越えて同郡東由利町舘合に至る、40km余りの路線である。
由利郡内を東西に横断する同路線は、国道7号線108号線107号線とをバイパス的に連絡するが、経路は山がちで、起伏が非常に激しい。
仁賀保矢島間については、鳥海高原観光の主要路線となっており整備も大分進んでいるものの、今回紹介する矢島東由利間の15kmには、未だ砂利道が残る。
この峠区間は、これといった名称がないようだが、便宜上付近の集落名をとり、軽井沢峠とさせてもらう。
矢島側から入り、東由利の下りで最初に出会う大吹川集落までをやや駆け足で紹介していこう。

この日は生憎の雨。
出発地はいつもの自宅ではなく、訳あって矢島町だった。
時刻は早朝、午前5時37分。
矢島町の中心部を通る国道108号線から分岐する県道32号線だが、国道にすらほとんど往来はない。
写真は、曇天に映えない分岐の青看。
ちょうどこの探索時には、その半年前に尊い人命と共に崩れ去った国道108号線の迂回路として、これから行く県道32号線の一部が利用されていたのだ。
国道は完全に不通となっており(2004年10月復旧しました)、この青看も、本来は正面が国道で行き先も「本荘」なのだが、上張りのシールで右折県道32号線が「本荘方面」と案内されていた。
もともとの目的地は、「新庄」(これは矢島町町内の字だ)で、東由利とは案内されていないのが、悲しい現実。

右折して県道に入るとすぐに子吉川を長泥橋で渡り、右岸へ移る。
そして県道は右岸に沿って新庄地区のある河岸段丘上に上っていくのだが、早くも国道迂回路としての県道の任務は終わりを迎える。
国道迂回路は県道から左折を指示され、そのまま町道を数キロで迂回を成し遂げ、本来の国道に戻る。
はっきり言ってほとんど使われていない山越え砂利県道の32号線の矢島東由利間の、ごく一部(約300m)一時期とはいえ、国道扱いとなったことは、同線にとって忘れられない思い出になったことだろう。
虚しい?
なお、写真に写っている“ヘキサ”(六角形の県道標識)が、今回紹介区間で唯一のヘキサだった。

国道から別れ2kmほどで河岸段丘上に新庄集落を迎える。
この辺から県道はいよいよ峠越えの登りにとりかかるわけだが、ここで猛烈な雷雨が私を襲撃した。
もうジタバタしてもどうにもならないような振り方だし、気温は高く濡れても寒くはないので、カメラだけを濡らさぬように気をつけながら、土砂降りの中に漕ぎ出した。
雨合羽など、ものの5分で無用のものと化していた。
チャリの姿勢というのは、腕から合羽内に水が進入しやすく、合羽無意味だな。
写真の通り、この日は峠区間に不通の告知が出ていた。
この時刻ならば強引に作業員の目を盗んで突破できるだろうから、気にせず進入することにした。
「8km先災害のため全面通行止」らしい。

あっけなく道は1車線となり、白線すら消えた。
いかにも古い造り、というか、古い集落道を広げただけのような急勾配路で、一気に高低差100mほどを上り詰める。
チャリンコでやるには、こういう急で直線的な舗装路が一番滅入る。
しかも、目を開けているのも辛いような雨。
カメラをカメラバッグから出す度に、ストレスを感じる。
防水カメラが欲しい…。

国道から5km地点。
実は、さっき登っていた峠は本番ではなく、ひとしきり登ると下りに転じ、それまでに折角稼いだ高度をほとんど全て放出してしまう。
こういう展開も、チャリには面白くない。
まあ、先が読めないならばまだ良いが、この道を通るのも二度目なので、先が分かるだけに前哨戦はつまらない。
雨だからテンションが下がりっぱなしなのかも知れないが…。
一つめの峠を過ぎると、軽井沢集落。
沢沿いに田圃が下流の十二ヶ沢の方まで続いているが、残っている民家はかなり少ない、数軒だ。
この辺には、廃村やそれに準ずる小集落が山間の小盆地や斜面に点在しており、地図上にも何も無さそうな山中に縦横に道が描かれており、地名も多く記載されている。
最近の地図では、地名の方は大分カットされているようだが…。
そんな生活道路や林道が、節操ない一筆書きのように転々と県道に認定されたのが、本区間の特徴である。
今はまだその説明がよく分からないかも知れないが、この先幾つも現れる分岐が、そのことを感じさせるだろう。
青看では、ここに来て県道の面目躍如。
しっかり堂々と「東由利」が案内されている。
ここまで来たドライバーは、「確信犯」だろうからな。

数百メートルほど広い沢底に拓かれた田圃の間を真っ直ぐ進むと、ヘアピンカーブと共に突如登りが再開される。
いよいよ、軽井沢峠本体の登りがここから始まる。
峠の標高は410mほど。
現在地からの比高はプラス230mほど。
登りの延長は、ここから4km程度。
まあ、一般的な低山の峠のスペックである。
もし峠の両側にあるのが町ではなく、どちらかでも市だったら、こんな峠はとっくに改良されてレポの対象にならなかったに違いない。

上の写真にも既に写っているが、一つめのヘアピンカーブの先で早くも新道は通行止となる。
麓で告知されていた災害によるものではなく、これはまだ道が出来ていないためだ。
元来の県道は、ごちゃごちゃと取り付けられた標識に従って、ここを右に入る。
一応目立つように「東由利町方面」と案内されてはいるが、この先はちょっと見所だったりする。
ところで、この分岐点にも赤字で『全面通行止』が表示されている。
理由はてっきり災害かと思いきや、驚いた。
「この先積雪のため」とあるではないか。
たかだか海抜400mほどのこの峠には、8月下旬まで積雪があるというのか?!
んなわきゃあるかよ! 下げ忘れだろ!看板!!

このもろに生活道路チックな急車道が県道なのだな。
主要地方道という名が泣いているぜ。
どことなく、相互リンク先の『街道WEB』さんのレポでよく見るような景色だー。
街道だったりした経緯もあるのだろうか?
最近生まれたような道ではないことは、どう見ても明らかだが。
いずれにしても、…自信を持って「東由利方面」などと宣う道でないよなー。

しかもアスファルト舗装が尽きて、いかにもなコンクリ舗装だし。
幅も2mがせいぜい。
結構秋田県内では県道の改良率が高いので、こんな道にはなかなか出会えないのである。
勾配もめちゃくちゃきつい。
ニヤニヤしながらペダルに力を込める私であった。
まだ“美味しい”ゾーンは続く。

もの凄く薄暗い、怪しげな登り。
恐らく勾配は15%程度ある。
幅は相変わらず3m未満。
標識など何も無さそうなのに、あるんだなー。これが。
秋田県内オリジナルの県道距離表示標識(黄色い小さなキロポストだ)が、ここの片隅、蛍光塗料にて光っている。
数字は「37」、それは仁賀保町からの距離である。

暗い杉林を抜けても、登りは一向に衰えない。
道幅は再び軽トラの轍と等しい程度に狭まった。
コンクリ舗装直後に通ってしまった軽トラのタイヤ痕(断定)が、グレート鮮明に残っている。
しかも、長々と。
…おいおい、ここは私道かよ…
恥ずかしい県道だな…。
秋田県の恥ずかしい県道ワースト3に入る景色だな…。

他県人にはちょっと見せられぬ恥ずかし県道は、現れた民家の裏手を掠めて、さらに登る。
雨が相変わらず強く、カメラを持つ手がびしょ濡れになっている。
もう、リュックの中身を含め、湿気っていない場所はどこもない。
こうなると、時間の問題でカメラも浸水・停止してしまう。
今回は、奥の手があるのだが。

なにやら最近舗装されたらしい道がちょこっと現れてみたり、

わずか30mくらい未舗装だったり、
とにかく、節操がないというか、落ち付き無く道の様子は変化する。
まるで駄目な道を継ぎ接ぎしたような県道だな。
笑えるぜ。
楽しいぜ。
…雨じゃなきゃナ。

変な道を700mほど登ったところで、新道によって旧道は遮られた。
この先はしばし、新道を行くより他はない。
旧道は巨大な切り取りや築堤といった土木工事で跡形もなく壊されている。
写真は、下り方向の新道。
下側もそうだったように封鎖されているものの、実はこの区間、もう出来上がっているようだ。
なぜ通さないのだ?
立派なヘアピンカーブ二つで、あの恥ずかしい県道を旧道に追いやれるのに。

3年くらい前に初めて通った時にも、この区間はもう出来上がっていたっけ。
相変わらず、ほとんど使われている気配がないままだな。
当時は、この下のヘアピンカーブの辺りで重機が唸りを上げていたはず。
いずれは全線がこんなに素晴らしい道になるのだろうか…。
いやいや、どうもその可能性は低そうだ。
この辺りの工事が終わったと同時に、この峠の改良工事も放棄されているようなのだ。
まだまだこの先に未改良の場所が残っているのに。
今日は通行止の告知が出ていたからなのか(多分いつもこうなんだろう)、今のところ一台も車に出会わない。
寂しい道だ。

過ぎたる2車線道路はあっけなく終わりを迎える。
わずか500mほどだった。
ここにも不案内な分岐点があり、地図が無くてはとても県道をトレースできないかも知れない。
この分岐では、峠は真っ直ぐだ。
全面通行止のバリケードが築かれているが、この天気では、工事も中止じゃないだろうか? それを期待しつつ、直進する。
向こうから路上を流れてくる水が、明らかに変な色だ。
これは…。

真新しい舗装を舐める様に流れる泥水。
一向に降り止まぬ豪雨は、土壌の保水力というダムを決壊させ、雨の降るままに出水を始めていた。
幸いにして、峠というのは雨には強い道だが、これだけの出水は不安を禁じ得ない。
チャリが流れに逆らって進むと、舞い上がった泥水が下半身に水しぶきとなって降りかかるが、もうそんな濡れなど、私の濡れ濡れから見れば、なんでもない。
もう、私は濡れている。
カメラの停止も時間の問題と理解した。
カメラにとっては決死の、耐久力テストの様相を呈していた。

遂に砂利道に。
峠まではもう2km程度。
轍にゴロゴロと砂利の流れ出す音を響かせながら、濁流が渦巻く。
おいおい…すげーな。
冗談抜きで、山チャリしている場合でなくなってきた?!