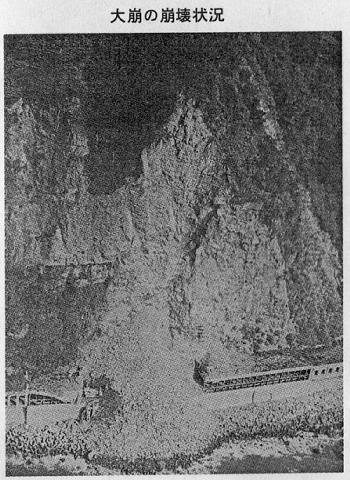2008/2/25 13:42
�@���ɗǂ����`�𗯂߂�u�Ε�����v�̐����B
�L�^�ɂ��ƁA��قǂ́u�Q���v�Ɠ������a18�N�̌����ŁA�Ε�詓����܂߂����̂R�̍\�������A�J�ʓ�������̂��̂ƌ������ƂɂȂ�B
�@�B��ɂ̓M���V�A��[�}�̌��z��f�i�Ƃ������̍��ӏ����{����Ă���A�Α��œ��{���Ȉ�ۂ̐Ε�詓��i�̎c���ꂽ�j�B���Ƃ͑傫���C���[�W���قȂ��Ă���B
���ɁA�傫�Ȕ���e���ґ�ɗp�����G�z�́A�R���N���[�g�ւ̒����肾�����Q������Ƃ̍ő�̑���_�ŁA�D�낳��������������B���͂ɐԂ��y�C���g�̍��Ղ�����A���ꂪ�����ȑ����ł������Ƃ�����A�������̈ӏ��Ƃ��Ă͗ޗ�̂Ȃ����̂ł͂Ȃ����낤���B

�@�S��104���̐Ε�����B
���݂ł͂��̒��x�̋K�͂̓���͏������������Ȃ����A��O�Ƃ��Ă͔��ɋK�͂̑傫�Ȃ��̂ł���B
�@�����詓��Ƃł́A���H����\�����Ƃ����_�͋��ʂ��邪�A���̐��i�͑S���قȂ�B
詓��͂��ꂪ�Ȃ���Γ������������Ȃ��Ƃ����A�܂蓹���̂Ɠ����Ȃ��̂ł��邪�A����Ƃ͗��������瓹�����̂��ړI�ł��邩��A�ЊQ�̔���������Ζ��p�̂��̂ł���B
��O�Ɏg�p����Ă������H�̍\���Ɋւ��郋�[���ɂ�����詓��Ɋւ����͂��������A����͒P�Ɍ��z���E�i�f�ʂ̑傫���j�ɋK�肪����݂̂ŁA���قǏd�v������Ă��Ȃ��������Ƃ��M����B�K�[�h���[�������h�~��Ɠ���Ɍ����A�ꓹ�H�t�����ɉ߂��Ȃ��B
�@�����̂悤�ɓ��H�̕ۈ���ɍׂ��ȃ��[���������A���t�͈������u���͒ʂ�����ł悢�v�Ƃ���Ă�������ɁA���傪�������B
������A��t����邱�Ƃ��������傪�A�J�ʓ������瑶�݂��Ă����B
����͂Ƃ���Ȃ������A���̏ꏊ�̕���̊댯���������]������Ă������Ƃ��Ӗ����Ă���B


�@�n���Ȉӏ����{���ꂽ�B��Ƃ͈قȂ�A�����͋@�\��ӓ|�̖����ȃR���N���[�g�\�������B
�����ɂ��d���������Ȓ��Ɨ��ɂ���ĊO�E�������ꂽ��ԂɁA�₽���C�����펞���������Ă���B
�����g�s����h�Ȋ�������܂��Ă͂��邪�A�g�y�₩�ɊC�𑖂�h�Ƃ����\�������Ă��ǂ��낤�����Ƃ̑Ί��́A�ƂĂ��傫���B
�d�ƌy�A�ÂƓ��̂���Ƃ����Ă��ǂ��B
�@�E�̎ʐ^�́A�܂Ƃ��ȗ����������A�H�ʂ���قƂ�ǂ��̂܂ܗ�������ł���H������A�C�݂������낵���l�q�B
�����̒����]���h�~�̖������p����̂��낤���A�l�⎩�]�ԂȂ�Γ]���͑�����Ȃ��B
�@�����̘H���́A���̂܂ܔ���̕t������ݕǂƂȂ��Ă���B
������啗�Ƃ��Ȃ�A���ڂ��̕ǂɔg���ӂ���p���z���ł���B
����ȂƂ��A���̓���ʍs����҂͂ǂ�Ȍi�F��ڂɂ����̂��낤�B�c�z�����邾���ŋ�������B
�C�㋴�̑��݂ŊC�݂ɑł���g�����₩�ɂȂ������݂ł͓�x�ƌ����Ȃ��A�����̏C���ꂪ�������ɈႢ�Ȃ��B

�@����́A�C�㋴���猩��Ε�����B
���Ԑ�����ȑ����炾�ƁA�K�[�h���[���̌������ɂ��̌i�F��N���Ɍ��邱�Ƃ��o����B
�t�ɁA�^�]��͂�����ƌ����Ȃ������m��Ȃ��B
����̏�ɂ́A���ɑ����ʂ̓y�����͐ς��A�����ɖX���炿�n�R�̈ꕔ�̂悤�ɂȂ��Ă���̂�������B
�@���̓��̗��j�������m��Ȃ��l�����Ă��A�ٗl�������͏\�ɓ`���Ǝv����A����Ȓ��߂��B
����͂܂�ŁA���ƊC�̍����ɗ��̐w�c���z�����A�h�ۂ̂悤�ł���B������ڂ��I�����c�B

�@�Ăѓ����B
�V���ɑ����ʂ̑͐ς����邱�̓��傾���A���̏d���ɂ����̂��A�����͌J��Ԃ��ꂽ�Ռ��������N�������̂��A����Ƃ����厩�̂̎��d������������̂��B
�ɂ߂Ċ�䂻���ȓ���̒����A�Ȃ�Ɲf�i�Ђ���j���Ă����B
���̎ʐ^�ł��A��O�Ɏʂ钌�̐��{���A���炩�ɊC���Ɍ������ČX���Ă���̂������邾�낤�B
�@���Ȃ݂ɁA�H�ʂ̏ɂ������I�ȓ��H�Ƃ͈Ⴂ��������B
�A�X�t�@���g�ܑ��ł͂Ȃ��A�R���N���[�g�̔łɂ��ܑ��ł���B
�Z���^�[���C���͕`����Ă��炸�A�ʐ^�Ɏʂ��Ă��铹�H�����t�߂̃��C���́A�S���ׂ̍��`���[�u���B�������A�����ɂ͂Ȃ��������̂��낤�B


�@�o���ɋ߂Â��قǁA���̏��݂͍����Ȃ���肾�����B
�Ō�̐��{�ȂǁA���͂₢���ꗎ���Ă��s�v�c�͂Ȃ��Ǝv����قǁA�����ׂ��Ă���B
�����ɖ��ߍ��܂�Ă�����R�̓S�����S�ɘI�o���Ă���A���������̈ꕔ�͒�����O��ėV��ł���B
���������Ȃ������ɂ́A�V����x������Ȃ��Ȃ�ɈႢ�Ȃ��B
�@�ǂ����C�ɋ߂������������ɂ�ł���̂́A���ݓ����ɂ͂܂��]�茤������Ă��Ȃ������g�S�R���N���[�g�̉��Q�h�ɂ��Ǝv���邪�A�Ȃ��ł������ɋ߂Â��قǕ��ꂪ�i�s���Ă��邱�Ƃ́A����̃��J�j�Y�������ꂾ���łȂ����Ƃ������Ă���B
�@�l���ɂ̂������ЊQ���ꂪ�A�ڑO�ɋ߂Â��B

�@���������A�Ăі������ԁB
�{���̘H�ʂ́A����y���̊�Ζʂɖ��܂��Ă���A�S�����݂�������Ȃ��B
����A�u�����Ȃ��v�ƌ������������������B
���݂͖��炩������̂�����B
�@�B������s���������ɂ́A���̎ʐ^�̂悤�ɋ���薳���B
�����ɂ́A���E�̔������Ղ�D�F����������R�B
����܂ŁA����ɂ���Ă��̑��݂���≓�����Ă����A�{���̂��̓��̗אl�B

�@�C�㋴���猩���A���ݒn�t�߂̊g��ʐ^�B
�Ε�����ɂ��Ă݂�A����́g�d���������˂��h�ƌ����ׂ��Ȃ̂��B
���\�L�̓y���ЊQ�ɂ���Ė�����Ă��܂����̂́A���̓��傪�r�ꂽ���̏ꏊ����悾�����B
����ł��A���Ȃ�̗ʂ̓y���������Ɠ����ɐ���ꍞ�l�q�����Ď���B
�@�����A���̌������猩����i�ɂ́A�����Ă�����̂�����B
�O��̋L�q���v���o���ė~�����B
�@���a46�N7��5�����A�R���Ζʂɑ���������A��5����101m�̈ꕔ42�D5�������ׁA29�D8�����Ђ��݁A�ʍs���̏�p��1�䂪���v���P�l�̑����]���҂��o�����B��5����t�߂́A3�̓��傪���Ԗ����A������t���J�o�[�h�ȓ��������B
�@�����Ă�����̂Ƃ́A�Ε�����i�P������j���A�����Ă������́A��T�����̎p�ł���B

�Ε��T����́A�ǂ��֍s�����H

�@���ꂪ�A�אl���ˑR�����o���ɂ�����̔j��͂ł���c�B
����A�u�É����y�؎j�v�Ƃ������K�̎����ɂ�����Ȃ���A�����ƌ��߂����Ă������낤�����B
������������ł́A���傪���傤�Ǔr�₦���ꏊ��y�����ꂪ�P�����悤�Ɍ����邪�A�����͈���Ă����̂��B
���̏ꏊ�ɂ��A�����Ɠ��̌��͑��݂��Ă����B
6000�������[�g���Ƃ����c��ȗʂ̓y���́A�|�S�̕ǂ������钴��I�Ȕj��͂��āA���傲�Ɠ��ƒʍs�l��@���Ԃ����̂��B
�@���݁A�H�Ղ͂����悻��70���ɂ킽���Ċ��S�ɓy���ɖ�����Ă���B
���̐�ɁA30���قǎc�����T������̎c�[������B
���̖��v��Ԃɂ��ẮA���R�A�댯�ȓ����ƂȂ�B
�����̏ꍇ�A�����ɂȂ�����ݕǂ���]�����������Ƃ�Ȃ����A���������ɑ�������ň��̌��������蓾��B
���������A���������Ă܂ł�����˔j���Ȃ��Ă��A�����̌�������s���~�܂�܂ŋl�߂邱�Ƃ͏o���邵�A���S�ɖ�����Ă��܂������ɁA�V�����̈�\������Ƃ��v���Ȃ��B

�@����A���̕�����Ԃ̓����́A�Ӓn�ɉ߂��Ȃ��B
�Ӓn���Ė����̂Ă�͔̂n�����Ă���Ǝv���邾�낤���A�I�u���[�_�[�ɂƂ��Ắg���S�����h�Ƃ́A�H�Ղ����v���Ă���ꍇ�A���̏㕔�n�\�ʂ��Ȃ��邱�ƂŒB���������̂ł���A�\�Ȍ���B���������ƍl����͎̂��R�Ȃ��ƂȂ̂��B
���_�A�Œ���̈��S��i�w�����b�g�j�͑����ρB
�@�ӂ��ł߂ĎΖʂɎ��t�����ŏ��ՁA�����Ɏ������t�����̂́c���낵�����ł͂Ȃ��A�ΖʑS�Ăߐs�����C�o���̞��������B

�@���̖݂����z���Ă�⍂���Ƃ���ցB
�ʐ^�͂P�������U��Ԃ��ĎB�e�B
�ӊO�ɂ��A�B���͂قƂ�ǖ����������B

�@���悢�挻�ꂽ�A���R�̊j�S�����B
�����ɂقƂ�ǐA��������Ă��炸�r���Ƃ������i�����A�Ζʂ̊p�x�͌����Ɉ����p45���ƂȂ��Ă���B
����āA���I�̎Ζʎ��̂͂��قǕ����ɂ������Ƃ��Ȃ����A�����̊댯�ɋ����邱�Ƃ��Ȃ������B
���Ƃ́A����̐S�z���������A�܂��A�������͉^�ł���B�������ƒʂ蔲���邾�����B
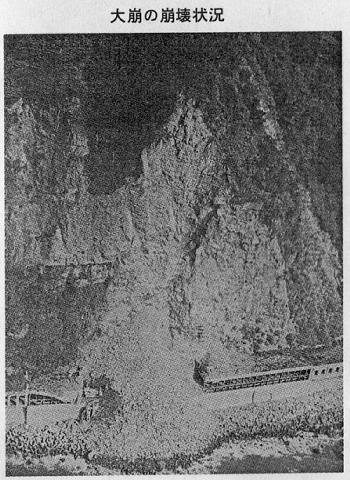

�@�u�É����y�؎j�v�Ɍf�ڂ���Ă�������̎ʐ^�ƌ���Ƃ��r���邱�ƂŁA�g�ǂ̂悤�Ȏ��㏈���h���s��ꂽ�̂���������x�\�z�ł���B
����̎ʐ^�ɂ́A�T������̂������ׂ���42���������S�Ă��i���R�̂��ƂȂ���j�ʂ��Ă���B
�����ꂽ�Ԃ̋~�o��ƂȂǂ����̌�œ��R�s��ꂽ�͂��ŁA����Ƃ̊֘A���͕�����Ȃ����A���݂ł͂T������̓��c���Ă���͔̂�Ђ�Ƃꂽ�����̋͂��ȕ����݂̂ł���B
�g����h�ɂ͝f�����p�Ŏc���Ă���T������̂P������Ɛڂ��镔����A���ו��̓��ɐڂ��镔���͓P������Ă���B
����ł́A���̓P�������̘H�Ղ����S�ɓy���ɖ�����Ă���̂����A����͌ォ��̕���ɂ����̂Ȃ̂��낤�B
�@�u���v�����]���҂����@�ł������ł�������Ă���v�ȂǂƂ����b��������B
����͂����炭�A���܂�̕���̐��܂�������o�Ă����\�ɉ߂��Ȃ����낤���A�����A�g����g���獡���Ɏ���܂ŁA���ו��̓y���ɏ������ꂽ�悤�ȍ��Ղ��c�ʐ^�̏ォ��ł͔F�߂��Ȃ��Ƃ����̂��A�����Ȋ��z�ł���B
�@�c����ȏ�m�M���Ȃ����ׂ��b��ł��Ȃ��Ǝv���̂ŁA�����ꐳ�m�ȏ�����܂ł��̘b�͒u���Ă������c�B

�@��A���v�X��3000�����̎R���̊┧�ƁA���̊C�ɖʂ�����ǂƂ��A�n���I�ɂ͋߂����̂ł���炵���B
�������Č���ƁA�m���ɂ���ȏs��̎R���Ɏ��Ă��Ȃ����Ƃ��Ȃ��B
�����A�����ƌ���I�ɈقȂ��Ă���̂́A������w��ɂ��Ă���ƌ������ƂƁA�����Ə�̕��ɂ܂ŃR���N���[�g�̐����t���������Ă��邱�Ƃ��B
�@���H���C��֓��������ƂŁA���܂ł͂��̐����t���ɈӖ��͂Ȃ��B
���\�N���X�V���ꂸ�A�������Ĕ����ꂩ���Ă��錻����A���ꂪ�悭������B
�����A���Ӗ��ƂȂ����ߋ��̐����t���H�ɂ��A��l�ɑ���h�ӂ�\�����ɂ����Ȃ��B
���������A�ǂꂾ���̑��ꂪ�z���ꂽ�̂��A�ǂ�ȂɊ댯�Ȍ��ꂾ�����낤���B
�@���̓����ꌂ�Ŗ��Ӗ��Ȃ��̂Ƃ��������̏��ՁB�������́A���ܐ������̂Ȃ��ΖʂƂ��đN���Ɏc���Ă���B

�@���ݒn�́A���߂��y���̎R�́A�����Ƃ�����オ���������B
�C���̘H���ł������[�g���B�R���ł�10�����炢�̌��݂ő͐ς��Ă���Ǝv���B
�ӂ�ɁA���̑��݂�`����悤�Ȃ��͉̂����Ȃ��B
���ׂ�������̕��ނ����ǂ��Ȃ��Ă���̂����A�s���ł���B�i�@��o����Ă���Ǝ��͎v�����j
�@�ʐ^�́A����ȏꏊ����C�㋴�������炷�B
�މ�̋����́A�v�Z�ɂ���ċ��߂�ꂽ��60���ł���B
���ꂾ�������Ă���ƁA�f�R�̕���Ƃ������X�N���犮�S�ɉ�������ƍl�����킯���B