-Hai Doro tunnel-
謎の横穴地帯

午前8時55分、入洞より50分を経過。
泥沼と化した廃水路らしき隧道は、なおも続いていた。
相変わらず一本の紐が壁に添って掛けられており、ときおり数字が書かれたビニールテープが取り付けられている。
その数字は徐々に減り続けており、現在“600”程度。
始めに見たときには“1160”だったが、この数字が出口までの距離である事を信じ、前進を続けていた。
階段付きの横穴を過ぎて以来、洞内に目立った変化はなく、淡々と隧道は続いていた。
我々が発する僅かな言葉と水音だけが、空虚な洞内に揺らいだ。
【腐れ動画 (784kb)…食事中閲覧厳禁】

…久々に横穴だ…。
向かって左、山側に向かって整わない断面の横穴が口をあけていた。
どうも山側に向かう横穴は不気味である。
水路なのだとしたら尚更、山へ向かう横穴は意味が分からない。

総素堀の内壁。
横穴には奥行きはなく、横穴と言うよりもむしろ、本坑に面した部屋のような大きさだ。
洞床もやや高くなっており、水没を免れている。
水路と知って興味を大部分失った細田氏は相変わらず無言だし、トリ氏もなんとなく嫌な気を感じるのか全く入ろうとしない。
私も余りいい気はしなかったが、この奇妙な圧迫感のある横穴へ身を潜らせてみた。
じっとりと沈滞した空気が重苦しい。
何か、本当に嫌な物(具体的に何といわれると困るが)を見るとしたら、おそらくこんな場所かも知れないと、そう思ってしまう。

地面には、思いがけない物があった。
よく野外の空き地や道路端で見るような、赤いボタン状の鋲。
おそらくこれは、行政で設置している境界標の一つだと思うが、まさかこのような地下空洞の一室にあろうとは誰が想像できようか。
部屋の中央に一つだけ見つけたが、この隧道内にも仙台市政は及んでいるということなのか。
安心するどころか、むしろ気持ち悪い気がした。
何か、意味がある空洞だったのだろうか…。

横穴を過ぎて更に進むと、そう行かずにまたしても側壁に大きな穴が空いていた。
今度はコンクリで巻かれている壁を、強引に破壊したかのように乱暴に口が開いている。
その上、本坑の左右両側に穴はあった。
ハテナマークを頭上に点灯させながら、まずは川側の穴を覗き込んだ。
しかし、これまでのパターンと違って、その先に僅かでも外の明かりは見えなかった。
それどころか、先ほどの横穴同様、小さな部屋状の空洞があるのみだった。
いよいよ、広瀬川の河原からも離れ、深い地中へと進んでいるというのだろうか…。
本当に我々は出口へ向かっているのであろうか……。一同は不安を覚えた。

それではと、山側の横穴へ進んでみる。
10mほど奥には、行く手を遮る岩の壁が見えていた。
風が流れておらず、水蒸気が立ち籠めている。
やはり部屋状になっているようだ。
陸地となっている横穴室内へ進む。

横穴は、明らかにコンクリートの巻立てを後から破壊してまで掘られた物に見える。
一体、これら行く手のない横穴群に、どのような意味があったというのだろう。
写真は、我々が足を踏み入れた横穴から本坑を振り返っている。本坑を通り越して反対側に見えている横穴が、川側の穴だ。
ひとしきり周辺を観察してふと気付くと、細田氏の姿が無い。

落盤を繰り返したらしい剥離崩壊の相を露わにする部屋の隅に、屈んでようやく通れるくらいの横穴を発見。
細田氏はこの先へ進んでしまったのだろうか。
私も、後を追った。
なんだ、この地底空間は… 本当にただの水路なのだろうか…。
一度は消えたはずの疑問符が、次々現れる横穴によってまた立ち上がり始める。
再び私の頭はもやもやしてきた。

狭い横穴にも、泥が堆積していた。
頭を汚さないように注意しながら、土臭い通路を進む。
10mほど先には、またも大きな空洞があるようだ。
何があっても、驚いてはいけない。
自分にそう言い聞かせながら、消えてしまった細田の影を探す。
トリ氏も後についてきているが、不安そうだ。

どういう事か。
我々は“U”の字型に横穴を歩かされていたらしい。
元の本坑の、我々が足を踏み入れた横穴の20mほど先にぶつかった。
これ以外に分岐はなく、この一本道であった。
一体、誰が何のために??
なぜコンクリートの内壁をぶち抜きまでして、このような大きな空洞を掘ったのであろうか。
或いは、多くはコンクリの壁に隠されているだけで、蟻の巣のように膨大な空洞が、この地底には点在しているというのだろうか…。
……分からない。
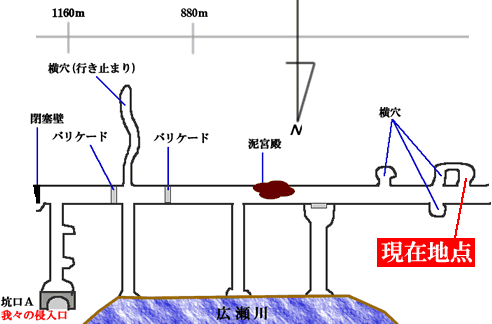
右の図の通り、洞内は単純に水を通していただけとは考えにくい複雑さを有している。
だが、東北大学新聞部による次のレポート(こちら仙台まる秘情報局)によれば、やはり我々の見立て通り、この隧道の正体は水路であったと結論づけて良さそうだ。
このトンネルは、八十年以上も前に作られ、名称を「仙台愛宕下水力発電所導水トンネル」という。その名の通り、水力発電のため水を川から引くために使われた。発電所は愛宕神社の周辺にあったが、建造の約十年後には操業が停止された。トンネルの総延長は約一・四キロメートルである。トンネルには、主抗のほかに、五つの横坑がある。標高は、上流の竜の口渓谷側が約二十四メートル、下流の愛宕山側で約二十三メートル、落差は一メートルに満たない。トンネルは発電所の操業停止から現在まで、一切使用されておらず、今後の具体的な使用計画も立てられていない。
『こちら仙台まる秘情報局』より引用
しかし、本当にそれが全てなのだろうか。
ただ水を通すためだけに掘られた隧道に、これらの横穴が必要だろうか、まして、横穴部のコンクリート巻は最初からこの形であったとは思えない破壊の相を見せている。
さらに、洞内に入って間もなく見た碍子は何だ。
あの隧道を塞ぐような壁と、その脇に掘られた小さな抜け道のような穴は何だったのか。
この穴は昭和初期までに水路として役割を全うした後、やはり何らかの再利用があったと見るべきだろう。
その決定的な発見は、我々が泥にまみれ黙々と邁進していたこの方向にはなかった。
本当の不思議空間は、“アノ壁”の向こうだった。
よみがえる戦慄のとき

午前9時03分、入洞よりちょうど一時間が経過。
都市の地底をすでに1km近く徘徊している。
だが、未だに出口の明かりは見えてこない、代わりに、これまでは殆ど真っ直ぐだった隧道が、左へ曲がっていくのが分かる。
素堀とコンクリ巻を交互に繰り返す内壁には、泥のオブジェが気色悪い姿を晒している。
歩いていても気付かぬ程度に登っているはずだが、そのことは、足元の水位が次第に下がり、泥の乾き具合が増していく事で知れる。
ますます足元の泥はえげつなさを増していくのであった。
これで臭いがあったら、おそらく我々は卒倒していたことだろう。

もはや、一体は完全に泥の海、昔の湿田にも劣らぬそのマッディぶり。
はっきり言って、私も細田氏もかなりどうでもよくなってきていた。
水路だと言うだけでも萎えなのに、この遅々として歩みの進まぬ泥海、両足が重い。
一方、生まれてこの方、おそらくこんな泥に入るのは初めてに違いないトリ氏は、相変わらずニコニコしながらついてきている。
デビュー戦がこんな場所になってしまったことを、少なからず気の毒に思っている我々を余所に、それなりに楽しそうである。
さっきから、細田氏の汚らしい「おえっ」「おーえっ」という声が、響く。
そんなとき、一番後ろを歩いていたトリ氏が突然言った。
あわ でてるー

一瞬固まる私。
泡!!
酸欠状態の泥海、その表面はやや乾きつつあって、パリパリの殻のようになっている。
そして、そこを豪快に攪拌して歩いている我々。
その足元から沸き立つ泡 …ガス!
細田氏は言った。
なんだか足先がさっきから温かい気がすると、発熱しているのではないかと!
詳細を確かめている猶予はないかもしれなかった。
泡が本当に泥の中から発生しているものであるなら、それは危険な有毒メタンガスの可能性がある。
この猛烈な泥の海を目の当たりにして以来、内心恐れていた状況が、いま生じていた。
この発言を機に、我々はさらに言葉少なになった。
私は、あの上北鉱山の悪夢のような一時間を、鮮明に思い出していた。
光を目指して

カーブの先に直線が現れた。
そして、針の先程度の小さな光芒が見えた気がした。
それが目の錯覚でないかを、全員のライトを一度消して確かめた。
確かに緑色の点が、出口らしき光が見えていた。
タグの数字はまだ「400」くらいあったと思うが、やがては外へ通じている事が分かり安心した。

泥が洞床に露出している部分と、うっすらと水が浮いている部分とが交互に現れた。
どちらにしても歩くのは苦痛でしかない、嫌な場所だ。
そんな景色が淡々と続くのだった。
もはや、横穴もなければ、目を引くものは何もない。
それは、出口までの消化試合の様相を呈していた。
いつになく細田氏の歩くペースが速いのも、つまらなさの顕れだったろう。

この穴は誰にとっても相当に不快なのだろう。
東北大新聞部のレポーターは別としても、殆ど立ち入る者もないようである。
都会の真下にありながら、そして誰でも自由に立ち入れる状況にありながら、肝試しさん達の土産物が全くない。
壁の「死ね」や「殺す」の落書きもなければ、空き缶一本落ちていない。
80年以上もこの大都市の地下に眠っていながら、……人々はこの穴を知らない。

一度出口が見えてからは、その出口の見え方だけが我々の話題だった。
出口のシルエットは、半円が水面に反射して円形に写っているように見えていたから、水没と、バリケードのような物で塞がれている事が懸念された。
特に、バリケードは大いにあり得る話だった。
この段階では、我々がどこへ出ることになるのか分からなかったが、おそらくは仙台市民憩いの場、青葉山公園付近だろうと想像された。
100万都市の代表的公園の一角に、よもやこのような穴が口を開けているはずがないではないか。
きっと、塞がれていると思った。
いま来た穴を戻るのは、もの凄く気が重い。

近付いてほっとした。
大丈夫、どうやら出られそうだ。
最後の方は、やや水位が高くなり、泥も少し浅め。
なんとなく、外気に触れている、という感じがする。
数分前まで我々がいた漆黒の中の泥海は、人々が目にすることなど全く予期しない、仙台の秘部であったに違いない。
生ぬるい空気が顔に当たる。
それが、こんなに嬉しいのも珍しい。
我々を迎えてくれたのは、夏の蒸し暑い空気だった。
だが、それさえも清冽なものに感じられた。

ここまで来て、この水路が間違いなく廃墟であったこと、やっと確信できた。
私は、万一水が流れ込んでくることがあるのではないかという不安を抱えて歩いていた。
だが、本坑最上流部の坑口は、土砂で半ばまで埋められ、さらにベニヤ板の覆いが1mほど取り付けられている。
もう、二度と水が通ることは無さそうだ。
さて、隙間から外へ出る事が出来るが、果たしてここはどこだろう。
後半はやや西寄りにカーブしていたが、全長1.4kmといわれる水路隧道のうち、1.2kmほどを歩いてきた。
しかも、より仙台市街中心部へ近付く方向へ進んでいた可能性が高い。
はたして、ここはどこだ?!

ここまで我々の心の拠り所になってくれた、細い紐。
これに取り付けられていた、出口までの距離を示すらしいタグがあったお陰で、引き返さずにここまで来られたと言っても良い。
もしこれがなかったら、何処へ続くとも知れぬ水路の、しかも泥の海の中を歩き続けられたか分からない。
そのタグの最後の一枚は、「0」の数字ではなく、「東北工大」と書かれてあった。
東北工業大学?
この隧道の、いまの所有者なのだろうか?
現在地判明!

午前9時17分、我々は1時間15分ぶりに地上へ出た。
そこは夏草に周囲を取り囲まれ、どこかの山の中のようだった。
コンクリート製の坑門は、明らかに水門に形をしている。
だが、そこから続いていたはずの水路の痕跡は無い。
果たして我々はどこへ来たのだろう。
そして、地上の明かりの中で見る我々の汚れ方は、常軌を逸していた。
まさに泥まみれ。
この姿で我々が行くべき場所は……、暗がりへと戻るより無いのではないか…。
このまま都会に出て良い姿ではない。
通報されかねない。

外へ出ると、目の前には低い山並みが見えた。
街や建物の姿はなく、人影も見られない。
坑口の前に道はなく、背丈に匹敵する夏草の薮が広がっている。
どうやら、草原のただ中に出てきたようだ。
霧のような雨が落ちていたが、我々の汚れはこんな雨では全く落とせそうにない。
ここから引き返すにしても、どこへ辿り着いたのかだけは知りたかった。
そのために、私は周囲を歩いてみた。
濡れた夏草を掻き分ける内に、ズボンの泥はいくらか綺麗になった。

草の海に埋もれた坑口。
少しでも離れると目立たない。
比較的新しそうな立ち入り禁止の立て札はあるが、それ以外に警告はなく、ここがおそらく人々の普段の往来から離れた場所なのだろうと想像された。

雨の音に混ざって聞こえた水音の方へ50mほど歩くと、そこには大きな川が流れていた。
広瀬川だ。
川は大きく蛇行して流れており、対岸の氾濫原と林の遠くにマンションやらビルやらがやや霞んで見えた。
都会の一角にいることは間違いなさそうだが、此岸には道や踏み跡さえない。
我々が最初に水路へ進入したのは、この下流の河川敷だった。
その方向を見ているのが右の写真だが、途中に沢山あったはずの横穴は見えない。

さらに坑口を起点にして周囲を捜索すると、川とは逆の方向に、一本の橋が発見された。
橋の向かいにはアスファルトの細い道、いかにも公園内の遊歩道のような道が見えた。
簡易的な作りに見える橋の銘板には、仙台市民でなくても耳覚えのある名前が記されていた。
竜ノ口渓谷といえば、市街地の川とは思えぬほどの急峻な断崖で知られる広瀬川の支流である。
その河口に、この昭和60年竣功とも書かれた小さな橋が架かっており、我々を日常社会へ呼び戻す役を果たしてくれた。
橋の坑口側に道はなく、その坑口が夏草の中に埋もれているだけだった。
橋は手持ちの地図に記載されていなかったが、ケータイのGPS機能を活用し、遂に現在地が判明した。

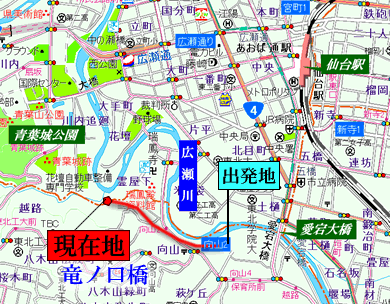
右の地図の赤い実線が、我々が通り抜けた地下水路の想像ルートである。
このように、広瀬川の蛇行一つ分をショートカットするように掘られていたものと思われる。
青葉山公園の外れである現在地から出発地へ戻るには、ほぼ直線であった地下水路を戻るのが最短ではあるが、全員が戻りたくないという意見で一致していた。
だが、陸路で戻ろうとすれば、最低でも市街を4km以上は歩かねばならない。
この姿で公共交通手段を使うのは、流石に気が引ける。
…困った。
細田氏は、私のある発案により、ここで再びケータイを握った。
実は、この日の探索にはもう一人参加を予定している人物がいた。
その彼の力を、いまこそ借りようという魂胆だった…。
次回最終回。
真実を求め… 残された領域… あの壁の奥の世界へ。
| 当サイトは、皆様からの情報提供、資料提供をお待ちしております。 →情報・資料提供窓口 | |
|
このレポートの最終回ないし最新の回の「この位置」に、レポートへのご感想など自由にコメントを入力していただける欄と、いただいたコメントの紹介ページを用意しております。あなたの評価、感想、体験談など、ぜひお寄せください。 【トップページに戻る】 |
|