入り口を確認しただけで、帰れれば、それが良かった。
もし、それに気がつかず、探索を完了していたなら、それが幸せだった。
(「山形の廃道」を知らなければ、実際、ここで引き返していたかもしれない…。)
そう。
まだ隧道は、あった。
それは、足元の下であった…。

入り口から見えていた5mの最奥部。
足元に、人為的な形をした朽木が見えていた。
そこに近付いてみると、それは、隧道の支保工であった。
僅かな隙間から、大きな空洞が、覗いていた。
そこが、入り口だった。
瓦礫の斜面は、暗い洞床に続いていた。
わたしは、意を決すると、この斜面を、ゆっくりと下り始めた。
チャリは、麓に置いてきている。
愛用のリュックを担ぎ、築92年の、洞穴へ、降りていった。

下っていく途中、ほんの数メートルの距離なのに、えらく長い時間に思えた。
正面を見ると、そこには、滑らかに削られた白い岩壁が、異様な美しさのまま、暗闇へと続いていた。
暗闇の向こうには、何がある?
少なくとも、明かりは見えない。
崩落し、閉塞しているのだろう。
すぐにでも、そういう結果が明らかになることを、期待していた。

洞床に立った。
足元は、たっぷりと水を含んだ砂地であった。
踏みしめると、水が染み出してくる。
まじまじと洞内を観察してみる。
意外に断面は大きかった。 一時期車道として供されていたというのも、頷ける広さだ。
ただ、それを否定したくなるような現実もあった。
足元の砂地には、まったく、轍がなかったのだ。
轍は、何もタイヤ痕ばかりではない。車が通る道には、2本の並行する轍が生まれる。
しかし、ここの路面は、まったく水平である。
それどころか、足跡一つ、なかった。
猛烈な心細さが、こみ上げてくる。
しかし、「山形の廃道」のfuku氏も、この同じ景色を、写真に収められているではないか。
ここはまだ、未踏の世界などではないのだ。
そう自身に言い聞かせ、恐怖心を、追い払う。

振り返り見上げれば、そこにはまだ、ほっとするような日の光が覗いていた。
しかし、入って3mも進んでないのに、この閉塞感は、一体なんだ!
一人旅を長く続けてきた私は、これほどにも臆病であったか?
自問してみても、異様な空気が絡みつくこの隧道内は、明らかに、いつもの廃隧道とは一線を画していた。
一つに、この入り口の狭さからくる「簡単には出られない」というイメージが、原因にあるだろう。
もう一つ理由があるとすれば、それはいま、私が愛車から離れ、一人山中にいるということである。
チャリから離れた私は、今、本当に、一人であった。
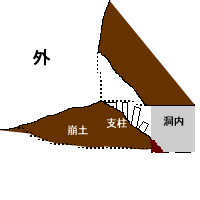
ここで、この入り口の状況の断面図を見ていただきたい。
だいたい、こんな感じである。
坑門上部の崩落の規模は、あの大切疎水道より大きいが、状況としては非常に似ている。
やはり、コンクリートなどで固められていない坑門というのは、洞内よりも早く風化してゆくものなのだろう。
これまで「ええカッコしい」と馬鹿にしていた、内部は素彫りのままなのに坑門だけが補強された状態にも、一理あるのだと思った。

勇気を振り絞り、先に進んでみた。
ここで、今回始めて実践投入した「大型懐中電灯」を装備した。
単一電池4本を利用することから、その重さがネックになったが、廃隧道探索での光量不足は、その成否に直接影響するだけに、我慢して持ってきた。
数歩踏み出すと、そこからは地底湖のように水没してしまっていた。
みたところ10mほどだが、水深が結構ありそうだ。
せっかく装備してきた長靴が耐えられるだろうか?
不安はあったが、とにかく長靴を履いてきたことの成功は確信した。
仮にここで長靴がびしょぬれになっても、ここまではいてきた靴が、まだあるのだ。
この先の旅を、乾いた靴で行えるなら、それでよい。
強気になった私は(長靴ごときで強気になれる私って、スゴイ?)、少し荒々しく、ばしゃばしゃと水音を立て、つきすすんだ。
結局、私はここで、(予感どおり)両足をびしょ濡れにした。
深かったのだ。

水没地を越えたとき、既に入り口の明かりはほとんど届かぬ世界だった。
振り返ると、30mほど向こうには、まだ白い光が覗いていたが、それは弱弱しく、とても私の先の暗闇を照らし出すものではなかった。
懐中電灯の灯りが頼りになったが、余りにも暗い!
電池も十分な筈なのに、この暗さは、なんだ!
足元を照らし出すのがやっとで、先を照らしてみても、素掘りの岩盤にオレンジの光がうっすらと燈るのみである。
それによって生じるかすかな陰影を頼りに進むことを、余儀なくされた。
あぁ、ヘッドライトがほしい。
川口探険隊(古くてすまん)のような、明るいヘッドライトが、私も、欲しい。

懐中電灯の頼りない灯りと、フラッシュをたいてデジカメで撮影した写真を確認しつつ、慎重に進んだ。
足元には、土が積もっていて、柔らかな感触がある。
そして進むにつれ、天井や壁面が崩れ落ちてきたらしい大きな瓦礫が、目立ち始める。
瓦礫を避けつつ、進む。
50mほど進んだだろうか。
懐中電灯の灯りの先に、岩山が写った。
ここは洞内である、岩山があるということは、遂に、閉塞点にたどり着いたということなのか?
近付くにつれ、鮮明に見えてくる。
崩落した土砂は、道の半分以上を、埋め尽くしていた。
その先が、まだあるようにも見えたが、もう無いで欲しいとさえ思った。
ここまでは、目には見えぬほど微弱でも、まだ入り口から届く明かりが、かすかに洞内を照らしていたはずだ。
ただ目が暗さに慣れてきただけかもしれないが、それは耐えられない暗さではなくなっていた。
しかし、この道の半ばほどを埋め尽くした崩落の向こうの空間はどうだ?
そこにこそ、真闇と呼べるものが、待ち受けているのではないか?
もう、自身が臆病者であるかどうかなど、どうでも良くなった。
この恐怖に、負けたくないという気持ちが、沸き起こってきた。
どんなに恐ろしげな場所でも、物理的に不可能にならぬ限り、進んでやろうじゃないか。
いけるところまで突き進んでやろうと、決心した。
遂に根性が座った私は、この崩落地帯の岩壁を、むんずとつかむと、ガッシガッシと登った。
その先は、やはり真っ暗…。
…と思ったが、意外にも、白い光が漏れ出していた。
正直目を疑ったのだが、距離感の掴めない暗闇の向こうに、点のようではあったが、さっき入り口に見た明かりと同じ色が、見えていた。
振り返ってみると、だいぶ遠くに、入り口の明かりが小さく見えた。
もう一度向き直る、遠くに見えるその明かりは、あまりにかすかで、たどり着けるものなのかは、半信半疑であった。
それでも、予想に反して完全閉塞ではなかったわけだ。
一気に、現実感というものが蘇ってきた。
さっきこの岩山に飛びついた一瞬など、私は“暗闇”に“飲み込まれ”かけていたのではないかと、空恐ろしく感じた。
ふたたび、私の体を“正常な恐怖”が支配した。
「生きて、あの光の下に、たどり着きたい」 そう、思った。

この崩落地点の写真を、画像処理によって明るくしたのがこの左の写真。
ここまでは、素掘りながらも概ねきれいな半円形を成していた断面が、ここでは跡形も無く崩れていることが分かる。
ひどい崩落である。
危険そうだ。

その先は、やはり困難な状態であった。
かつて路面があったはずの場所には、人間大の瓦礫がごろごろしていた。
洞内でずっと、どうしても頭の中から離れない、嫌な想像をしていた。
「…もし、人の死体があったら嫌だな。」
「でも、あるかもしれないよな。」
「人の死体を隠すとしたら、ここなら、きっと、見つからないもんな…」
足元のいろんな形の瓦礫が、私には、気持ち悪く思えてきた。

中間地点くらいだったろうか。
150mは来たと思う。
未だ、正面に見えるかすかな明かりは、かすかなままである。
それは、間違いなく外の光であったが、果たして、外に出ることが出来るのか、不安だった。
足元には、それまでの岩塊に混じって、いくつか木製の物体を見つけた。
かなり大きく、長い。
たぶんこれも、入り口にあった支保工と同様のものの残骸ではないかと思うが、周囲にはなく、ここだけに何本かあるのは、不思議であった。
余り詮索したい気分でなかったので、先を急いだが。


最もひどく崩壊していたのは、ちょうど中央部と思われる50mほどの区間であった。
そこを過ぎると、ふたたび、平穏になる。
丁度その場所から撮ったのが、左側の写真である。
これでは確認は困難なので、さらにその一部分を2倍に拡大したのが、その右の写真になる。
うっすらと、出口の明かり(らしき)ものが写っているのが、お分かりいただけるだろうか?
こんな明かりを頼りに先に進むというのは、生きた心地のしないものだ。
しかしもう、来た道を戻るのは、かなり欝だ。
絶対に、脱出しちゃる!
実は、ここで紹介した以外にも、多くの写真を撮影したが、光量不足で、まったくといって良いほど像を結んではいなかった。
だが、写真撮影以上に何度もここで行ったことがある。
それは、デジカメでのビデオ撮影である。
音声付の動画を撮影できるのだが、まるで、実況中継のように頻繁に録画していた。
やはりそこにもほとんど映像はなく、延々と音声が続いているのだが、声を出して実況することが、一人でいることの心細さを、幾分緩和してくれた。
また、実況で取材という目的をはっきりさせることも、探索続行の勇気に繋がったとおもう。
とにかく、恐ろしい場所なのである。
築90年の廃道は、並ではなかった。
もう、二度と一人では行きたくないかも。
出口に近付くにつれ、深く泥が堆積していた。
最も深い場所では、30cm以上あったようで、一時、足をとられ身動きが取れなくなったほど。
やはり長靴の上まで泥に沈み、もう、汚れと濡れについてはどうでも良くなってしまった。
そうそう、書き忘れていたが、さっき、入り口付近で長靴の中まで浸水したあと、両足は切るような寒さに凍えていた。
なんか、足の先の方が棒にでもなったような感触であった。
その事実すらも、この隧道のインパクトに霞んでいたのだが…。

そして、遂にたどり着いた、出口。湯野浜側坑口である。
洞内侵入から10分強。
この暗闇から開放されるチャンスが訪れたが、しかし、坑門はものの見事に、崩落している。
埋もれている。
その狭さ、善宝寺側の比ではない。
抜けられるか?

出口を塞ぐ崩落に取り付く。
その高さは、隧道の高さと同じだけある。
取っ掛かりはたくさんあり、登ることはそう大変ではなかったが、狭い。
外の明かりが、目に飛び込んでくる。
出口のすぐそばまで積雪しているのが、内部からも分かる。
何本もの小さなツララが、漆黒の闇と外の世界との境界線を成していた。
私の体重は、50キロしかない。
今はそのことに感謝だ。
なんとか、リョックがつかえながらも、この最も狭い場所で高さ30cmほどの隙間を、突破した。

生きて、この笹立隧道の通行に成功した。
この廃隧道の状況は、私がこれまでに挑戦したものの中で、もっとも、通行が困難であった。
特に、精神的に。
それに、この閉塞状況は、限りなく「完全」に近く、いつ、本当に埋もれてしまうか、分からない状況である。
出口に立って、岩の裂け目のような今来た道を見下ろし、まじまじとそう思った。
さらに、探索は続く。
湯野浜側は、果たしてどんな景色なのか?
そこにも、相当の驚きがあったのだが…
続く
| 当サイトは、皆様からの情報提供、資料提供をお待ちしております。 →情報・資料提供窓口 | |
|
このレポートの最終回ないし最新の回の「この位置」に、レポートへのご感想など自由にコメントを入力していただける欄と、いただいたコメントの紹介ページを用意しております。あなたの評価、感想、体験談など、ぜひお寄せください。 【トップページに戻る】 |
|