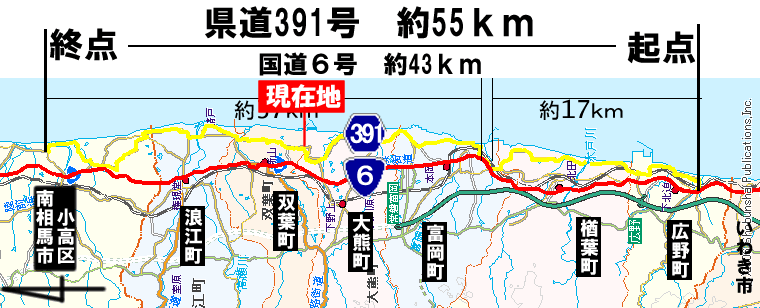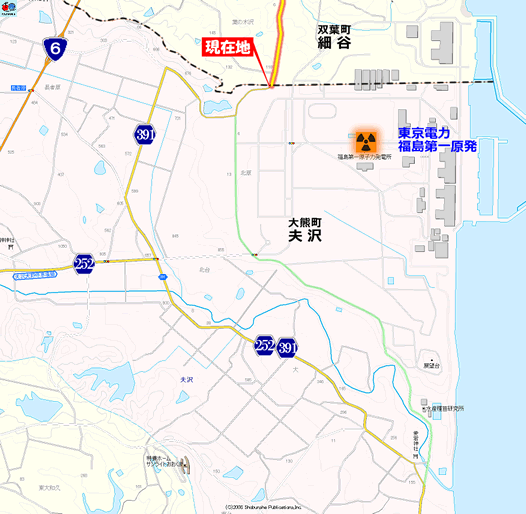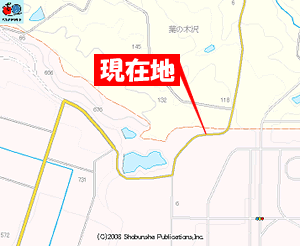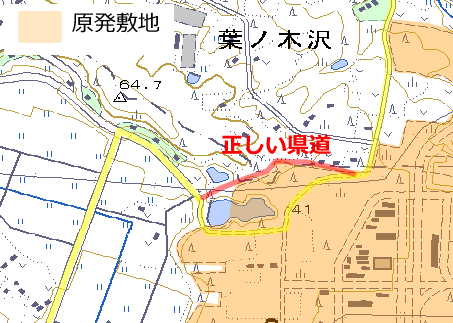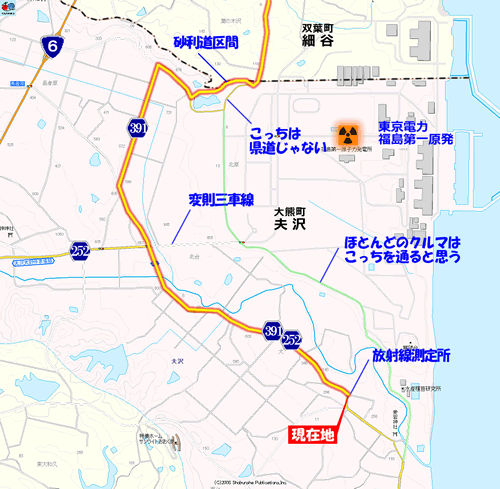10:42 大熊町境
ここから大熊町に入る。
現在のところ1.5車線の県道だが、握りしめた地図を見る限り、この先の展開はかなりの屈曲が予想される。
事前の段階でも、この先の原発から逃げるような線形は注目していた部分である。


大熊町に入って50m。
この、最初に現れた丁字路。
ナビクマちゃん曰く、「ここ右!」とのことである。
でも私は、まったく予想外の事態に固まった。
実はここ。
地図やカーナビを頼りに辿ろうとすると、まず間違いなく間違えるポイント。
正解は、ナビクマちゃんの言うとおり右なのであるが…。
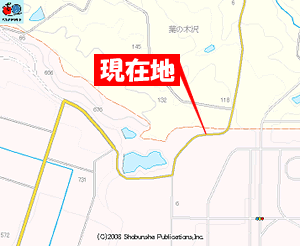
市販の地図やカーナビ、googlemap、さらには一番の頼りの地形図に至るまで、全ての地図は間違っている。
実際にはここに右折する分岐があって、県道はそちらであるのだが、分岐がそもそも描かれていない。
ここを正しく辿るには、これまで繰り返し出てきた小さな標識を見落とさない必要があるのだ。

ついに出た。
出ちゃったよ。
砂利道が。
3桁県道における砂利道自体はさほど珍しくないが、山地ではないところ(しかも住宅地の中)にあるのは、レア。
しかも、県道以外の道はちゃんと舗装されている中で、わざわざ砂利道を県道に指定したようにしか見えないのが、不思議。
不思議ゆえ、印象深いのだ。
長い長い県道391号だが、砂利道なのはここだけだ。

ちなみに、反対側から県道ハンティングをする人の事も相双建設事務所は大切にしているぞ。
砂利道から出てきた正面のガードレールにも、ナビクマちゃんがいる。
この相双建設事務所のこだわりは、一体どこからきているんだろう。(たぶん、管理者自体が県道がどこか分からなくなるからだよね…)
全国の有名無実幽霊部員県道を管轄する管理団体には、ぜひ見習って欲しい。

平凡な景色が続く県道391号のなかでは、珍しく語るべき言葉の多い場面である。
なんといっても、地図にない道なのだ。
しかも、地図にないのに不通ではないし、砂利道とはいえ道幅はこれまでと変わらずあるという、まさに「書き忘れ」臭の漂う道。
ぶっちゃけ、となりの道があるんだからそっちで良いジャン。
そう言われている気がしてしまう。
そしてここは、県道391号の中でもおそらく一二を争う閑散区間だろう。
なんといっても、地図に無い道。
そして、砂利道。
そもそもが、冒頭の地図に示した“緑の道”を使えば全て解決。
県道ハンターの他に、誰が好きこのんでここを走ろうとするのだろうか。
「語るべき言葉が多い」などと言いながら、気づけば2つしか言ってないね。
「地図にない」と、「砂利道」の、2つだけ…。
スポンサーリンク
|
ちょっとだけ!ヨッキれんの宣伝。
| 前作から1年、満を持して第2弾が登場!3割増しの超ビックボリュームで、ヨッキれんが認める「伝説の道」を大攻略!
| 「山さ行がねが」書籍化第1弾!過去の名作が完全リライトで甦る!まだ誰も読んだことの無い新ネタもあるぜ!
| 道路の制度や仕組みを知れば、山行がはもっと楽しい。私が書いた「道路の解説本」を、山行がのお供にどうぞ。
|
|
|
|
|
|


砂利道県道を楽しみながら(どう楽しんだのかと言えば、気怠い感じに楽しんだ)進んでいくと、呆気なく開けた場所に出た。
さして上り下りがあるわけでもなく、本当に呆気ないぞ。右折から350mほど走った地点である。
ナビクマちゃんが居て、右を示している。
まだここがどこなのか把握できないが、左からぶつかってきた道も砂利道である。
脳内コンパスを総動員して、現在地を想定してみる。
おそらく地図に描かれている県道というのは、このぶつかってきた道だろうと判断する。
まあ、判断が正しかろうと間違っていようと、道路管理者直結のナビクマたんは、絶対だ。
右折する。

右折すると、30m先に舗装路が待ちかまえていた。
なんとも準備が良いのである。
据え膳か。
…いや。
よく考えるとこれは据え膳ではなく、私(県道)が空気なのか。
どう見ても、この舗装路は左から来て正面に行く途中で、何となく県道を拾っているだけだ。
ナビクマちゃんが居ないので、地図を見て直進を決めた。
県道391号唯一の未舗装区間は、400m足らずで終わりを迎えた。

12:49
写真は、振り返って撮影。
こちら側から辿ろうとする場合は、さらに難しいと思われる。
2車線の舗装路から砂利道に直進するだけでも面食らうのに、即座に左のさらに狭い、まるで空気な砂利道に入らないと正確に辿れないのだ。
うっかりナビクマちゃんを見逃してまっすぐ行ってしまっても、400mほどでまた自然に県道に復帰してしまう罠。ミスしたことさえ気づきにくいのである。
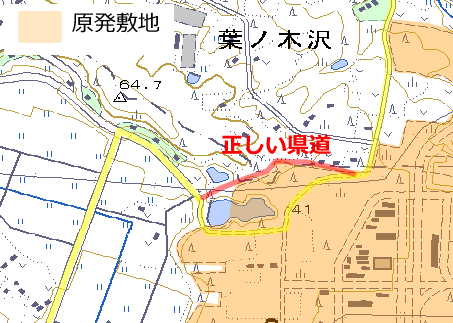
ちょっといま来た道を振り返ってみたい。
地形図に正しい県道を書き加えた上で、「特定地域界」の記号で囲まれている敷地(ここでは原発の敷地であろう)を色分けすると、早速その意味が見えてきたのである。
地図にない県道は、あくまでも原発の敷地には入りたくないよと言う、県道の強い意思表示だったのである。
実際には敷地内にも一般に開放されている道があるわけだが、そこは県道たり得ないルールがあるのだろう。
地形図でも、敷地内の道は破線の「庭園路」として描いていて、厳密に分けている。
例の“緑の道”も破線である。道理で県道には出来ないのだ。
県道を原発敷地から出すためだけに、わざわざ並行路線が多数あって通行量も皆無な中で、新たに400mもの砂利道を造ったのだろうか。

何事もなかったかのように2車線の舗装路が始まったが、大熊町に入ってからのナビクマたんの活躍ぶりは異常。
300mも行かないうちに、今度は左折である。
ナビがなければ全く地図頼みとなる唐突な丁字路。
しかも、やや左後方への左折である。
「原発から1kmくらい離れたし、もう大丈夫かな?」
そんな道の声が聞こえてきそうである。


先ほどとはうってかわって、今度は爽快なロングストレートである。
ここぞとばかりにフルスペックのヘキサも登場して、県道391号であることを誇示している(してないか?)。
だが、相変わらずクルマが走ってない!
だって、この600mほど西には国道6号が並行しているし、原発の敷地内を通ることを気にしないドライバーならば500m東にも良い道がある。
取って付けたようにここだけ立派な県道であるが、前後とも丁字路で分断されていて不便である。
どこまで行っても、駄目な道なのだ。(楽しいけれど)

直線区間はぴったり800mあった。
そして突き当たったのは、また2車線の道。
左折である。
あたりは久々の集落らしい集落で、福島第一原発に最も近い集落(直線距離で約1.3km)と言えるだろうか。
原子炉自体はもう少し離れているが。
向かいの通りは国道と原発を結ぶ道で、クルマ通りもそこそこある。
しかし生身の人影を見ないような気がするのは、もちろん気のせいだろう。
いたって平凡な家並み。
平凡な暮らしが営まれている、はず。

10:56 【現在地(別ウィンドウ)】
左折して進むこと400m。
なんだか久々に見る気がする。
信号だ。
そう思って過去を振り返ってみると、前に信号があったのは「だるまさんが転んだヌコ」のところだったから、もう7km以上も前である。
山道ならばいざ知らず、基本的に人里の近くを走ってきたのに、通行量の少なさが伺えるというものだ。
そんな久々の信号だが、ここで県道391号は、また新しい友人と出会う。
第四の友人、県道252号夫沢大野停車場線である。
友人は右から来て、県道391と一緒になって直進の方向に進むことになる。
ナビクマちゃんとも、これでお別れだ。

この交差点も、なんだ変だ。
2車線の県道2本が合わさって1本の県道になるのに、その先の道が1車線しかない。
その一方、大熊町道であるはずの道は3車線ある。
この3車線町道は、原発の正面玄関への道である…。
おそらく、ウラン燃料もここから運び込まれるのだろう。どんなクルマが持ってくるのか、想像できないが。
それになぜか、この3車線は2−1の変則車線になっている。
原発に行くクルマよりも、戻ってくるクルマが少ないという事でもあるのだろうか。

慎ましさには定評のある県道391である。
第四の相乗り友人に名乗りを委ね、1.5車線の穏やかな道が続く。
大熊町に入ってから、ずっと夫沢という大字だ。長い。
だから何だというわけでもないのだが…。
ちなみに、大熊町のマスコットキャラは、誰でも予想できそうなクマのキャラで、おおちゃんとくうちゃんと言うらしい。
だから何だと、言うわけでもないのだが……。

何かを語りたくなるような風景に出会うこともなく、1.5kmほどスルーした。
すると、「大」という字の集落で、ゴミ集積所のとなりに見慣れないものを見付けた。
嘘です。
外見的にはただの雨量計測所か何かだと思ったのだが、近づいてみて、これが珍しいものであることに気づいたのだった。

次第に離れつつある原発を、いまいちど思い出させられる。
いや、何より強く印象づけられる、そんな光景。
さあ、これは何でしょう?

Watch !! 【なんだか寒々しい動画】
うわー。
こういう施設って、あるんだね…。
住んでいる人も、毎日チェックしたりしているのだろうか。
「なんか今朝は数字が大きいな」とか。嫌だな。
念のため調べてみたが、この37ナノグレイ/時という数字は、正常である。
自然界の平常時が、20〜200ナノグレイ/時というから、いたって正常である。ほっ。
ちなみに、5000ナノグレイ/時になると、それが「通報すべき」基準らしい。
でも、それでもそんなに危険という訳ではなくて、「事故・緊急事態」と呼ばれるのは、「500000ナノグレイ/時」であるという。
…大丈夫。
何となくだけど、このデジタルは6桁も表示しそうな感じしないから…。
大丈夫だよね。