「峠の隧道が2本ある」という仮説の実地検証


2010/6/6 15:23 《現在地》
最初に洞内へ入った私から外へ脱出した。
予測していたとおり、崩土の斜面を四つん這いになってよじ登る脱出作業は苦闘そのものであり、大量の土や砂を顔面や頭髪で受けるという今夜の風呂場を掃除する人が可哀想になるような汚れ方をしてしまった。
しかしともかく20分ぶりに這い出した地上は、本当にホッとする生き心地のよい場所だった。
そして、私の沢山の成果報告を、我がことのように喜んでくれる細田氏にも癒やされた。
私に続いてたつき君とちぃさんも生還し、おそらく十和田山中で最も謎と危険に満ちた隧道から、全員が生きて戻った。
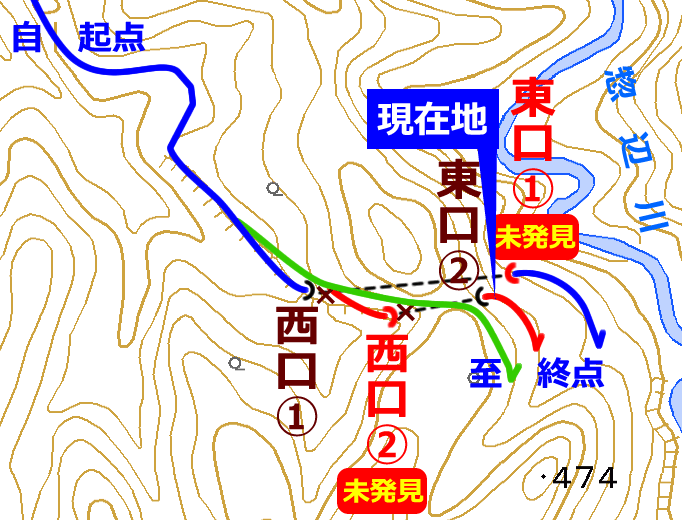
さて、改めて探索の今後の進め方を決めよう。
現在地は右図の「東口②」の前である。
「東口②」の反対側の坑口が「西口②」であるが、これはまだ見つかっていないので、一旦峠の西側へ戻って探そうと思う。
これが見つかってくれれば、「峠の隧道は2本ある」という仮説が、晴れて仮説ではなくなる。
その後は東側に戻って来て、最初に発見した「西口①」に対応する未発見の「東口①」の捜索を行う。
そこまで終わったらこの地を離れ、軌道終点&車デポ地点に向け、惣辺川沿いの未知の軌道跡の探索を進めよう。まだまだ探索の先は長い。

というわけで、まずは内部を探索し終わったばかりの隧道の出口を探しに行く。
←こんなに土被りの小さな短い隧道である。
こちら側の坑口と峠の位置関係を脳内にインプットした上で、隧道の延長線上をくまなく探していけば、すぐに反対側が見つけられるはずだ。
もし見つけられなければ、その時は「無い」と結論して良いだろう。

峠の切り通しを乗り越え、再び峠の西側へ。
そして改めて道の周囲を探してみると…
うん! 確かに怪しい地形がある!
たつき君が覗いている先の凹んだ地形が、まさにお誂え向きであろう。
なお、往路もこの景色を横目に見てはいたのだが、既に西口は発見済みという前提であり、まさか2本目があるなどとは全く考えていなかったので、気付くことは無かった。というか、この眺めだけで勘付けというのは、さすがに無理があるだろう。
私は斜面を直接下って、「西口②」の擬定地へ入った。


15:32 《現在地》
ここだな。ここが、「西口②」跡地だ。
さっき私の前を塞いだ土の壁の先である。
位置的にも、地形的にも、他に可能性のある場所はないので、間違いない。
そして案の定と言うべきか、完全に閉塞していた。
おそらく、底設導坑は貫通していたと思うのだが、自然に埋没してしまったようである。冷気も感じられなかった。
これを見て、改めて私は思った。
東口が開口していたのは、ほとんど奇蹟だったのではないかと。
なにせこの隧道は未成であり、断面が極端に小さかった。埋まってしまうのに必要な崩土も、通常サイズの隧道よりは遙かに少なかったのである。
あの奇蹟がなければ峠の隧道の正体は永遠に闇の中で、なぜ2本分の痕跡があるのかが、今より遙かに難解な謎になってしまっていたであろう。


坑口跡を発見したが、それに繋がる道はどうなっていたのかも気になるところ。
検証してみたところ、坑口跡の前には平場があり、それは10m程度は起点方向に伸びていたものの、その先の現在の峠道と合流する間際になって、突如痕跡が失われてしまった。
未成隧道に繋がる未成道であったために、ここまでしか施工されなかったのか、それとも単に崩れたのかは、残念ながら判断が付かない。
右の写真は、峠道側の想定される分岐地点から西口②の方向を撮影したが、一度素通りしてしまったのも当然なほど、何でもない景色である。分岐は見あたらない。
しかし、これは少しこじつけのきらいが有るかも知れないが、峠道はこの地点を境に勾配が変わっており、峠側は極端な急勾配で軌道跡を否定している。
対してここより下側は、勾配はあれど常識的な範囲内なのである。未成隧道が軌道用であったとすれば、そうあるべきと思える通りにはなっている。
これで「西口②」の探索は完了。
再び、峠を越えて東側へ向かおう。

続いて探すのは「東口①」と命名している坑口で、最初に見つけた「西口①」の反対側の坑口である。
西口①は峠から直線距離で100mほど離れた、高度的にはマイナス30m程度の位置にあったので、東口①は概ねその対照の位置にあると考えられたが、隧道がどの方向に伸びているかが分からないため、探す範囲は相当に広くせざるを得ない。闇雲に探しても時間を浪費する畏れが高い。
これらの坑口を結ぶ隧道こそが、昭和35(1960)年の地勢図に描かれていたもだと思われる。ということは、東口にも西口同様の明確な路盤跡が通じているはずである。
そう考えた我々は、峠越えの道を順当に下った先で路盤跡出会うのを待つことにした。急がば回れの精神で。

峠越えの道は、西側と同じように急勾配でぐんぐんと下って行くが、少し下ったところで振り返って撮影したのが、この写真だ。
ここは、先ほど内部を探索した東口②から伸びてきた平場が、峠道と合流する推定地なのだが、こちら側も合流の直前で平場は斜面になってしまい、いまいち判然としなかった。
これにより、峠直下にある未成が強く疑われる「短い隧道」は、前後の路盤が共に跡絶えている事が分かった。
未成であればこそという感じはするが、周辺は斜面崩壊も多発しているので、単なる偶然かもしれない。
間違いなく言えるのは、それが峠越えの道よりも現在使われておらず、踏み跡がないと言うことくらいだ。


今回撮影した「西口①」画像
それから1分も下らないうちに、今度はとても鮮明な道形が、我々の下に現れてきた。
そしてこの直後、我々の道が軟着陸するような形で、この鮮明な道形と一つになったのである。
この展開、もしも峠の西側に関する知識が全くなければ、一体何の道だろうかと思うところだろうが、今の我々にとっては、まさに予期して待ち望んでいたものであった!
これぞ今から1時間10分前に我々の前に現れ、その後の謎と興奮に満ちた隧道探索のきっかけとなった「西口①」の続きとなる正当な雲井林業軌道の軌道跡であるに違いなく、これを峠の方向へ引き返した先には――

まだ見ぬ「東口①」が、待っているはず!
果たして、坑口は開いているだろうか。
峠寄りの「短い隧道」は、底設導坑だけという極小の断面にも関わらず、東口は(辛うじて)開口していた。
対して今度の「長い隧道」は、雲井林業軌道が所有する内燃機関車が運行していたというくらいである。
断面は段違いに大きく、我々が見馴れている通常の林鉄隧道のサイズであったと想像される。
開口部が現存する条件は、「短い隧道」よりは幾分は良いと思われる。

1時間以上ぶりに歩く、軌道らしい緩やかな勾配を持つ道。
さすがにそう都合良く枕木やレールが出迎えてくれるようなことはなかったが、先ほどまでの峠道とは、やはり雰囲気が違っているように感じられた。
しかし、峠の西側で歩いたときには見せることのなかった“表情(かお)”も、ここにはあった。
それは――、廃道の表情。
廃止されてから経過した時の長さが、鬱然とした濃い藪という鎖錠に形を変えて、我々の行く手を遮った。
常に踏み跡を朋として、明るい日射しに満ちていた、西側の路盤とは全く異なる表情だった。
シェイキチ氏がクマを怖れて立ち入らなかったという峠の東側、惣辺川沿いの未知の軌道跡は既に始まっている。
その恐ろしさ、困難の片鱗を私は感じていた。しかしまずは隧道跡だ。

|
キター! 斜面に沿っていた道形が、突然の心変わりのように左へカーブ。そして、峠尾根の方向へと正対する。 この展開は、まさに西口で見たことの再現であった。 内部を探索する“最後のチャンス”と対面だ! |

|

15:48 【現在地は後述】
終わったー!!
「東口①」は開口せず!
思わず、失意体前屈(orz)を作りそうになったが、現実は受け入れなければならない。
負け惜しみにしか聞こえないかも知れないが、失意や落胆もまた探索の醍醐味なのだ。クリアがないTVゲームは欠陥品だが、現実の探索は違う。
西口①と東口①が共に埋没した「長い隧道」は、もう永久に探索することが出来ない。それが現実だった。
それに、ここにあるのは落胆ばかりではない。
こうして最初は仮説上の存在に過ぎなかった坑口跡が残らず発見された事により、峠の“2本の隧道”が現実となったのだ。こうした仮説と検証こそ醍醐味だ。

隧道が地上に残した痕跡を求めて、周辺を更に捜索する。
坑口跡のすり鉢状に凹んだ地形の規模は、既に見た3箇所の坑口のどれよりも巨大だったが、完全に安定した土の斜面と化していて、空洞を疑わせる冷気も漂っていない。まさに絶望の状況だった。
さらに坑口跡地から尾根方向の地表には、連続した窪地が見られた。
これはおそらく地下の坑道の落盤に伴う陥没地形であると思われ、洞内も惨憺たる状況になっていそうである。
だが、この陥没地形が暗示する坑道の存在は、坑口跡しか残っていない「長い隧道」もまた未完成だったのではないかという疑惑を、ある程度まで払拭してくれるものだと思う。
このように、峠の大地には今なお「長い隧道」の断末魔の叫びが、深く刻み込まれていた。
一帯は全体的に土の山であり、隧道を長期間保存しておくにはいかにも不向きである。岩山ならばこうはならなかっただろうから惜しい。
そして、一時とはいえこんな隧道向きでは無さそうな土地に隧道を完成させて運用していた雲井林業という集団の技術力、ないしは根性の強さに感銘を覚えた。
華やかな奥入瀬渓流のバス停に名前だけを残して忽然と姿を消した雲井林業とは、いったい。

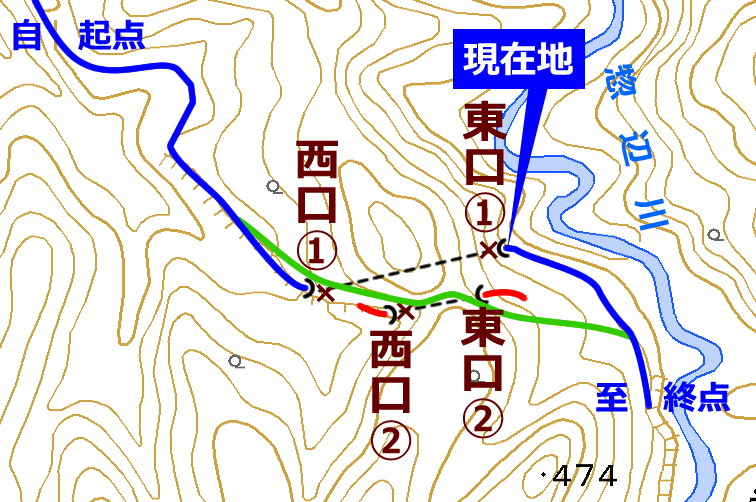
(←)「長い隧道」東口①跡地からは、「短い隧道」東口②および峠の切り通しを遠望できた。
この探索ではGPSを利用していないので各坑口の絶対的に正確な位置は分からないが、右図のような位置関係が推測出来る。
これによれば、「短い隧道」の全長はおおよそ50m、長い隧道は150mくらいで、前者は峠の切り通しの直下に、後者はその北側に芯をずらして抜いている。
2本の隧道だけでなく、それらに付随する路盤の位置も注目である。
「短い隧道」の前後の道が断絶していて、他の道と繋がっていないことが印象的だ。
また、「長い隧道」の路盤は、いかにも林鉄らしい勾配の特徴を持っていると思われる。
おそらくこの路盤には、峠の前後においても一様に終点から起点方向に下る勾配がついている。おそらく洞内もそうだろう。
林鉄の通常の運用では、麓から山へ入る時は軽荷であるから上り勾配も走行できるが、山から麓に出る時には大量の木材を積載しているため上り難くなる。運材方向の下り坂を順勾配、運材方向の上り坂を逆勾配といい、逆勾配区間をできる限り避ける事は林鉄路盤の重要な使命であった。その点でも「長い隧道」の路線は優秀で、「短い隧道」の路線は不出来といえる。

こうして、今回の探索の最大の目標物であった“峠の隧道”を巡る探索は、ひとまず終了した。
続いては終点へ向けて惣辺川沿いの軌道跡を探索していくが、峠の隧道については未解明の謎がまだ色々と残っている。
- なぜ、2本の隧道が存在しているのか。
- なぜ、「短い隧道」は完成前に放棄されたのか。
- 2本の隧道はいつ建設され、どちらがより古いのか。
諸々の謎に後ろ髪をひかれながらも、生還のために我々はここを後にする。
足元には、ここから新たに始まる薄暗い路盤跡。
背には、早くも暮色を浮かべる峠の稜線。
仲間がなければ先へ進むという気力を萎えさせてしまいそうな淋しい現場。
だからこそ、私は務めて明るく後半戦へと舵を切った。