短いが前人未踏? 北口からのアタック


2008/10/23 7:37 【現在地(別ウィンドウ)】
城里町七会の下赤沢と大沢を結ぶ峠にあるという一本の廃隧道。
「てんてん」氏によってもたらされた衝撃的な情報を元に捜索を開始した私だが、下赤沢側(南側)の旧道入り口は発見できなかった。
そのまま昭和60年に開通したという新道で峠を越えて大沢側へ下り、今度は北側の旧道入り口へ立った。
地形図曰く、このカーブの地点(左写真)から右に旧道が分かれており、坑口までは僅か50mほどの隔たりであるはずだが、あるべき道の姿はない。
そこにあるのは、現道が築き上げた数メートルの段差と、そこを覆う猛烈な草藪であった。

少しでも踏み込めば確実に絡め取られる激藪に、はじめの一歩をなかなか踏み出し切れない私だったが、かといって踏破を諦めるわけにもいかず、20mほど現道を峠方向へ進んだ杉林からの迂回アプローチを決行した。
普段は面白みのない景色として敬遠される杉の植林地だが、通行するという意味においてはかなり自由度が高い。(ただし自転車は現道に置いてきた)
杉林から谷の中に入ると、草むらとなった最低地より一段高まった斜面に、道路跡らしき平場を発見。
これが旧道の跡と思われる。
てんてん氏も未見であるという北側坑口の出現に、否が応でも期待が高まる!

7:41
決着は何とも味気ないものだった。
考え得る限りの最悪の決着と言っても良い。
道跡らしき平場を50mも辿らぬうちに沢の奥に突き当たったのだが、そこには期待された坑口が口を開けていなかったばかりでなく、場に似つかわしくないコンクリートブロックの壁が跡地と思われるあたりに長々と築かれており、一切の隧道の痕跡を失わせていたのである。

かつて隧道が口を開けていたはずの斜面だが、いかなる痕跡も残されてはいなかった。
ただ、そびえ立つ山腹の広大さ、スカイラインの遠さが、この隧道の持つ140m近い長さを物語っている。
斜面の最下段に土留めとして築かれたコンクリートブロックの壁は、この山腹で大規模な治山工事が行われた過去を物語っている。
そのときにはすでに隧道は崩壊していたのか、復旧されることなくそのまま埋められたのだろう。
この時点で、目指す隧道にはただ一つの坑口しか残されていないことが確定した。
オブローダーにとって最も甘美であると同時に、その身を冒す毒をも孕んだ禁断の果実。廃隧道。
その出現が、いま約束された。
|
スポンサーリンク |
ちょっとだけ!ヨッキれんの宣伝。
|
最終坑口への直下降

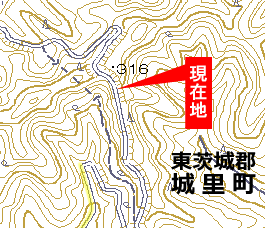
7:49
失意の北口を後に峠へと戻った。
峠の西側には急な斜面が口を開けているのだが、地形図ではこの直下の約50mほどの地点に隧道が描かれている。
てんてん氏がそうして坑口に至ったように、私もこのルートにチャレンジすることにした。
チャリは峠の広場に停めて置くことにしたが、たまたま通りがかった人にそれが不法投棄物と間違われないかが心配である…。

細い木々が疎らに茂り下草はほとんど無い、斜度45度ほどの斜面。
土壌は比較的柔らかく、ほどよく足をグリップしてくれるので、結構なペースで跳ねるように下っていくことが出来る。
これならば、どうにか登ってくることも出来るだろう。
それにしても、目に余る不法投棄物の量だ。
空き缶やペットボトルなどの生活廃棄物を中心に、プランターや植木鉢などの園芸道具、布団やテレビなどの家財道具、さらにドラム缶や便器など、あまたのゴミが斜面の広範囲に散らかっているのである。
隧道へのショートカット路は、心ないゴミによって導かれた。


休むことなく30mは下っただろうか。
まだ谷底は先だが、斜面の途中に左写真の土留めがあった。これは上の車道と同じくらい新しそうだ。
多数のゴミがここに引っかかっているが、バウンドしてさらに落ちていったものも少なくない。
斜面の途中で見た、小さな突起がたくさん付いた、ツタとも木ともとれない怪しい植物(→)。
葉もつけず、根もなく、明らかに異形だ。
ゴミを際限なく捨てつづける人間に対し、怒り心頭となった木の形相か。

行く手に谷底が見えてきた。
そこに道らしい道は見えないが、右の方には大きく陥没したような凹地がある。
あそこが隧道か!?
とても地味な「大沢道」に秘められた、140mの廃隧道。
ようやくその姿を私に示す時がきたようだ。
斜面を駆け下る私の鼓動が、脳波が、1mごとに興奮値へと近づいてゆく。

廃隧道出現!
まるで “あなぐら” のような坑口が、
ゴミのロードに導かれた薄暗い谷底に、ひっそりと口を開けていた。
下に何があるかなどと考えもしなかった人々が放り捨てた、無数のゴミ。
坑口前は、そんなゴミたちが土に帰ろうと万年を過ごす、終の地であった。
見通せぬ闇をたたえ、僅かに水を漏らしつづける隧道は…まるで…、
哀れな

普段の私なら、廃隧道を見つけてもすぐに近づきはしない。なぶるように、ねじるように、いろいろなアングルから撮影をしながら近づいてゆくところだが、今回は脇目もくれず坑口へと吸い寄せられた。
この隧道の怪しい外見や谷底という立地が私の心を鷲づかみにしたためだが、それだけではない。
もっと重くて、挑戦的で危機的な心持ちもあった。
端的に言えば、「この隧道に入るのか?」という“怖さ”だ。
そして、ゴミ同然に傷ついた我がカメラ(LUMIX DMC-FX30)は、間近で坑門を撮影することに何らかの抵抗を見せた。
現地では気づかなかったのだが、その写真はご覧のようにデジタルデータの「赤色」がほとんど欠損していた。
映像素子までも隧道を畏怖したと言えばあまりにオカルティックだが…。
ともかく、そんな威圧された心境のまま、私は初めて洞内に光条を投げるのだった。
大沢隧道(仮) 洞内探索

7:54
坑口からチョロチョロと水が流れ出していることからも、洞内の水没は約束されたものであった。
問題はその水位ということになるのだが、てんてん氏が洞内探索を断念したというそれは、甘いものではなかった。
それなりの覚悟を要する水位である。
数字にすれば、50cm以上1m未満くらいの水位。
長靴ではフォローしきれ無いが、胴体にまでは至らないという水位。
命の危険まではないが、普通の大人にとって腰まで濡らすというのは、もはや非日常に類する行為となる。
オブローダーとしての本気を試される水位だ。

引き返すという選択肢ははじめから無かったわけだが、それでもやはり、「その日一番目の探索で唯一の靴を濡らしてしまった悲しさ」は、股間に届かんとする冷水以上にドシンと心を揺らすのであった。
毎度おなじみ、長靴を履いていても必ず足が濡れるのが「山行が」クオリティーだ。
もっとも、一度の濡れに一日を嘆き過ごした頃の私ではない。
いまや長靴の下には「ネオプレーンの靴下」を装備しており、水の冷たさは敵ではない。
独特の不快さも、あと30分も経てば慣れてしまうに違いないのだ。

隧道水没の原因は、坑口に堆積した大量の土砂である。
スコップとツルハシがあれば、小一時間で水位は30cmくらい下げることも出来そうである。
もっとも、そんな回復策をとったところで、本隧道の閉塞という事実は揺るがない。
全長エックスが0から140までのいずれかの数字をとるのか。
その一点に私の興味も使命感も集約されている。
土臭い素堀の廃隧道に、それ以上の期待を持つべきではない。

洞内の水位は、予想通り入洞直後が最も深く、股間に届くかどうかというレベルであった。
また、洞床に堆積した泥の層の厚さも、奥へ進むにつれて水深以上に早く減衰していく。
足裏に確かな地面の固さが感じられるようになるのは、すぐだった。
水没隧道ではおなじみの光景が眼前数十センチで展開している。
まるでタコの墨吐きを見ているような泥雲の襤褸。
洞床の目視確認は、一歩ごと1秒程度しか許されない。
これもセオリーである。

水没した洞床に沈む、不気味な黒い物体たち。
それは入洞した時点でもチラチラと目に付いたが、坑口から20mほど進んでもなお途絶えなかった。
腐りきった体を寄せ合うような物体の正体は…。
一斗缶であった。
“塵の王”は、その体内にまで無数の一斗缶を遺棄されていた。
そして、やがて隧道は水没。
暗く静かな水中で、それは真っ黒い錆に全身を冒された異形に成りはててなお、形を留めつづけて来た。

好奇心から、一斗缶の変わり果てたモノを軽くつま先でつついてみた。
すると、ザクッという微かな感触を返しただけで反発が無く、長靴の先端はいとも容易く缶の壁を突き破ってしまった。
その感触は、口の中でお菓子のパイを噛むときのそれに似ていた。
元は堅くしなやかな金属だったモノが、触れただけで砕け散ってしまうのだった。
一斗缶の正体が不明なだけに、靴越しとはいえ触れるのは気持ちが悪かった。
だが、その破壊の感触は、常識的な「金属>肉体」という常識を覆すカタルシスに満ちており、私は悪のりしていくつも爪先で砕いてみた。
5個目あたりだったろうか。
同じように突くと、ザクッという感触と同時に、ゴボゴボッと泡の固まりが水面に飛散したのは。
一斗缶の腐りきった片隅にかろうじて残されていた、最後の一息だったのだろう。
その空気を見た瞬間、私は我に返った。
ここで無意味な遺構の破壊を楽しんでいる場合ではない。

隧道は完全に素堀であるが、壁面や天井に目立って崩壊の跡はない。
断面は一般的な馬蹄形に近く、道路トンネルとしてはやや縦長の印象を受ける。
幅員3m、高さ4.5m程度というのが私の目測だ。
洞床は未舗装で、土道のようである。
坑口から50〜60mほど進んだ地点で、水位は20cm程度にまで下がった。
これは、洞内に勾配がつけられているということだ。
この後で閉塞している北口へ向かって再び下り勾配となる場合には、また水位が上昇してくることが予想される。(拝み勾配)
このまま陸地のまま終われば、それは片勾配であったということがいえる。
そして、このあたりから洞内の靄が濃くなってくる。
閉塞隧道ゆえ風の流れがないからこういうことが起こる。
靄の弊害は、フラッシュを使って撮影したときに鮮明に現れる。
そのほか、気温の低さから自身の吐いた息も白くなり、これもフラッシュ撮影の邪魔をする。
この種の廃隧道では、必要以上にハァハァしてはならない。
立ち止まってから息を整え、カメラを出来るだけ口から放して、それから撮影する必要がある。
 70〜80m地点でも、水位はまだ10cm程度あった。
70〜80m地点でも、水位はまだ10cm程度あった。なかなか陸は現れないが、一斗缶は一つも現れなくなった。
そこで、右側の壁に屈めば大人が2〜3人が入れるくらいの大きな凹みが現れた。
その姿は、まるで鉄道用トンネルの待避所のようである。
…これは、小さいようで非常に大きな発見である。
この位置の凹みは、意図的に削ったのでなければなかなか自然崩落で発生するものではないと思われるし、未だかつて道路用トンネルで待避所があるものはごく少数しか発見されていない。
まして、素掘り隧道では鉄道用トンネル以外に待避所のあるトンネルを見たことはない。
これは何を意味しているのだろう。

振り返って見た待避所の様な凹み(左側の壁にある)。
それは、明らかに人工的な凹みである。
この凹みについて考えられる可能性は…
1.実は鉄道用トンネルとして掘られていた。
2.道路用トンネルだが、歩行者と自動車のすれ違いを考慮して待避所を掘った。
3.待避所ではない、別の用途のある凹みであった。
…と言うようなことが考えられる。
この隧道に関しては、本当の名前はおろか竣工年も建設のいきさつも分からない。
よって、これ以上突っ込んだ推理は難しいのだが、最も興奮できる推理は「1」だろう。
現在も机上の調査を続行中である。

なお、天井にも正体不明な凹みは存在している。
横の凹みの少し奥の地点で、天井が縦横2m、奥行き1mほども膨らんでいるのだ。
壁が全面的にごつごつしているため、どこが崩壊面で、どこが人工的に削った部分なのか、判別が効かない。
もし崩壊跡だとしても、落ちた土砂はすでに運び出された後であり、洞床は平坦だ。

100mも来ただろうか。
当然のように出口は見えず、まっすぐ素堀の隧道が続いている。
唯一の変化としては、ついに洞床が陸地に変わったことくらいである。
そして、この陸となった部分には、トラックのものと思われる太い轍が残っていた。
轍には、いまだにタイヤパターンが残っており、さほど古くないものと思われる。
だが、ここで問題になるのは、水没した洞内に多数残されていた一斗缶である。
一斗缶を破壊せずにクルマが通行することは不可能であるから、普通に考えれば、このクルマは北口から進入したのである。
これは全くの推定だが、北側坑口を完全に埋め戻した治山工事の際に、何らかの事情によりここまで工事車両が進入していたのではないかと思われるのだ。

うおっ!
コウモリが飛んできた。
ますます靄が深くなってきたが、閉塞地点も近いようだ。
私の止まらぬ進撃に痺れを切らしたコウモリの先鋭部隊が、威嚇と思しき飛行を開始したのである。
彼らには申し訳ないが、閉塞を確かめるまでこの足を止めるつもりはない。

き、 来た…。
閉塞している。
入り口からは、120〜130mほどである。
かなりの確率で、ここは埋め戻された北口付近である。


8:01
閉塞地点は、明らかに埋め戻しの痕跡を留めていた。
天井などに崩壊はないにも関わらず、天井まで全く隙間無く土砂の山が出来上がっている。
さらに、土砂は洞内の岩石片をほとんど含んでおらず、外から運び込まれたものと考えられるのだ。
また、南口では全く見られなかったものとして、大量の廃材の存在が挙げられる。
その一部は土砂に半ば埋没しつつも壁面に沿って直立しており、これらが支保工であったことを教えている。
失われた北口は支保工付きの、おそらくは【こんな坑門】だったと思われる。
尊い下半身の犠牲と引き替えに、隧道の探索は極まった。
しかし、まだもう少しレポートは続く。
| 当サイトは、皆様からの情報提供、資料提供をお待ちしております。 →情報・資料提供窓口 | |
|
このレポートの最終回ないし最新の回の「この位置」に、レポートへのご感想など自由にコメントを入力していただける欄と、いただいたコメントの紹介ページを用意しております。あなたの評価、感想、体験談など、ぜひお寄せください。 【トップページに戻る】 |
|