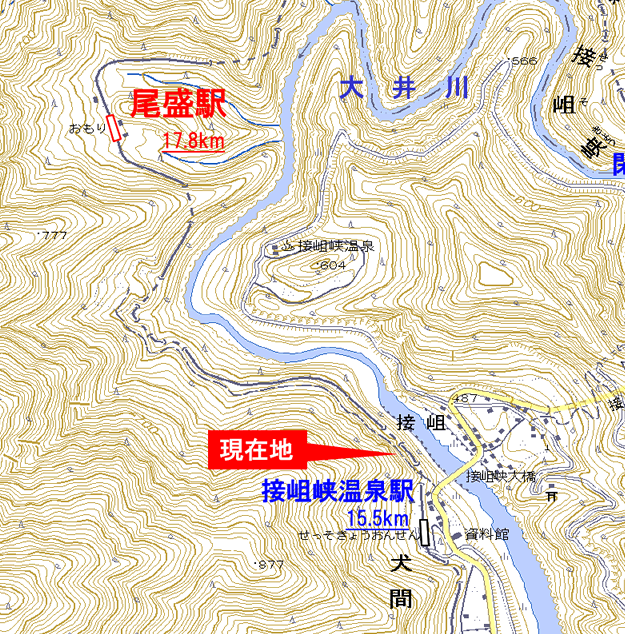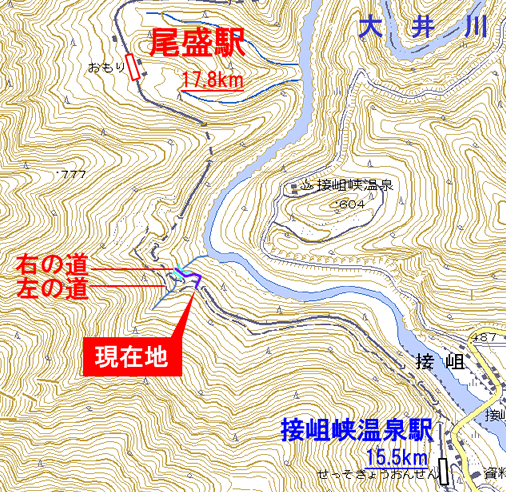駅周辺に民家は無く、その上駅に通じる車道も1つも無い。このため鉄道でしかこの駅へ来ることはできない。
そのため、一部の鉄道ファンに日本で最も理想的な秘境駅といわれている。
2008年度の年間乗降客数は574人である。
wikipedia:尾盛駅 より引用
果たして私は、
“日本一理想的な秘境駅”の「常識」を、
覆せるか!
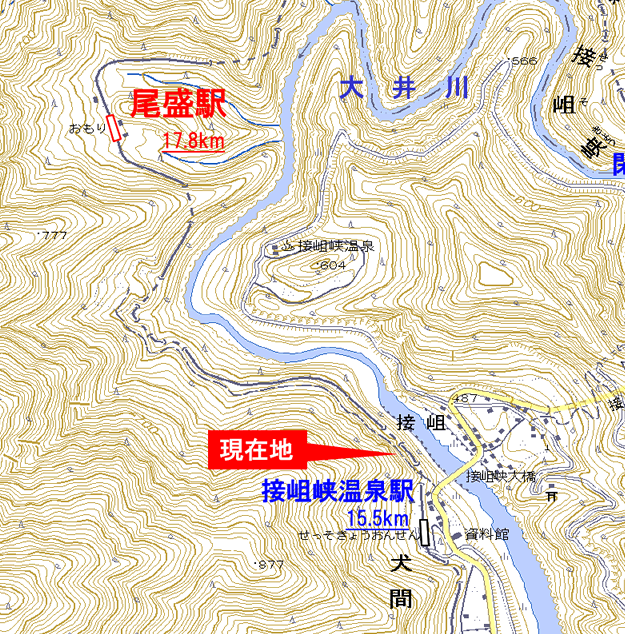
現在時刻 13:28
★乗車目標 (第1希望)
尾盛発 14:53 (千頭方面行き)
☆乗車目標 (第2希望)
尾盛発 15:10 (井川方面行き)
○最終防衛ライン(終電…)
尾盛発 16:28 (千頭方面行き)
現在地(右図)は、接阻峡温泉駅を出てひとつめの「(井川線)第27号隧道」の地先であり、駅間線路長2.3km中の300m程度をこなしたに過ぎない。
とりあえず路面状況は「まあまあ」だが、予断は許さない…というか、まだ全然先の展開が読めない状況だった。
オブ・チャレンジング・ナウ!

「第一竹の花橋」だという。
木製の桟橋で、谷側のみに手摺りが設けられている。
この幅1.2mほどしかない路盤上には溢れんばかりに落ち葉と瓦礫が載っているが、左の斜面から地続きにもたらされたものであろう。
親柱は無い代わりに、気の利いた立て札に前述の橋名のみが書かれている。
竣工年度を伝えるものはない。
そしてこの橋、よく見ると(よく見なくても?)ただの木橋ではない。
木床板の下には、鋼鉄製らしき赤塗色の“アイビーム”が敷かれているのだ。
さらにこのビーム桁を支える橋台は、小振りながらコンクリート製であって、空積み石垣の小さな築堤に続いている。
上部構造は間違いなく「遊歩道」のそれであり、平成以前とは思われない。
だが下部構造については、それ以上の規格(例えば軽車道)としても通用しそうな強度を持っていそうに見えた。


←
すぐ先に、今度は少し大ぶりな橋が現れた。
「第二竹の花橋」だという。
→
それからまた100mほどで、再びよく似た橋。
しかし、意外に谷は深いので、橋がなければ苦労したっぽい。
「第一井戸沢橋」。


←
連続して、写真を見ただけじゃ区別が付かないくらいよく似た橋が現れる。
順当に、「第二井戸沢橋」。
→
「井戸沢」の由来が気になるところだが、橋の脇に古い水槽らしきものがあった。
遊歩道のタイムスケールは平成だが、この水槽はもっと古そうだ。

同橋から大井川を見下ろすと、
V字に切れ込んだ意外に険しい谷が、
20mほど下で井川線のガーダー橋に跨れていた。
現在地は、井川線が接阻峡温泉駅から2本目の隧道(第28号隧道)を抜けた辺りだ。
そしてこれを撮影した直後、井川行きの列車が林間をすり抜けていった。
意外にあっという間で、上手く撮れなかった。

再び桟橋が現れたが、崩土によって上部構造はほとんど崩壊していた。
それでも、堅牢な鋼鉄のビームのおかげで、まだ当分は渡ることが出来そうである。
なお、本橋はついに「立て札」が行方不明で、名称不明であった。

壊れた橋を抜けても、路上の荒れ方はすぐに治まらなかった。
いかにも歩道らしい華奢な欄干(ガードバー)は、倒木に打たれて延々と倒れてしまっている。
荒れた印象から始まった杉林だが、実は中だるみの始まりであった。
むしろ、ここまでが相当に険しい地形であり、橋が完備されていなければかなり難儀したと思う。
スポンサーリンク
|
ちょっとだけ!ヨッキれんの宣伝。
| 前作から1年、満を持して第2弾が登場!3割増しの超ビックボリュームで、ヨッキれんが認める「伝説の道」を大攻略!
| 「山さ行がねが」書籍化第1弾!過去の名作が完全リライトで甦る!まだ誰も読んだことの無い新ネタもあるぜ!
| 道路の制度や仕組みを知れば、山行がはもっと楽しい。私が書いた「道路の解説本」を、山行がのお供にどうぞ。
|
|
|
|
|
|

13:44 《現在地》
接阻峡温泉駅前を出発してから30分を経過。
私は、地形的にも景色的にも変化に乏しく、現在地の把握が難しい杉の一大美林地帯を歩いていた。
特に障害物もアップダウンもないので歩行のペースは順調だが、現在地が分からないというのが不安である。
尾盛駅に私が乗りたい列車が来るまで、あと70分弱しかないことになる。
廃道歩きの1時間など、意外に短いものである。
…それにしても…
杉林を走る井川線は、まるで生きた林鉄を見るかのようだ。
実際この路線の黎明期において、ダム資材運搬の傍らの林産物の輸送が、重要な任務であった。
ある意味ここは、「軌間1067mmの林鉄」だったのである。

橋がありそうもないところに、お馴染みの「立て札」が立っていた。
「立枯橋」だというのだが…
で、橋はどこ??
もしかしてこれは、管渠なんでは…?
それに、人工林にある「立枯橋」って…KY…。

“KY橋”を過ぎてすぐにまた橋。
穏やかな林間の水涸れした小沢を、やや大仰な感じで跨いでいる。
「第二日影橋」というらしいが、そういえば「第一」が見あたらなかった。もしかして、さっきの名無し橋がそうだったのか。
そろそろスタートから1kmくらいは歩いた気がするのだが、景色の変化が乏しくて少し飽きてきた。
このまま尾盛駅に行けちゃったら、それはそれで拍子抜けだニャア。

第二日影橋の10mほど先。
路肩に、こんなものが置かれていた。
…見覚えのあるこの形、サイズ、塗色。
明らかに、これまでの各橋に使われていたアイビーム桁である。
なぜ置き去りになっているのかは不明である。
ビーム桁なのでプレミア感はどうしても薄いが、廃橋に違いはない(と思う…)。

何か見えた!
なんか、安っぽい…リゾートの雰囲気…。

あれれ?
分岐??
ち、地図にない分岐だ……。
線形的な“道なり”は左っぽいのだが、手摺りは右に付いている。
特に道案内のようなものは見あたらない。

これが、左の道。
明らかに道がある。
しかも等高線に沿っていて、道としても順当だ。

今度は、右の道。
…って、谷底に吊り橋が見える!!
これは大井川の本流ではなく、それに流れ込む支流の谷であるようだが、今まで見てきた小川レベルの谷とは段違いの深さと大きさ。
ザーザーと水の奔る音もここまで届いてくる。
そしてよく見ると、吊り橋の左側に沿って梯子状の鉄道橋が確認された。
2本の橋が谷底に並行しているらしい。
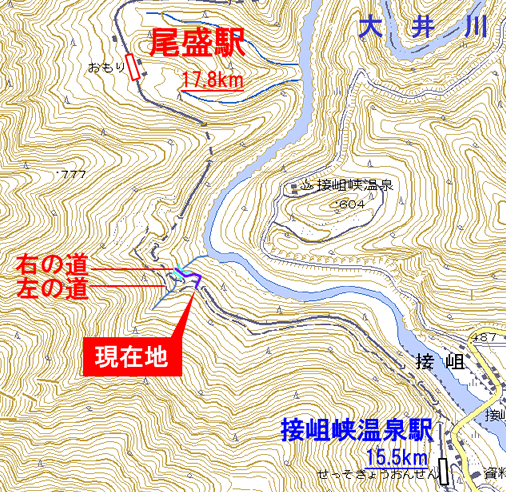
14:00
現在地は、ちょうど井川線の3本目のトンネル「第29号隧道」の真上である。
このトンネルのお陰で、久々に現在地点を確信することが出来た。
ここで地形図にある「破線道」と、地形図にはない谷底へ下る急坂の道が分岐している。
一体どちらを選べばいいのだろう…。
どちらかが尾盛駅へ繋がり、他方は行き止まり…或いは、どこか別の場所に行くのだろうか。
信念的には、「より古そうに見える」左の道を選びたかったのだが、結局右の道を選ぶことになった。
その訳は…
吊り橋である。 いうまでもなく…。

吊り橋への逸る気持ちを受け止めんとするかのように、さっき木の間に見たウッドテラスが待っていた。
清掃されないままで、かなり見栄えは悪くなってしまっているが、まだ使えないほど傷んではいない。
が、遠からず、“世の木橋”と同じ末路を辿るに違いない。
苔色に変色したウッドチェアやテーブルで交わされた笑顔の数は、果たしていかほどだったのか。
ゴミひとつ落ちていないのは喜ばしいのだが、使用感の乏しい印象を受けた。
…下手したら、未成ではないかというくらいに。

右の写真は、テラスに置かれていた鳥の図集。
個人的にあまり興味のある題材ではないのだが、この案内板の最初の活躍の場面かも知れない気がしたので、じっくり眺めてみると、発見した。
一番下の所に、小さな文字でこう刻まれていたのである、
日 影 山 展 望 台
地形図にはない地名だが、ここは日影山というらしい。
そして日影山こそ、失われた尾盛への道の、正統な経由地名かもしれない。

幾分のプレミア感がある(?)、日影山展望台よりの眺め。
目指す尾盛駅は、典型的な河跡地形による小山間盆地にあり、
ここからだと外輪山的な役割を果たす峰が邪魔をして、見通すことが出来ない。
しかし、距離感としてはだいたいを捉えることが出来た気がする。
…正直、あと1時間弱で辿り着けるかどうかは、道の状況次第だと感じる距離である。
スタスタ行ければ30分くらいだろうが、今眼前に大きな谷が口を開けている状況で…
大口は叩けない。

吊り橋へはこれを下るのか。
今までのアップダウン控えめの道とは別物といえる、急転直下の大階段である。
やっぱり左の道が“正解”だったのではないかという疑念を懐かざるを得ない。
が、もしミスだったら戻る時間も必要となるわけで、ちょっと駆け足で下った。

14:03
吊り橋に到着!
地形図にはない橋だが、意外に立派である。
踏み板こそ木張りだが、手摺りも密で、余り揺れそうにないし、安心して渡れそうである。
しかし、こんなすぐ隣に井川線の立派なガーダー橋が架かっているとは、意外。
橋の両側はトンネルだが、これならば大勢の乗客が見ているはずなのだ。
この吊り橋を。
これを見て「尾盛駅への道がある」と疑った人は、今まであまりいなかったのだろうか。

トンネルに入る度に甲高く「ポー!」 と鳴くので、列車の接近はかなり手前から予期できる。
そしてひときわ大きな「ポー!」のあと、一瞬だけ静けさを戻してから打ち返すように大きくなった爆音の主が、対岸の「第30号隧道」からヒョコッと顔を出した。
対向の千頭行きだ。
初めて間近に見る、井川線の列車。
トンネルのサイズとかわんねー!
ワラっちゃうほど小さい。
自分自身と同じくらい大きな銀色のポーナル風プレートガーダーに、ガタガタギャギャギャと乗り込んできた。

キタ――!
めっちゃ運転士さんこっち見てる。

ポ――――ッ!
行ったか…。
ちょっと、ワルニャンがドキドキしたぜ…。

間もなく何事もなかったかのように、脚下の瀬音が耳に戻ってきた。
両者を隔てる僅かばかりの橋も、もちろん、残ってくれていた。
この橋の第一印象(遠景)は脆弱だったが、近付いてみると意外に堅牢だった。
しかし渡ってみた最終的な印象は、やっぱり脆弱。

正確には、老朽化による弱化である。
外見以上にこの橋は衰えが進んでいて、踏み板は腐朽のため部分的に波打っていた。
もちろん踏み心地も相応で、ユラユラのうえにフカフカするという有様。
橋自体が高くないので、今はまだ鼻歌レベルだが…。