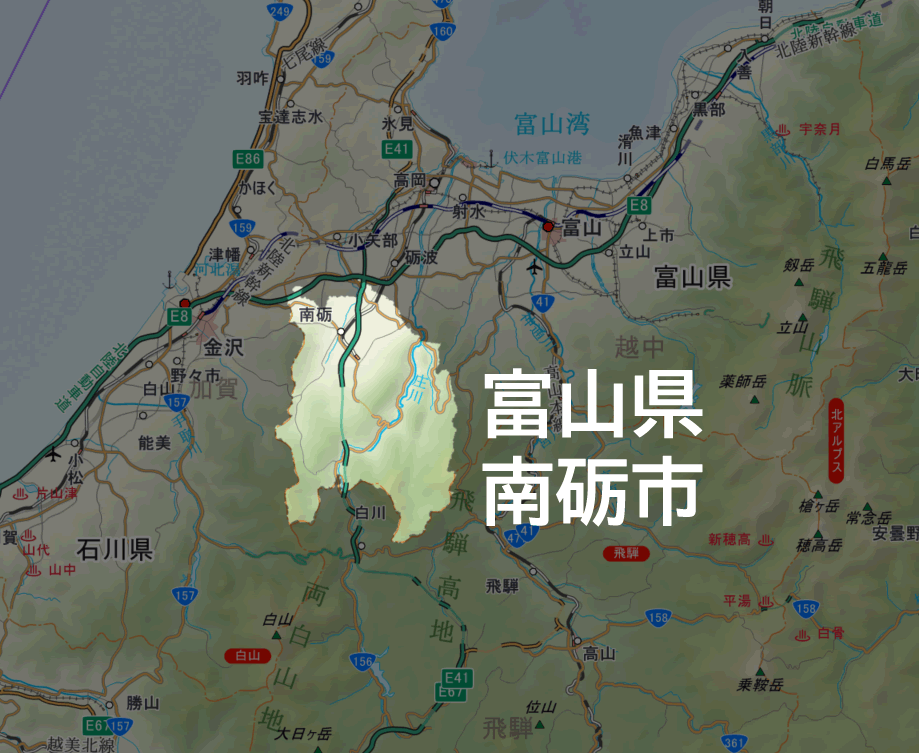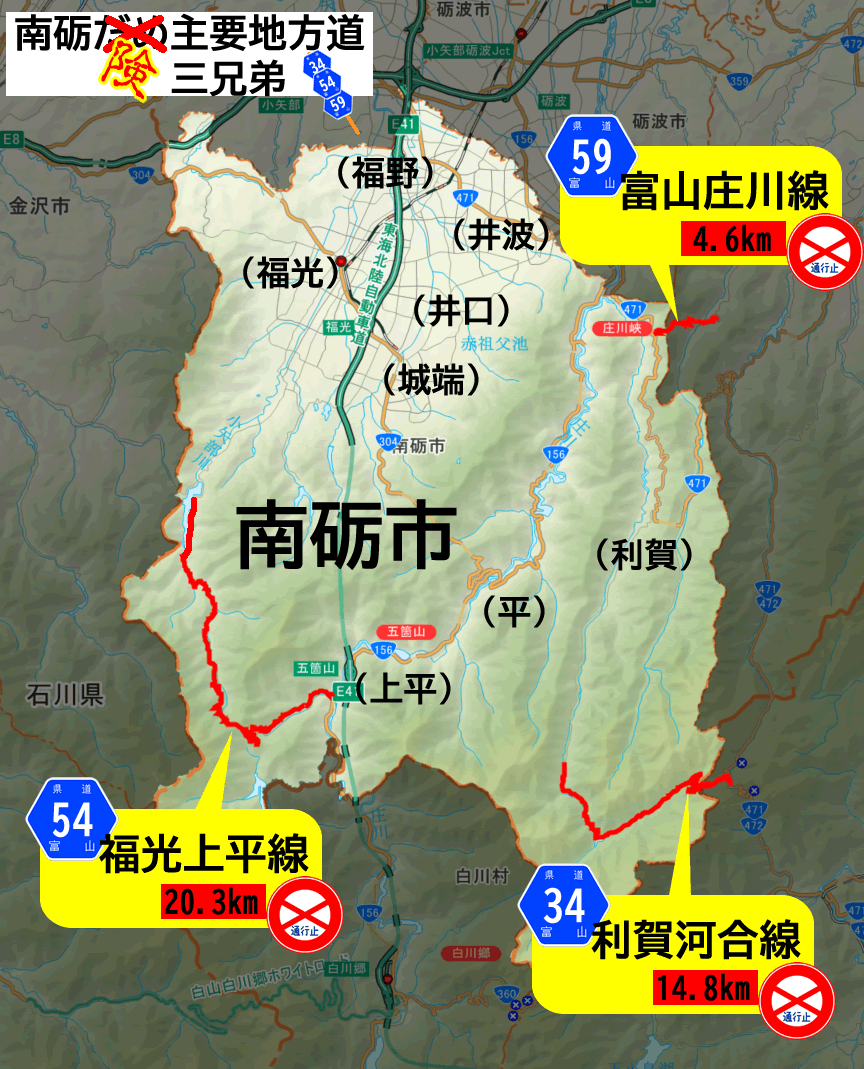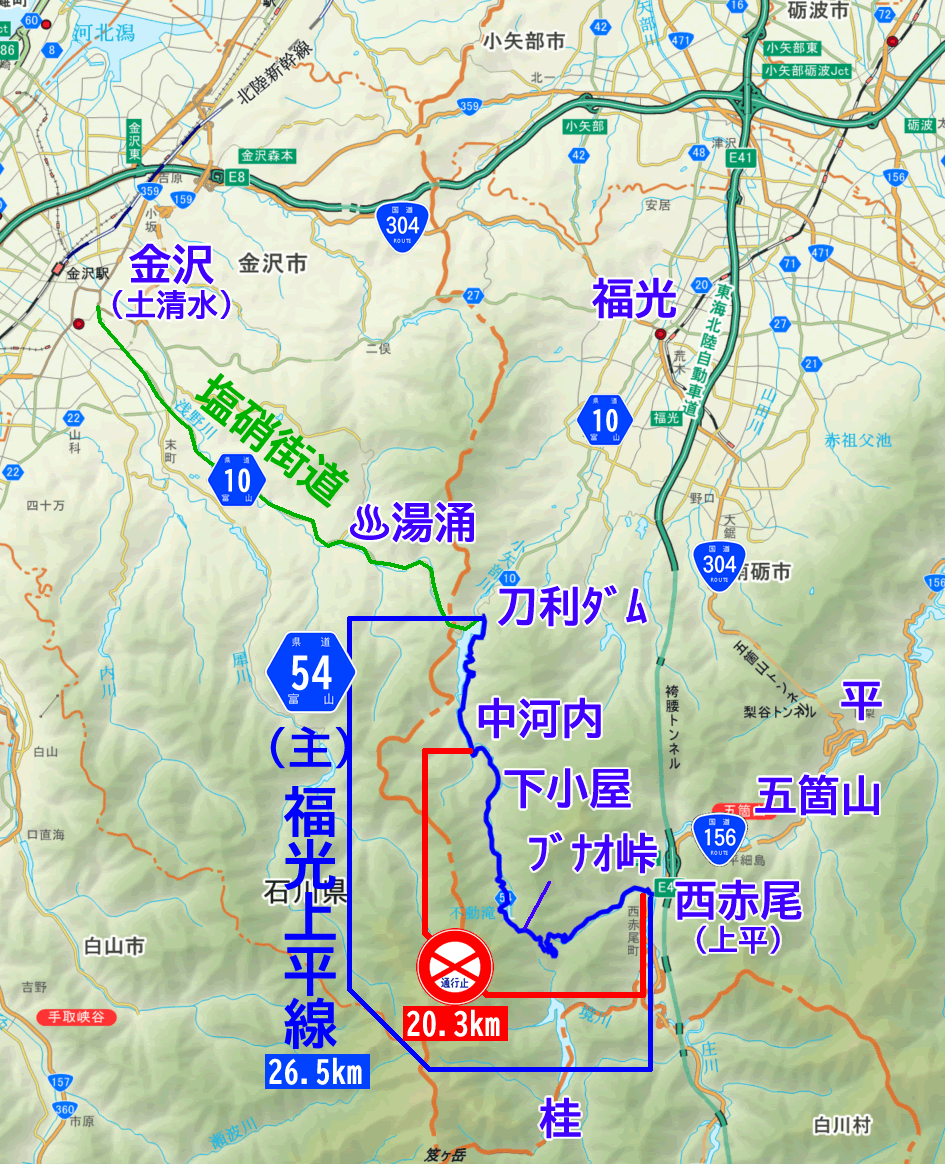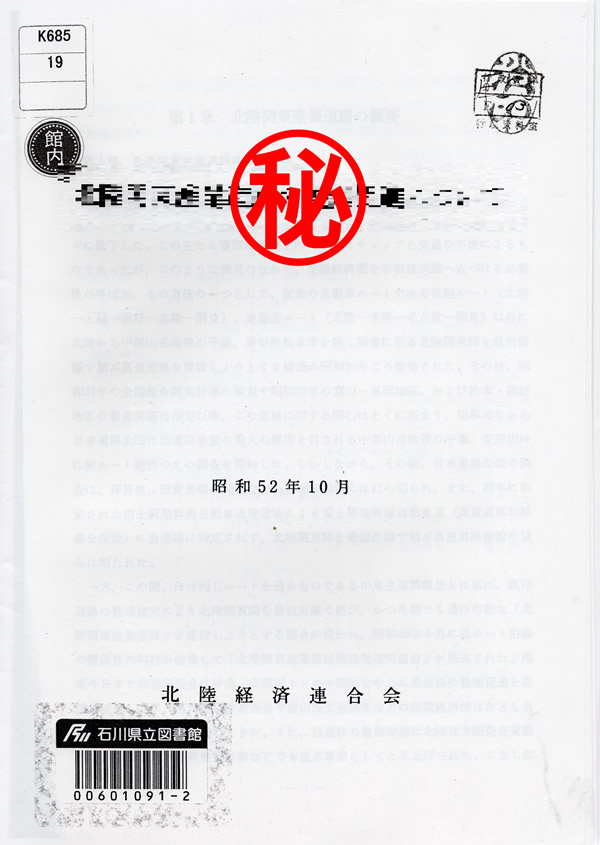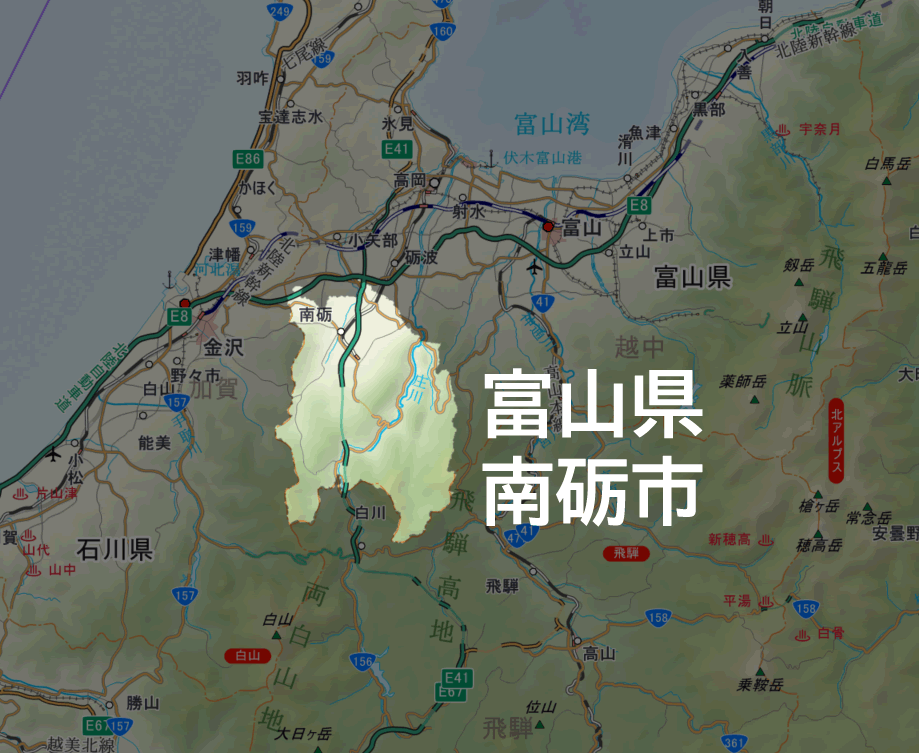
《周辺地図(マピオン)》
皆さまは、富山県で2番目に広い面積を誇る南砺市(なんとし)が誇る、
南砺[険]道3兄弟
を、ご存知だろうか?
いや、きっと誰も知らないだろう。
なぜなら、私が勝手に呼んでいるだけだからな(爆)。

[長兄] 富山県道34号 利賀河合線
(現在の通行止区間の長さ 14.8km)

[次兄] 富山県道54号 福光上平線
(現在の通行止区間の長さ 20.3km)

[末弟] 富山県道59号 富山庄川線
(現在の通行止区間の長さ 4.6km)
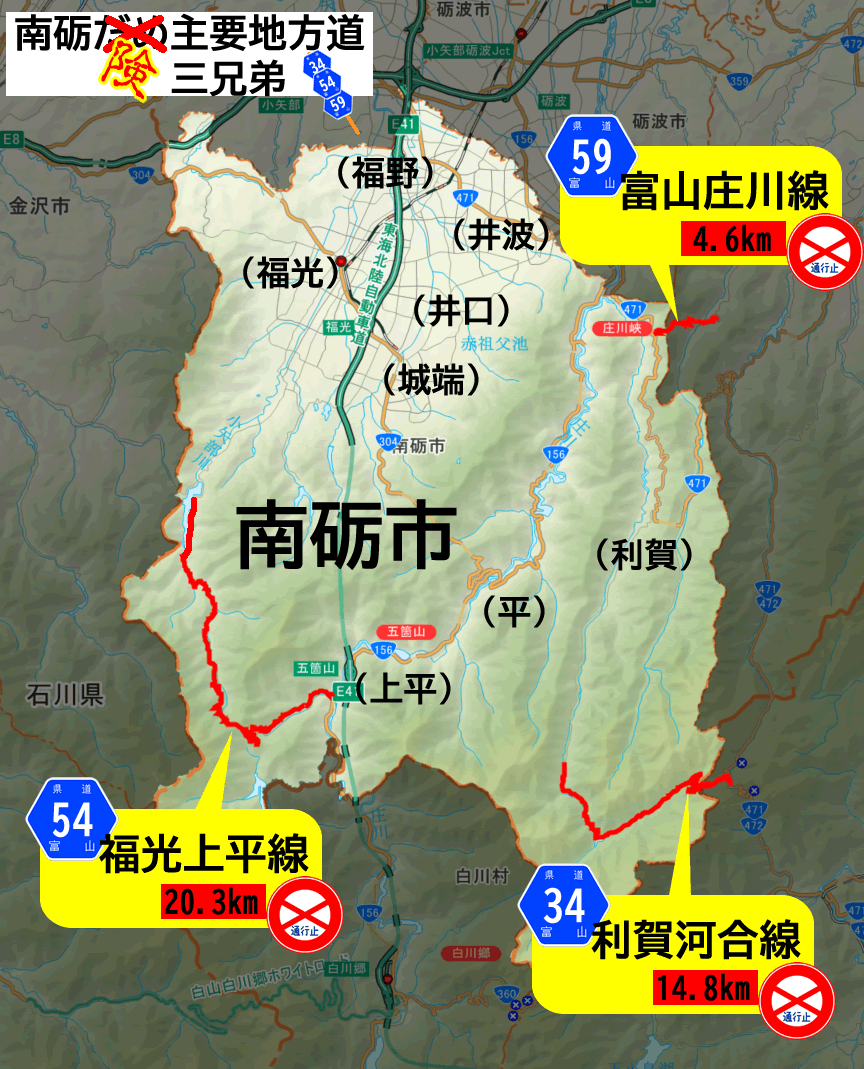
南砺市の三方を取り囲む高峻な山岳に鼎立する、いずれ劣らぬ“険”を誇る3“険”道。
その全てを体験した私が、勝手にこう呼んでいるのである。
南砺[険]道3兄弟。
今回は、3兄弟で最も長い通行止区間(2024年5月22日時点)を有する次兄、富山県道54号福光上平線を紹介しよう。
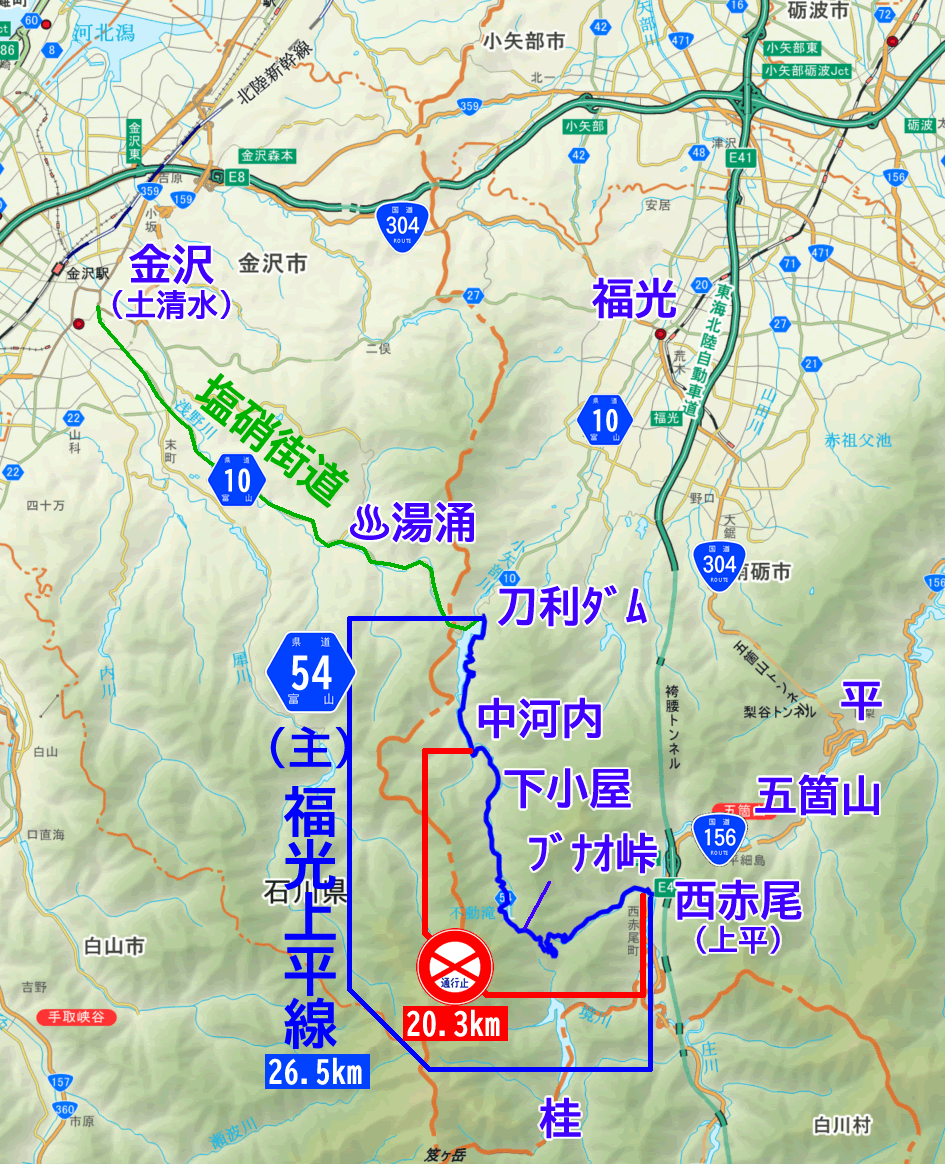
富山県道54号福光上平線は、南砺市刀利(とうり)と同市西赤尾町を結ぶ、全長26.5kmの主要地方道である。
平成の合併で8町村が一つの南砺市になるまでは、路線名の通り、西礪波郡福光町(ふくみつまち)と東礪波郡上平村(かみたいらむら)を結ぶ越境路線だった。
富山県サイトの県管理道路の通行規制状況によると、これを執筆している2024年5月22日現在、本県道には「南砺市中河内〜同市ブナオ峠(8.0km)」と「南砺市ブナオ峠〜同市西赤尾(12.3km)」の連続する二つの通行止箇所があり、その規制理由はいずれも「道路の破損、欠壊等」となっているうえ、規制解除見込日は「当分の間」という、無期限封鎖でしばしば見られる道路管理上の“死亡宣告語”が使われている。
この路線の最高所は、かつて郡境であり町村境でもあった
ブナオ峠であるが、この峠の前後が
合計20.3kmも無期限で通行止になっている現状があるわけだ。
既に述べたとおり、この路線の全長は26.5kmなので、なんと全長の4分の3あまりが通行止になっている“惨状”とは……、オブローダーなら当然興味を持つだろう。
ところで、もし手元に道路地図があるならば、ブナオ峠の辺りを見てみて欲しい。もしかしたら、県道名の他に路線の通称が書かれているかも知れない。その場合、「塩硝街道」と書かれていると思う。
塩硝(えんしょう)という鉄砲火薬などの原料となる硝石の結晶は、中世から近世にかけて五箇山周辺の特産品であった。これを年貢として納入先である金沢城下に輸送するために足繁く通われたのが、このブナオ峠を含む山道である。
山深いブナオ峠の道は、近世まで五箇山の暮らしと経済を支える道であったのだ。
昭和54(1979)年に刊行された『角川日本地名辞典(富山県)』には、ブナオ峠として一項が設けられている。その内容を以下に転載する。
私も予備知識としたこの情報を獲得してから、探索本編へ進んで欲しい。登場する地名などは右の地図を見ると分かりやすいはずだ。
・ ブ ナ オ 峠
西礪波郡福光町と東礪波郡上平村の境にある峠。標高976m。県道刀利西赤尾線が通る。峠名は、付近一帯にブナの原生林が広がり、峠にブナの大木があったのに由来する。文明年間にはすでに開けていて、蓮如上人も越前に出るのに当峠から桂村へ抜けたと伝える。戦国期には敗残の将兵や無頼の徒が飛騨から加賀・越中へ抜ける間道であった。そのため、刀利で出入国者の取締りにあたった。江戸期には飛騨や江戸に急派される使者や隠密の利用する間道であった。また、五箇山で製造された塩硝もこの峠道を越えて、土清水(つちしようず)の塩硝蔵まで運搬された。かつては下小屋から谷沿いに峠へ、赤摩木古(あかまつこ)の谷を下って上平村桂へ出ていたが、昭和43年現在の県道が開通した。峠には西南方の大門山への登山口、北方の大獅子山を経て猿ケ山に至る尾根道の入口がある。
『角川日本地名辞典(富山県)』より
どうだい?
ワクワクしてきただろう?
山を越える長大な通行止の峠を、己の自転車のみで走破する、まさに私というオブローダーの原点のような探索を行う。
なお原点だけあって、探索日は今から10年も前の2014年6月2日だ。
当時と今では今の方がより荒れていそうではあるが、全体的にはそう大きくは変わっていないと思う。
当時でさえブナオ峠の西側は通行止になってからかなり時間が経過している気配があったから…。
そして、探索が終わった後は、お楽しみの机上調査を予定している。
今回、この10年の間になかなか面白い一編の資料を発見しているので(↓)、それを最後に紹介するつもりだ。
ブナオ峠に秘められた“ある壮大な構想”の開陳を、ぜひ楽しみにしていてほしい。
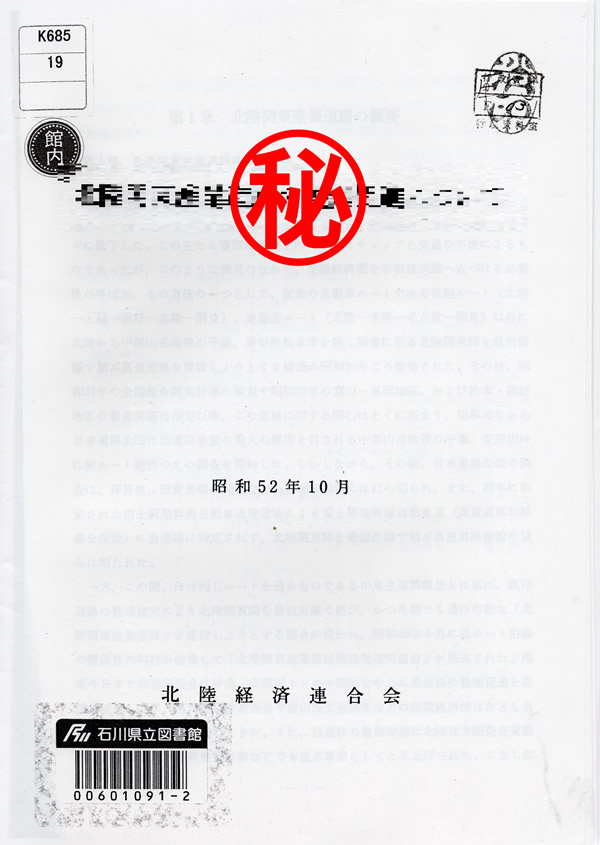
石川県立図書館で見つけた興味深い資料の表紙 (加工済)
終点から探索スタート! 西赤尾町の香ばしゲート風景

2014/6/2 7:10 《現在地》
ここは富山県南砺市西赤尾町の国道156号に架かる赤尾橋の橋の上だ。既にいつもの自転車で出発済。
すぐ先にガソリンスタンドが見えるが、あそこの前が目指す県道54号の分岐である。
ちゃんとした青看も設置されており、県道54号の行先は「刀利ダム(Tori Dam)」と表示されていた。
刀利ダムはブナオ峠を越えた先であり、普通に通り抜け出来るかのような表現である。

そのまま丁字路へ。
信号はなく、そのため交差点名の表示もないが、この交差点こそが県道54号福光上平線の終点である。
これからこの県道の全長である26.5km先にある起点刀利を目指し、この道に突入する。
この地点にも「著名地点」の案内標識があり、県道の方向に「ブナオ峠野営場 Mt. Bunao Camping Atea 10km 」を表示している。
ちょうど峠の頂上付近に野営場(キャンプ場)があるようだ。
不便を買ってでも楽しむのがキャンプだが、この県道を10kmも進んでからやるキャンプは、キャンプ好き以外には罰ゲームでしかなさそう……。
そんな余談はさておき、進路を県道へ!

丁字路から覗き見る県道54号の入口。
挨拶代わりのヘキサがあるが、見るも無惨な傷だらけの姿をしている…!
なんでこんなに痛んでいるんだろう。誰かにいたぶられたんだろうか?
そして、少し入った先には、早速にして“赤色の標識”がいくつも躍っているのが見えた。
ロクデモナイ道の始まりに付き物の、あの赤い標識たちの気配である。
道の入口で路駐とは思えぬ大胆な停め方をしている軽トラにも注目したい。このトラックの主はこれが手前の国道であっても同じことをしただろうか。いやしないはずだ。この県道の現状を知っているからしているのである。
なんとも香ばしい“険”道の香りがするではないか!

通行止標識の大乱舞じゃあああ!!!
左側にあるのは、電光掲示式の道路情報板。
当地方の有力な観光資源である合掌造り民家のシルエットを思わせるさんかく頭が可愛らしいが、おそらく着雪を防ぐ為の三角屋根だろう。
肝心の表示内容は、西赤尾〜刀利の区間が冬季閉鎖中ということだが、これは即ち起点から終点までの全線が冬季閉鎖中ということになる。
この探索日は6月2日だったのだが、まだ冬季閉鎖が明けてないのか!
右側にあるのは、標識板がパタンと倒れて表示内容を変更できるタイプの通行止予告標識。
表示内容はずばり、通行止。
こちらは冬季閉鎖とは書いておらず、「ブナオ峠から中河内まで」が「当分の間」通行止であることを告知している。
まとめると、左の道路情報板が告知している冬季閉鎖中でなければ、ここからブナオ峠までの上平側の道は通れるが、その先の福光側に通年の通行止区間があったというのが、2014年当時の状況だった。
これを執筆している2024年時点では、西赤尾からブナオ峠を越えて中河内まで通年通行止とされているので、10年前はまだマシな状況だったのである。
県管理道路の通行規制情報のページをInternet Archiveで過去に遡って調べたところ、上平側については令和2(2020)年のシーズンまでは規制が行われていなかったが、2021年から通年通行止となっているようだ。
一方の福光側については、確認できた最古の版である平成27(2015)年1月の時点で既に通年通行止となっていたが、私がその前年の2014年に探索した当時でも、この県道が何年も前から通行止であることは、オブローダーの耳に自然に入ってくるくらい有名な事実だった。探索した動機も、そういう情報に触れていたからだった。
また、冬季閉鎖についても同様に確認したが、例年11月14日頃から翌年5月上旬(稀に下旬)まで、県道全線が冬季閉鎖されている。
ただ、6月まで冬季閉鎖が続いた年は見当らなかった。2014年は特別に雪が多かったのか知らないが、6月2日の時点でも冬期閉鎖中になっていたのである。

そして、なぜかゲートは半閉状態だった。
電光掲示板では、ここから冬季閉鎖中になっていたが、実際はこのように半分開いたままになっていた。これを道路管理者が開けたのかも分からないが。
また、ゲートにも「通行止」の標識と、「ブナオ峠より中河内 通行止」と書かれた工事看板が取り付けられていた。
状況的には、峠までは解放されていると判断しても良いのかな?
ゲート入ってすぐ右の路肩に2台の小型バイクが駐車してあるが、1台はナンバープレートが未装着だった。まるでゲートの奥は私道みたいな雰囲気だが、仮に冬季閉鎖中の道でも公道であることには違いはないはずだぞ……苦笑。
7:11 西赤尾ゲート・イン!

ゲートより振り返る、旧上平村西赤尾町の風景。
と、県道の終点である旨を補助標識が教えてくれている、こちら向きのヘキサ。
西赤尾町は、かつての白川街道(北陸地方と飛騨地方を結ぶ街道)と西赤尾道(西赤尾からブナオ峠を越えて金沢へ通じる間道)の分岐点に栄えた宿場で、近世までは人と荷の他国往来を監視する口留番所も置かれていた。特に五箇山の村々から年貢として集められた特産品の塩硝は、ここからブナオ峠経由で金沢城下へ運ばれ、西赤尾町は塩硝街道とも呼ばれた。しかし廃藩によって塩硝生産は中止され、明治以降は養蚕や稲作によって生活した。
これらの街道が、現在の国道156号と県道54号のもとになった。
ゲートに立って眺めると、里の家並みに護られた国道と、一軒の沿道家屋もなく直ちに入山する県道の差が歴然だ。
こんな入口の側にゲートがあるなんて、県道を行けば先にはもう山しかないと明言されているに等しい。

ゲートを過ぎると、直ちに道は山の中へ。
そして最初からきつめの上り坂が迎えてくれる。
道幅は2車線分あるが、センターラインはもうない。
この先、ブナオ峠の頂上まで約10kmあるが、その間に海抜330mから980mまで約650mの登高がある。ひとことで言えば10kmも上り坂が続くわけで、自転車で行く場合じっくり腰を据えて2〜3時間を見るべき長程だ。
通行量に対して過剰なほど立派な青看(内容は普通)の下を潜って、いざ戦いの舞台へ。
(オブローダーの気持ちを昂ぶらせる香ばしさに満ちた入口の様子を紹介しただけで随分と文章量を使ってしまったので、続きは次回。
次回は一気に進むぞ!)
|
当サイトは、皆様からの情報提供、資料提供をお待ちしております。 →情報・資料提供窓口
|
|
このレポートの最終回ないし最新の回の「この位置」に、レポートへのご感想など自由にコメントを入力していただける欄と、いただいたコメントの紹介ページを用意しております。あなたの評価、感想、体験談など、ぜひお寄せください。
【トップページに戻る】
|
|
|
|
|
|
|
|