終点を出発し、国道との重複区間を抜けて ……ん? これは?!

2023/6/7 8:41 《現在地》
いざ出陣!
ヘキサのある魅惑の駅前未舗装路から、速やかに国道392号へ戻る。
道道665号としては、終点から起点へ向けて逆順に進むことになるが、基本的にはこの順序でしか完全走破は出来ないはずだ。なにせ起点は山の中で、そこへ通じる道道以外の道はないようだから。
終点から約120m、国道とぶつかったら、左折する。
この先しばし、国道との重複区間である。

昭和57(1982)年に、道道本別白糠線が昇格して国道392号が誕生した。
明治30年代に茶路川流域の入植が行われた際に整備された拓殖道路が元になっており、このような由来を持つ道の例に漏れず、多少の起伏は無視して直進する傾向が強い。
国道昇格前後は、廃止される白糠線の代替バスの走行確保が重視され、大々的に整備が進められた。
確かに現在の国道392号は北海道にある大半の国道の例に漏れず、走りやすい快走路である。
写真は上茶路集落内のメインストリートだ。
古い航空写真を見ると、向かって左側の土地には炭住が編み目のように建ち並んでいたが、既に跡形もない。右にある現住の住居は、おそらく炭鉱開発以前から住まわれている開拓者の末裔ではないか。
この一連の重複区間内に、道道665号の気配を感じることはなかった。

猫注意!!!
なんだって〜〜〜!!!
クマ注意なら分かるが、危険なヌコが出没するのだろうか。
いや、あり得るのかも知れない。
この似顔絵の凜々しさは、なかなかのものである。

8:46
上茶路駅跡入口の丁字路から約500m国道を北上すると(道道終点から約650m)、それまでの直線が崩れ、緩やかな左カーブと下り坂が同時に始まる。
このまま道なりにあと200mほど下ったところが道道665号との再度の分岐地点であり、そこへ行くのに遠回りは必要ないのだが、私は敢えて遠回りを選びたい。
実はこの場所には国道の旧道が存在する。
現道の線形に引っ張られて分かりづらくされているが、旧道はチェンジ後の画像に示した赤破線の通り、ここまで続いた直線を延長するように通じていた。
現状でも黄色い矢印のように進むと、この旧道へアプローチ出来る。
ここで突然旧国道へ行こうとする理由は、この先に道道665号の旧道区間があると考えたからだ。
| ① 地理院地図(現在) | 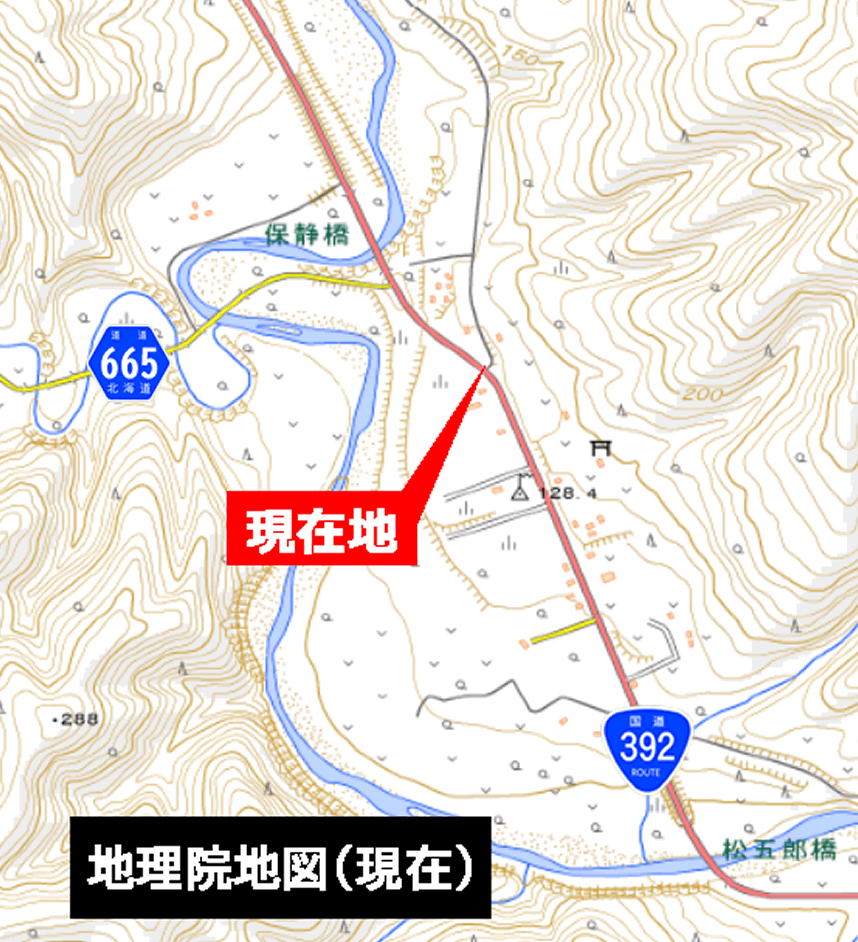
|
|---|---|
| ② 昭和48(1973)年 | |
| ③ 昭和42(1967)年 | |
| ④ SMD24(2024) |
ここに新旧3世代の地形図+αの比較を用意した。これらはレポートの冒頭でも比較したが、改めて現在地の周辺にフォーカスして見て欲しい。
①は最新の地理院地図である。
国道は「現在地」から左へ曲がり、「保静橋」の手前の丁字路が道道665号の分岐地点である。
これを②昭和48(1973)年版と比較すると、太く描かれた道道本別白糠線(後に国道へ昇格)は右方向へ延びており、少し先から道道上茶路上茶路停車場線(既に認定済)が左へ分岐している。
改めて①を見ると、今でもこの旧道道は途切れながらも描かれているようなので、現状を確認したかったのだ。
③昭和42(1967)年版は道道認定前の状況だが、分岐の位置が少し違って見える。おそらく白糠線延伸に伴う跨線橋の開通で、道が少し変わったのだろう。
④地形図ではなく、2024年版のスーパーマップルデジタルだ。
この地図だとなぜか、今なお旧道区間が道道として塗られている。
単なる間違いだと思うが、こういう地図もあるという参考まで。

というわけで、旧国道へ突入しました!
特に通行規制はないが、あまり車が出入りしている雰囲気は感じない。
地図を見ると、2.5kmほど茶路川の左岸を進んだ先で、再び現国道にぶつかる様子。
現国道には2度の茶路川横断を含む4本の橋があるが、いずれも平成18(2006)年竣功となっていることから、同年辺りが国道の切り替え時期と思われる。
旧国道に入っても、もちろん道道665号重複の気配はないのであるが……

8:47 《現在地》
旧道に入って200mほどで、さっそくその場所が現われた。
地図上から判明した、旧国道と旧道道の分岐地点。
道道が重複区間から単独区間へ脱皮する旧の地点だ。
しかし正直に言うと、一度私は通り過ぎている。
通り過ぎた後に、あれ? おかしいな? と距離を見て、引き返して撮り直したのが、この写真だ。
ここが道道の分岐地点だったって分かります?
分かりにくいよね? 道路と道路の分岐というより、単に沿道にある農地の入口っぽいのである。というか、そうとしか見えなくない?
でも、実際に曲がろうとすると……

うおぉ〜〜〜!
またしても、珠玉を感じる廃道味のある風景が!!
目移りしちゃうほど、いろいろなアイテムが残されている!!!
そしてまたヘキサがあるじゃないか!!
ワクワク……! 今から一つずつ見ていこうね!

まずはこれ。真っ先に眼球に飛び込んで来た、俺の眼球みたいに濁った白の道路情報板。
なんか白いってのは珍しい気がする。だいたい黄色いよね。
もう道と一緒に役目を終えているようでボロボロだが、旧国道時代はちゃんとここで道道の道路情報が提供されていたことが分かる。
「上茶路」って地名がハメコミプレートになっているが、ここを変えると他の路線にも使えるのは便利そう。
まあ、「上茶路」の範囲は滅茶苦茶に広いので、これだけだとどこの情報なのかよく分からない気もするが…(笑)。

はいはい。

これは振り返って撮影。
この「止まれ」がないと、道路っぽく見えないくらいには、轍が薄くなっている。
というか、道道665号旧道は初っ端から未舗装だったのか。
駅前の短い単独区間も未舗装だったが、こっちもなのか。
最近では、いわゆる不通区間のようなところを除けば、そうそう未舗装の都道府県道は出会わない気がするが、さすがはダート王国北海道?

またも出会ったヘキサちゃん!
本標識もそうだが、特に補助標識の退色が著しく、ほとんど読み取れなくなっていた。
そしてやっぱり支柱は銀色だ。全く錆びてない。
この旧道区間の現状は廃道さながらであるが、道道としての供用自体は廃止されていないんだと思う。
そう考える根拠はこの後でも出てくるが、だからこそ道路標識の類が一つも撤去されず残っているんではないかと。

旧道道の入口から50mほどの地点に架かる1本の短いコンクリート橋。
その名も、「上茶路跨線橋 Kamicharo kosenkyo」。ちゃんと案内標識が完備されていた。
しかし、親柱や銘板などはない。
だが、この橋の名前を検索すると、「令和7年度箇所表」という、北海道道路局の資料がヒットする。
そして判明。
この外見的には廃道に見える旧道上の橋、なんと、令和7年現在も道道665号上茶路上茶路停車場線の現役施設であった! 北海道橋梁長寿命化修繕計画の対象リストに入っているではないか!
全国Q地図の「2018年度全国橋梁マップ」にも本橋が道道の橋として記されている。それによると、竣功は昭和42(1967)年、全長20.6m、幅6.1mの橋である。
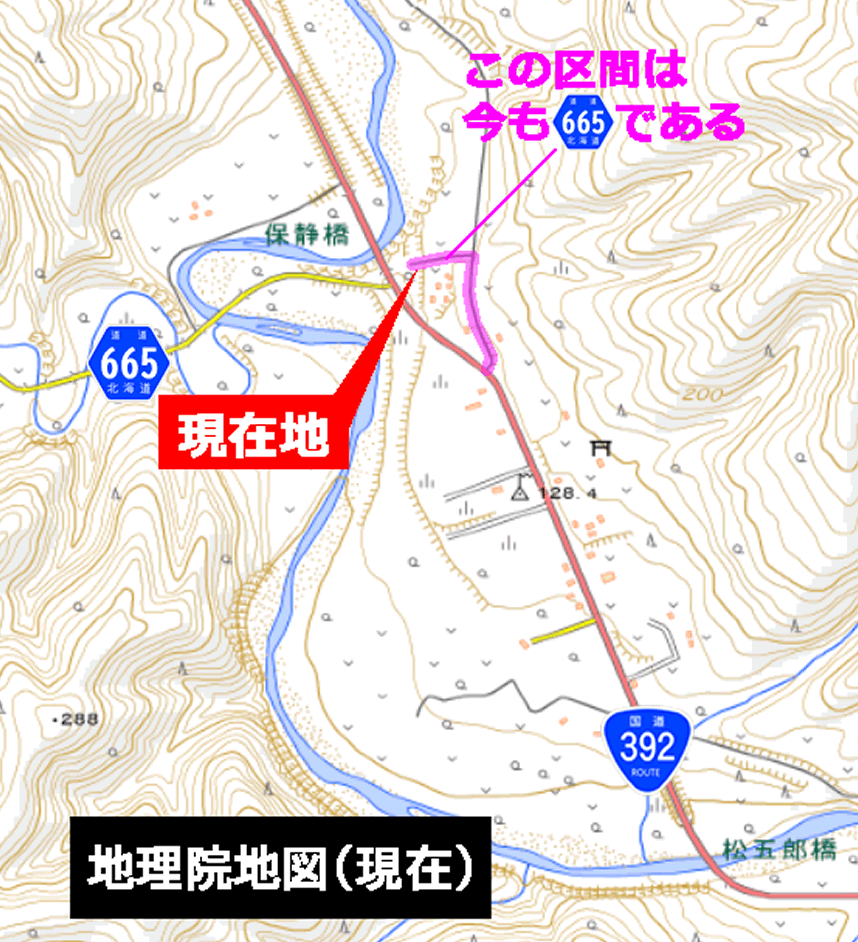
そんなわけだから、この地図上にピンクでハイライトした部分は、どうやら道道665号の単独区間としての供用が続いている模様(そして通行規制がされている)。
侮ったスーパーマップルの地図の方が、地理院地図よりも正解に近かったという大逆転発生だ(意図した記述かは不明だが)。
いずれにしても、旧国道の国道指定が解除されたことで、道道の単独区間が少し増える結果になった模様である。
だからなんだと言われたら、マッタクカエスコトバモナイガ。
普通に道道を利用したいだけなら、現国道からアプローチすれば事足りる。
完全に道路マニア専用のどうでもいい話。

この上茶路跨線橋が跨いでるのは、言わずもがな、白糠線の廃線跡だ。
竣功年からしても、間違いなく白糠線の北進駅延伸時に作られた橋である。
線路が掘った切り通しを跨ぐ橋であり、線路がなければ橋が生まれる理由がない。
写真は、橋の上から北進方向を撮影したが、樹木が多く見通しはほとんどない。
葉がなければ、間近にある第11茶路川橋梁の雄姿を眺められたはずだ(葉陰に僅かに見えるが)。
(参考までに、保静橋からの同橋の眺めを【ここ】 に。なお橋の上にはレールは残っていない)
に。なお橋の上にはレールは残っていない)
跨線橋から同じように上茶路駅方向を見ててみたが、やはり見えるのは緑ばかりだった。

だが、薄暗い切り通し底の廃線跡に目を凝らすと、
ここもレールは敷かれたままなんだねぇ〜。
これが林鉄跡だったら飛び降りる勢いで急行したに違いないが、今は道道の時間だ。ヨシとしよう。
(白糠線の廃線跡については、毎度お馴染み歩鉄の達人さんがドローンも活用した非常に見応えのあるレポートを公開されているのでオススメだ)

とっても賑やかだった旧道区間(法的には現役)の入口を後に、跨線橋まで渡り終えると、この旧道自体の終わりはすぐだ。
前方下を横切る現国道が現われ、その“対岸”に道道の本来の続きが見えた。
跨線橋から現国道まで、地理院地図には道が描かれていないが、一応道は存在する。現国道と摺り合わせるために急ごしらえした道だろうか。シケインみたいな曲がりと急坂である。

8:50 《現在地》
下りきって、現国道のガードレール外へ到達。
広い国道の“対岸”に、通常アプローチすべき道道665号の単独区間の入口が待ち受けていた。
鉄壁のガードレールによる無言の封鎖に、手も足も出…………さないと先へ進めない。
こんな真っ当に辿り着きようがない区間にある上茶路跨線橋で、今年どんな橋梁長寿命化修繕計画が練られるのか楽しみである…。
廃線を跨ぐ事実上廃道である橋の修繕、ぜったいにむだだとおもいます(笑)。
次回、 ようやく! やっとか! 今度こそ!! 真っ当に道道の起点を目指す。
確定した行き止まりへと通じる道道の実態に迫る

2023/6/7 8:51 《現在地》
上茶路駅跡「終点」より約1km。道道665号に国道392号との重複明けの時が来た。
現国道の保静橋(ほしずはし)の袂にあるこの丁字路(旧道道側も加味すれば十字路だが…)から入るのが、道道665号だ。
SMD24だと、この位置に「シュウトナイ入口」というバス停があることになっているのだが、見当らないうえ、検索してもヒットしない。調べてみると、白糠線の廃止と引き換えにスタートした白糠町営バスの運行は現在も続いているものの、完全予約制のコミュニティバスとなっているため、バス停は撤去されたようである。
さてここから、道道である道路の記載が山中で途絶える「起点」とみられる地点までは、地理院地図でもSMD24でも約7kmである。
また、この7kmほどのうち1.5kmについては、現在は災害を理由とした通行止であることが国土交通省の道路情報提供システムに表示されていた。
そうした前提を踏まえて、改めてこの入口を観察してみると……
「通行止」という言葉が、喉元まで出掛かっているカンジがする。
右側には、脇に寄せられた形ではあるが、すぐにでも立ちはだかれそうな「通行止」のバリケードが用意されているし、反対の左側には無造作に「通行止」の工事看板が置かれたままである。
とりあえず、この地点から通行止なわけではなく、通行止の予告という認識で良いのだろうか。片方は寄せてあるくらいだからな。
そんな「通行止」に関する表示を除けば、あとは質素だ。
各地の道道の入口に大抵設置されている北海道オリジナルの路線名付きヘキサがあり、悪魔の数字に1足りない路線番号と復唱したくなる路線名が記されていた。
国道側には案内標識がなく、どこかへ通じている期待感は到底持たれなそうな入口だと感じた。
ワレ勇ンデ突入セリ!

こんな曰くありそうな道道だが、この入口から先5km近いところまではストビューが入っているので、その上で私が気になったものを中心にペースを上げて紹介していこう。
まず気になったというか、気付いたこととして、この道道は初っ端から未舗装である。
そして、この先に鋪装された区間がある気がしないので、これは現代においてほぼ絶滅したと考えられる、全線未舗装の都道府県道だ!(国道や旧国道との重複区間を除く)
それでも道路幅については2車線を満たせる余裕があるのが、北海道らしい。
さらに、舗装がなくても、除雪など決してしないような道であったとしても、2車線幅の道道には最優先で設置されている気がする積雪時に路端の位置をドライバーや除雪オペレーターに伝える頭上の矢印板も設置されている。このアイテムを見ると北海道へ来たと感じる道外者は私を含めて多いと思う。実は青森県などにも少しあるが。
初っ端から未舗装の道道は、交差点から(もっと言えば旧道道の入口から)下り坂が続く。
山へ入っていこうとしているのに不可解だが、その前に茶路川を渡る必要から下るのである。

入口から100mほど進んだ下り坂の途中に、路傍の樹木に隠されそうになっている通行止の予告標識があった。
「この先ゲートあり 冬季異常気象時 通行止」だそうである。
このような表示自体は、いろいろな路線にありそうで、固有なものではなさそうだ。
まだ入ったばかりだが、ゲートが開いているか注目だ。
チェンジ後の画像は、ほぼ同じ地点で振り返って撮影したもの。
反対向きに設置された北海道道では標準デザインとみられるキロポストがあった。
「7km」とのことで、これが今から向かっている「行き止まり」までの残距離である。
地図上から読み取った行き止まりまでの距離と、だいたい一致することがここで確認できた。

8:55
入口から約350mの地点で、パッと行く手の視界が開け、そこに明るい大きな橋が現われた。
「第一号橋」という素っ気ない名前の橋だった。
名前も外見も素っ気ないが、この路線の来歴 〜上茶路炭鉱の開発に伴って整備された産業道路〜 を踏まえれば、なるほどイメージ通りだと思う。
資料に拠れば、この第一号橋の諸元は、昭和39(1964)年竣功、全長60m、幅5.5mとのことである。
渡っているのは、茶路川である。
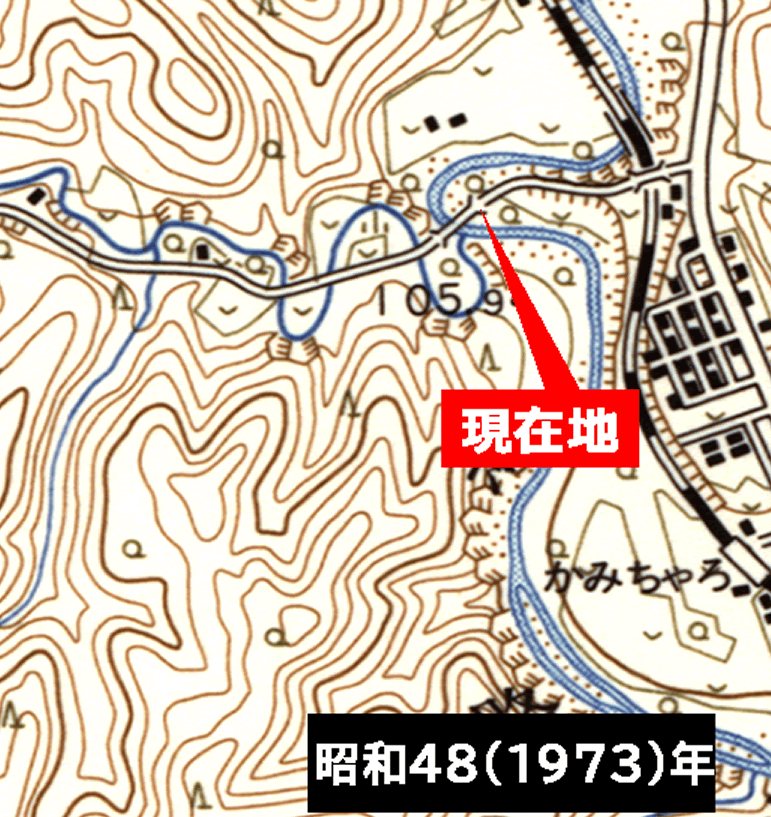
「現在地」周辺の昭和48(1973)年板と昭和42(1967)年板の地形図を比較してみると、茶路川を渡る橋の数やルートが微妙に異なっていることが分かる。
前者は、現在の「第一号橋」であるに違いないが、前者に描かれているのは、その旧橋である。
現橋は茶路川だけを渡っているが、旧橋は茶路川を渡った直後にシュウトナイ川を渡る別の橋がセットであったようだ。
この旧橋の遺構とみられるものが、現地でも確認できた。

この“矢印”の位置を現道から見下ろしてみると……
チェンジ後の画像のような、現橋よりも一段低い築堤のようなものが残されていた。
先端に橋台が見当らないので、木造橋だったのではないだろうか。

現橋上から見る、茶路川とその支流シュウトナイ川の出合の状況。
旧橋は両川の間の陸地に一度タッチしてから、すぐさまシュウトナイ川も渡って、シュウトナイ川上流への進路を採っていたようである。
もう人工物と分かるものは残っていないようだが。

第一号橋を渡った道は、そのままシュウトナイ川の左岸に取り付き、同川源流を目指すことになる。
ここに車を転回可能な広場があり、その奥に予告のあった通行規制ゲートが設置されていたが、解放されていた。
ゲートの傍らに、異常気象時の事前通行規制区間の案内板があり、ご覧の通りの内容で規制が行われることが示されていた。
この看板はまだ新しく見え上茶路駅前の「森に溶けるヘキサゴン」と同じ路線だが、こちらは真っ当に管理されている区間という印象を受ける。
ゲートも開いていることだし、まだしばらくは安泰に進めそう。

ゲートの時点で奥に見えていた「第2号橋」という橋。
今度は支流のシュウトナイ川を渡る橋となり、一気に規模は小さくなった。
四隅に親柱があり、銘板が嵌まっていた痕跡もあるのだが、老朽化のために失われている。
資料に拠ると、第1号橋と同じく昭和38年の竣功で、全長12.7m、幅5.6mである。
なお、旧橋時代の遺構が近くにないかを探したが、特に見当らなかった。
あと、この道路は何かの工事車両が通っているようで、そのドライバーに向けた看板が、なぜかひっくり返った状態で設置されていた。
探索的には、工事中で通れない場所がないことを願いたいが、今のところそれらしい車とは出会っていない。

第2号橋の100m先で待っていた、これまたよく似た第3号橋という橋。
やはり四隅の親柱は酷く傷んでいたが、辛うじて竣功年を刻んだ1枚の銘板が外れずに残っており、「昭和38年11月竣功」とあった。
資料によると、竣功年はその通りで、全長12.6m、幅5.5mだそうである。
第2号橋もそうであるが、親柱は竣功当時からのものに違いないだろうが、両側のガードレールは後年のものだと思う。親柱より明らかに高欄が高い場合、そう考える方が適切だ。

ポンポンテンポ良く、また100m足らずで次の橋、第4号橋が現われた。
資料に拠ると、昭和38年竣功、全長12.6m、幅5.5mで、第3号橋と全て共通している。
ただし、この橋には四隅に親柱がない。もとはあったのだろうが、補修時に撤去されているようだ。
チェンジ後の画像は橋を渡ったところで振り返ったものだが、第2、第3、第4号橋は綺麗な直線上に並んでいる。
蛇行するシュウトナイ川を串刺しにしながら、道はまっしぐらに行き止まりである奥地を目指していた。
まだまだ木橋が優勢だった昭和30年代という早い時期に、コンクリート橋を贅沢に連ねた道が整備されたのは、そこまでして目指す価値あるものが行き止まりに待ち受けていることの証しといえるだろう。

入口から約750m、3度シュウトナイ川を渡った先には、山谷の少し開けた明るい草地が広がっていた。
写真は振り返って撮影したもので、奥のカーブのところに渡ったばかりの第4号橋がある。
道の左側(進行方向としては右側)に、ここまでで初めて見る「待避所あり」の道路標識があったが、退色しすぎて通常の配色とは逆の配色になっているのが面白かった。
また、反対側の草地に、見慣れない白い標柱が立っていた。
近寄って見ると、「1級基準点K17-48 北海道横断自動車道白糠町本線用地測量等業務」と書かれており、上茶路駅前のシーンでも少し話に登場した道東自動車道の工事関連の基準点であった。
道東自動車道はシュウトナイ川から山を南に一つ越えた谷沿いに整備されているが、この谷や道とはどのような関わりがあったのだろう。
年代的に、この路線にある橋が補修や補強されたことと関係があるのかもしれない。

9:03 《現在地》
草原から森へ移り変わるところに、道の右手の少し離れた川沿いに建つ一軒の廃屋を見つけた。
いかにも開拓者の住宅というイメージに相応しい、今にも薪ストーブの匂いがしてきそうな建物だった。
最新の地理院地図には描かれていないが、【昭和48年版の地形図】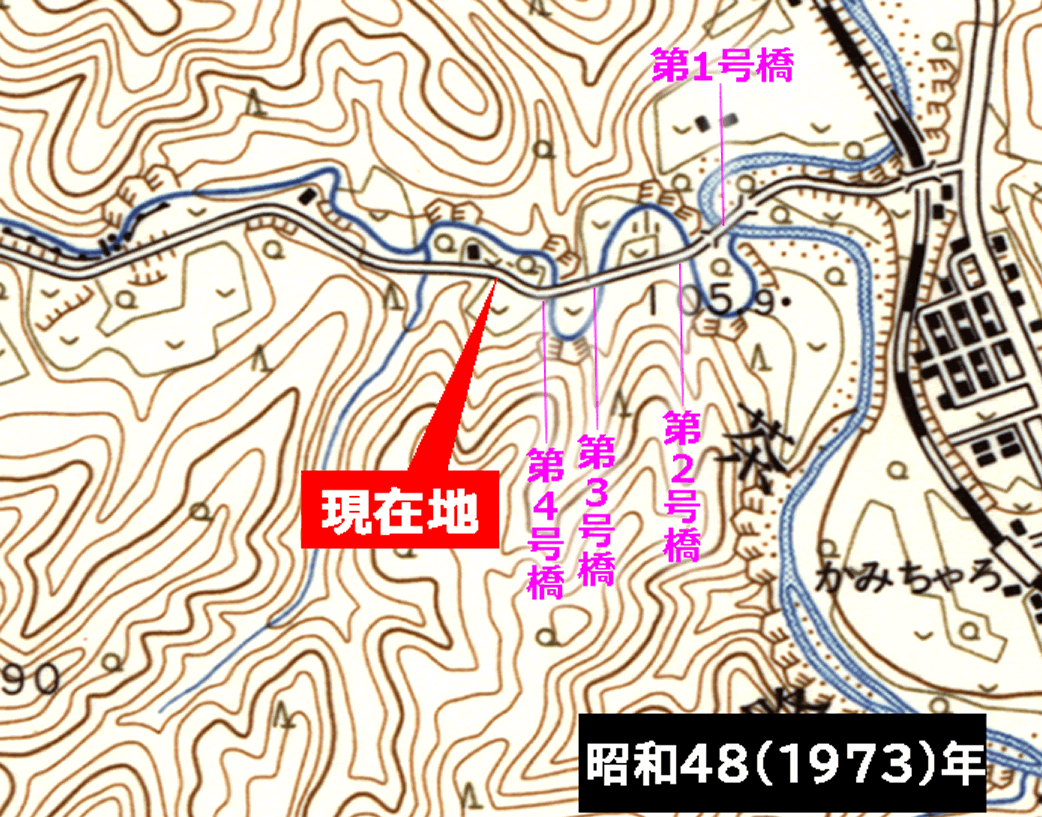 だと確かにここには1軒の家屋があったことが分かる。
だと確かにここには1軒の家屋があったことが分かる。
「第6号橋」はいずこに?!

2023/6/7 9:03 《現在地》
入口から約1kmの地点、現われましたる次の橋。
気付けばもう5本目とのことで、その名も第5号橋である。
そしてこの橋には、規模的にはよく似た第2号〜第4号橋との違いがいくつもある。
まず一つは、シュウトナイ川に架かる橋ではなく、その無名の支流に架かるものであること。
そして、橋名を表示する案内標識のデザインも変わって、ローマ字表記が追加されたより今風なものになった。
「Dai 5go Bridge」というローマ字表記が、国際化に対応した英語表記と言えるかは、異論がありそうだが…(笑)。
さらに、最大の違いとして……

本橋の高欄は、とても低い! マジでビックリするくらい低かった。
だが、親柱の高さと比較してみると、これこそが竣功当初の高欄であろう。
第2号〜【第4号橋】 の高欄は、地覆部分を流用しつつ、その上の高欄だけをガードレールに作り替えていたことが分かる。昔の手厚くなかった安全基準では、高欄の高さなんてこんなもんで十分だった。
の高欄は、地覆部分を流用しつつ、その上の高欄だけをガードレールに作り替えていたことが分かる。昔の手厚くなかった安全基準では、高欄の高さなんてこんなもんで十分だった。
チェンジ後の画像は親柱に取り付けられた銘板だ。
本橋の壊れかけた親柱には2枚だけ銘板が残っており、そのうち1枚には「昭和38年11月竣功」とあり、残る1枚にこの画像のように、「シュウトナイせん だい ご ごうはし」という竣功当初の路線名とみられるものが刻まれていた。敢えてひらがななのは、失われた銘板の中に「シュウトナイ線 第五号橋」と書いたものがあったのだろうと、後に登場する橋との比較から合点がいった。
既に紹介しているように、この道路はもともと、昭和38(1963)年に開坑した上茶路炭鉱へ至る「産業道路」として整備されたそうだ(角川日本地名辞典)。ただ、「産業道路」というのは法的な道路の種別ではなく、「生活道路」と対になる概念の通称であり、道路法の道路としては、市町村道であったり都道府県道であったり国道であったりする。この場合は白糠町の町道として整備され、その路線名が「町道シュウトナイ線」であったのだろう。その後の昭和44(1969)年11月に本路線は道道上茶路上茶路停車場線へと昇格するが、肝心の上茶路炭鉱が翌昭和45年に閉山しているという間の悪さも前述の通りである。
ここまでの橋は全て、この町道シュウトナイ線時代に建設されたものが、大なり小なり補修改築されながら、現在まで使われている。
その中でも、この第5号橋は最も当初の原形を残していると思う。
盛大に土埃を纏う鉱石運搬トラックが、沿線の開拓民や牛馬をクラクションで蹴散らしながら爆走した風景が目に浮かぶような橋だった。(実際の運転マナーがどうだったかは分からないが)

第5号橋を渡って間もなく、またも育ち盛りのシダやフキが日光をほしいままに謳歌する草地が現われ、そこに前回よりも数字を「1」減らした「6km」のキロポストが、やはり反対向きに設置されていた。
ここまでは至極順調である。未舗装ながら、道も全然悪くはない。
チェンジ後の画像は、広々とした草地の様子だ。
よく見ると、奥の方に廃材が山と積まれたところがある。
昭和48年の地形図だと、ここにも人家が描かれていたから、その跡形だと思う。
明るいからか、ここはそれほど寂しくないな。

9:07
その後も坦々たる砂利道が続く。
これは1.3km地点付近にある、山中としては稀に見る長い直線の道路だ。
丘を切り割り、谷を埋め立てながら、2車線分に匹敵する幅に1車線分だけの轍が刻まれた直線ダートが続く。
フラットダート好きのドライバーやライダーには、なかなかタマラナイコンディションかもしれない。私もこういう道は嫌いじゃない。
チェンジ後の画像は、長い盛土の道だ。
そしてこの盛土区間の終わりに、興味深いものが待っていた。

9:09 《現在地》
入口から1.6km地点に、「第6号橋 Dai 6go Bridge」の案内標識がある。
が、なぜか橋が見当らない。
そして、見当らない橋の代わりでもないと思うが、道のすぐ隣に見慣れない光景があった。
シュウトナイ川が珍しくどうどうという逞しい水音を響かせていると思えば、その音源は滝であり、それが深い切り通しの底にあった。
川が、明らかに人工的な切り通しの底を、滝となって流れていた。

上流側から見ると、ここの地形の特異さがよく分かる。
左に見える切り通しの底を【細い滝】 となった川が流れている。
となった川が流れている。
この滝は地理院地図にもちゃんと滝の記号で描かれているが、特に名前の注記はない。
川の周囲はグランドキャニオンのミニチュアのように赤茶けた岩の露出した風景で、それが周囲の緑の調和を著しく破っている。
ひとことで言って、とても不自然な地形である。
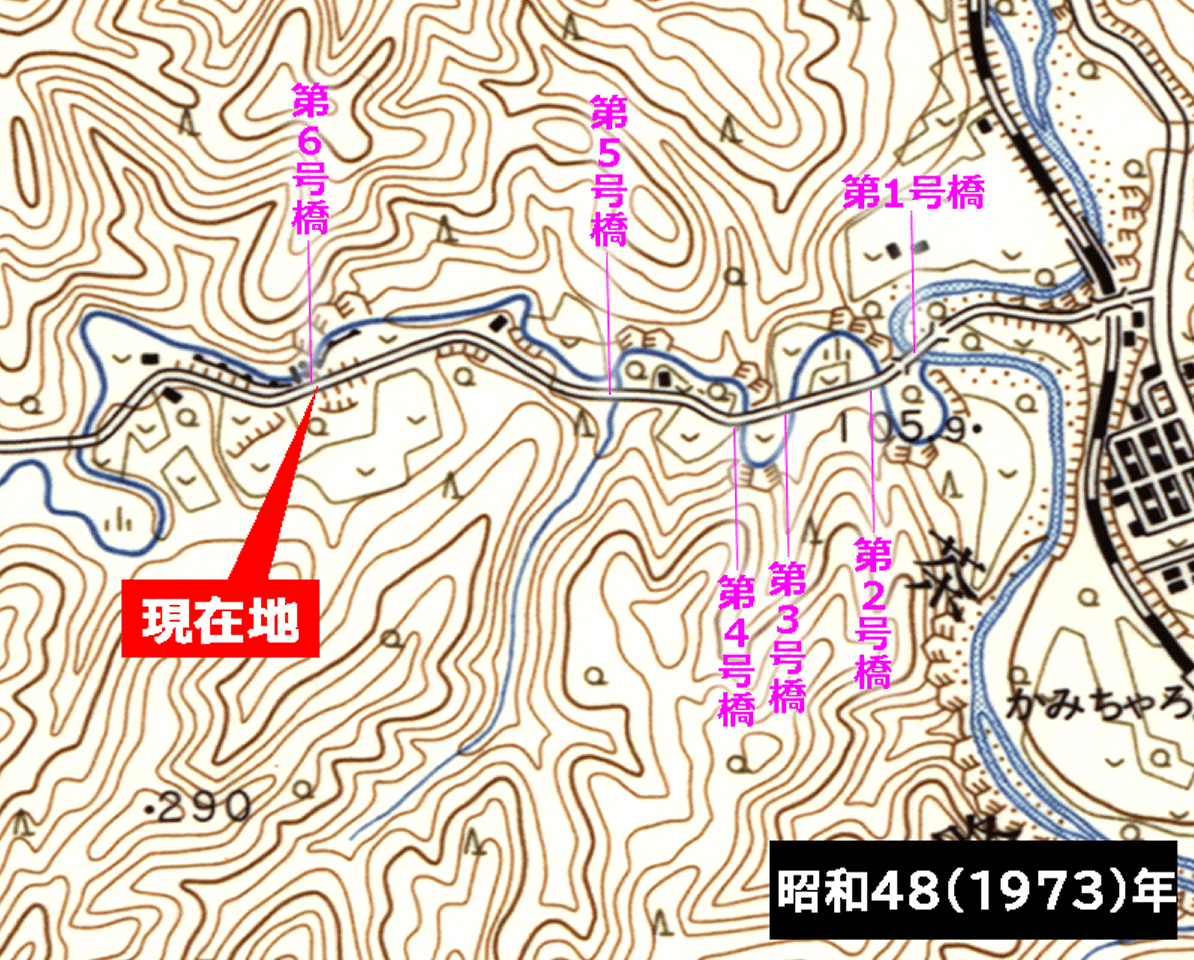
この不自然な川の原因は、昭和48年と昭和42年の地形図を比較することで、たちどころに明かされた。
この短い期間に、川が瀬替えを受けて流路が変更されていたのである。
W字型に大きく蛇行していたシュウトナイ川の蛇行を切り通しによって短絡し、陸地となった旧河道には畑の記号が出現していた。
また、この瀬替えに伴い、川沿いの道路も大々的に付け替えられていることが分かったが、それを知ったのが探索後であったため、旧道は捜索できなかった。
ただ、現場に忽然と案内標識が存在する「第6号橋」の捜索は行ったので紹介しよう。

これが、第6号橋だ。
案内標識の前後は旧河道を横断する【高い築堤】 になっているが、その築堤を背丈に近いシダに埋れながら下って行くと、“これ”を初めて見ることが出来る。
になっているが、その築堤を背丈に近いシダに埋れながら下って行くと、“これ”を初めて見ることが出来る。
旧河道を渡るコンクリート製の“これ”は……
ボックスカルバートである。
どこからどう見てもボックスカルバートな暗渠であって、橋じゃないと言いたくなったが、道路管理者が橋と命名した以上は橋である(真理)。
なお、資料でもちゃんと橋扱いで、そのデータは、昭和39(1964)年竣功、全長3.8m、幅6mとなっていた。

第6号橋と滝を過ぎると、その先にはこれまで沿道で見た中でも圧倒的に最大規模の明るい平地が広がった。
道道は、蛇篭を高く積み上げた現代的な護岸によって、新たな河道を固定する役割を今も与えられており、山中の別天地を守る要となっていた。

そしてこれが、旧河道とその周囲に造成された、あまりにも美しい土地である。
人工的な地形に起因するもので、自然美というのとは違うのかも知れないが、ここに水鳥でも配置すれば絵画や撮影のモチーフとして申し分ない。
しかし、昭和48年の地形図では畑であった一帯が耕作されている様子はない。
新たな炭鉱へと通じる産業道路の開発と、瀬替えによる農地の安定が、一石二鳥の公共事業として実現したのではないかと現場の状況から想像したが、「国破れて山河あり」の“山河”の部分に“国”の痕跡が残るという稀な事態が、とんでもなく美しい光景を生み出していた。

瀬替えによる明るい別天地の終わり附近、入口より1.9kmの道路右側にも、最新地図からは跡形もない人家の名残が残っていた。
周囲に柵も看板も何もないのではっきりしたことは言えないが、季節的に放牧地のような利用が行われているのかもしれない。完全放置でこんなに整った草地が出来るとも思えないし、この完成された牧歌的風景には相応しい利用の場面があって欲しいとも思う。
それにしても、今回は進めば進むほど幸せな場面に満ちていて、私はとても良い気分である。
今回は、私にとっては稀な“ボーナスステージ”のようだ!! 嬉しい!