پ@‚±‚êٹشˆل‚ء‚½‚إ‚µ‚هپHپ@ٹشˆل‚ء‚½‚و‚ثپHپI

2023/6/7پ@9پF16پ@پsŒ»چف’nپt
“üŒû‚©‚ç–ٌ2.1km’n“_‚ةپAپuƒVƒ…ƒEƒgƒiƒCگü ‘و7چ†‹´پv‚ج–ء”آ‚ًŒf‚°‚½‹´‚ھ‚ ‚ء‚½پB
ٹOٹد‚ح‘و5چ†‹´‚ئ‚»‚ء‚‚è‚إپA–ء”آ‚©‚ç•ھ‚©‚éڈ؛کa39”N5Œژ‚ئ‚¢‚¤ڈvŒ÷“–ژ‚جژp‚ً—¯‚ك‚ؤ‚¢‚é‚و‚¤‚¾‚ء‚½پB
‘و4چ†ˆب—ˆ‚جƒVƒ…ƒEƒgƒiƒCگى‚ً“n‚é‹´‚إپAژ‘—؟‚ة‚و‚é‚ئپAڈ؛کa39”NڈvŒ÷پA‘S’·10.8mپA•6m‚إ‚ ‚éپB

‚±‚ج‹´‚ج4–{‚جگe’Œ‚ة‚ح–ء”آ‚ھ‘S‚ؤژc‚ء‚ؤ‚¨‚èپA‚»‚ج‘g‚فچ‡‚ي‚¹‚حپAڈvŒ÷”N‚ً‹L‚µ‚½‚à‚ج‚ھ2–‡‚ئپAپuƒVƒ…ƒEƒgƒiƒCگü ‘و7چ†‹´پvپuƒVƒ…ƒEƒgƒiƒC‚¹‚ٌ ‚¾‚¢‚ب‚ب‚²‚¤‚ح‚µپv‚إ‚ ‚ء‚½پB
‚ـ‚½پA‹´‚جهش‚ة”’‚¢چHژ–•W’Œ‚ھ‚ ‚èپA•½گ¬18(2006)”N‚©‚ç—‚”N‚ة‚©‚¯‚ؤ‰½‚ç‚©‚جچHژ–پi‚¨‚»‚ç‚ڈC‘U‚â•â‹پj‚ھچs‚ي‚ꂽ‚±‚ئ‚ھ•ھ‚©‚éپB
•½گ¬23(2011)”Nچ ‚ة‚±‚ج‹وٹش‚ً‘–چs‚µ‚½•û‚©‚çپAپu“–ژپA“¹“Œ“¹‚جچHژ–‚ھچs‚ي‚ê‚ؤ‚¨‚èپAƒ_ƒ“ƒv‚ھ‘½گ”پA“¹“¹665چ†‚©‚ç”’‰¹—ر“¹Œo—R‚إچHژ–Œ»ڈê‚ةŒü‚©‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پBژ„‚àƒ_ƒ“ƒv‚ج—ٌ‚جŒم‚ë‚ة•t‚©‚¹‚ؤ’¸‚¢‚½Œ`‚إ665چ†‚ً‘–‚è‚ـ‚µ‚½پB‚»‚جچغ‚ة•â‹“™‚ھچs‚ي‚ꂽ‚©‚ا‚¤‚©‚حپAژc”O‚ب‚ھ‚ç•ھ‚©‚è‚ـ‚¹‚ٌ
پv‚ئ‚جƒRƒپƒ“ƒg‚ً‚¢‚½‚¾‚¢‚½‚ظ‚©پA•½گ¬24(2012)”N6Œژ‚ة“¹“¹“üŒû‚ج’n“_‚إژB‰e‚³‚ꂽƒXƒgƒٹپ[ƒgƒrƒ…پ[‚ج‰و‘œ‚ًŒ©‚é‚ئپAƒKپ[ƒhƒ}ƒ“‚ھ—§‚ء‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚ھ•ھ‚©‚ء‚½پB
‚±‚¤‚µ‚½ڈطŒ¾‚â”’‰¹—ر“¹‚ةٹض‚·‚éڈî•ٌ‚ً‘چچ‡‚·‚é‚ئپA‚±‚ج“¹“¹‚ح“¹“Œژ©“®ژشŒڑگفچHژ–Œ»ڈê‚ض‚جƒAƒvƒچپ[ƒ`ƒ‹پ[ƒg‚ئ‚µ‚ؤپA2010”N‘م‚جگ””NٹشپA‘هپX“I‚ة—ک—p‚³‚ê‚ؤ‚¢‚½‚±‚ئ‚ھ•ھ‚©‚ء‚½پB
‚©‚آ‚ؤ’Yچz‚ج•آچ½‚ة‚و‚ء‚ؤ–ًٹ„‚ج‘ه•”•ھ‚ًڈI‚¦‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½“¹‚ةپA“ٌ“x–ع‚ج‘ه‚«‚بٹˆ–ô‚ج‹@‰ï‚ھ‚ ‚ء‚½‚ج‚¾پB’·گ¶‚«‚ح‚µ‚ؤ‚ف‚é‚à‚ج‚¾‚ئپA“¹“¹ژ©گg‚àژv‚ء‚½‚©‚à’m‚ê‚ب‚¢پB
‚ب‚¨پA–â‘è‚ج”’‰¹—ر“¹‚ج“üŒû‚ـ‚إ‚حپA‚ ‚ئ3km‚ظ‚ا‚ ‚éپB

2.5km’n“_‚ة‚à‹´‚ھ‚ ‚èپAڈ‡“–‚ة‘و8چ†‹´‚ً–¼ڈو‚ء‚ؤ‚¢‚½پB
ƒVƒ…ƒEƒgƒiƒCگى‚ً“n‚é‚à‚ج‚إپAڈ؛کa39”NڈvŒ÷پA‘S’·10.4mپA•6m‚ئ‚¢‚¤ƒXƒyƒbƒN‚¾پB
‚»‚ë‚»‚ë‹´‚جڈoŒ»‚ةگV‚½‚بƒRƒپƒ“ƒg‚ھژv‚¢‚آ‚©‚ب‚‚ب‚ء‚ؤ‚«‚½‚ھپAŒ»ڈê‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚حگ”•ھ‚ئ‹َ‚¯‚¸‚ةŒ»‚ي‚ê‚é‚ج‚إƒeƒ“ƒ|‚ھ—ا‚‘ق‹ü‚ًٹ´‚¶‚é‰ة‚ح‚ب‚¢پB
‚»‚ê‚ب‚è‚ةڈم—¬‚ضگi‚ٌ‚إ‚¢‚é‚ھپA‘ٹ•د‚ي‚炸ƒVƒ…ƒEƒgƒiƒCگى‚ج—¬‚ê‚ح‰¸‚â‚©‚إپAژضچs‚ً‚؟‚ه‚‚؟‚ه‚ƒVƒ‡پ[ƒgƒJƒbƒg‚µ‚ب‚ھ‚ç•ہ‘–‚·‚铹“¹‚إ‚³‚¦‚ظ‚ئ‚ٌ‚اڈم‚èچâ‚ًٹ´‚¶‚ب‚¢‚‚ç‚¢‚ن‚ء‚½‚肵‚ؤ‚¢‚éپB
‚±‚¤‚¢‚¤’nŒ`‚جٹة‚â‚©‚³‚àپA’Y“c’n‘ر‚ة‚ ‚è‚ھ‚؟‚¾‚ئژv‚¤پBپi’Y“c‚ح‚»‚جگ¬ˆِ‚ھ’ل•½‚بژ¼’n‚âڈہ‘ٍ’n‚إ‚ ‚ء‚½‚ح‚¸‚إپA‚»‚جŒم‚ج’nٹk•د“®‚ھ‚ ‚ء‚½‚ئ‚µ‚ؤ‚àŒ€“I‚ةŒ¯‚µ‚¢ژRٹx’n‘ر‚ض‚ئ•د‰»‚·‚é‰آ”\گ«‚ح’ل‚پA‚ـ‚½‚»‚¤‚ب‚é‚ئ’Y“c‚ئ‚µ‚ؤ‚جڈ¤‹ئ“Iگ¬—§‚ةŒ‹‚ر‚آ‚©‚ب‚¢‚ج‚¾‚낤پj

‘±‚¢‚ؤ‚ح2.8km’n“_‚ج‘و9چ†‹´پB
ƒVƒ…ƒEƒgƒiƒCگى‚ة‰ث‚©‚é‹´‚إپAڈ؛کa39”NڈvŒ÷پA‘S’·10.4mپA•6m‚ئ‚¢‚¤پAچإ‘پƒRƒsƒy‚إ‘«‚è‚»‚¤‚بƒXƒyƒbƒN‚¾‚ء‚½‚ھپA‚؟‚ه‚ء‚ئ‚µ‚½پg”Œ©پh‚ھ‚ ‚ء‚½پB
‚±‚ج‹´‚جهش‚ة—§‚ء‚ؤ‰؛—¬‘¤‚ً’‚ك‚é‚ئپcپc

‹Œ‹´‚ج‹´‘ن‚炵‚«گخ‘¢چ\‘¢•¨‚ھپI
–¾ٹm‚ب‹Œ‹´‚جˆâچ\‚ًŒ©‚é‚ج‚حپA‘و‚Pچ†‹´ˆب—ˆ‚ج‹vپX‚¾‚ء‚½پB

ٹشˆل‚¢‚ب‚پA‹Œ‹´‚جˆâچ\‚¾‚ء‚½پB
”Œ©‚µ‚½ٹغگخ—ûگد‚ف‚جگخ‘¢‹´‘ن‚ج‘خٹف‚ة‚à–¾ٹm‚ب’z’ç‚جچگص‚ھ‚ ‚èپA‚±‚ê‚ç‚ھ‘خ‚ً‚ب‚µ‚ؤ‚¢‚½پB
Œ…‚â‹´‹r‚ح‘S‚ژc‚ء‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚ھپA‹´‘ن‚جŒ`ڈَ‚©‚çپA‚ظ‚ع‚ظ‚ع–طŒ…‚ج‹´‚¾‚ء‚½‚±‚ئ‚ھ•ھ‚©‚éپB
‚³‚ç‚ةپA‹Œ‹´‚ج‘OŒم‚ة‚ح‚»‚ꂼ‚ê30m‚‚ç‚¢‚إŒ»“¹‚ئگع‘±‚·‚é‹Œ“¹‚جچگص‚ھ‚ ‚ء‚½‚ھپA‚»‚ج“¹•‚ح3m‘«‚炸‚إ‚ ‚èپA6m‚ظ‚ا‚ ‚錻“¹‚ئ”ن‚ׂé‚ئ‚¢‚©‚ة‚àŒأ‚©‚ء‚½پB
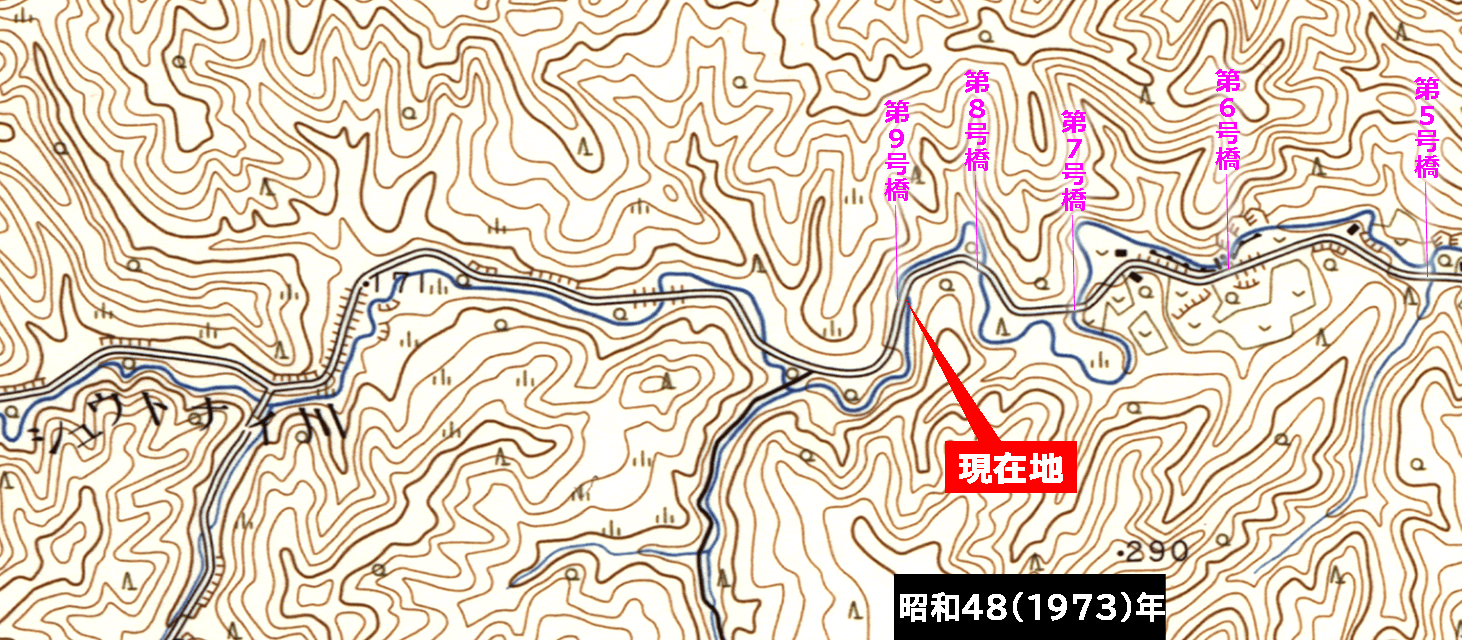
‚ب‚¨پA‚±‚جˆت’u‚ة‹Œ‹´‚ھ‚ ‚邱‚ئ‚حپAˆسٹO‚إ‚ ‚ء‚½پB
‚ئ‚¢‚¤‚ج‚àپAڈ؛کa48”N”إ‚ج’nŒ`گ}‚ة‚حٹù‚ةŒ»چف‚ج“¹‚ھ•`‚©‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ج‚¾‚ھپA‚»‚ج‚P‚آ‘O‚ج”إ‚إ‚ ‚éڈ؛کa42”N”إ‚¾‚ئپA‚»‚ج‹Œ“¹‚ة‚ ‚½‚铹‚ح“r’†‚إڈI‚ي‚ء‚ؤ‚¢‚ؤپA‚±‚±‚ـ‚إ‚ح’ت‚¶‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚±‚ئ‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ج‚¾پB
‚µ‚©‚µŒ»’n‚جڈَ‹µ‚حپA‚±‚ج’nگ}‚جڈî•ٌ‚ً•¢‚µپA‹Œ“¹‚à‚±‚جˆت’u‚ـ‚إ—ˆ‚ؤ‚¢‚½‚±‚ئ‚ً•¨Œê‚ء‚ؤ‚¢‚½پB

“üŒû‚©‚ç–ٌ3kmگi‚ٌ‚¾’n“_‚ة‚حپA4kmƒ|ƒXƒg‚ھ‚â‚ح‚蔽‘خŒü‚«‚ةگف’u‚³‚ê‚ؤ‚¢‚½پB
5kmƒ|ƒXƒg‚حŒ©“–‚ç‚ب‚©‚ء‚½‚ج‚إپA6kmƒ|ƒXƒgˆب—ˆ‚جچؤ‰ï‚إ‚ ‚ء‚½پB
ˆّ‘±‚«پA“¹‚جڈَ‘ش‚ةˆ«‰»‚ح‚ب‚پA‚·‚±‚ش‚éڈ‡’²‚إ‚ ‚éپB

9پF29پ@پsŒ»چف’nپt
“üŒû‚©‚ç3.3km’n“_‚ة‚ؤپAگ‹‚ةگ”ژڑ‚ة‚ھ‘ه‘ن‚ةڈو‚ء‚½‘و10چ†‹´‚ئ‘ک‹ِپB
“ْ–{’†‚إ‹´‚ج–¼‘O‚ًŒ©‚ؤ‚«‚½ژ„‚¾‚ھپA“¹کH‹´‚ة‚¨‚¢‚ؤپA‚±‚جژè‚جƒiƒ“ƒoƒٹƒ“ƒO‚ج‹´–¼‚ھپg‘ه‘نپh‚ة’B‚·‚é‚ج‚ح‚·‚²‚’؟‚µ‚¢‚±‚ئ‚إ‚ ‚éپBپi“S“¹‹´‚ب‚ç’؟‚µ‚‚à‚ب‚¢‚ھپj
‚â‚ح‚è–ء”آ‚ة‚و‚ء‚ؤ‹´–¼‚ھ—ک—pژز‚ةٹJژ¦‚³‚ê‚邱‚ئ‚ھ‘½‚پA‚»‚¤‚إ‚ب‚‚ؤ‚à—ک—pژز‚ھ’¼گعژè‚ًگG‚ê‚éگg‹ك‚ب‘¶چف‚إ‚ ‚铹کH‹´‚جڈêچ‡پAƒiƒ“ƒoƒٹƒ“ƒO‚ئ‚¢‚¤–،‹C‚ب‚¢–¼‘O‚ً‘I‚ش‚و‚è‚حپA‚¢‚ë‚¢‚ë‹أ‚ء‚½–¼‘O‚ً’T‚µ‚ؤ•t‚¯‚éŒXŒü‚ھ‹‚¢‚ج‚¾‚ئژv‚¤پB
‚»‚ٌ‚ب‚ب‚©پAمY—ي‚³‚ء‚د‚è‘و1چ†‚©‚ç‘و10چ†‚ةژٹ‚é‚ـ‚إپA‹@ٹB“I‚بƒiƒ“ƒoƒٹƒ“ƒO‚ةڈIژn‚µ‚½‚±‚ج“¹‚حپA‚â‚ح‚è“ءˆظ‚¾پB
‚»‚à‚»‚à’n–¼‚ھ–R‚µ‚¢ژR’†‚ةگ®”ُ‚³‚ꂽ“¹‚إ‚ ‚ء‚½‚±‚ئ‚âپAژY‹ئ“¹کH‚ئ‚¢‚¤Œّ—¦—Dگو‚جڈoژ©‚ھپA‚±‚ٌ‚بƒlپ[ƒ~ƒ“ƒO‚ةŒ‹‚ر‚آ‚¢‚½‚©‚ئژv‚¤پB
‚±‚جگوپAƒiƒ“ƒoƒٹƒ“ƒO‚ھ‚ا‚±‚ـ‚إگL‚ر‚é‚ج‚©‚àپA’n–،‚ةٹy‚µ‚ف‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚«‚½پBپi“ْ–{ˆê‚ھ‚¢‚‚آ‚©‚ح•ھ‚©‚ç‚ب‚¢‚ھپA‚à‚µ‚©‚µ‚½‚ç–عژw‚¹‚é‚©‚àپHپj

‚»‚µ‚ؤپA‚±‚ج‘و10چ†‹´‚ة‚àپA–¾—ؤ‚ب‹Œ‹´‚جچگص‚ھ‚ ‚ء‚½پB
چ،“x‚حپA‰ح’†‚ة“ث‚ء—§‚آƒRƒ“ƒNƒٹپ[ƒg‚ج’ل‚¢‹´‹r‚إ‚ ‚éپB
‚ـ‚½پA—¼ٹف‚ة‚à’z’ç‚جچگص‚ھژc‚ء‚ؤ‚¢‚½پB
”z’u“I‚ةپA‹´‹r‚ھ‚±‚ê‚P–{‚¾‚¯‚ئ‚حچl‚¦‚ة‚‚¢‚ھپA—¬‚³‚ê‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½‚ج‚¾‚낤پB
ƒ`ƒFƒ“ƒWŒم‚ج‰و‘œ‚حپAŒ»“¹‚ئ‹Œ“¹‚ج•ھٹٍ’n“_‚إژB‰e‚µ‚½پB
چ¶‚ھŒ»“¹‚إ‚ ‚é‚ھپA‚»‚ج‰E‘¤‚ة•½چs‚·‚é’ل‚¢’z’ç‚ھŒ©‚¦‚é‚ئژv‚¤پB‹Œ“¹‚جˆâچ\‚إ‚ ‚ء‚½پB
ٹî–{“I‚ة‹Œ“¹‚ئŒ»“¹‚حڈd‚ب‚ء‚ؤ‚¨‚èپA‹´‚ھ‚ ‚é‚ئ‚±‚낾‚¯•تƒ‹پ[ƒg‚¾‚ء‚½‚و‚¤‚¾پB
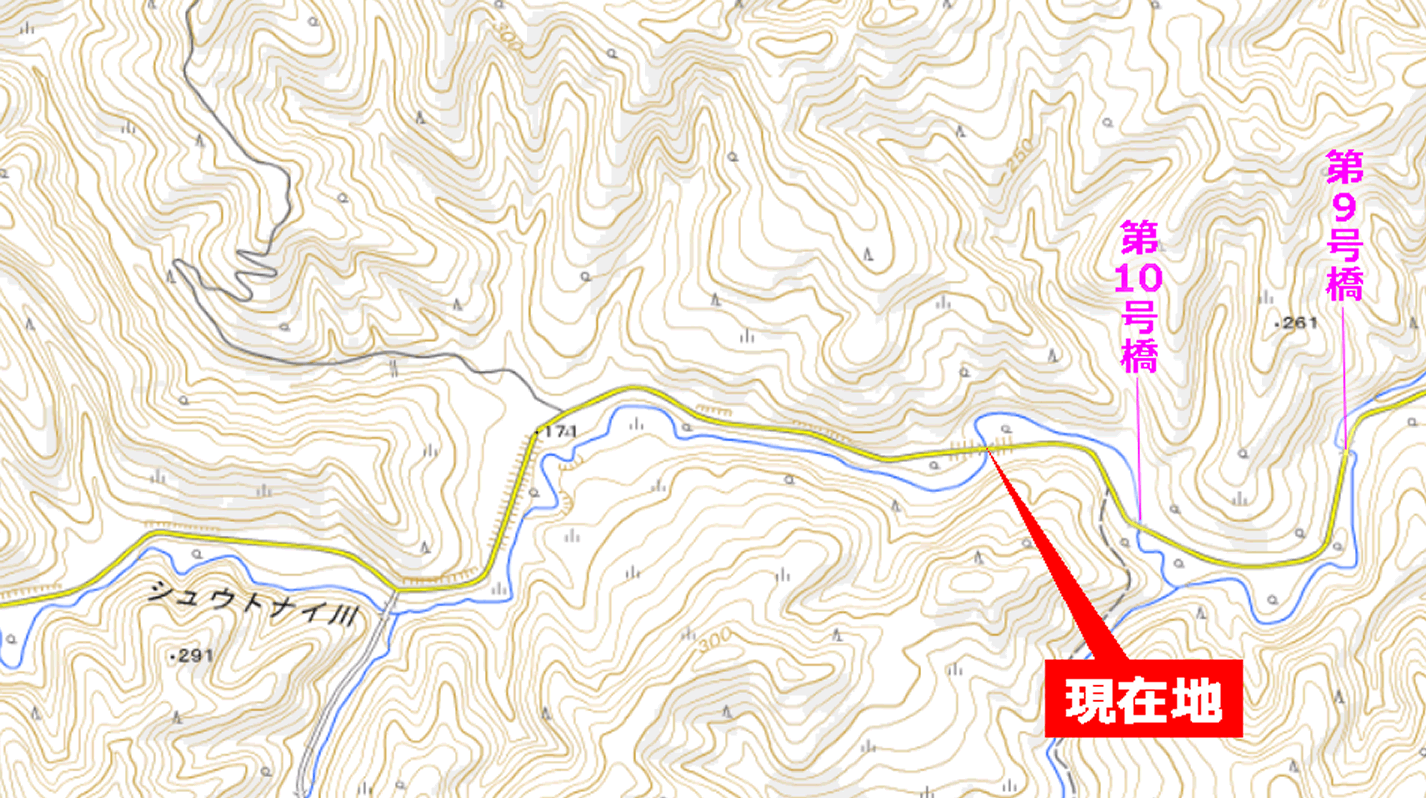
9پF31
“üŒû‚©‚ç3.7kmپA‘و10چ†‹´‚©‚ç–ٌ300mپA‚à‚¤‰½“x–ع‚©•ھ‚©‚ç‚ب‚¢ƒVƒ…ƒEƒgƒiƒCگى‚ج‰،’f’n“_‚ضپB

‚»‚µ‚ؤپAŒ»’n‚ة‚ح“–‘R‚ج‚و‚¤‚ةŒ»‚ي‚ê‚éپAژں‚ب‚é‹´‚جژpپB
‰“–ع‚ةŒ©‚ؤ‚àپA–¾‚ç‚©‚ةچ،‚ـ‚إ‚ج‹´‚ئ“¯‚¶Œ`‚جگe’Œ‚âچ‚—“‚ھ‚ ‚éپB
‚±‚ج‹´‚ھ‘و11چ†‹´‚ئ‚¢‚¤–¼‘O‚إ‚ ‚邱‚ئ‚حپA‚à‚ح‚â‹ك‚أ‚¢‚ؤٹm”F‚·‚é‚ـ‚إ‚à‚ب‚–¾‚ç‚©‚¾‚ء‚½پB

— ‚ً‚©‚©‚ê‚郈ƒbƒL‚ê‚ٌپI
پu‘و2ƒ{ƒbƒNƒX‹´ Dai 2 Box Bridgeپv
‚»‚ê‚ھˆؤ“à•Wژ¯‚ة‚و‚ء‚ؤٹJژ¦‚³‚ꂽپAˆسٹO‚ب‚é–{‹´‚ج–¼‚إ‚ ‚ء‚½پB
‚ب‚¨پAپuƒ{ƒbƒNƒX‹´پv‚ئ‚¢‚¤‚ج‚حپA‚¨‚»‚炃{ƒbƒNƒXƒJƒ‹ƒoپ[ƒg‚ج‚±‚ئ‚ًژw‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ئژv‚ي‚ê‚éپB

چؤ‚ر— ‚ً‚©‚©‚ê‚郈ƒbƒL‚ê‚ٌپI
‘S‘Rƒ{ƒbƒNƒXƒJƒ‹ƒoپ[ƒg‚¶‚ل‚ب‚¢پIپIپI
‚ا‚±‚©‚ç‚ا‚¤Œ©‚ؤ‚à•پ’ت‚جŒ…‹´‚إ‚ ‚èپA‘و2پ`‘و5‚¨‚و‚ر‘و7پ`‘و10چ†‹´‚ئ“¯‚¶Œ`ڈَ‚جŒ…‚¾‚ء‚½پB
‚ب‚ٌ‚إ‚±‚ê‚ھƒ{ƒbƒNƒX‹´‚ئ–½–¼‚³‚ꂽ‚ج‚©پB‚»‚ê‚ةپA‚ب‚؛‘و1ƒ{ƒbƒNƒX‹´‚ھ‚ب‚‘و2ƒ{ƒbƒNƒX‹´‚ب‚ج‚©پB
“ن‚ھگ[‚¢پB

‚»‚µ‚ؤپA“ن‚¾‚¯‚إ‚ب‚پAˆإ‚àگ[‚¢پB
‚ب‚؛‚©‚±‚ج‹´‚جژl‹÷‚جگe’Œ‚©‚ç‚حپA‘S‚ؤ‚ج–ء”آ‚ھژو‚èٹO‚³‚ê‚ؤ‚¢‚½پB
ژ©‘R‚ة’E—ژ‚µ‚½‚ئ‚حژv‚¦‚ب‚©‚ء‚½پB
ژ„‚حژv‚ء‚½پB
–{“–‚حپuƒVƒ…ƒEƒgƒiƒCگü ‘و11چ†‹´پv‚ئ‚¢‚¤–ء”آ‚ھ‚ ‚ء‚½‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚©‚ئپB
‚µ‚©‚µپA‚±‚ج‹´‚ًپu‘و2ƒ{ƒbƒNƒX‹´پv‚ئ–¼•t‚¯پA‚»‚ج‚و‚¤‚بˆؤ“à•Wژ¯‚ًگف’u‚µ‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½Œ»چف‚ج“¹کHٹا—ژز‚ھپA‚±‚ج•sˆê’v‚ً‰B‚·‚½‚ك‚ةپAگe’Œ‚©‚ç–ء”آ‚ًژو‚è‹ژ‚ء‚½‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚©‚ئ‚¢‚¤‹^کfپcپB
‚ب‚¨پAژ‘—؟پi2018”N“x‘Sچ‘‹´—ہƒ}ƒbƒvپj‚إ‚àپA‚±‚ج‹´‚حٹm‚©‚ةپu‘و“ٌƒ{ƒbƒNƒX‹´پv‚ئ‚¢‚¤–¼‘O‚إپAڈvŒ÷‚حڈ؛کa40(1965)”NپA‰„’·10.5mپA•ˆُ6.2m‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚½پB

Œ»‹´‚جپg“نپh‚ئپgˆإپh‚ج‰e‚ة‰B‚ê‚é‚و‚¤‚ةپA‚±‚ج‹´‚ة‚à‹Œ‹´‚جچگص‚ھ‚ ‚ء‚½پB
20m‚ظ‚ا‰؛—¬‚جگى’ê‚ةپA‘½کAژ®–طگ»‹´‹r‚جٹî‘b‚ھ“]“|ڈَ‘ش‚إژc‚ء‚ؤ‚¢‚½پBژl–{‚ج’Œ‚ً•ہ‚ׂ½‚à‚ج‚إ‚ ‚ء‚½‚و‚¤‚¾پB

‘و“ٌƒ{ƒbƒNƒX‹´‚ً“n‚é‚ئƒVƒ…ƒEƒgƒiƒCگى‚جژضچs‚ھژû‚ـ‚èپA‹´‚جکA‘±ڈoŒ»‚àڈI‚ي‚ء‚½پB
“¹‚حˆث‘R‚ئ‚µ‚ؤ•½‰¸‚إ‚ ‚èپAƒqƒOƒ}ڈo–v‚جٹë‹@ٹ´‚±‚»ڈي‚ةژ‚ء‚ؤ‚ح‚¢‚½‚à‚ج‚جپAژüˆح‚جگX‚جŒ©’ت‚µ‚àˆ«‚‚ح‚ب‚©‚ء‚½‚ج‚إپA‚µ‚ء‚©‚艹‚ً–آ‚炵‚ب‚ھ‚çگi‚ق‚±‚ئ‚إپA‹°•|گS‚ح‚¾‚¢‚ش—}‚¦‚éژ–‚ھڈo—ˆ‚½پB
‚»‚µ‚ؤ“üŒû‚©‚ç4km‚ج’n“_‚إپAژc‚è3km‚ً’m‚点‚éƒLƒچƒ|ƒXƒg‚ئڈo‰ï‚ء‚½پB
ژc‚è3kmپcپcپ@‚و‚¤‚â‚‹——£‚جڈم‚إ‚àŒم”¼گي‚¾پB

9پF37پ@پsŒ»چف’nپt
“üŒû‚©‚ç–ٌ4.6kmپA‘و“ٌƒ{ƒbƒNƒX‹´‚©‚ç0.9km‚ش‚è‚ج‹´‚ھŒ»‚ي‚ꂽپB
‰ت‚½‚µ‚ؤچ،“x‚ج‹´‚ح‚ب‚ٌ‚ؤ–¼‘O‚ب‚ج‚©پB
‚à‚ح‚â“ا‚ف‚ھ’ت‚¶‚ب‚¢ڈَ‘ش‚إ‚ ‚ء‚½‚ھپA‚»‚ج‹´‚ج—lژq‚à‚±‚ê‚ـ‚إ‚ئ‚حˆظ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚½پB
‚ـ‚¸‚حˆلکaٹ´پBپ@‚±‚ê‚ـ‚إ‚ح•K‚¸‚ ‚ء‚½ˆؤ“à•Wژ¯‚ھŒ©“–‚ç‚ب‚¢پB

‹´‚حƒ{ƒbƒNƒXƒJƒ‹ƒoپ[ƒg‚إ‚ ‚èپA‚©‚آپu‘وڈ\“ٌچ†‹´پv‚ج–ء”آ‚ھژو‚è•t‚¯‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚½پI
ژ„‚حژ@‚µ‚½پB
Œ»چف‚ج“¹کHٹا—ژز‚حپA‹´‚ج–¼•t‚¯‚ًŒë‚ء‚ؤ‚¢‚éپB
ƒ{ƒbƒNƒXƒJƒ‹ƒoپ[ƒg‚إ‚ ‚é‹´‚ة‘خ‚·‚é–½–¼‚ًپAŒ…‹´‚ج‚à‚ج‚ئ‚ح•ت‚جƒiƒ“ƒoƒٹƒ“ƒO‚ة‚·‚é‚ج‚إ‚ ‚ê‚خپA‚±‚ج‹´‚ًپu‘و2ƒ{ƒbƒNƒX‹´پv‚ئ–¼•t‚¯‚é‚ׂ«‚إ‚ ‚ء‚½پB
‚»‚ج‚¤‚¦‚إپAژہچغ‚حƒ{ƒbƒNƒXƒJƒ‹ƒoپ[ƒg‚إ‚ ‚éپy‘و6چ†‹´پz ‚ًپu‘وˆêƒ{ƒbƒNƒX‹´پv‚ئ–¼•t‚¯‚é‚ׂ«‚إ‚ ‚ء‚½پB
‚ًپu‘وˆêƒ{ƒbƒNƒX‹´پv‚ئ–¼•t‚¯‚é‚ׂ«‚إ‚ ‚ء‚½پB
‚»‚¤‚·‚ê‚خپAپuƒ{ƒbƒNƒX‹´پv‚ج1”ش–ع‚ھŒ‡”ش‚ة‚ب‚邱‚ئ‚ح‚ب‚©‚ء‚½‚µپA–{—ˆ‚حپy‘و11چ†‹´‚إ‚ ‚é‚ׂ«‹´پz ‚ھپu‘و2ƒ{ƒbƒNƒX‹´پv‚ئ–¼•t‚¯‚ç‚ê‚ؤ‚µ‚ـ‚¤‚±‚ئ‚à‹N‚ç‚ب‚©‚ء‚½پB
‚ھپu‘و2ƒ{ƒbƒNƒX‹´پv‚ئ–¼•t‚¯‚ç‚ê‚ؤ‚µ‚ـ‚¤‚±‚ئ‚à‹N‚ç‚ب‚©‚ء‚½پB
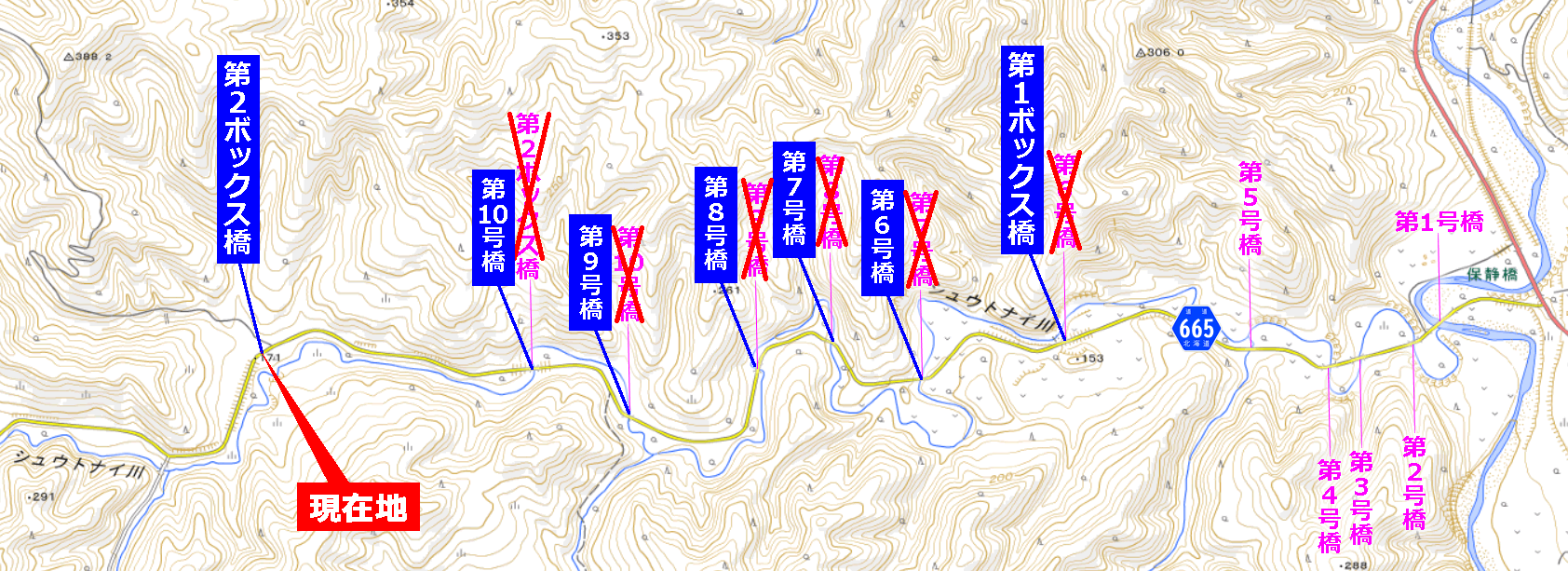
ڈم‹L‚µ‚½‹´–¼‚جڈCگ³‚ًچج—p‚µ‚½‚ج‚ھڈم‚ج‰و‘œ‚إ‚ ‚éپB
‚±‚¤‚·‚ê‚خپA‹´‚جچ\‘¢‚ئ–½–¼‚جگ®چ‡‚ھٹm•غ‚³‚ê‚éپB
‚½‚¾پA‚±‚ج‚و‚¤‚ب–½–¼‚ًچs‚¤‚ئپA‘و7چ†‹´ˆبچ~‚ج‹´‚حپA–ء”آ‚ئ‚ح‹´–¼‚ھˆê’v‚µ‚ب‚‚ب‚é‚ئ‚¢‚¤–â‘è‚ھگ¶‚¶‚éپB
‚»‚ê‚ً”ً‚¯‚é‚ج‚إ‚ ‚ê‚خپA‚»‚à‚»‚àƒ{ƒbƒNƒX‹´‚جƒiƒ“ƒoƒٹƒ“ƒO‚ً•ھ‚¯‚é—]’n‚ح‚ب‚©‚ء‚½پB
ƒ`ƒFƒ“ƒWŒم‚ج‰و‘œ‚حپAژY‹ئ“¹کH‚ئ‚µ‚ؤٹJ’ت‚µ‚½“–ڈ‰‚ج‹´–¼‚ًچؤŒ»‚µ‚½‚à‚ج‚إ‚ ‚éپB
‚±‚ج‚ـ‚ـ•د‚¦‚é•K—v‚ح‚©‚ء‚½‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚©‚ئ‚àژv‚¤پB

‚ئ‚à‚©‚پA‚±‚جƒ{ƒbƒNƒXƒJƒ‹ƒoپ[ƒg‚حŒ»ڈَ‚ة‚¨‚¢‚ؤپA“¹کHٹا—ژز‚ة‚ح‹´‚ئ‚µ‚ؤ–½–¼‚à”Fژ¯‚à‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ب‚¢پB
‚¾‚©‚çپAژ‘—؟‚ة‚à‚±‚ج‹´‚جڈ”Œ³‚ح‹Lک^‚ھ‚ب‚¢پB
Œ×‚¢‚إ‚¢‚é‚ج‚حƒVƒ…ƒEƒgƒiƒCگى‚ج–³–¼‚جژx—¬‚إ‚ ‚éپB
‚¨‚»‚ç‚‚ح“¹کHٹا—ژز‚جƒ~ƒX‚ًŒ´ˆِ‚ئ‚·‚éˆê•”‚ج‹´‚ج•sژ©‘R‚ب–½–¼‚ئ‘ک‹ِ‚µ‚آ‚آ‚àپA‘Oگiژ©‘ج‚ة‚ح‘S‚ژ肱‚¸‚邱‚ئ‚ح‚ب‚پcپc

9پF42پ@پsŒ»چف’nپt
“üŒû‚©‚ç5km’n“_پA”’‰¹—ر“¹•ھٹٍ‚ة“’BپB
‚±‚±‚©‚ç‚جژc‚è‚ح2km‚حپAچs‚«ژ~‚ـ‚è‚إ‚ ‚éپu‹N“_پv‚ـ‚إ‚جˆê–{“¹‚¾‚ھپcپc

‚ پc
| “–ƒTƒCƒg‚حپAٹF—l‚©‚ç‚جڈî•ٌ’ٌ‹ںپAژ‘—؟’ٌ‹ں‚ً‚¨‘ز‚؟‚µ‚ؤ‚¨‚è‚ـ‚·پBپ@پ¨ڈî•ٌپEژ‘—؟’ٌ‹ں‘‹Œû | |
|
‚±‚جƒŒƒ|پ[ƒg‚جچإڈI‰ٌ‚ب‚¢‚µچإگV‚ج‰ٌ‚جپu‚±‚جˆت’uپv‚ةپAƒŒƒ|پ[ƒg‚ض‚ج‚²ٹ´‘z‚ب‚اژ©—R‚ةƒRƒپƒ“ƒg‚ً“ü—ح‚µ‚ؤ‚¢‚½‚¾‚¯‚é—“‚ئپA‚¢‚½‚¾‚¢‚½ƒRƒپƒ“ƒg‚جڈذ‰îƒyپ[ƒW‚ً—pˆس‚µ‚ؤ‚¨‚è‚ـ‚·پB‚ ‚ب‚½‚ج•]‰؟پAٹ´‘zپA‘جŒ±’k‚ب‚اپA‚؛‚ذ‚¨ٹٌ‚¹‚‚¾‚³‚¢پB پyƒgƒbƒvƒyپ[ƒW‚ة–ك‚éپz |
|