幻の上部軌道を目指して! (前編)

7:11 《現在地》
濁河索道は、とても楽しかった。
だが、それだけだった。
現役時代も(公式的には)そうであったように、運材用索道は人が移動するためのものではない。空に渡された鉄索は、私が対岸に眠る上部軌道へ移動するための通路にはなり得なかった。全く当たり前の事である。
とはいえ、上部軌道がどのくらいの高さにあるのかという、リアルな位置関係を感じる事が出来たのは収穫で、何より、古地形図に描かれた索道や軌道が絵空事などではないことを確信出来た。
一旦林道のワルクードに戻り、対岸へアプローチを改めて探すことにする。
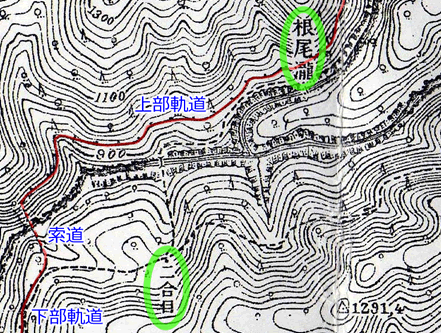
前説を思い出していただきたいが、現在の地形図には描かれていない対岸へのアプローチルート(濁河川を渡る橋)が、昭和25年応急修正版の古地形図には存在していた。(→)
それは、「二合目」(これはおそらく御嶽山の二合目ということだろう)という地点で濁河川へ降りて行き、絶壁に囲まれた濁河川を小さな橋で渡ってから、しばらく右岸伝いに遡って「根尾瀧(滝)」で終わっている徒歩道である。
あまり深く考えることなく来てしまったが、これは根尾滝観覧を目的とする遊歩道のようなものと解して良いのだろうか。
だとすれば、この滝の規模にもよるだろうが、現在も滝へアプローチする道があると期待できるのではないか。
…今の地形図にそれが描かれていないのは不安だが、まずはワルクードで「二合目」とやらへ行ってみよう。

7:16 《現在地》
おおっと!
索道があった倉ヶ平から約500m林道を奥へ進むと、広場というレベルではない、立派な駐車場というべきものが用意されていた。
標高は50m上がって950mに達している。真新しい鋪装もここまでで、この先は本来の林道らしい未舗装である。
旧版地形図の「二合目」にはまだ少し届かない位置ではあるが、とりあえずここに駐車場があるというのは、根尾滝への遊歩道が存在するためと考えて良さそうだ。

オーケー! 駐車場は案の定、根尾滝のためのものだった。
しかも、案内板に書かれたイラストマップによれば、ちゃんと対岸へ渡るための橋も用意されているようだ。まさに渡りに舟。
ここまで(自転車のデポとか)お膳立てしたのに、対岸へ渡ることさえ出来ずに撤収というのは耐え難い悔しさだったろうから、ここで地形図に描かれていない遊歩道に出会えたのは、とても嬉しかった。
本編に登場するかは分からないが、折角なので栄えある「日本の滝百選」にも選ばれているという根尾滝の説明書きを転載しておこう。
霊峰、御嶽山の頂や原生林から流れ出る渓水を絶壁から一気に落す根尾の滝。標高1000m、落合国有林内を流れる濁河川にあり落差63m。奥深い山中で水煙を上げるその美しい姿は、江戸時代の文献にも記され、日本画の題材になっています。平成2年3月「日本の滝百選」に選ばれ、滝までの遊歩道開通によって“秘境の名瀑”を目前で観ることが出来ます。
…とのことである。遊歩道の開通が平成2年以降と比較的新しいことが、地形図に道が描かれていない理由かも知れない。江戸時代から滝までの道はあったのだろうが、平成の時代まで廃道同然にうらぶれていたのだろうか。知る人ぞ知る秘境の滝であった時代なら、軌道跡とは関係なく訪れたかったかも。

だが、遊歩道という表現の割には、結構な険路を予感させる注意書きが出されていた。
「滝までの往復約2時間(休憩時間除く)」「遊歩道入口から濁河川を渡る吊り橋まで750m」「吊り橋から滝まで1450m」「急な坂道を下ったり、上ったり、岩場を歩く」などなど、私がこの駐車場で得た情報の数々は、遊歩道とはいえ侮れないことを教えていた。
しかも私の目的地は、遊歩道のゴールとは違っているのである。
対岸に渡り次第、私はどこかで遊歩道を捨てて、谷底から100m以上の高所にあろう“軌道跡”を目指さねばならない。
そこにいかなる道が存在するかは、まだ全く明らかになっていない。
その部分だけは、今回の探索で正真正銘の「行き当たりばったり」を余儀なくされたのであったが、踏破する全体の規模から考えれば、納得出来ると思える程度のリスクだ。もはや最初に古地形図と今の地形図を見較べたときに感じた“闇雲”を探るような状況ではないのである! 俺は頑張れると思う!

7:23 《現在地》
背中に体温が残ったままのリュックを再び背負い、車とサヨナラする。
駐車場から未舗装の林道を200mほど歩くと、左に入る脇道が現れた。
旁らには、「根尾の滝遊歩道 滝まで2.2km 片道約50分」の立派な指導標も有り。
対岸の軌道跡を目指し、今度こそ濁河川の突破を狙う。
遊歩道へ足を向けつつも、心の中では虎視眈々と歩道外の獲物を狙う、そんなワル狼の気分だった。

林道から遊歩道に入ってすぐのところに、刻んだ年月の長さが一目で見て取れるような苔生した碑が立っていた。
表面には大きく分かり易い文字で、「二合目」の刻字。
左右にもそれぞれ小さな文字で、「右 ●●●(読み取れず)」「左 ネオタキ」とあって、立派な道標石だった。記年は見あたらないが、江戸時代っぽいような。
うっかり遊歩道に導かれて忘れかけていたが、旧地形図で根尾滝入口地点の目印になっていた「二合目」は、この場所に違いない。
先ほど駐車場で読んだ根尾滝の案内文には、滝が江戸時代から日本画の題材になるほど知られていたとあったが、道標石の横にも案内板があって、「旧御獄登山道2合目 この標識は覚明行者が開山した旧御獄登山道の2合目を表すものです」と記されていた。
「ネオタキ」というカタカナ表現が、なんかNEOな感じで時代錯誤のかっこよさに見えてしまったのはどうでもいいが、これから辿る遊歩道が、単なる軌道跡へのアプローチとして黙殺するには勿体ない、由緒ある山の道であることは特筆したい。


林道から分け入ると、初めの数十メートルだけは全く平坦に近いヒバ林を歩く事が出来るが、すぐに林が切れて見えてきたのは、索道所(倉ヶ平)で見たのよりも50mだけ視座が高くなった、見覚えのある対岸の山形だった。
道は早速にして、濁河川の巨大な谷へ挑みかかる模様。いよいよ“落ちる”という段になって、「十六折れ」と書かれた手作りの案内板があったのも、おそらくは江戸時代からの由緒ある名前なのだろう。見せていただくとしよう。十六折れとやらが、名にし負う物であるのか否かを!

ガッチガチの電光型九十九折り!
熱い。
地形図に描かれた等高線通りの急な斜面だが、
車道では許されないクイックな切り返しの連続で、
歩道としては無理のない勾配で下っていた。

だが、まだ見えぬ下の方は、もっと急勾配になっていそうだ!
この眺め、怖ろしい。先が見えない。
本当に、遊歩道があってくれて助かった。
地形的には、確かに歩道が無くてもここを選んだだろう。
ここ以外は、基本的に下れる状況ではなかった(後述)ので、
私は最終的には野性の勘でここに行き着いたと信じたい。
だが、そんな状況で道無き道を下るとしたら、
この鍋の底を覗くような眺めは、あまりに怖すぎただろう。
道があるのだと分かっていても、私はこんなにゾクゾクしたのだから。

「ここ以外は、基本的に下れる状況ではなかった」と私が判断するに至ったのは、この写真に写っている大岩の存在を知ったからだ。
その名も、心太(ところてん)岩!!
(江戸庶民が好みそうなネーミングセンスだ。これが明治頃の名付けなら、漢文調になりそう、玄武岩とか。現代の名付けなら、もっとお洒落になりそう、兜岩とか。)
心太岩の何が怖ろしいかって、こいつは横幅がとんでもなく広い。
奥の霞んでいる向こうまで、高さこそ変化はあるが、ずっと続いているようだ。
また、反対に右を見ても、やはり似たような岩場が横並びだった。
これは大昔に御嶽山が流した溶岩流の名残である。
谷を流れた溶岩流の名残が、こうした大断崖になって渓谷の縁に残っている。
こうした地形はもっと遙かに下流にもあり、麓に有名な「巖立」という景勝地を作っている。
御嶽山が我が国有数の大火山であったことの名残であり、御嶽山に広壮な高原的景観と、苛烈な渓谷美の両方を与えている。
そして十六折れが通じている小さな枝谷(というかガレ谷)は、この屏風の如き玄武岩の大岩盤に、浸食による幾ばくかの間隙を与えている。
それで階段による上り下りが出来る状態なのである。
ここを除けば、おそらく濁河川への出入りは、相当に困難だと思う。

十六折れの高低差は、実に150mを越えている。
心太岩があるのは谷底から100mくらいの位置だから、その下から谷を覗いても底はまだ見えず、対岸の明るい山腹が、現実感の乏しい浮遊したような眺めに感じられた。
わずか400mほどの道のりでこれだけの高低差をクリアするのだから、九十九折りになっているとはいえ、道は急である。
簡単な木製のステップで階段が刻まれているとはいえ、遊歩道というよりは登山道に近い道である。
むろん、欄干や手摺りのような保護柵もない。落石避けもない。
ほぼ全線にわたって同じガレ場の中を左右左右するので、多人数が同時にこの道を歩くと、人為的な落石が怖そうだ。
私の探索中は、誰ひとりとも出会わなかったが。

二合目から17分くらい歩いた所で、本日初、濁河川の水面とご対面の時がやって来た!
濁河(にごりご)なんて名前だけど、こうして見る限り水の流れは清澄で、やや水量が多いどこにでもある渓流である。
仮に遊歩道が存在しなかったり、廃道だったりして橋が無かった場合のことも思考実験してみたが、太腿くらいまで水に浸かる覚悟ならば、渡れないことも無さそうな水量と水流だった。
しかし、返す返すも、「遊歩道サマサマ」だ!
こいつがなかったと思うと、もう何かあって引き返すのさえ命がけだったからな…。ガレ場斜面を150mもよじ登るとか、考えただけで憂鬱。
今日一番の元気な川音を間近に聞きながら、遊歩道の橋が見えてくるのを楽しみに歩き続けた。

7:44 《現在地》
出発から21分、私は首尾よく濁河川に架かる吊り橋に辿りついた。
現在地の標高は820mで、駐車場から150m低い。
そして、上部軌道があると推測される高さからも同じくらい低い!
今回の探索中に歩いて廻る地点の中では圧倒的に低い場所がここだ。
吊り橋は人道用ではあるが、鋼線を用いた頑丈そうなもので、揺れも少ない。
残念ながら銘板はなく橋名は不明だが、工事銘板があって、平成5年10月に小坂町が架けた物と判明した。
それ以前は昔ながらの木製吊り橋だったのだろう。
踏み板がシースルーのため、冷たい川風が全身に感じられる橋を颯爽と渡り、いよいよ念願の対岸へ!!
私の自転車が9km上流の標高1350m地点に待つ、そんな右岸世界へ“戻ってきた”。

先ほどまでの急転直下の大立ち回りが嘘のような平穏な道。
人が植えた森の安心感が古い生活路を思わせる、木洩れ日の似合う道。
或いは御嶽参りの白装束の人々が禊ぎへ参った、滝への道、祈りの道。
そんな完成されている道を、私は自らの決断で逸脱しなければならなかった。
それは、上部軌道を歩くために必要な儀式、禊ぎのようだった。

7:45〜55
私はまだ右岸の道を歩いていた。
どこかで道を逸脱しなければならないのは分かっているが、出来れば道を辿って行きたいという臆病さがあった。
索道は人を運ぶためのものではないから、どこかに索道非経由の道があって然るべきだという確信もあった。
だが、私がその道を見つけ出す事は無かった。
右岸の道のめぼしい範囲を一往復半してみたが、地形的に恵まれている緩斜面にも関わらず、この山を上っていこうという気概ある脇道を見出せなかった。
10分ほど時間を費やし、やはり意を決するしかないと悟った。
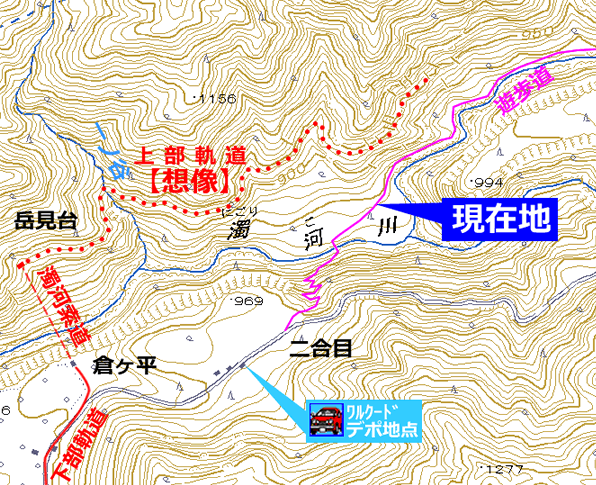
上部軌道へのアプローチを地形図で最終チェックする。
上部軌道の推定位置を点線で書き込んでいる。
この位置の根拠は、旧地形図の上部軌道が標高940mの等高線付近に存在するという厳然たる事実だ。
現在地から標高+100m、直線距離にして最短150mほどの至近にあるが、等高線的に最短距離の直登は困難と思われた。
そこで、歩く距離は長くなるが、緩斜面を最大限利用しつつ高度を稼ぎ、急勾配の区間も出来るだけ手掛かりが多い谷筋を選ぶのがセオリーと考えた。
そうして導き出したのが、紫線で示したアプローチルートである。
幸いにして今の私は、地形図だけでなくGPSも携帯している。
特徴の乏しい山野にあっても、かなり正確に現在地を把握できている。
上部軌道へのアプローチとしては他に選択の余地はないほど理想的に見えるこのコースで、本日の最初にして最大の課題をクリアしたい!

次回、
この山の上に私が見るものは。
| 当サイトは、皆様からの情報提供、資料提供をお待ちしております。 →情報・資料提供窓口 | |
|
このレポートの最終回ないし最新の回の「この位置」に、レポートへのご感想など自由にコメントを入力していただける欄と、いただいたコメントの紹介ページを用意しております。あなたの評価、感想、体験談など、ぜひお寄せください。 【トップページに戻る】 |
|