橋、隧道、そして大樽沢。

2010/4/21 11:14
千頭堰堤以来3本目の隧道。
これをくぐって、先へ進む。

3本中で最も短い隧道は、長さ20mほどしかなく、
さらに完全にコンクリートで巻き立てられているので、
内部については特にレポートすることが思いつかない。
ステージチェンジを告げる門。
そんな控えめな存在感であるが、
既に、“橋とのゴールデンコンビ”という
かけがえのない存在感を示しているので、十分だろう。
Try Next Stage!

隧道を抜けるとそこは広場で、路盤は川に沿って左にカーブしていた。
もちろんこの川は寸又川で、隧道は川の蛇行によって生じた小尾根を抜けただけだった。
そしてこの広場には、屋根だけを地上に残してぺっしゃんこになった小屋があった。
素性は不明なり。

忘れちゃイケナイ、振り返って隧道の北口をチェック。
短い堀割を従えた坑門は、林鉄用の隧道としてはなかなか手の込んだ形をしていた。
すなわち、坑門上からの土砂の流入を防ぐための土留工と、坑門が一体となったデザインだ。

一瞬、 レールが敷かれてる?! と色めきだったが、よく見たら、外されたレールが置かれているだけだった。
でも、おそらくここで使っていたレールを、そのまま脇にどかして置いているだけじゃないかと思う。“R”が一緒だ。そして一本だけではなく、何本も並べられていた。
…そういえば、今回はじめて見る廃レールかも知れない。
意外にここまでは見あたらなかった。
そして、すぐ先には何か、“百葉箱”みたいなものが見えてきた。


立て札曰く、ここは中部電力の「河川流量調査敷」。
“百葉箱”の方には、「天地測水所」という具体的な施設名が書かれていた。
よく見ると、平成20年に使用期限が過ぎているが、昭和11年から設置されているとのことで、千頭堰堤の運用開始に伴って設置された歴史ある施設らしい。
今の施設が何代目かは知らないが、そう古くはないようだ。
それにしても、ポツンと陸に置かれている小さなハコで、どうやって水の量を量っているんだ?
どういうメカニズムなんだろう。
そう思って川を見た私は、そこに意外なものを発見した。

こ、これは…
野猿!!
野猿と書いて「やえん」と読み、主に西日本で古くから谷を渡る道具として使われてきた、手動式のロープウェーである。
それを鉄のワイヤーと鉄の搬器(ゴンドラ)で再現したものが、ここにあった。
でも、乗る人独りだけでは動かせないのかも。
電気が来ていないので電動と言うことはないだろうが、左に見える何かの機械で操作するんじゃないだろうか。
「立入禁止」って書いていたので近付かなかったが(この理由はウソです…、単に軌道と無関係だし、古くないと思って油断してました。でも、今になってみると、乗ってみれば良かったと猛烈に後悔! 仮に手動では動かなくても、あのゴンドラに揺られてみたかった!)、まさかこんなモノをここで見ることになるとは。
おそらくこの野猿で人が川の中ほどまで行き、そこで検水棒みたいなものを垂らして水位を測るものと思われる。
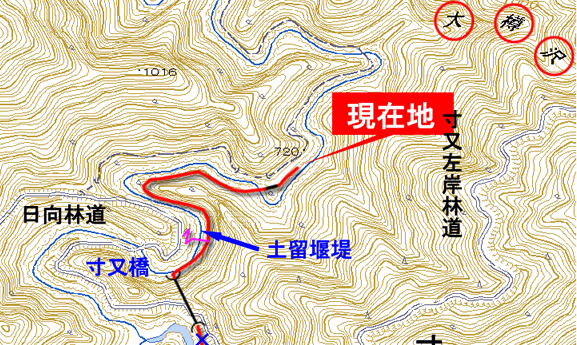
いよいよ近付いてきた大樽沢。
そこには何が待ち受けているのだろうか。
何も情報はない。
千頭林鉄と言えば林鉄の中では結構メジャーな方だと思っていたが、千頭堰堤以奥の情報は。驚くほど少なかった。
それもこれもアクセスが壊滅的に悪いからだろうが、いま私はその重い扉に手をかけているのだ。
見る景色がみな新しい状況に、そんな特別の幸福を実感した。
そういえば、日向林道は再び“あちら”の方向へ遠ざかってしまったが、別の破線の道が近付いてきているのだ。
近付いてきているどころか、もうすぐ傍にあるはずなのだ。
実は前回も、川の対岸にそれを探しながら辿ってきたが、見つけられないでいた。

地形図を見て、改めて“その道”を探す。
もちろん目を向けるのは、今いる所の上の斜面だ。
すると… あった!
30mほど上方の山腹に、もう一段の石垣。
あれだ。
昭和42年版地形図にも描かれている、「逆河内(さかさこうち)支線」だ。
現在の地形図だと、支線は破線で描かれているのに本線が消えているという、ちょっとした逆転状態になっているが、果たしてどんな塩梅なんだろうか。
まだ状況は分からない。
でも、とりあえずアクセス可能な位置に現れたことは好材料だ。
万が一の場合には、向こうに避難できるかも。

さらに200mほどは何事もなく平穏に進んだが、周囲にまた岩場が増えてきた。
平穏な時代は終わりを迎えつつあるのかも知れない。
川面も遠くなりつつある。
まだ慣れない左山右谷の状況で、前方には久々の危険地帯だ。
路盤が大きく陥没しており、通れるのは苔生して緑になったコンクリート路肩工のみという状況。
岩場を見上げてみても、なぜか、並行しているはずの「逆河内支線」は見えなかった。

実際に路肩工を通行すると、遠目に見るより怖い。
これだけ豪勢に苔生していれば、それなりに滑りやすいのである。
そして幅は30cm以上はあると思うが、その下に見える空洞がかなり深くて、ドキドキする。
この路肩工の下は、“トンネル” になっている。
この“路肩渡り”の最中に、改めて上部岩盤を見上げた私は、見てしまった。

逆河内の野郎…
豪勢に隧道かよ!
さっき見上げても見えなかったのは道理で、向こうは隧道の中だったのである。
そして、最初に見たときからは、驚くくらい近づいて来た。
合流が近そうだ。
なお、逆河内支線は昭和35年から37年にかけて全長3790mが新設された、千頭林鉄網最後の新線(全国的に見ても昭和30年代末の林鉄の新設は少ない)である。
今回は大樽沢で本線探索を終え、帰路は逆河内支線を辿るつもりであった。

穏やかな森の路盤が帰ってきた。
そして、ますます逆河内支線が近付いてきた。
林道だったらとっくに合流しているのだろうが、林鉄の悲哀、こんなに近付きながらなかなか一つになれない。
でも、そこが愛おしい。
いったいどんな合流が待っているのか、ワクワクする。
それに合流するときが今回の目的地、「大樽沢」到達の時だとも思う。

合流へのカタルシスが高まっていく。
路盤同士が近付きすぎたせいか、法面が80度くらいの石垣から、垂直のコンクリートの擁壁に変わった。
林鉄と言えば石垣の印象が強いので、コンクリートのツルッとした擁壁が続いている光景は新鮮な感じがする。
普通の道路の廃道ならば、別に珍しくもないのだが。
そして川側には、植林された杉が杉並木のように薄く連なっている。
そういえば今日は今まで林鉄を辿りながら、人工林を見た憶えがない。

キタッ! またキタッ!
またしても、コンクリート製のキロポストがニョッキリと。
表示されている内容は、「KM 1/2 24」。
これは鉄道用のキロポストと同じ流儀で、24.5kmということだ。
前回のキロポストから500m進んだことになる。
つまり、大樽沢まではあと100mだ。
もうすぐだ!
それにしても、ここに来て急に2連続でキロポストが出現するなんて…。
24kmよりも手前では、あんな路盤状況だったからやむを得ないんだろうけど、一本も見つけられなかった。
見過ごしがあったのかな。

緑のコンクリートウォールが、
上下二段の軌道を分けるただ一枚の壁。
森の鉄道ならではの景色だろう。

さあ、来るか来るか!
合流、来るか!
いよいよ二本の軌道の落差は限界まで小さくなり、その気になればピョンと逆河内線に移れる状態。
|
スポンサーリンク |
ちょっとだけ!ヨッキれんの宣伝。
|

orz…
ガッカリだよ、キミには…。
一番美味しい場面だけ
大 崩 落
なんて… 狙ってやってるとしか思えない!
チクショ……。
イクしかねーんだろ。どうせ。

ガラガラガラガラ…
ガラガラガラガラ…
バシャバシャバシャバシャ…
誰に遠慮することもなく、豪快に岩を蹴り落としながら横断する。
とりあえず下まで行かなきゃ、こんなとこ怖かねーぜ!
だいぶ荒くれてますよ、はい。
せっかく合流地点を期待していたのに〜ッ!

ほらーッ! やっぱりだ。
幅20mほどの大崩落を過ぎたときには、もう2本の路盤はすっかり1枚の平面になってしまっていた。
ただ、幅だけは確実に複線(以上)のものがある。
…まあいい。
とりあえず、これでまた一つ進んだ。
ここが大樽沢停車場 か。
何か残っているのだろうか。
予定通り引き返すにしても、何か区切りのあるところで…。
ん? なんか見えてきた。

見えていたのは、枕木を井桁に積み上げたものだった。
ここはひときわ路肩が広くなっていて、複線どころか複々線、或いはそれ以上の敷地がある。
それだけでも、ここが林鉄運用上の拠点的場所だった事が分かる。
流石に更地になってしまっているようだが…。
そしてそんな立地を考えると、この整然と積み上げられた枕木にも、何か意味を持たせたくなるが、やはり単なる撤去枕木だろうか。
とても丁寧に積まれていた。

右側は川が近く、この路盤上は何とも理想的なテント場であるなぁ…などと、次回以降探索の構想さえ練りながら進んでいくと、また何かが見えてきた。
さっきよりも大きな“影”が、若緑の木々の合間に写っている。
そして近付くにつれ、それが意外な大きさであることに気付くのだ。
あれあれあれれ…。
…なんと…なんと。

2010/4/21 11:32 《現在地》/【路線図】/【広域図】
千頭堰堤を出発してからちょうど4時間。
早朝に寸又峡温泉を自転車で出発してからだと5時間半ほどで、路線図(正確には「千頭営林署林道系統図」)上では「千頭堰堤」の次の停車場とされている「大樽沢」に到着した。
距離は4.3kmほどであったが、前半は非常に辛い展開であったと思う。
つか、
なんじゃこれは!
3階建ての木造建築物が、そっくりそのまんま残ってる!
普段は廃墟なんて見ても{フーン}だが、これは間違いなく営林署関係の建物だと思うだけに、林鉄と無関係ではないと思うだけに、のび太くんの住んでいる家に似ていると思うだけに、捨て置けない!
これには正直、感激&興奮した。
これまでもチラホラ崩れた小屋とかあったけれど、林鉄跡を探索していてこんな立派な廃墟に出会ったのは初めてだ。
秋田じゃ雪が悪さして、こんなモノが残っているはずがないのだろう。(くやしいです)
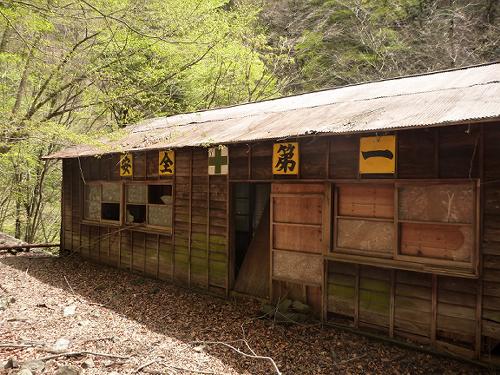
“安全+第一”
まさにこれこそ、林業事業所のあるべき姿だ!
少なくとも私の中では、この「安全+第一」があってこその営林署の建物なのである。
前に見たのは、ずいぶん遠い昔になってしまったが、宮城県の定義森林鉄道はインクラインの上部巻揚小屋だったか。
側面から見ると豪壮な3階建て木造建築も、路盤側からだと、かなりみすぼらしい平屋である。
入口の扉も壊れ、ガラスなんかも割れていて、普通に廃墟の姿である。
それでも、取り合えず入ってみようという気持ちにさせるくらいの壊れ方だ。
まあ一歩中に入ると、そのまま地上三階の高さなワケで、実は意外に危ないのかも知れないが…。
入らないわけには、いかないよね?
次回はこの区間の最終回。
すなわち、このときの本線探索最終回となる。
もちろん、「山行が」初?の廃墟探索だけでは終わらない…。
想定外の光景がッ。