چإŒم‚ةپAچ،‰ٌ‚ج’Tچُ‚إژc‚ء‚½“ن‚ًگ®—‚µپAٹ÷ڈم’²چ¸‚©‚ç‚ج‰ً–¾‚ًژژ‚ف‚½‚¢پB
“ن‚ئ‚¢‚¤‚ج‚حپA“r’†‚ة‚ ‚ء‚½ƒgƒ“ƒlƒ‹‚ةگs‚«‚éپB
–¼‘O‚³‚¦Œ»’n‚إ‚ح•ھ‚©‚炸پA‚ئ‚è‚ ‚¦‚¸پuگ{“cٹLè©“¹پv‚ئŒؤ‚ٌ‚إ‚¢‚½‚ج‚¾‚ھپA‚¹‚ك‚ؤٹJ’ت‚µ‚½‚ئ‚«‚ج–¼‘O‚إ‚à‚¤ˆê“xŒؤ‚ٌ‚إ‚â‚肽‚¢پB
‚»‚ê‚ةپAŒ»“¹‚ةگط‚è‘ض‚¦‚ç‚ꂽپi‚آ‚ـ‚茻“¹ٹJ’تپj‚ج”Nژں‚à•s–¾‚إ‚ ‚ء‚ؤپAژہ‚حˆسٹO‚ة•ھ‚©‚ç‚ب‚¢‚±‚ئ‚¾‚炯‚جŒ»’n’Tچُ‚إ‚ ‚ء‚½پB
‚ـ‚¸è©“¹‚ج–¼ڈج‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚¾‚ھپAژں‚ج‚و‚¤‚ب—L—ح‚بڈî•ٌ‚ھپu‘O•زپv‚ً‚¨“ا‚ف‚ة‚ب‚ء‚½“اژز‚³‚ٌ‚©‚ç‚à‚½‚炳‚ꂽپB
‚ـ‚½“¯گ}‚إ‚حƒoƒX‚ح‚±‚جژٹْƒgƒ“ƒlƒ‹‚ً’ت‚ء‚ؤ‚¨‚èپAŒ§“¹گ…ڈم•ذ•iگü‚ئ‚ج•ھٹٍ‚جڈ‚µگو‚ة‘هˆ°پB
گ{“cٹLƒ_ƒ€‚ئ‚ج•ھٹٍ“_‚ج‚sژڑکH‚ةگ{“cٹL”“dڈٹ“üŒûپB
‚»‚µ‚ؤ“´Œ³ƒgƒ“ƒlƒ‹‚ً”²‚¯‚ؤ‹}ƒJپ[ƒu‚ً‹ب‚ھ‚ء‚½گو‚ة“´Œ³گ…گ_‘O‚ئƒoƒX’â‚ج–¼ڈج‚ھ‹Lچع‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
‚؟‚ب‚ف‚ة“´Œ³گ…گ_‘O‚جژں‚حŒ§“¹‚ةچ‡—¬Œم‚©‚ب‚è—£‚ꂽ“´Œ³‰·گٍ‘O‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB
ژہ‘ش‚ھ‚ا‚¤‚إ‚ ‚ء‚½‚©‚ح”»‚è‚ـ‚¹‚ٌ‚ھژQچl‚ـ‚إ‚ة‚¨‘—‚è‚¢‚½‚µ‚ـ‚·پB
ژ„‚à‚©‚آ‚ؤڈH“cŒ§”إ‚ً‚±‚و‚ب‚ˆ¤—p‚µ‚ؤ‚¢‚½پuگl•¶ژذپv‚ج“¹کH’nگ}‚جڈî•ٌ‚إ‚ ‚éپB
‚»‚ê‚ة‚و‚é‚ئپAƒgƒ“ƒlƒ‹–¼‚حپu“´Œ³ƒgƒ“ƒlƒ‹پv‚ئ‚¢‚¤‚炵‚¢پB
“´Œ³‚ئ‚¢‚¤‚ج‚ح“ق—ا–“ƒ_ƒ€‚ج‚·‚®‰؛—¬‚ج•س‚è‚جŒ»چف“¯–¼‚ج‘ê‚ھ‚ ‚é•س‚è‚ج’n–¼‚إ‚ ‚é‚©‚çپAè©“¹‚©‚ç‚à‰“‚‚ح‚ب‚¢پB
‚ئ‚¢‚¤‚©پAگ{“cٹLƒ_ƒ€‚جƒ_ƒ€Œخ‚ج–¼‘Oژ©‘ج‚ھپu“´Œ³Œخپv‚¾‚ء‚½‚ج‚ً–Y‚ê‚ؤ‚¢‚½پB
‚ب‚é‚ظ‚اپAƒgƒ“ƒlƒ‹‚ج–¼ڈج‚ح‚±‚ê‚إ‚ظ‚عŒˆ‚ـ‚肾‚낤پB
ژں‚ةŒ»“¹‚جٹJ’ت‚جژٹْ‚ئپA‚»‚ج——R‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚¾‚ھپB
پc‚à‚»‚à‚»پB
ژہ‚ح‚±‚êپAˆسٹO‚ة‚â‚₱‚µ‚¢ژ–‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ؤپAڈ‚µگà–¾‚ةچ¢‚éپB
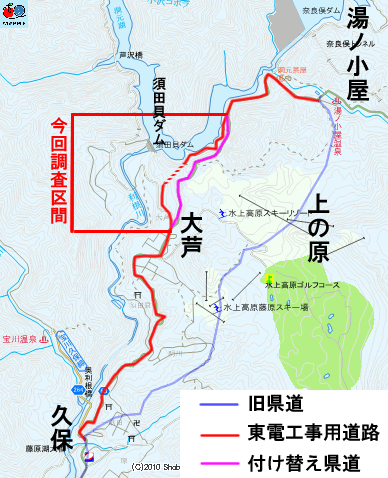
ژ„‚ھ—ٹ‚ء‚½‚ج‚حڈ؛کa39”N‚ةڈo‚½پu’¬ژڈ‚ف‚ب‚©‚فپv‚ب‚ج‚¾‚ھپA‚±‚ê‚ً“ا‚ٌ‚إ•ھ‚©‚ء‚½‚±‚ئ‚حپAژں‚ج‚و‚¤‚ب‚±‚ئ‚إ‚ ‚éپB
‚ـ‚¸پAچ،‰ٌ“¥چ¸‚µ‚½پu“´Œ³ƒgƒ“ƒlƒ‹پvپi‚±‚ج–¼ڈج‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚ح’¬ژڈ‚إٹm”F‚إ‚«‚¸پj‚ًٹـ‚ق“¹پi’nگ}’†‚ةگش‚ژ¦‚µ‚½ƒ‰ƒCƒ“پj‚ج—R—ˆ‚حپAڈ؛کa29”N‚ج‘OŒم‚ةگ{“cٹLƒ_ƒ€Œڑگف‚ج‚½‚ك“Œ‹“d—ح‚ھ•~گف‚µ‚½پA‹v•غپ`“’‚جڈ¬‰®ٹش‚جچHژ–—p“¹کH‚¾‚ء‚½پB
‚»‚µ‚ؤƒ_ƒ€‚جٹ®گ¬Œم‚ح‘¬‚â‚©‚ةگ…ڈم’¬“¹‚ة‚ب‚ء‚½‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚إ‚ ‚éپiکHگü–¼‚ح’¬“¹پu“’ƒmڈ¬‰®–{گüپvپjپB
‚ب‚é‚ظ‚اپB
‚±‚ê‚إپu“´Œ³ƒgƒ“ƒlƒ‹پv‚ھ‹ة’[‚ةڈü‚è‹C‚ج‚ب‚¢ژp‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚½——R‚ھŒ©‚¦‚½‹C‚ھ‚·‚éپB
“–ژ‚ج“Œ“d‚ئ‚¢‚¤‚©“ْ–{‚ج“d—حژù—v‚حپA”ِگ£‚ًƒ_ƒ€‚ة’¾‚ك‚邱‚ئ‚ًگ^Œ•‚ةŒں“¢‚·‚é‚ظ‚ا•N”—‚µ‚ؤ‚¢‚½‚ج‚إپA‚ئ‚ة‚©‚چHژ–‚ً‹}‚¢‚¾‚ح‚¸‚¾پB
ƒgƒ“ƒlƒ‹‚جچى‚è‚à•K—vچإڈ¬Œہ‚ة‚ب‚ء‚½‚ئ‚µ‚ؤ‚à•sژv‹c‚ح‚ب‚¢پB
‚»‚µ‚ؤ’¬ژڈ‚ھ”چs‚³‚ꂽ“–ژ‚جŒ§“¹‚حپAŒ»چف‚جژه—v’n•û“¹پuگ…ڈم•ذ•iگüپv‚إ‚ح‚ب‚©‚پAˆê”تŒ§“¹پu‘هŒٹ“’ƒmڈ¬‰®گüپv‚ئ‚¢‚ء‚ؤپAƒ‹پ[ƒg‚à‘ه‚«‚ˆظ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚½پB
’¬ژڈ‚جگ}‚ة‚و‚é‚ئپA‰Eگ}‚ةگآ‚إژ¦‚µ‚½‚و‚¤‚ب‚à‚ج‚¾‚ء‚½‚ئ‚¢‚¤پB
‚±‚ê‚حٹ®‘S‚ة—\‘zٹO‚¾‚ء‚½پB
‚©‚آ‚ؤ‚جŒ§“¹‚حپAŒ»چفپuگ…ڈمچ‚Œ´ƒXƒLپ[ڈêپv‚ھ‚ ‚éپuڈم‚جŒ´پv‚ئ‚¢‚¤’n‹و‚ً’ت‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ھپAچ،‚ج’nگ}‚ة‚ح”jگü‚ج“¹‚³‚¦•`‚©‚ê‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚µپA“–ژ‚ج’nŒ`گ}‚إ‚³‚¦‚ح‚ء‚«‚肵‚½گü‚إ‚ح‚ب‚¢پB
“’‚جڈ¬‰®‘¤‚ج“üŒû‚ً‘{چُ‚µ‚½‚ھپA“¹‚炵‚¢‚à‚ج‚حŒ©‚ ‚½‚ç‚ب‚©‚ء‚½‚ج‚إپAڈƒگˆ‚بژR“¹‚¾‚ء‚½‚و‚¤‚إ‚ ‚éپB
‚µ‚©‚µنD‚ة—ژ‚؟‚ب‚¢‚ج‚حپA‚±‚جŒ§“¹‚جکHگü”F’è‚ھڈ؛کa34”N‚¾‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚¾پB
ڈ؛کa29”Nچ ‚ةژش‚ج’ت‚éچHژ–—p“¹کH‚ھڈo—ˆپAڈ؛کa30”Nپiƒ_ƒ€ٹ®گ¬”Nپj‚ة‚ح’¬“¹‚ئ‚µ‚ؤٹJ•ْ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚½‚ة‚à‚©‚©‚ي‚炸پA‚»‚جŒم‚إژش‚ھ’ت‚ê‚ب‚¢ژR“¹‚ًŒ§“¹‚ة”F’肵‚½‚±‚ئ‚ة‚ب‚éپB
•s‰آژv‹c‚¾‚ھپA—کچھگى‰ˆ‚¢‚إ‚ح‚ب‚¢‚à‚¤ˆê–{‚جژش“¹‚ھ—~‚µ‚¢‚ئژv‚¤’¬–¯‚ج‹Cژ‚؟‚ھپA‚±‚¤‚¢‚¤کHگü”F’è‚ًگ¶‚ٌ‚¾‚ج‚¾‚낤‚©پB
‚ب‚¨پA’¬ژڈ‚و‚è‚àŒم‚جڈ؛کa43”N‚ة”چs‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپu“¹کHƒgƒ“ƒlƒ‹‘هٹسپv‚جٹھ––‚ة‚ ‚éƒgƒ“ƒlƒ‹ƒٹƒXƒg‚ة‚حپAپuŒ§“¹‘هŒٹ“’ƒmڈ¬‰®گüپv‚جƒgƒ“ƒlƒ‹‚ھ2–{‹Lچع‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ھپA‚»‚±‚ة‚à“´Œ³ƒgƒ“ƒlƒ‹‚ح‚ب‚¢پB
‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚¾‚©‚çپAپu“´Œ³è©“¹‚ھ‹ŒŒ§“¹‚¾پv‚ئ‚¢‚¤ژ‘—؟“I‚بچھ‹’‚ح–³‚‚ب‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½‚±‚ئ‚ة‚ب‚éپB

“’ƒmڈ¬‰®‘¤‚جپg‹ŒŒ§“¹پh‚ج“üŒû’n“_
پi“’‚جڈ¬‰®ˆê–{ڈ¼ƒoƒX’â‘OپjپBژتگ^’†‰›‚ة‹ŒŒ§“¹‚ح
‘±‚¢‚ؤ‚¢‚½‚ئ‚³‚ê‚é‚ھپA“¹‚炵‚«‚à‚ج‚حŒ©‚¦‚ب‚¢پB
‚إ‚àپA‚ب‚ٌ‚©“y”X‚ھگد‚ٌ‚إ‚ ‚é‚ج‚ھ‹C‚ة‚ب‚éپcپB
‚µ‚©‚µپA‚¾‚©‚ç‚ئ‚¢‚ء‚ؤ“´Œ³è©“¹‚ھ‹ŒŒ§“¹‚إ‚ح‚ب‚¢‚ئ’f’è‚·‚邱‚ئ‚àڈo—ˆ‚ب‚¢پB
’¬ژڈ‚â‘هٹس‚جژ‘م‚ئŒ»چف‚جٹش‚ج40”N—]‚è‚ج‹َ”’‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپAچ،‰ٌ–„‚ك‚«‚ê‚ب‚©‚ء‚½‚©‚炾پB
Œ§“¹‘هŒٹ“’ƒmڈ¬‰®گü‚ھ‚â‚ھ‚ؤŒ»چف‚جŒ§“¹گ…ڈم•ذ•iگü‚ة‚ب‚é‚ھپA‚»‚ج‰غ’ِ‚ج‚ا‚±‚©‚إژش‚ج’ت‚ê‚ب‚¢پuڈم‚جŒ´پvƒ‹پ[ƒg‚ًژ~‚كپA’¬“¹‚¾‚ء‚½‘هˆ°Œo—R‚جƒ‹پ[ƒg‚ة•د‚ي‚ء‚½‚ح‚¸‚إ‚ ‚éپB
“´Œ³è©“¹‚جŒ§“¹ڈ¸ٹi‚ھگو‚¾‚ء‚½‚ج‚©پA‚»‚ê‚ئ‚à•t‚¯‘ض‚¦‚ج“»‰z‚¦ƒ‹پ[ƒg‚جٹJ’ت‚ھگو‚¾‚ء‚½‚ج‚©پB
‚±‚ê‚ً‰ً‚‚ة‚حپAڈ؛کa40”N‘مˆبچ~‚ج’nŒ`گ}‚ًهl’ׂµ‚ةٹm”F‚·‚é‚©پA’¼گعŒ»’n‚إ•·‚«ژو‚è‚ً‚·‚é•K—v‚ھ‚ ‚邾‚낤پB
ڈ¬‚³‚ب“ن‚ئپA’·‘ه‚بپgŒ¶‚جŒ§“¹پh‚ھژc‚ء‚½پB



















