今回だけは、“道”というテーマを完全に離れた、いわば番外編である。
丁場とも呼ばれる石切場の風景を、とくとご覧いただきたい。
この独特かつ壮大な丁場景色を前にすると、首の筋肉の消耗と引き替えに、先人たちの偉大な力を知ることが出来る。
前回までで説明的な台詞はほとんど吐き終えた。
語る言葉は、もうあまりない。
手抜きじゃないぞ。
今回だけは、“道”というテーマを完全に離れた、いわば番外編である。
丁場とも呼ばれる石切場の風景を、とくとご覧いただきたい。
この独特かつ壮大な丁場景色を前にすると、首の筋肉の消耗と引き替えに、先人たちの偉大な力を知ることが出来る。
前回までで説明的な台詞はほとんど吐き終えた。
語る言葉は、もうあまりない。
手抜きじゃないぞ。

2011/2/8 7:57 《現在地》
オーバーハングした人工的な絶壁の下には既に森が生長しており、放置された未回収の石材を覆い隠しつつあった。
そしてその中には、鉄の骨組みにトタン屋根を乗せただけのごく簡単な小屋が一棟あった。
壁はもともとなかったようだが、壁代わりにツタが育っていた。
のれんのようなツタを分けて、恐る恐る中を覗いてみる。

ここは作業員の日よけを兼ねた休憩所だったのだろう。
「国土総合開発KK」というネームが入った安全帽がひとつ、落ちていた。
それだけである。

そしてこの小屋の傍らには、写真にある微妙な高さの段差があり、それだけならば特に気にすることもなかっただろうが、ちょうどこの段差の先に“小さな石祠”が建っているのを見つけてしまったのである。
そこはこの段差の分だけ周囲よりも高い一角になっており、作業場の全体を見下ろしているといえばそう言えるが、全周にこの高さの壁があり、かつ上り下りするための施設がないために、直接お参りすることが出来ない状態になっているのである。

左の写真の段差を、木の根を頼りによじ登り、石祠へ接近した。
写真を撮る前に、まずは礼拝。
あたりは平坦ではないが、整形された数片の石材で不陸を正された上に、高さ60cmほどの祠が安置されていた。
ここで私が期待していたのは、祠に年号のようなものが刻まれている事だったが、それは見あたらなかった。
しかし、さすがは石の専門家達の仕事場に安置されていたものである。
単純な造形ではありつつも、下石に参道のような階段を一刀彫り要領で彫り付けていた。
肝心のご本尊は不在であったが、石切の守護神とはどのような神だったのか。
しかし祠の存在は、この神業的造形を見せる採石場の造成に関わった人々もまた我々と同じ日本人であったという、そんな当たり前の事を感じさせた。

そしてこの祠の背後にも、ここに立って初めてその存在に気付くことが出来る、
“コ”の字状に切り込まれた“採石壁”が、待ち受けていた。
まるで巨大な城塞に、一人立ち向かうかのような気分である。
だが、手前の斜面に育った照葉樹の緑が、城塞が廃墟であるという事実を教えていた。

白亜の宮殿。
おそらく日本に現物は存在しない、
物語の中のそんな風景がイメージされる。
周囲の高すぎる壁が風雨や日光をある程度遮っているおかげか、
最上質の房総石「桜石」だけが見せる、
ほのかな赤みを放つ神秘の岩盤が、
いま、私だけの前に、
“秘密の空間”を現した。
地上とは思えぬ静寂のなかで、
しばし言葉を失う。

人の貪欲が生んだ、逆さ階段。
てっぺんは、鋸山の主稜線から遠くない筈である。
垂直に切り出された壁は、その尾根の直下まで迫っていた。
しかもあろう事か、岩壁は高さ10mおきくらいに、約3mの巨大なオーバーハングを交えており、
その全体形として、重力の法則さえ無視した、逆階段状の壁を形成している。
どんなプロのクライマーでも道具を使わずにこの壁を登頂することは出来まい。
人の欲が、自然の法則をねじ曲げているかのようである。
終始圧倒されながら、石祠をその中心部に擁する石切場を後にした。
|
スポンサーリンク |
ちょっとだけ!ヨッキれんの宣伝。
|
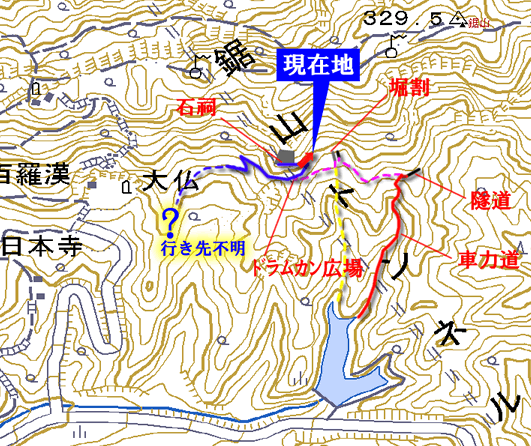
8:14
地名が分からないので、便宜的にこれまで探索していた採石場を“石祠丁場”と呼ぼう。
石祠丁場の探索が終わり、次に私は赤矢印のように、東へ等高線に沿うように移動してみた。
特に明確な道があったわけではないが、起伏は緩やかで、かつ照葉樹の森は下草も少なく、移動するのは難しくなかった。
おそらくこの方向に進めば、30分ほど前に私の前に立ちはだかった、【崩れた隧道と崩れた堀割】の“向こう側”へ行くことが出来るだろうという読みだった。
地形図はなぜか、この採石場跡の地形をほとんど無視して描いており、堀割の裏側にあるに違いない窪地も全く描かれていなかった。
だが、そこにはこれまで以上に唖然とするような、凄まじい景色が潜んでいた。
率直にいって、
私は絶対にあなたを驚かせる自信がある。

上図の「現在地」の地点に着くと、そこには窪地が待ち受けているどころか、天然と思われる岩場が立ちはだかった。
遠目には、まさしく行き止まりの地形そのものであった。
しかし、ここまでの探索で、鋸山の地形は一筋縄ではいかないもの、どこに人為が潜んでいても不思議ではない。
その事を理解していた私は、行き止まりに見えた岩盤の根元に近付いてみた。
そして撮影したのが、左の写真である。
やはり写真では分かりにくいが、黄線で示した部分には、遠目には絶対に気付かぬ、隙間が存在していた。
そして、この地割れの如き隙間こそ、別天地の入口だった。

ええと、これは…。
地割れの奥は斜めに下りながら、10mほど先で“別の地上”に繋がっている……?
ず、隧道なのか?
自然の地形としては、流石に不自然であろう。
この洞内を埋めている土砂は明らかにズリであり、人為的に埋めた雰囲気だ。
さらによく見ると、いままで私がいた洞穴の入口側の地平も、全体的にズリ山の跡地が森林化したような感じである。
採石場内の2つのエリア(丁場)を隔てる天然の岩盤に穿たれた連絡用の通路(坑道)が、手前側エリアの事業終了&埋め戻しにより放棄されたような状況も想起される。

私は迷うことなく、見つけたばかりの“洞穴”へ潜り込んだ。
洞内は全体に天井が低く、入口側だけでなく、出口側もそれは同じだった。
また、地面も瓦礫の斜面でしかなく、歩く度にガラガラと乾いた音を立てて崩れた。
内壁にも人為的な整形の痕跡は全くなく、突き崩されたままの岩盤であった。
これでは、本当に人工物であるのか、判断が難しい。
隧道と呼ぶには余りにも異形であり、仮にそうであったとしても、相当に限定的な存在(坑道と呼ぶ方が相応しい)だったと思える。
しかしともかく、この“通路”のおかげで、周囲から隔絶されていた“窪地”へ侵入する事が出来たのである。
これに気付かなければ、この次からの風景を目にすることは、決してなかっただろう。

8:15 《現在地》
地形図に描かれていない窪地の大きさは、想像を超えたものだった。
そして窪地の主稜線側には、その広がりを担保するだけの、尋常ではない落差を持った大断崖が存在していた。
先ほどの丁場の崖も高いと思ったが、今度が桁違いに高い。

ここがあの慣れ親しんだ、千葉の大地の範疇なのか。
時として人は、自然をも凌駕する巨大地形を生み出すものらしい。
正面の右下がりの尾根が、元来の山腹の位置である。
そこからこの地平まで、切り下げられたものと考えられる。
100年どころではないに違いない。
鋸山で石が切り出された江戸時代から昭和時代まで、通して採石が続けられてきたのでは無かろうか。
この美しく青みを帯びた巌壁にはきっと、全ての石切人を虜にする、究極の価値が内包されているのだろう。

岩盤に刻まれた、石切場の年輪代わりとも言える水平の線は、
数え切れない。
おそらく、200年分はあろうかと思われる。
しかし、さきほどの石祠丁場よりも、こちらが先に廃止されたような感じを受ける。
なぜなら、この窪地の自然回帰度は、石祠丁場の周辺よりも遙かに進んでいる。
ここで最も成長している木は、高さ20mを越えるような大木になっている。
もっとも、ここでは他の場所よりも背を伸ばさなければ満足に日光を得られないので、
総じて木が高木化している印象は受けるが。

主稜線側の崖は総じて凄まじく高いが、中でも最も高いと思われる一角が、中央北側にあるこの壁面。
100m以上あるかも知れない。
岩盤の表面には、雨水の流れた痕が、枯れ滝のような紋様を見せていた。
これは周囲を彩る様々な木々とともに、無機質の中の有機質的要素である。
すなわち、廃墟の風景の最も端的な美点を形成していた。
この場所の存在は、おそらくさほど多くの人には知られていないだろう。
地面には踏み跡はおろか、ゴミも全く見あたらなかった。
私は、覆い被さってくるような巨大質量に首元を絞められるような思いがして、何度も何度も遠い空を見上げた。
主稜線側の写真しか撮影しなかったが、反対側も高い崖になっていて、ここからの脱出経路は極めて少ない。

オーバーハングはせず、ただ垂直に切り取られた壁面。
特徴的な水平縞模様の他に、より大きくゆるやかな凹凸が存在しており、特に上部ほどそうである。
上部に行くほど古い時代の採石地なので、技術的な違い(手堀→機械堀)や、風雨による浸食がその原因であろう。
手の届く範囲の岩盤には、手堀の特徴である斜め方向の鑿痕が見あたらないので、明らかにチェーンソーを用いた機械堀である。
撮影された写真を改めて確認すると、唖然丁場の岩盤は下層においてもすべて鑿痕が残っていることが判明。
したがって、唖然丁場では機械堀が行われていない可能性もある。この判断は素人には難しいので保留したい。

主稜線に正対して撮影。
最も左側の岩壁(すなわち北西端)の下部に、私がここへ入ってきた地下通路が口を空けていた。
壁面の上部は、遠目にも風化が進んでいて、次第に自然の崖と区別か付かなくなってきているように見える。
それにしても、こんな超絶風景が…

↑この平凡な遠景に内蔵されているとは…。
鋸山はマジで懐深いなぁ。

窪地の北東側の隅には、なにやら周囲よりも薄暗く、そこだけ夜のような一角が…。
足場が悪いのに注意しながら、恐る恐る近付いてみると……。

超が付く完璧な行き止まり!
こんなところに追い詰められたら、どんな正義のヒーローだって、観念するよ。
ご都合主義全開の仲間たちだって、ゼッタイ助けられないはず。
↑首痛くならないでね。

地上とは思えぬほど、薄暗い地面。
流石に草一本生えていない。
空気も、澱みきっている。

そして、堅牢であると思われた大岩盤だが、
余りに深く掘り込まれた反動か、この“行き止まり”の周囲の崖には、
見るも怖ろしい亀裂が、大量に発生していた!
こんな所で地震をくらったら、流石に生きた心地はしない。
この岩盤が大々的に崩れ落ちたら、それが新たな震源になりやしないかと、心配されるレベルである。

窪地の地面は平坦ではないが、概ね100m四方の広がりがあり、
写真はその南東端に近いあたりから、主稜線の大岩盤を振り返って撮影した。
ここまで離れると、岩場の風景はまさしく“日本のギアナ高地”という感じで、
そこにわずかな人為を見出すことも難しくなる。
この空間に入り込んだ誰もが口をあんぐり開けて、狭い空を見上げることだろう。
だからこの丁場は、“唖然丁場”と勝手に命名。
鋸山の丁場、恐るべしだ…。
| 当サイトは、皆様からの情報提供、資料提供をお待ちしております。 →情報・資料提供窓口 | |
|
このレポートの最終回ないし最新の回の「この位置」に、レポートへのご感想など自由にコメントを入力していただける欄と、いただいたコメントの紹介ページを用意しております。あなたの評価、感想、体験談など、ぜひお寄せください。 【トップページに戻る】 |
|