�@�C�[�W�[���[�h�ł��N���A�ł��Ȃ����͗ǂ�

2023/10/27 10�F10�@
�����Ȍ͂�F�ƂȂ��������A�R�̎Ζʂ��߂ɉ���Ȃ���o���Ă����B
���ɒJ�̋C�z�͉����Ȃ�A�߂��Ɋ�������B
�ƂĂ��u���ŋC�������ǂ��B
�u���l�̂��߂��ƌ��ɐ��܂������̓��H�v�i�R�Ɵ�J�Ёw�k�̕����������x�j�Ƃ������t�ɂ͌����m��ʔ��͂����������A��藧�Ă�����̂��������B
���̌��ꂪ�����ƂȂ�A���ɔp������ʂĂ��Ƃ́A�ǂ�قǟT�X�Ƃ����A�����͌������������铹�ł��낤���Ɛg�\���Ă����B
�����A���R�ɂ������J���Ă����g�̊č��h�̊Â��ɂ��������A���͗\����傫�������ƂĂ��u���ȋC���ŕ����Ă���B
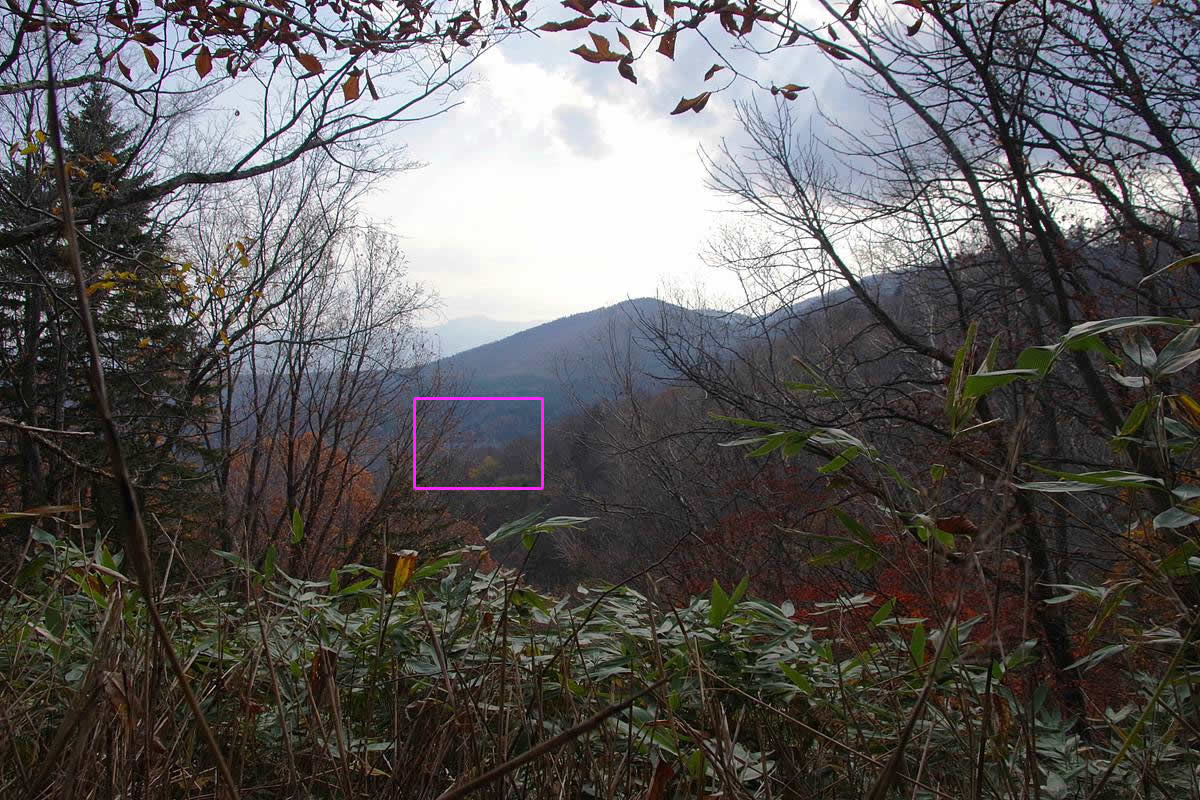
���x���オ�������ƂƁA�J�̏o���߂��֖߂��Ă������ƂŁA�����̎��E���J���Ă����B
���܌����Ă���̂́A�ڎw�����Ƃ͔��̗N�ʐ쉺�������A�k�����ʂ̕��i���B
���n�ł���A�X�Ƃ����X�M�̐A�ђn�ł�������A���H�̃��C���A�S���A�d�g���ȂǁA���낢��Ȑl�H�������������ȂȂ��炩�ȎR�X�����A������l�H���́A�R�������鑖�鈮���ʎ����ԓ������������B�������p��������̉�����h�b�̈ē��W���������Ă����B
���̓��̌��݂ɏ]���������l�����̌������i���A�卷�͂Ȃ��������낤�B
�������A�ޓ������Ă���Ă���ԑ��W���Ă��炱�̏ꏊ�́A150km�ȏ������Ă���B
�����Ă��̊u��͑S�āA�ޓ����g����J�����������H�̓��̂�ł������B
���g�Ƃ��̓��E�̌��Ɗ��ŊJ��������H���āA�V���Ȍ���֓���A�����ɓ���B
���̉c�X�Ƃ����J��Ԃ��ɂ���āA�ԑ����炱�̓��̘[�֎��铹���A�����铹���A�͂�1���N�̂����ɑ���ꂽ�B

10�F14
�J�ꂩ�炸���Ə���y�����Ă����z �̂́A���̕ӂ肾�낤�B
�̂́A���̕ӂ肾�낤�B
�������߂Â��A���E�̒����玩����荂�x�̂���y�n�������Ă����B
�Ƃ͂����A���̗D�z���͂��肻�߂ŁA�܂��z����ׂ����̕��������Ă��Ȃ������߂ł���B
�Ԃ��Ȃ����̔�������荞�ޏ�ʂ����āA�V���ȃX�e�[�W�ւƎ����ł��낤�B

10�F15�@�s���ݒn�t�@�C��670m
�Ō�̐�Ԃ�����A��Ⓑ�X�Ƃ�����400m�̃g���o�[�X��E���A��t���Ă��������̐�[����荞�ޏ�ʂƂȂ����B
���������1.7km�A�C��670m�̒n�_�ł���B
����Ŋ��S�ɃX�v���R�����x�c��𗣂�A���͎��Ȃ铻���̎g�ҁA�E�m���ɖʂ���Ζʂɓ����Ă����B
���܂ŁA�c���Ƃ��됄��3.0km�B
���x���́A�����悻200m�ł���B
�����ɂ��Ă͂܂��c��3����2�����A���x�͎c�蔼���قǁB
���������āA�c��͔�r�I�Ɋɂ₩�Ȍ��z�ŒW�X�ƎR�������f���铹�H�ł���A�S�[���̓��܂ŋ�\��܂�Ȃǎ咣�̂�����`�͈�Ȃ��A�n�}��ɂ����Ă͂قƂ�Ǔ��������̂��̂��B�ꕾ�����ꂸ�����A�P�������ȓ��ł���B����̑����ȂǁA����n�`�Ƃ������Ƃ���藧�ĂĂ͂Ȃ������B

�����̐�[������Ă��������J�[�u���A�͂�������o�����F�̖�Ɖ����Ă����B
�T���ɂ������x�Ƃ��ẮA����͖{���Ɍb�܂ꂽ�u�C�[�W�[���[�h�v���������Ă��Ǝv���B
�������A���\�N�Ɉ�x�Ƃ����p�x�ł��������ʋM�d�ȃC�[�W�[���[�h���B
���������܂ł̌͂���̏�ʁA���߂����悻1km���A�S�ăo���o���̐��ł������Ƃ���ƁA�̗͓I�ɂ����ԓI�ɂ��A�S���̓_������A����ɂ͌��ʂ��s�ǂɂ��F�Ƃ̕s�������̊댯���Ƃ����_������A�S�Ăɂ����Ă����Ƒ�ςł������͂��B
������������A���̑傫�ȗD�������邨�����ŁA���͐�s�T���҂����j�Ɏ��s�����Ƃ����k�����̋������ӊO�ɗe�Ղ����j�o���Ă��܂���������Ȃ��B
����͂���łǂ��Ȃ낤�Ƃ����C�������[���ł͂Ȃ��������A�Ƃ͂����M�͍D���ł͂Ȃ����A�����܂ŗ��ē��j�o�����Ɉ����Ԃ��̂����ɃL�c�C�W�J�Ȃ̂͊ԈႢ�Ȃ�����A�C�[�W�[���[�h���������̂͏��w���܂ł��Ƃ��Ă��A���������ꂽ���Ƃ����̂��C�����̑啔���ł������B

10�F18
��������荞�r�[�A��C�ɓW�J���������āu�O�G�[�b�I�v�ƂȂ�̂���Ԃ����i�H�j�A���x����͂����������^���������Ƃ��Ȃ��A���ς�炸���͌͂�Ă������A���̌͂������Ȃ��{�����Y��Ɍ��^���~�߂����������Ď�������Ɋ�����B
�ԓ��Ƃ��Ă͑����ς�炸�\�����͋͏��ŁA�������̃C���[�W�̂܂ܒW�X�ƎR������Ă��邾��������A��\�����I�Ȗʔ��݂͖R�������A�Ƃɂ��������Ղ����A�i�F���ǂ����ŁA�{���ɉ������B
�`�F���W��̉摜�́A���̓�����ɂ����V���Ȓ��߂��B
�ቺ�ɍL���鋐��ȒJ���E�m���ŁA���Ɍ�����Ζk���������痬�ꗈ�Ă���B
�z����ׂ��������̐��ɂ��邪�A�n�`�ɉB���ꌩ���Ă͂��Ȃ��B
���ʒ����̂ǂ�����Ƃ����R���A���������ނ���R�ŁA�C��1445m�̃`�g�J�j�E�V�R�ł���B�Œ�̓o�R���͂Ȃ��A��ɃX�L�[�o�R�̑Ώۂł���炵���B

10�F30�@�s���ݒn�t�@�C��690m
��������荞��ł����10����A���������2km�n�_�B
�ˑR�Ƃ��ċɂ߂ď����B
�����M�����X�ɂ͂��邪�A�S�̓I�ɒ�w�ŁA���x���Ⴍ�A���͂�Ă�����̂��唼�������B
�H�ʂ͓y�����������Ă���A���ɂɂ����܂Ŏ��]�Ԃ��������߂Ă�����A���s���\�ł��������낤�B
�������A����10���Ԃ̑O�i�ŁA���͈ȉ��̓�̂��̂����Ă����B

���`�`��B
�r����������I
�ɓo�肽�������̂��ȁc�H
�܂��y�����������H
����Ȃɕ����Ղ����A�P���m���������ė��p���Ȃ��������Ȃ���ˁB

���`�`��A�傫�Ȃ����ՁB
�����傫�������̌ܖ{�w�́A�N������˂��c�c�B
�c�c
�c�c�c�c
����AI�Ɏ��₷��ƁA�K�����������B
�F�̑��Ղ�������A�߂��ɋ���؋�������A�����Ɉ����Ԃ��ƁB
����A�������B�F�ɑ���Ȃ����Ƃ��ړI�Ȃ�A���̒ʂ肾�낤�B
�������̖ړI�́A�u�F�ɑ���Ȃ��v�Ƃ����̌������邽�߂ɎR�ɓ����Ă���킯�ł͂Ȃ��B
�F������R�ɓ���Ȃ��ƒT���ɂȂ�Ȃ��B
�����Ă���͈�@�ł��Ȃ�ł��Ȃ��B���͒T�����������B
�l�Ԃ̑��݂�m�点��蕨�͑S�Ďg���Ă���B
��������ŐϋɓI�ɏP���Ă���̂�������A���Ƃ͂������ɕt�����X�v���[�œn�荇�������Ȃ��B�[�����Ă���Ă���B
���Ղ����낤���A�����������悤���A�ǂ����ĂĐi�ނ��B�i����͂܂��Ȃ����A���ɂ���܂ł������Ƃ�������Ă����j

10�F32
�ω����B
�ω�������B
�����ω��������A������܂��H
���̐�A���̎��͂ɂ�����́A�͂�Ă��Ȃ��悤���B
�K���A�H��ɂ͔ɖ��Ă��Ȃ����c�c�B

�`�g�J�j�E�V�R�̌��������A�܂������ς�����B
��O�̎R�Ƃ̎�荇�킹���ς�������������邪�A�R���̒��ɍۗ����̊�������苭���Ȃ����B
�������A���̖k�̑�n�ɂ����Ă͊��ɔӏH���I��肩�����Ƃ����̂ɁA���̎��肪�G�ߊ��̖R�������ɖ����Ă���̂́A��������ʂ̍��������炾�낤�B����䂦�A�ĎR�o�R�̋L�^���Ȃ��̂��Ƃ��v���B

10�F36�@�s���ݒn�t�@�C��730m
���c
���ɗ^����ꂽ�D���{�[�i�X�A���Ɏg�����������c�c�B
���������2.3km�̒n�_�������B

�����M�A���e�i�A�����Ɏ@����B
����̓��o�������c�B
�i�ŋ߃��|�[�g��������́A�����Y��邱�Ƃ��ł��Ȃ��s�n���v���o�����c�j

����I
�@�����͂�����O�l����(?)���M�ɁA�S������

2023/10/27 �@�s���ݒn�t�@�C��730m
�O��Ō�̏�ʂ���B
���Ɍ͂�Ă��Ȃ����M���s����������Ղ����B
���ʂ��Ȃ��̂ʼn��s���͕�����Ȃ����A�߂Â��ߒ��Ō������͈͂����ł�100m�ȏ�͂��肻���������B
�����炭�A���̑O�ɒT�������l�𑽂��ɋꂵ�߁A���j��f�O�������Ƃ�����k���������ő�̏�Q���A���ɂ�����n�߂����̂Ǝv���B
�M�ȂǁA���F�͐i�H��W�Q���i�s��x�������邾���̏�Q���ł����Ȃ����낤�B
���Ԃ�������ΒN�ɂł��z��������̂ł��邩��A���ꂪ���߂ɖ����j�Ƃ����̂́A�����^�����������Ă���̂ł͂Ȃ����B
����́A�Ⴊ���邩��G�x���X�g�͓o���ł��Ȃ��ƌ����Ă���悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��̂��B
������������A���̂悤�ɍl����l�͑��������m��Ȃ��B�M�����̌o�����Ȃ���A�Ȃ����炻�����낤�B
�������������A��{�I�ɂ͂��̂悤�ȍl�����ł���B
����܂ł��낢��Ȕp�����M�ɔs�k���ēP�ނ��Ă��鎄�����A�M�̂��߂Ɉ����Ԃ��̂́A���̌����̏ꍇ�����Y�܂����A�������A�D�ɗ����Ă��Ȃ����Ƃ������B���̑I���́A�{���Ɏ��g�̌��E�ł������̂��낤���Ɖ�ڂ��A������܂݂����ł���B
�������A�k�C���ɂ������M�́A���̒n����M�����i�i�Ɋ댯���傫���Ǝ��͍l���Ă���B
���̗��R�́A���ʂ��̗����Ȃ��M�̒��ŁA�q�O�}�Ƌߐڋ����ő������郊�X�N�ł���B
�������A�����M�̒���Â��ɕ������Ƃ͏o���Ȃ�����A����Ɉړ����Ă������́A����̕���������Ă����\���������Ǝv���Ă��邪�A����ł����͂����ʂ��Ȃ������ɁA�܂Ƃ��ɐg�������Ƃ�Ȃ��M�̒��Ŗҏb�ɏP����z��������͔̂��ɋ�ɂł��邵�A���ɂ����M�֓˓����悤�Ƃ��Ă��鎄�̑����ɑ傫�ȃq�O�}�̑��Ղ����������ƂŁA���h�����Ă���̂ł���B
10�F38�@�c�c�c�c�˓��B

��ʂ̑O�Ɏ����玟�ւƊ|�����Ă�����̑�t���A������g���ĕ��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�K�T�S�\�̖Z�����M���B
�M�̏�͔w��ꡂ��ɒ����Ă���A�����ɐL���Ă��O����͌����Ȃ��ł��낤�B
����ȏꏊ�Ŏl���̖ҏb���ːi���Ă�����A�m���ɃA�E�g���B�X�v���[�˂���ɂ��^���Ă͖Ⴆ�Ȃ����B
����ȋ��|�����邾���ɁA�o���鉹�͑S���o���Ȃ���A����ɂ��l���鎞�Ԃ�^����C���[�W�ŁA�}�����Q�Ă��i��ł����B
�K���ɂ��āi�H�j�A���M�Ƃ��ẮA����͂܂��܂����̌����B
���������邩��ꌩ�h��Ɍ����邪�A�n�\�߂��ɂ͖��ĂɃP���m���g�̂�ʂ��邾���̃X�y�[�X������A�l�Ԃ������g�ɂ͂��܂��R���������ɑO�i�ł���B�Z�����͎̂�ɏ㔼�g���B
�����A���̂��Ƃ��]�v�ɃP���m�Ƃ̔����킹�̋��|���������Ă��镔�����������B�N�������̃P���m����ʂ邾�낤����ȁB

10�F41
3���قǂŘH����M�͓ˑR�������A�܂������Ղ��y�����n�܂����B
��x�͊o������߂�����ł����������ɁA�����̔��q�����͂��������A�������������C�������傫�������B
�܂��A�y�吳13(1924)�N�n�`�}�z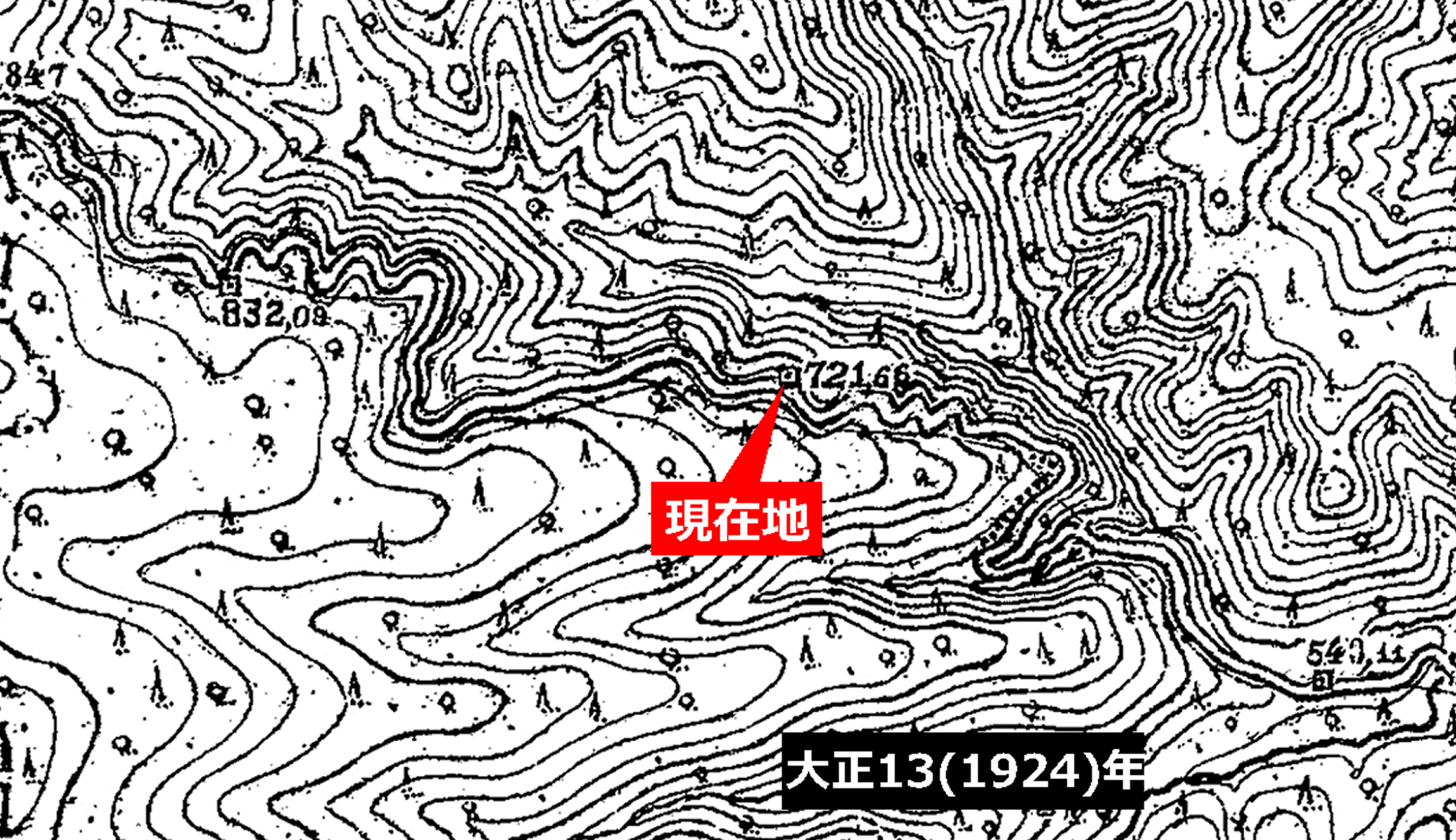 �ɂ́A���傤�ǂ��̕ӂ�ɐ����_�i�W��721.66m�j���`����Ă����B
�ɂ́A���傤�ǂ��̕ӂ�ɐ����_�i�W��721.66m�j���`����Ă����B
���������ɂ������_���`����Ă�������A���������2km�i��ł���킯���B
���̂��Ƃ��ӎ����ĕW���Ȃ����T���Ȃ�����������A��͂茩����Ȃ������B�H��͂Ƃ������H���͍����ɖ��Ă���ꏊ��������������A�P�Ɍ������Ă���\���͏\�����邪�B

10�F43
�����āA�܂������Ɏ��̍��M�͍~��Ă����B
�������c�c

10�F45
��قǂ����i�i�ɔZ���I�I
�O�Ƃ̑傫�ȈႢ�́A�����܂ł݂������M���l�܂��Ă��āA�P���m���ƂȂ肻���ȋ�Ԃ����݂��Ȃ����Ƃ��B
���̏�ʂŐ��ɁA�g���l���H�h�͊��S�Ɂg�~�`�h�Ƃ��Ă̋@�\��r�����A���͂̎R��ƕς��ʋ�ԂɂȂ������Ƃ��������B
�������A�Ȃ������R�ł���Ƃ����_�ɂ����āA�����̎R�����ꡂ��ɋ~��������̂ł��邪�c�c�B

10�F52
����̓L�c�C�I�I�I
����͑O�̎ʐ^�̃V�[������7�����̕��i�����A���̊Ԉ�x���M�������邱�Ƃ͂Ȃ��A����ǂ��납�A�ߋ��o���������ł��ŋ����x���̋������M�֕ω����Ă��܂����B
���I
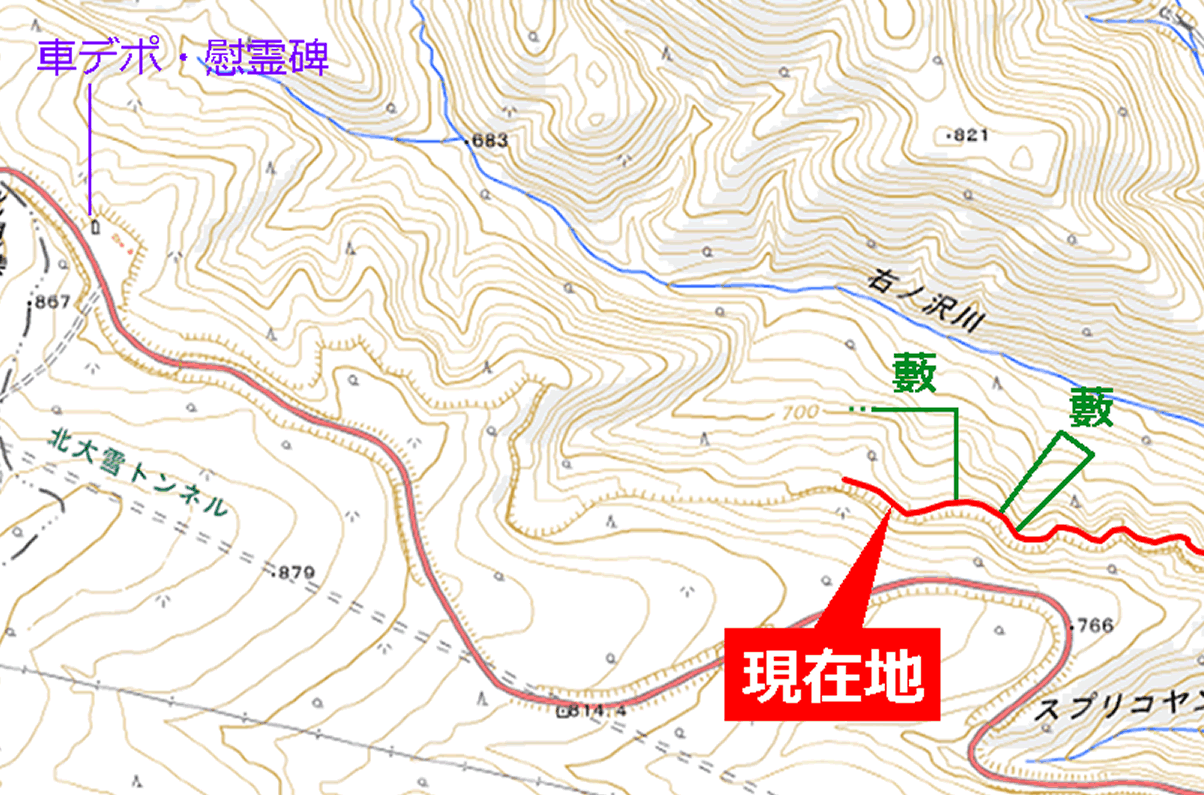
�����Љ����Ƃ���l�ނ́A���������ꏊ�ɓK�������i���͐����Ă��Ȃ��B
���R�̂��ƂȂ���A���̐i�s���鑬�x�͖��c�Ƃ��������l���Ȃ��قǒx���Ȃ����B
GPS�Ń��A���^�C���Ɍ��ݒn��m�邱�Ƃ��o����̂����A2�x�ڂ��M�ɓ˓������n�_������7�����₵�āA100m�����i�߂Ă��Ȃ��I
����14m�̐��E���B���܂�l�������Ȃ����A���܂Ŏc��2km���S�Ă����M���Ƃ�����A�x�e�Ȃ��ł����B��140����v����v�Z�ł���B
�c�c����A�܂��A�c��̋��������̂��炢������A���l���Ȃ�u�s����v�ƌ���ꂻ���Ȏ��Ԃł͂�����A�������A2���Ԉȏケ��𑱂���̂́c�c�B
�������ȒP�ɉI��ł���ꏊ�ł�������A���R�̒���ł������Ȃ�A���Ԃ�P�ނ�I���������낤�B
���������M��2km�ł͂Ȃ�5km�������댯������Ƃ�����A���Ȃ��ɓP�ނ����B
�ő�ł�2km���Ƃ������A�P�ނ��O�i�����f����ő�̍����ƂȂ��Ă����B
����͂����S�ɁA�y�����Ƃ��c�}���i�C�Ƃ��l����̂������e�A��������2���ԍ쓮�����M���J�}�V�[���̓���𑱂���Ƃ����o������߂�B�i�o�偁�S�͖��ł͂Ȃ��Ƃ����c�b�R�~�̓����e�B�ӎu���������M�ɓ����̂́A�P���m�ł����Ȃ��}�V�[����������c�j

10�F58
���˂��M�������邱�Ƃ��Ȃ�������Ă��邪�A���ꂩ�牽�����o���Ă��M�͑S�������Ȃ��B
�����A�����ɋ͂��ɏ㔼�g���o����ꏊ������������A���p��������悤�ɋx�~�����Ă���Ƃ��낾�B
�l�������̑S�Ă�����3m�̍��M�Ō��ʂ��Ȃ�����A�����ȊO�̒N���̗��Ă鉹�ɕq���ɂȂ��Ă���B���̂Ƃ���͑��̃P���m���߂��ɂ���C�z�͂Ȃ����B
�Ƃ������A����͑S���w�p�I�ɍ����̂���b�ł͂Ȃ����̏���Ȋ�]���݂̗\�z�Ȃ̂����A���̂��炢�̌��M�̒��́A�q�O�}�����̃V�F���^�[�Ƃ��ċ@�\����̂ł͂Ȃ����B
�ޓ��͂�����͂������ƌ����Ă��l�Ԉȏ�ɑ������A�n�\�߂��ɂ��ꂾ�������b���������Ă���A�^�P�m�R�̐����鎞���ł��Ȃ�����A�����Ē��ɓ��낤�Ƃ͍l���Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B
���ꂪ���̒���A�ɒ[�ɖ����������M�̒��͌F�����ɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ƃ����������B
�F���܂͂ǂ��v���܂��H

11�F00
�������I�@�v�X�Ɍ���A���{�d�M�d�b���Ђ̕W���B
�O�����͓̂��ؐՂ��߂��������9�F31�̒n�_�ł��������A�������̂��܂��������B
�������������\�����e�͕ς���Ă���A�O��́uN22�v�ł��������ʂ̕\�����uN20 A1�v��2�s�ɑ����Ă����B�Ӗ�����Ƃ���͈ˑR�Ƃ��ĕ�����Ȃ��B

11�F11�@�s���ݒn�t�@�C��750m
�}�W�ŃL�c�C�ł��B
�ŋ����x���ɔZ�����M���A���x�����x���g��U���̂悤�ɉ����Ă���B
�g�Ɣg�̊Ԃ����M�Ȃ͕̂ς�炸�ŁA�������ꂱ��30���߂��͘H�ʂ����Ă��Ȃ��B
�n�`�}�����Ă��A���̍Ō�܂ŕς��Ȃ��W�X�Ƃ����g���o�[�X�ł���B
�n�`�ɉ����ē��ɃJ�[�u�͂��邪�A����������ς�炸�̍��M�ŁA������i�F�ɂ��ω����S���������Ȃ��B
GPS�Ō��ݒn��m�邱�Ƃ��o���Ă��邩��A�ω����Ȃ����ł��ꉞ�O�i���Ă��邱�Ƃ������邪�A���ꂪ�Ȃ���Ας����Ȃ����낤�B

11�F12
�������炵�炭�A����YABU�}�V�[���ɐ�O���邽�߂ɁA���̂��l���邱�Ƃ���߂�̂ŁA���|�[�g�̖{���ł́A�䂪���̓y�؎j��ł��H�L�ȗ�ł���g���l���H�h�̍H���Ɋւ��A�����炭�����̓ǎ҂��^��⋻����������ł��낤�����ɂ��āA���̒m�镶�������菊�Ɍ���Ă݂����Ǝv���B
�T���ɂ��Ă͂��炭�A�����Ɖ摜������\������̂łˁc�c�B
���g���l���H�h�̂������C�ɂȂ�i1�j�@�H�����ɓ��S�������l�͂��Ȃ��̂��H��
�L��ȉ��O�A��������A�������R��ł̓y�؍�ƒ��A���S�i�E���j���l������l�����Ă��s�v�c�ł͂Ȃ��Ǝv�����A�ǂ��������낤���B
�ȉ��ɏЉ��̂́A���̍H���ɊŎ畔���Ƃ��Čg������ۓc�r�v���̉�z�w�ԑ��č����v�j�x����̈��p���B
��������҂���������܂����B�������A�R�̒��ɓ��荞��ł����p�������ĐH�����Ȃ��Ƃ�������܂悤����ł�����A���Ǒ啔���͕����߂��Ă��ĕ߂܂�܂����B��g���疈����l���炢�͓����҂��o�܂����B
��͂�A��������Ă���l�͏��Ȃ��Ȃ������������B
�������A�啔���͌��ꂩ��傫������邱�Ƃ��o���Ȃ������Ƃ����B�������̒n���͐��\�������ɑ��̓����S���Ȃ��悤�ȏŁA�y�n�ӂ��Ȃ��l�Ԃ�������O��Ăǂ������̐l���܂œ������邱�Ƃ́A�܂���������̂ł��낤�B���S����Ă邱�Ƃ͗e�Ղ��Ƃ��A���������邽�߂ɂ̗͑͂��C�͂��K�^�i���^�H�j���K�v�������B
�������R�A�č������݂��݂����̂悤�ȃ`�����X��^����Ӑ}�͂Ȃ��c�c�B
������Ƃ��ړ����Ă䂭�k�ӂ́g�����č��h�O���̋K���͌������Ċɂނ��Ƃ��Ȃ������B�������Ȃ��ߒɂȎ��k�̐S����[���Ɏ@������B��������]�����̋ɂɒǂ����܂ꂽ����������x�������ׂ����ꍇ�́A�P�ǂȎ��ӏZ���͂ǂ��Ȃ邱�Ƃ��B�i�����j�@�����͏��m�A�����܂ł��ˊэH���̔����ŏI�n�����̂ł���B
���̂悤�ɁA�ˊэH���̘A���ɂ���ċɌ��܂Ŏ��l���J�����邱�Ƃœ��S�̗͂�D�����Ƃ���}���ꂽ�B�P���ɍH�������邱�Ƃ������ߍ��ȍH���̖ړI�ł͂Ȃ������B
����ɂ́A���S�������邽�߂̕����I����s���Ă����B
����́A�������H�̌��݂�̃��`�[�t�ɂ��Ă��鍂�q���剉�̐l�C�f��w�ԑ��ԊO�n�x�i��1��j�ɂ��`����Ă���̂ŁA�����m�̕���������Ǝv�����c�c�B

11�F20
�����̊č����́A�u�Ⴕ�A��ނ������O���ɕ������ނ�Ƃ��͓S����p���Ď��l��l��A�����c�c�v�Ƃ���A2�l�̎��l�����̂��̂̍��Ɋ��������𑫎�܂Ő��炵�A�����A���������̂ŘA���ƌĂ����̂ł������B
����Ɂc�c
�Ŏ�͏e���Łi���������j���l�̑����Ƃ߁A�A���łȂ��ꂽ2�l��ǂ��ߒ�R�҂��a�E����B������u���ߎa�E�v�Ƃ����A�Ŏ�̌����Ƃ���Ă����B���ߎa�E���ꂽ�҂͑��ɍ��������܂ܖ������ꂽ���A����͊����ɒ�R���A�Љ�ɖ��f�����������Ƃɑ����ʂւ̌������߂̂��߂ł������A�Ƃ���Ă���B
���̂悤�Ȏ���������āA��N�ɍ����t�����܂܂̎��l�̖S�[���H�T�ɔ��@����邱�Ƃ����������A�����łȂ��Ă�����g�ɂ����܂܉ߍ��ȘJ�����s�������Ɏ��S�������l���������߂ɁA�������H�̉����ɂ́u���ˁv�ƌĂ�閄���n�������������B
���̂悤�ȑ����������ŁA���������ǂꂭ�炢�̎��l�������ē��S�ɐ��������̂ł��낤���B
�����̊č����̋L�^�Ƃ��āA�H���ɏ]���������l�̑�����A�H�����̑���ҁA�����͋��ߎa�E�ɏ����ꂽ�l���Ȃǂ�m���|��͂��邪�A�O�𒆂̍s���s���҂Ƃ��Čv�コ�ꂽ�҂͂��Ȃ��B
���ꂪ��l�Ƃ��ē����ɐ������Ȃ��������Ƃ��Ӗ����Ă���̂��A�č����ň�̂��m�F���Ȃ��܂��S�ƌv�サ���̂��͒肩�łȂ����A�����炭���l�̈ꕔ�͊m���Ɍ��ꂩ�瓦���ʂ��A���̂܂܊����̒ǐՂ����ꂽ���A�������R��̂ǂ����Ől�m�ꂸ�ɑ���������̂ł��낤�B����قǂ܂łɓ����̖k���E�ԑ��n���́A�l���̂܂�ȃ��C���h�G���A�ł������B

11�F29
���g���l���H�h�̂������C�ɂȂ�i2�j�@�Ȃ������������̎��l���S���Ȃ����̂��H��
�������H�̌��݂Ɍg��������l�̎��Ґ��Ƃ������̂ɂ́A�������̎���������B
����͒������H�̍H�����A����22�N����24�N�ɂ����ď����A��m�W���āA���H�W���āA�ԑ��W���ĂƂ��������̊č�����̊O���ɂ���ċ�Ԃ��Ƃɍs���A�܂��������ɒ������H�ȊO�̒Y�z��ƂȂǂ̊O���Ɋւ�鎀�҂����������߂ɁA���S�n�⌴���ɕ��G�ȕ��������邽�߂��B
�����A���̂����ő�̍H���K�͂��ȂĖ���24�N��4������12���ɂ����čs��ꂽ�ԑ��W���Ă̊O���ɂ��ԑ��`�k�����`���z�̍H���i���ݒT���n���܂ށj�ɂ��ẮA211�l�����l�̎��Ґ��Ƃ��ē`�����Ă���B�܂����̍H�����ē����Ŏ��6�����S���Ȃ��Ă���B�i�w�ې��z���j�x�ق��j
���ł��Ƃ�킯�]���҂����������̂́A����24(1891)�N9������12���̊��Ԃɐi�߂�ꂽ�A�����`�k�����`���z�i���ݒT���n���܂ށj18���P���i70.8km�j�̍H���ł������B
���̍H���ɂ�1115�l���o���������A����186�l�����S���Ă��邩��A6�l��1�l�͐����ċA��Ȃ������B
�H������1�q����2.7�l�A���Ȃ킿380m��1�l�̊����ł���B
�����炭�䂪���̓��H�ł͍ő����[�X�g�̏}�E�Ґ��ł͂Ȃ����Ǝv���B�i���̕s���_�ȋL�^�����������铹�𑼂ɕ��������Ƃ��Ȃ����c�j
�ł́A�Ȃ�����قǑ����̎��҂��o���̂��B
���̗��R�͂͂����肵�Ă���B
���̔N�i����24�N�j10��21����m���q�t�̗����K���́A�a�Ăɓ��Ă��Ă������ː��̋�̏����Ɏ��������A���̒��w㱗����^�x�̂Ȃ��ŁA�u�������A����a�m�׃j��a�Z�����k�}�\���\�A���W�a�m�׃j�Y�����B���m���ރ������i���B�o�w�Y��Ѓm�M�������k�m�׃j�V���j���Q�^���v�ƁA���S�Ȉ�[�����������c�c
�ԑ��W���Ă̌����ȋL�^�ɂ����Ă��A8��17������11��30���̊Ԃ�1916�l������r�C�ɖ`����A����156�l�̎��S���L�^����Ă���B
�H�����̕s���̎��̎���A�O�o�̋��ߎa�E�A���E�A����ɂ͓����ɂ��E�Q�Ȃǂ����������A���|�I�����́A���̐���r�C�ɂ��a���ł������B
����̓r�^�~��B�̌��R�ɂ���Đ�����a�ŁA�q�����̈��������邪�A�ő�̌����͐H�Ƌ����̕s���ɂ������B
9�����̍H�����Ԓ��A���Ϗo��1000�l�Ƃ���Ή���27���l���ɒB���邪�A����23�N�̖ԑ��S�S�̂̍k�n�͋͂�34��5���ɉ߂����A��������27���l�����̐H�Ƃ��������邱�Ƃ͕s�\�ŁA���n����D�ʼn^�э���H�����R���̌���܂ʼnהn�ԂȂǂʼn^�э����A���̊Ԃɖ�̑N�x�������A���|�I�ȃr�^�~���s���ƂȂ������̂ł���B���������ӂ̎R��ɖڂ�������ΎR�̕�ɂł���A�R�S�~�Ȃǂ�����ł��r�^�~���ނ�⋋����H�Ƃ͂��������A�K���̂��߈�ؗ��p���邱�Ƃ͂Ȃ������Ƃ����B
���̂��߂ɁA�Ŏ���܂ޑ������]���ƂȂ����B

11�F30
YABU�}�V�[���Ɍ���R�A�Đڑ��B
�܂��������A�d�b���̕W���B
�uN19 A2�v�Ƃ���A�ԍ��I�ɑO�������̂̎��̔Ԃ��낤�B
�܂��A����܂Ō������W���ł͑ۂ̂��߂ɋC�t���Ȃ��������A���ʂɁu��28.12�v�Ƃ���������2�s�ɕ����č��܂�Ă����B
���a28(1953)�N12���̐ݒu�Ƃ������Ƃł��낤���B���Ƃ���A���̓������ꋉ����39���ɔF�肳��ĊԂ��Ȃ����ł���B

11�F31
���������H�I�@�A�����Ĕ������������B
���x�́A�Nj����B
���������Ȍk���i�M�őS�����ʂ��Ȃ����j���A�ې������q���[���ǂɂ���ē��̒����̐ꏊ������Ă����B
�N��I�ɂ́A�ꋉ��������̂��̂��낤���B
���̃q���[���ǂ̕ӂ肩��A�M�̒��ɓ��炵�����A�����悻45���Ԃ�Ɍ��Ď���悤�ɂȂ�c�c1����A

11�F32�@�s���ݒn�t�@�C��790m
�����Ђ傧����������������!!!!!
�A�N���m���E�i���u�K�A�P�^�H�I
�k�����g���l���H�h�̍����ꂵ���M��Ԃ��A���Ƀ��b�L����YABU�}�V�[�������z�����\�������邼�B