県道576号の単独区間=未供用区間へ

2024/11/3 13:52 《現在地》
さて、ここからが県道576号の単独区間とみられる道である。
だが繰り返し述べているように、ここから先の県道576号は未供用だが、区域の決定は行われている状態であると判断していた。
ただ、その道路区域を確認する術がないので、これから辿る道が厳密に県道576号の未供用区間であるという証明が出来ない。
ここから辿る道について資料的な裏付けを持ってはっきりと言えるのは、魚沼市道上折立13号線に認定されているということだ。
さて、この入口には、いわゆる不通県道には付き物ともいえる見慣れた「通行止」の看板が置かれていて、「この道が県道であることの弱性の示唆か!」と一瞬色めきだったのだが、一緒に「工事中」の看板があるので、そちら絡みのものと冷静に判断した。(事実、この工事が行われる前の2014年に撮影されたストビュー画像には「通行止」の看板は見当らない)
一緒に設置された工事看板によると、この先で農業用取水堰の工事が先で行われているらしく、そこを通り抜けられるのか不安があるが、自転車なら小回りが利くので突入した。
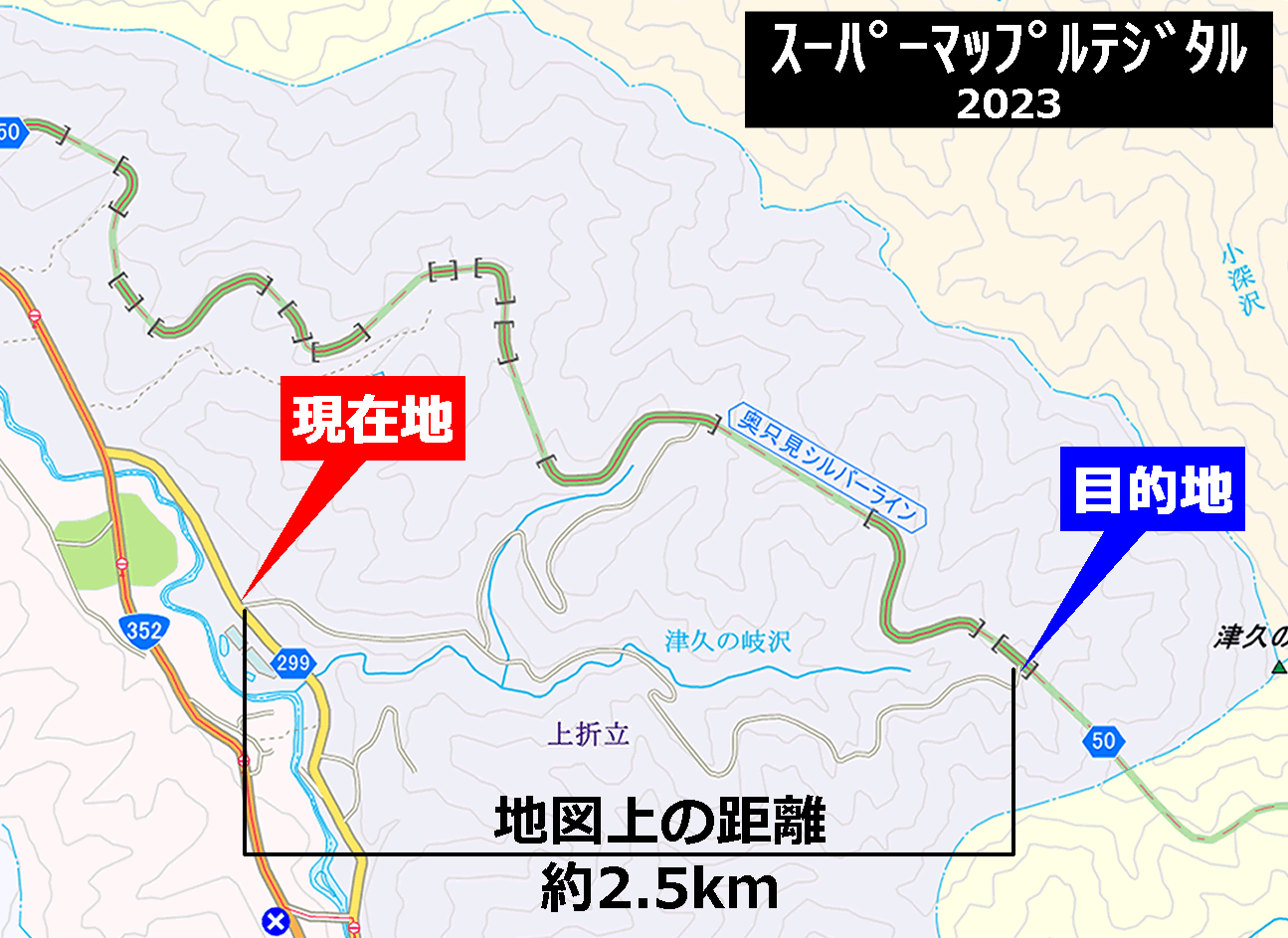
ここで、探索の最中に考えていた、この先の見通しについて語りたい。
実は、旅先でも愛用している昭文社の電子地図『スーパーマップルデジタルver.24』(2023年発売)には、県道576号の未供用区間と見られる道が、通常の車道のような表現で描かれている。
これはおそらく、元にした地形図のデータの古さから、チェンジ後の画像のような最新地理院地図からは一部抹消されている(工事用道路由来である)この道が描かれ続けているだけだと思うが、そのおかげで、この地図ソフトの機能を使い簡単に「現在地」から「目的地」までの道のりの距離を計算することが出来た。
その距離は、約2.5kmであった。
ここから正しい道を約2.5km進むことが出来れば、県道576号の“前代未聞”の完抜に成功した!……となるはずである。そしてこれが探索の最終目的。
だから今からそれを目指すわけだが……
実は今回、この地図任せの距離計算に大きな落とし穴があった……。

さて、これは入って50mほど進んだ地点。
道幅は1車線で狭いが、一応舗装がされている。
道は最初にググッと登って、あとは緩やかになった。同時に視界が開け、右手に佐梨川の明るい谷と、その奥に聳える奥只見の門戸である高い山並みを見渡すことが出来た。
だが、まもなくこの道は佐梨川の本流を離れて、津久の岐(つくのまた)の谷へ引っ張られるはずだ。

入口から100mほどで、呆気なく未舗装路となった。
道幅は変わらないが、車道としてはこれ以上は狭くなりようもないというのが正しいだろう。
前方、早くも入口に看板を立てていた工事現場が始まりそうだ。
だが、ここまで来ても工事の音が聞こえなかったので、さらに進む。

津久の岐沢の谷へ入って間もないここが、工事の現場であるようだ。
道路の工事ではないが、待避所のない狭い路上に工事車両が止まっていて、自転車で無ければすり抜けて進むことは出来なかっただろう。
ただ、ちょうど昼休みにあたったのか、辺りに人の気配がなかった。
ここぞとばかりに、さっさと通過する。

工事現場を過ぎた途端に廃道が始まることを心配したが、そうはならず、引続きよく踏まれたダートが続く。
風景としては、どこにでもありそうな林道そのもので、それ以上でも、それ以下でもない。
果たして、このように自転車で労せず進める道は、どの辺りまで続いてくれるのだろう。
2006年のシルバーライン探索で、この道の「起点」(今日の「目的地」)を先に見てしまっており、そこには完全な廃道しかなったような記憶があるため、どうしても先行きについて楽観的にはなれなかった。
いや…、仮にこの2006年の経験が無かったとしても、そもそも、工事用道路というものに対する私の信頼感はとても低い。
おそらく工事用道路――それも昭和32年に工事が完了している――に来歴を有する道に、私は端から多くを期待していなかったし、恐れてもいた。

抜けるような秋空の下、色づき始めた森の道を爽快に進んでいる。
しかし、期待以上に深く刻まれているこの路上の轍は、いったいどこへ向かっているのだろう。
2006年の探索から随分と年を空けての今日であるから、もしかして、道が復活しているなんてことが、あり得る?
だとしたら、とても助かるのだが……。
ぶっちゃけ今回、この謎に満ちた県道を踏破してみたいという熱量はあるが、途中の径路上で県道らしい“何か”を見つけることについては期待していない。これは“フリ”とかではなくて、県道が未供用であることははっきりしているので、仮にここで何を見つけても、県道の用地かもしれない場所にある何かに過ぎない。
ともあれ、道路を辿ることに専念しよう。

14:02
入口から650mほど進んだところで、工事関連らしい土嚢や土管が置かれた広場に辿り着いた。
ここまでの道が予想に反して多く踏まれていたのは、ここに工事の資材置き場があったお陰ということかな?
途中に全く広い場所が無かったので、それはそれで納得出来るが。
……ちょっとがっかり。

待て。
待ってくれ。
広場に立って来た道を振り返ると、切り返して登っていく道があるではないか。
ということは、ここ……(↓)
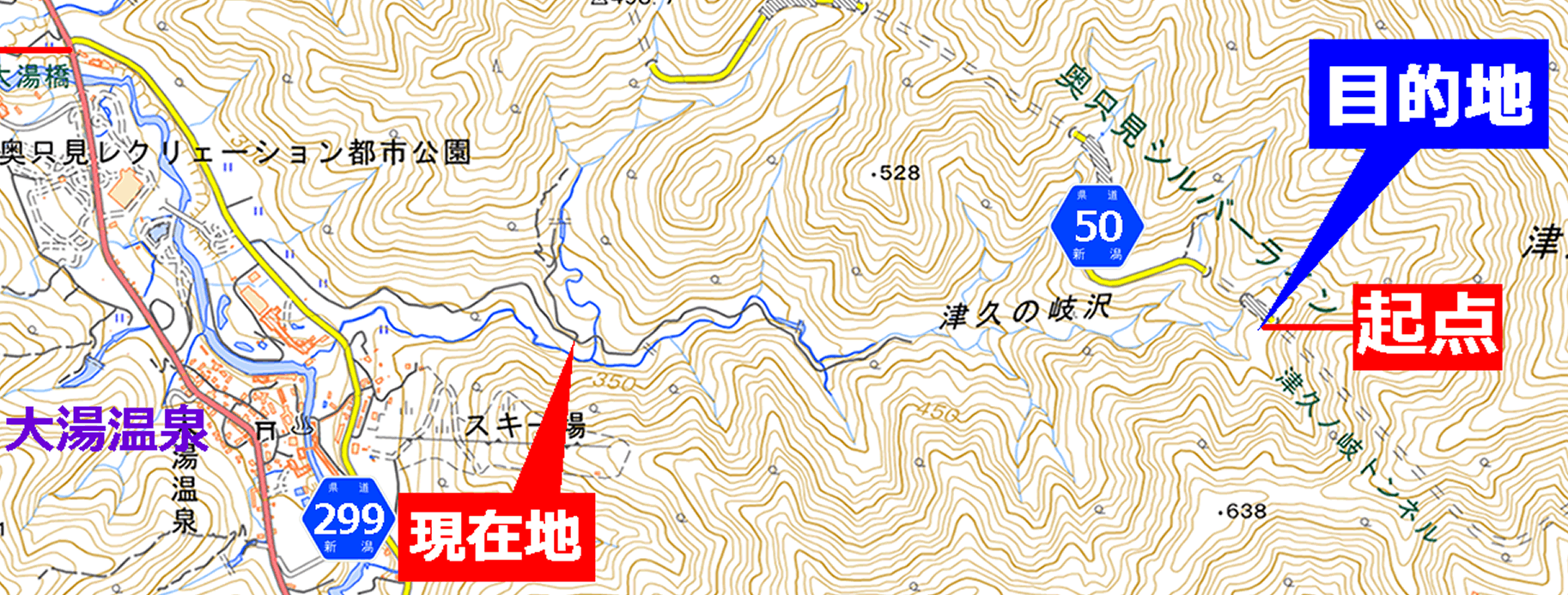
地図上の「現在地」の場所であることが、強く疑われる。
もしそうだとすると、県道576号の想定経路は、ここから折り返すのではなく、直進せねばならないことになるが……。

この土嚢の山の向こうが、辿るべき道ということか?!
うわーー……。 嫌な予感しかしない。
悪寒を噛みしめながら、土嚢の山の向こうを見てみると……

谷を渡る高い築堤が、ごっそり崩れていた。
ただ、そのまま放棄されてはおらず、築堤を復旧させる前提で再び土盛りを始めている最中らしかった。
必要な高さの3分の1くらいまでの盛土が終わっていて、対岸側の足りない分は梯子で穴埋めされていた。
そして、近くに工事関係者は見当らない。長期休工中のような雰囲気である。
親切な梯子が置かれているお陰で、先へ進むことは出来そうだが、自転車はここまでだろう。
案の定、一筋縄では行かないか。
早くも相棒と切り離されて、孤独な戦いに身を投じることに。
14:07 自転車と別れて、突入。

ブル道っぽいスロープを下って、谷底近くへ(写真は振り返って)。

で、この梯子を登る。
ぎーし… ぎーし……
(いつからこのままなんだろ、ここ?)

14:09 《現在地》
道の続きへ、辿り着く。
案の定、こっからは廃道っぽいな。
でも、これで入口から約700mを踏破。
シルバーラインまで、残り推定1800m。
市道上折立13号線から13-1号線への最重要アプローチ

14:09
これは、梯子を登って辿り着いた道の続きを進み始めた直後の風景である。
濃い轍が頼もしかった林道然のダートは、欠壊地を越えた瞬間に一変してしまった。
路面をぼうぼうの草が覆い隠し、車の轍はおろか、人が歩く分だけの刈払いも見当らない。
絵に描いたような、ヤブ道である。
直前の崩壊地を見た時、崩れてから数年ではなく10年は経過しているような印象を受けたが、この藪の濃さは、それを裏付けている。
今のところ、道としての幅自体は変わっておらず、大きく崩れている様子もないが、この藪の濃さは障害だった。
しかも、晩秋の草藪と言えば、いろいろと着衣に憑くものが多く、探索後にまで障りを残すことが多いのだ。
ここまで来た以上、藪くらいで撤退が許されない覚悟はしてきたつもりだが、億劫さは隠せないよ。

変化は藪だけでなく、勾配がかなり急になったこともある。
道が沿っている谷の急さを裏付けるように、「津久ノ又沢砂防堰堤」の看板が現れた。
藪のせいで谷底を目視するのは困難だったが、身体を潜り込ませてどうにか一部の【撮影に成功】 した。
した。
ところで、さきほどから明るい写真が多いと思うが、この谷の中にいる間は、急峻な地形にも関わらず、ほぼ常に空が見えていた。
その理由は単純で、空を広く遮るような大きな木が谷の近くに少ないせいだ。
これは極端に雪の多い地方の急斜面でしばしば観察される植生の特徴で、実際歩いていると特異さを感じるが、的確に表現する用語を私は知らない。たぶん、これがもっと進んで植生が皆無に近づくと、アバランチシュートと呼ばれるものになるのだと思う。

14:14
老いて柔軟さを失い、タワシのようになったススキを掻き分けて進む時間は、キツイ上り坂であることと相まって、あっという間に私を汗まみれにした。
前方、法面が崩れて岩山が露出しているところがあり、一見すると障害っぽいが、相対的にはむしろ草藪が薄くて歩き易いと感じた。
ひとたび雨天の探索を決行すれば、太陽の下を歩ける幸運を思い知るのだが、今は太陽が育てた藪の深さと、その逃げ場の無さを、臆面もなく憎んだ。
少し先に綺麗な円錐形の一本立ちのスギが見えるが、次の写真は、ここから3分掛かりで辿り着いたその根元の場面である。

14:16 《現在地》
津久の岐沢を渡る橋が架かっていた。
入口から約1km(決壊地点から約350m)の位置である。
地形図に描かれている谷沿いの車道が津久の岐沢を渡るのはこの一度きりだが、先ほど支流の谷を横断する築堤は決壊していたので、少なからず状況を不安視していた。
が、幸いにして、無事であった。
今度は築堤ではなく、小さいなりにも橋が架かっていたということも嬉しい発見だった。
長さ10mに満たない短い橋だが、高欄代わりに設置された左右の地覆や硬い足裏の感触より察するに、木橋ではなくコンクリート橋(永久橋)である。
そして橋があれば当然、銘板を探し出して橋名や竣功年を知りたいところだったが、残念ながら設置されていた様子がない。
全国Q地図で見られる「2018年度全国橋梁マップ」にもこの橋は掲載がなく、橋名その他、一切の諸元は不明だ。(もし掲載されていれば、ここが市道として供用中であることが確定したのだが)
まあ、素性が不明だとしても、外形が何の変哲もない平凡なコンクリート橋だったら、敢えて注目することはなかっただろう。
しかしこの橋、だいぶ奇妙なナリをしているのである。

最初にお詫びするが、周囲のあらゆる方向の藪が酷く濃いために、橋を横方向から観察すること自体が容易でなく、現場を知らない人に理解して貰えるような鮮明な写真を撮ることは出来なかった。なので私が目視でどうにか把握できた範囲で説明を試みたい。
まず、この橋は単純なコンクリート桁橋(RC橋)ではなく、鋼鉄のIビーム桁に鉄筋コンクリートの桁を乗せた、混合桁橋であった。【桁の拡大写真】
特段に珍しい構造ではないが、頑丈そうであり、現状の利用度からすれば少々過剰な印象だ。
まあ、道幅が1車線分しかないから、将来の県道化を見越して設置された橋などと言うつもりはないが。
そしてもう一つ気になるのが、橋のすぐ下に木橋時代の旧橋台を思わせる石とコンクリートの構造物が、川幅を相当狭める形で設置されていることだ。【旧橋台?の拡大写真】
藪が深すぎて分かりづらいが、おそらく、この旧橋台の上に盛土をして、そこに今の桁を乗せてある。
津久の岐沢に初めて車道が通じたのは、昭和29年にシルバーラインの前身である電源開発専用道路が着工した当時と思われる。
おそらくそれが旧橋台の正体であり、その後に何か別の目的(例えば砂防工事とか林業とか?)で、より頑丈な桁を架け直したのではないかと想像した。

これは渡った後に対岸側から振り返って撮影した橋の様子だ。
橋の長さに対して、水が流れている谷の幅はとても狭い。
桁下に埋設されている旧橋台らしい構造物が、谷が狭めているせいである。
そのせいもあって藪が濃く、谷底を流れる水の様子はほとんど見えない。ここに掲載した数枚の写真を撮るだけでも苦労した。

構造物の存在に期待を持っていなかった中で、橋があったのは嬉しかったが、渡り終えた先の道はさらに藪が深くなっており、うんざりした。
しかも、この凶悪な藪の中で、私はそろそろ、“重大な探し物”を始めなければならないはずだ。
すなわち……(↓)
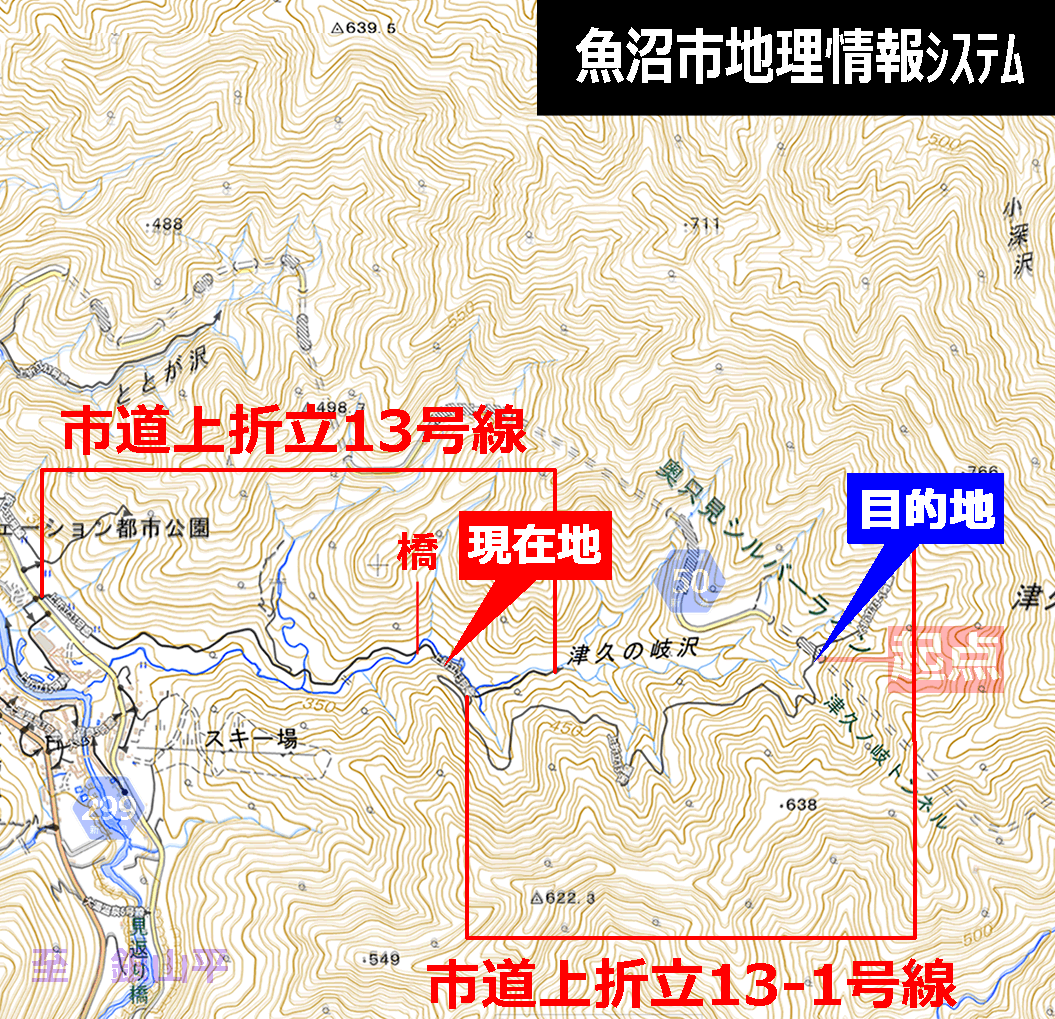
今辿っている「市道上折立13号線」から、「市道上折立13-1号線」が分岐する地点を見出して、確実に13-1号線を選択しなければ、「目的地」へ到達出来ない!
そして、恐るべき未供用県道のマイナーさゆえ、入口から1km強の位置にあるこの先の分岐地点ですら、かつて到達したという報告を聞いたことがなかった。
その前人未踏ぶりは、さながら2007年当時の清水国道の縮図のよう。(←随分ちっちぇ縮図だな)
したがって事前情報は皆無であるが、ここ最近の展開から、きっと良い状況ではないだろうと予感されるのだった。
なお、分岐も、13-1号線も、地理院地図には描かれておらず、「魚沼市地理情報システム」の市道地図が目下の頼りだった。
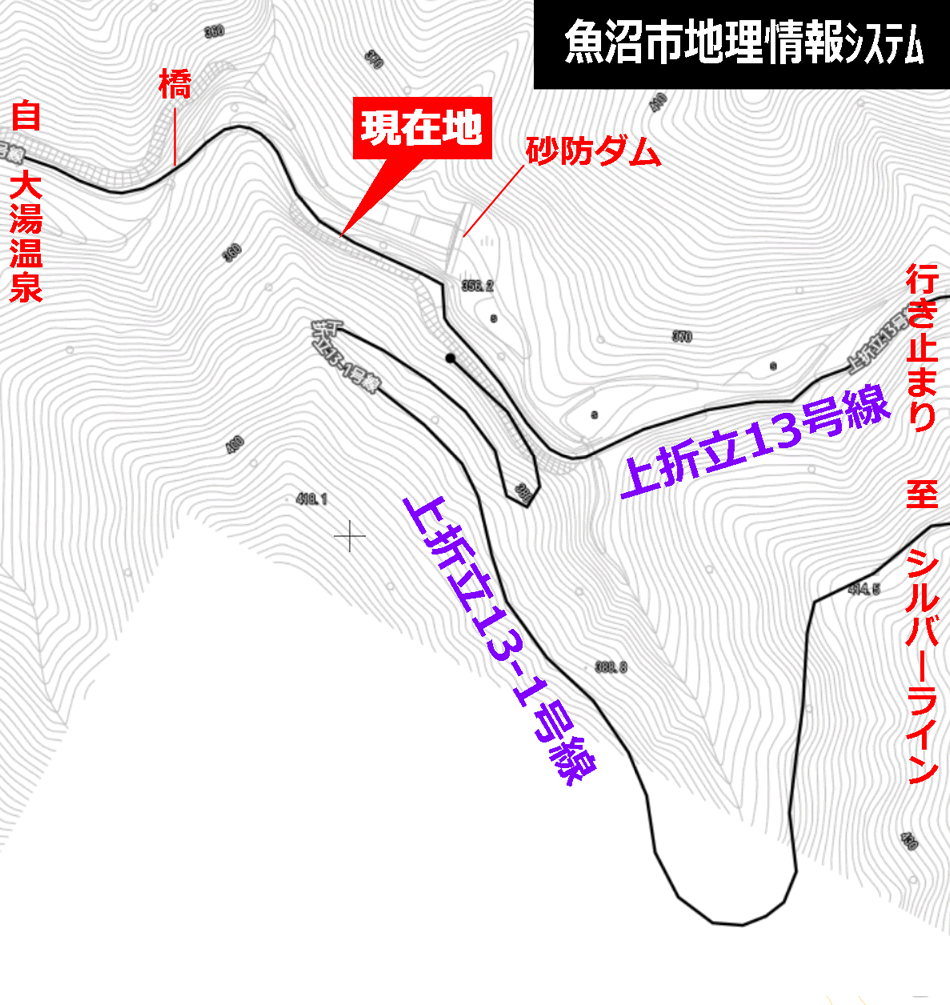
これは同図を限界近くまで拡大したものだ。
分岐部分で道が繋がっていないという不可解な表現になっているが、それは縮尺の荒さによるものだろう。
この地図から推定される分岐の状況は、川沿いの13号線から、山側に13-1号線が分岐し、少し並走してから切り返して上方へ離れていくというものだ。
また、分岐の目印になりそうなものとして、まもなく谷底に砂防ダムがあるようだから、それを過ぎたら、道の右側に全集中!!
この方針で行こう!

わわわわ……。
路上を覆い尽くす藪の種類が変化してきた。
陽当たりのよいススキの藪から、ジメジメとした灌木の藪へ。草藪から木藪への変化である。
一般的に、行き止まりの廃道は奥へ行くほど通行量が減り、藪も濃くなるのが普通だ。
ここでもその傾向が如実に出ていると思われる。
チェンジ後の画像は、正面奥に立ちはだかっている稜線を望遠で撮影した。
シルバーラインへ登っていく13-1号線は、あの山肌の中腹あたりを右から左へトラバースしているはずだが、樹木のために全く道形らしいものは見えない。
この距離で見えなくても不思議ではないと思うが、いったいどの程度の道幅があるのか不安だ。
工事用道路といっても、その規模はピンキリなんで、予想ができない。

14:20
これは……、もしかして、分岐があるか……?
来た道から切り返す方向に、幅1.5mくらいの極めて狭い道が分れているように見えた。
……が……、しょうじき言って……、
これが目指すべき道だとは思いたくないな……。
まず、車道としては狭すぎるし……、なにより……(↓)

こんなん、一度入ったら二度と生きて戻れぬ“藪密度”では…。
いまから日没までの残り2時間では、正直歩ききれる自信が……。
それにそもそも、まだ目印となるはずの砂防ダムは来ていないし、分岐の向きも地図とは違う!
ここで間違った道でいたずらに時間を費やしたら、シルバーラインに到達できないだけでなく、明るいうちに撤退することさえ出来なくなる恐れがある。
ここは普段以上に慎重に、安全側の選択をしよう。
結論。
この分岐は無関係と判断し、無難にスルー!
いやぁ、危ない危ない……。

14:22
砂防ダム、発見!
藪のせいで路上からは全く見えなかったが(チェンジ前の画像)、水の落ちる音を聞き分け、路肩を探って探し当てた(チェンジ後の画像)。
この先まもなく、右方向へ分岐する道があるはず!

14:23
分岐、無いんだが……。
そもそも、地形に無理がないか。
この写真でもよく分かると思うが、道の山側はとても急な斜面で、2本の車道が並行しながら分岐する余地があるとは思えない。
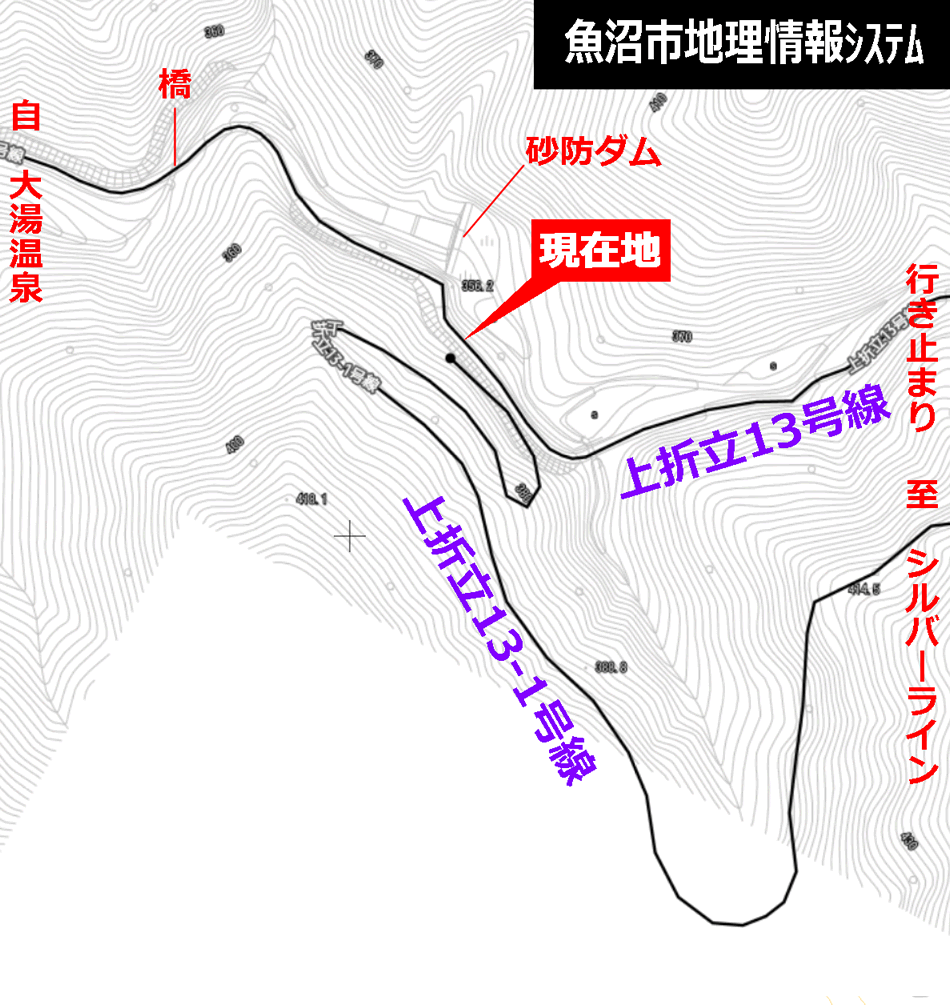
例の地図を思いっきり拡大すると、川沿いの道(上折立13号線)の法面が切り立っていることも、ちゃんと表現されている。
にもかかわらず、その切り立った法面を無視して、13-1号線が分岐している。
これはいった、どういうことなんだ……?
ここに来るまでは、工事用道路というバックボーンを有する13-1号線が、実は存在しない道だなんてことはほとんど考えなかったが、なんだか、急に不安になってきた…。
“9:1”くらいで道自体はあるはずだと思っていたのが、急に“5:5”くらいの自信のなさになったというか……。

だって……
なければならない場所に、ないんだもの!
この写真は、分岐があるとされる山側の法面を、見上げて撮影した。
13-1号線は、この辺りで山側に分岐した後、切り返してきてその上を左から右へと横断、さらにもう一度切り返して今度は右から左へと、都合、目の前の斜面を3度も横断することになっているから、段々の地形になっていなければイケナイのだが、そういう感じが全然しない。
そもそも、人手が加わったことありますかね? この斜面に…。

14:24 《現在地》
参ったな…。
結局、分岐する道の気配すら感じられないまま、地図にも表現されている支流の谷の入口まで来てしまった。
ここで谷沿いの市道上折立13号線は左へカーブし、右から合流してくる支流を跨いで、左の本流の谷へと進むが、その先は行き止まりである。
本来進むべき13-1号線は、右の支流の上部を巻きながら、そこでもどんどん高度を上げて、シルバーラインを目指すように描かれていた。
いやはや……、
いくら藪が濃いとはいえ、ここまでしっかりとした地図を持ち、かつGPSでリアルタイムに現在地を補足しながら、地図に描かれている道を見つけられないとは思わなかった。
ちょっとした異常事態じゃないか……。
俺の目が衰えてるのか?
本当に実在する道なんだとしたら、悔しい……。
でも、本当に見当らないんだよな。 せいぜい、さっきの小径くらい?

どうしようか決めかねながらも少しだけ前進すると、曲がった本流の先の世界が見通せた。
あ。

シルバーラインだ。
……ははは…
なんか、シルバーラインって、他の道が無いところをひたすら孤独に(大半はトンネル内を)進む一本道という印象が強烈過ぎて、こうやって地上にある姿を外から観察するのは、なんだかとても新鮮だ。
前代未聞の眺めなんじゃないか?
……さすがに大袈裟か?
本当に、裏口入学のようなワクワク感とビクビク感がある眺め。
県道576号があそこまで辿り着く未来なんてものも、どこかにはあったのかなぁ……。
シルバーラインまで、一応、残り1400mくらいまで来てるんですけど、どうしましょうねぇ…。
道を無視して地形を強引に突破すれば、見えているシルバーラインに辿り着けそうではあるけれど…。
どうしよう。