�@�������珉��詓��̓����֓˓��I
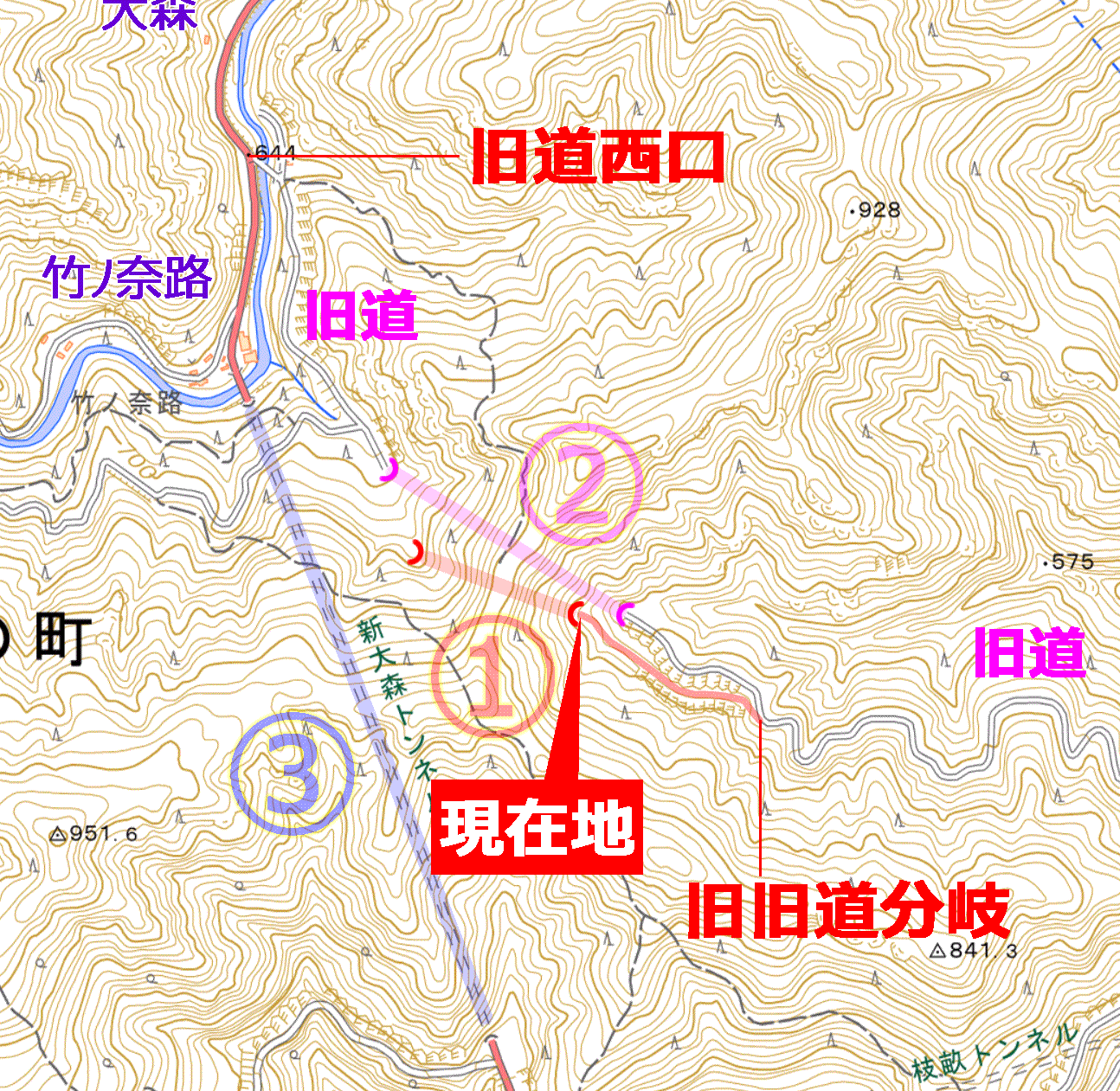
2024/2/27 17�F56�@ �C��740m
�����I�@�����X�g���l���A�����B
�C�ۑ䔭�\�̓��v����4���O�̓��B�ł������B
�M���M�����������A�ЂƂ܂����邢�����ɒH�蒅���ăz�b�Ƃ����B�撣���Ĕ�����b�オ�������B
�����Ă�������GPS�Ŋm�F�������ݒn�́A���̔��������110m���̒J�̂ǂ�l��A�C��740m�̒n�_�������B2��ڃg���l��������̂Ɠ����J�����A40m�قǍ����ʒu���B
���Ƃ̔䍂�ł���110m�Ƃ�����������������A�債���ቺ�ł͂Ȃ��Ǝv�������m��Ȃ����A���̓������͔��ɖ��ŁA�e�Ղɓ��݉z��������ł͂Ȃ��B
����Ȍ�����������ʂ炸�����z���邱�̃g���l�������A�{���̓����i�������j�ȏ�ɒm��ꂽ�g���E���h�̂��������ߋ��֒ǂ����A�����ɖ{�쑺���g�l���̃`�x�b�g�h�Ƃ����i�z�����m�̃`�x�b�g�Ɏ���ȁj�������~���o�����A�O�E����{�쑺���֒H�蒅�����L�O���ׂ��ŏ��̎ԓ��ł������B
�������A�T���̎��_�Ŏ����c�����Ă������̏���g���l���̏��́A�ƂĂ����Ȃ������B
�`���ŏЉ���w�y���̓����y�L�x�ɂ������u���a�\�N�ɏ���̃g���l���������v�Ƃ����ꕶ�ƁA詓��̍ݏ���T�����߂ɓ��肵�����a32(1957)�N�ł̋��n�`�}�i���`�F���W��̉摜�j���炢�������Ǝv���B�i�l�b�g��ɐ�s����T���L�^�����������A�����ĕ��Ă����j
������A�����Ɏ������o�܂�o�߁A���邢�͔p�~���ꂽ������������Ă��Ȃ��������A�w���H�g���l����Ӂx�̔��s���_�Ŋ���2��ڃg���l���ɓ��������Ĕp�~����Ă������߁A�����Ȃǂ̏��������炩�ł͂Ȃ������B
�����������ɂ��ẮA���ꂪ�`����Ă��鏺�a32�N�ł⏺�a43�N�Œn�`�}�̕\�L����A�����悻250�`300m���x�Ɛ�������Ă����B
����250m�Ƃ��Ă��A���a�����Ɍ@��ꂽ���H�g���l���Ƃ��Ă͌����ĒZ�����̂ł͂Ȃ��B
�ʂ����Ă��̒Z���͂Ȃ��n���̈ł��A��������89�N�A�p�~����ł�60�N�i���a39�N�p�~�Ɖ���j���o�߂����p詓��Ŋђʂ��邱�Ƃ��o����̂��B
������A�����T�����J�n����I

�܂��͍B���O�̑S�i�ł��邪�A
����ۂ́A������ ���I
��ʂ̕��y���B���O�߂Ă���A���̂����ŊJ�������������Ȃ��Ă���̂͊m���Ȃ̂����A�����łȂ��Ă�������詓����Ǝv�����B
�i��ɂ�����H���o�X���ʂ��Ă����ƕ����ċ������j
�����ɂ�����Ȃ����Ȉ�ۂ̉��ڂɂ͐l���p�ƌ������悤�ɏ����ȍB�����B����Ɣ�ׂ��2��ڂ͖{���ɑ傫���Ȃ��Ă����B
����ł���250m�ȏ�̒��������肻�����Ƃ������ƂɁA�V���v���ɕs�����������B
�ђʂ�ۂ��Ă���̂��ǂ����Ƃ����s�����B
�ڋ߁B

�B�傪����ɉ��Ă���Ȃ��c�c
�B��H�́A���ɒn�R��}����ǂƂ��Ă̖����͕ۂ��������Ȃ��Ă���B�ꕔ�͓|�A�c��ɂ��傫�ȋT�����Ă����B
����ȉ�ꂩ���Ă���㔼���ƁA���ɒn���ɖv���Ďp�����邱�Ƃ����o���Ȃ��������A���������̂������{���̑S�̑���z�����Ă݂����A2��ړ��l�̃V���v���ȏꏊ�ł��R���N���[�g�̍B�傾�B��͂葕���I�v�f�����Ȃ��B
���ꂪ���݂��ꂽ���a���N��Ƃ����A�S���̔_�����𒆐S�Ɍ������s���i���a�_�Ƌ��Q�j���N���Ă���A���̐V���Ȍ��ւƂȂ�L�O���ׂ��g���l���̊�ł����Ă��i������������t��������ł͂Ȃ������̂�������Ȃ��B�����I�Ɏ��Nj��~�y�؎��ƂƂ̊ւ����z�肵����B�ѓ��p�̃g���l���݂����Ȏ��f�����������B

����Ȏ��f�ȍB��ɂ́A2����ڂɂ͂������G�z�����Ȃ������̂�����ǂ��A�悭����Ɓc�c
�G�z�͂Ȃ����A�G�z�̎�t���z��ʒu�ɒ���詓������A������Ă����I�I
�G�z���Ȃ��Ƃ����A���f���ɗւ������邱�̎�@�A�ȒP�ɂ��肻���Ɍ����Ď��ۂ͐������A�ȃp�^�[�����B
���������A�ǂ�����Ď{�H�����낤�B
����̕ǂƈꏏ�Ɏ��i���˂����j�̉��Ȗ͗l�����邩��A���̈ꕔ�ɕ�����z�����āA�^�����������낤���B�����Ԃ��Y��ȕM�������o�Ă��邪�c�B
���ƁA2��ڂ̝G�z�Ɠ������������������Ȃ̂��n���ɋC�ɂȂ�B
��O�̝G�z�͑�̉E���������i��ł͂Ȃ��j�A����͒������B
���̂Ƃ��덪���͂��̕����������������A���͐��ɉ��߂č��ꂽ�B��Ƃ����\�����^�킹��v�f���c�B�J�ʓ����̎ʐ^�����������̂��B
�B��̊ώ@���I���B
�w�b�h���C�g��_�������A���܂Ȃ��Ɠ���������J�������A���߂ē����ւƎ������������B

17�F57
�������I
�I�c�c�@����́A�ǂ��Ȃ��ł��c�c�B
�����J������������u�ԁA�j�ɂ�����Ƃ������Ԃ̔M�C�̎c����������B
�����āA��u�ŃJ�����̃����Y�������܂����B
�B���ɁA���̗���������Ȃ������B
�����ē��R�̂悤�ɏo���̌��͌����Ȃ��B
�������J�[�u���Ă���\���͂��邵�A�����͊��ɏo�����Â������Ȃ̂�������Ȃ����A����͕s�������闧���オ�肾�c�c�B
���ȗ\�������A���Ȃ������B
�y�̎R������悤�ɉ����āA�{���̓����߂��ցc�c�B

�U��Ԃ�A�B���B
�����ɑ͐ς��Ă�����̂́A�㕔�Ζʂ���̗����낤�B
�c��J�����́A�����ɂ���1.5m�قǁB����ׂ��f�ʂ�3����2������Ă���B
��قǂ̋K�͂̕���łȂ�����A���Ŋ��S���v�Ƃ͂Ȃ�Ȃ����낤���A������́c�B

17�F58�@�i����1����j
�����b�I
���v�����c�c�B
��C�̂�����ɁA�o���̌������A�����āc�c����B
������������A�ǂ��Ȃ��v�f�����Ȃ��Ȃ��c�B
�B���ɓy���������ς����Ă��āA�r��������Ă���l�q���Ȃ����Ƃ���A�o�債�Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ͓��S�v���Ă������A�����Ă����ɐ��v���c�c�B
�������猩�ʂ���25m���炢��܂ł́A���ׂĐ��v���Ă���B
���̉��͈łŕ�����Ȃ����A���傤�ǂ��̕ӂ�ŃR���N���[�g�̊������Ă��I����Ă�����ۂ��B���͑f�@��̉\����B
���́A���̐��̐[�����A���i�ނɂ�Ăǂ��ω����邩���B
���z���̃g���l���Ƃ��Ă͍ł����ʂ́g�q���z�h�ł���A��Ԑ[���͍̂B���ŁA�i�ނقǂɐȂ邱�Ƃ����҂ł���B
�����A���̑�X詓���2����ڂ́A�������琼���ւ̈���I�ȉ���Ќ��z�ɂȂ��Ă����B
���̏ꍇ�A���܂��铌������i�ނقǂɐ��[�͑���������B250m�ȏ�̒���������Ƃ���ƁA�ԈႢ�Ȃ��w����[���Ȃ��Ă��܂����낤�c�B
����G�炵�ē������Ă��A�ʂ蔲������ۏ͂Ȃ��̂ł���B
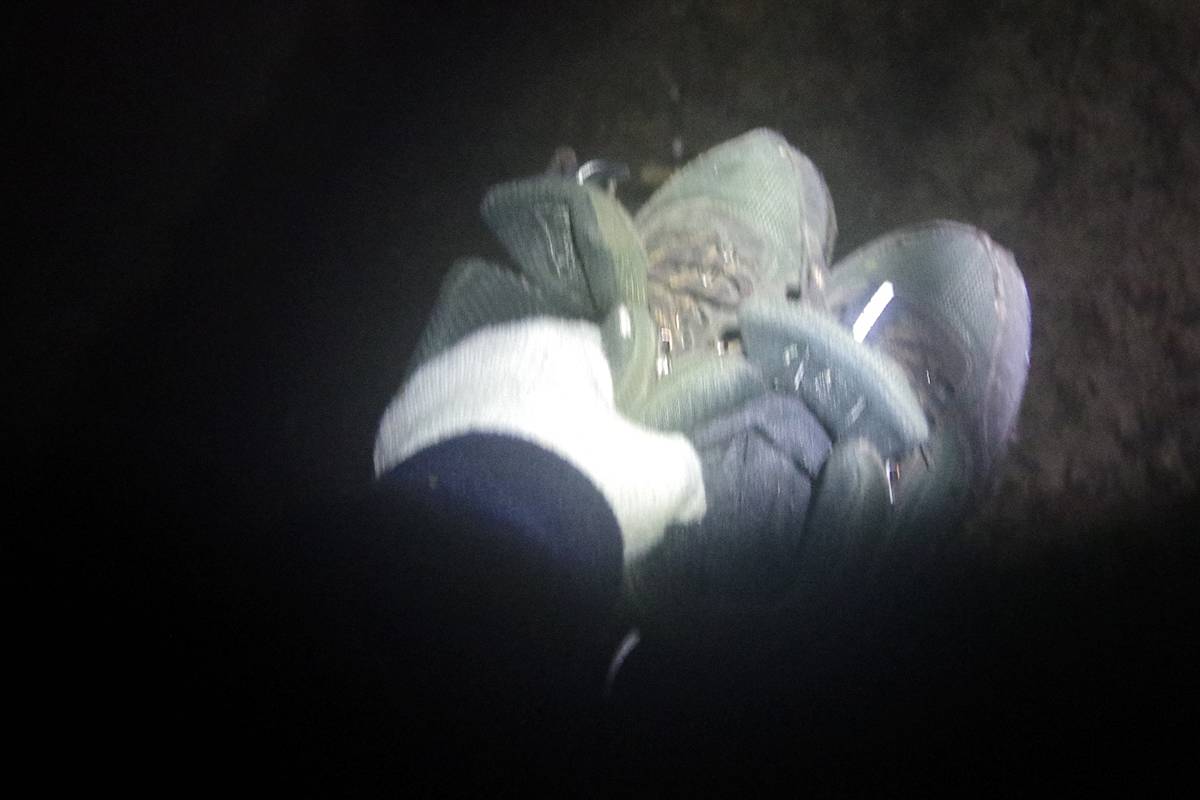
17�F59�@�i����2����j
������������A���T�C�g�̏n���ǎ҂��A�����A�u���v���Ă��邩������Ԃ��܂��v���A�ȒP�ɂ͋�����Ȃ��B
�j���Ȃ���Ȃ�Ȃ��قǐ[�����Ƃ��A���̒�Ȃ��D���ł���Ƃ��A����Ȃ��Ƃł��Ȃ���A���v�����������ň����Ԃ��͓̂���Ƃ���ɗ��Ă���B�����g������Ă��܂����u�Z�I���[�v�ɉ��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��A����Ȋ�тƋꂵ�݂�����B
��������́A�������̎����A�l���Ȃ��ɓ˓����Ȃ��B
�����Ȃ�C���G��邱�Ƃ͂��\���Ȃ��ɓ��邪�i�{���͌��Ȃ�j�A����́A�\���B
����̎l�������́A���ȍŒ��ł���A��7���Ԃ̒T���v��ŁA���������̓��͂܂�2���ڂ��B���C���̌C��G�炷�ƁA�c��̓������Ɋ��������Ƃ͓���B�ւ��̌C�͂�����̂́A�J��s���̃~�X�ŔG�炷�\��������̂ŁA���v詓��Ȃ�ďꏊ�ł݂͂��݂��G�炵�����Ȃ������B
�c�c�l�̌܂̌����āA�S�����l�c�c�B
���J�n�I
�܂��͗����Ă���C�ƌC����E���ŁA�����b�N�֎��[�B
����Ɏ��o�����A�E�H�[�^�[�V���[�Y�𒅗p�����I
���̗p�r�̂��߂Ƀl�I�v�����̌C���������Ă����͂����������A�Ȃ��������Ă��Ȃ������̂Łi�c�j�A��ނ����������̃E�H�[�^�[�V���[�Y���B
����ŌC�̊������������A�����˔j�o����͂��I
�����A�����I

��߂Ă�������!!!
���x���₽�����B
2���̕W��700m�̒n�����̗₽�������A�������u�ԗ��X�l���s���s���ɂ݁A�ܐ悪�W���W���ƂȂ�o�����B
�ӂ���@�ӂ���@�ӂӂӂӂӂ���������@���ނ��I�I�I
�����͔n���������B�Ɋ����������I�I�I
�������A�z������w�h���̐[���������B
�ŏ��̈���ڂŃY�u�Y�u�ƒ�ɑ�������Ă����A��Â������̂̓X�l�����S�ɐ��ɐZ�������[���ł������B�܂�A�����悻50cm�̐��[���������B
���\�N���Ƃ�������Ȃ��w�h���������������āA�җ�ȃw�h���L�U����B�\������x�Ƀq�U�܂Ō����Ă����Y�{���́A�����Ƃ����ԂɃw�h�����h��ɁB
�C�����͎��Ă��邪�A�Y�{���͏I�����������c�c�B

18�F02�@�i����5����j�@
���̗₽���A�����Ȃ�Ă��Ƃ͂Ȃ����A�˓���������ɂ̓g�R�g���܂ŁA�O�i�J�n�I
��������������܂ł͓����ʂ����n�������A50cm�قǂ̐[���œ����߂Ă����B
��͐i��ł����Ă��ꂪ�Ȃ邩�A�[���Ȃ邩�A�ς��Ȃ����A�g�������Ċm���߂�B
�Ƃ肠�������̂Ƃ���͕ω��������Ȃ����A�����������ǂ̊������Ă̏I��肪�߂Â��Ă����B��͂艜�͑f�@��炵���B
�`�F���W��̉摜�́A�������ĉE���̕ǂ̗l�q���B
�悭���ė~�����̂����A���傤�ǎ��̓��������炢�̍��������ɁA�ǖʂ̗l�q������Ă���B
���̍�����艺���ɂ����A��R�̊������S�~�i�͗t�̎c�[�Ȃǁj���t�����Ă���̂ł���B
���̏͊ԈႢ�Ȃ��A���Ă��̍����܂Ő��ʂ��オ�������Ƃ������Ă����B
���ꂪ���̏o�������͕s�������A��ʂ̃S�~���܂ސ������̔w���荂�����܂������Ƃ��������̂��B
���������ׂ�A����ł����܂͐����Ȓᐅ�ʂƂ�����̂��c�c�B
�c�c���肪������ׂ��Ȃ̂��A������c�c

18�F03�@�i����6����j
��������30m�قǂ̒n�_�ŁA���ǂ����S�ȑf�@��ցB
�������Ă̕������A�̒f�ʂ��傫���Ȃ����̂���������B
��3.5m�A����4.5m���炢���낤���B�����͑��ς�炸50cm���x���v���Ă��邪�B
��ԋC������Ȑ��[�́A���̂Ƃ���[�������Ȃ��Ă��Ȃ�����������B
�D�͍ŏ��قǐ[���͂Ȃ��B
�Ƃɂ����₽���B�������ɏオ�肽�����A���̂܂܍Ō�܂Ő��v��������L�c���ȁc�B

17�F05�@�i����8����j
�}�W���c�c�B
�嗎�Ղ��Ă܂��c�B
���������B
���v�ɗ��ՂɁA�}�W�ŃR���v���[�g������肩�H�I�@�p詓��ɂ��肪���ȏ�Q���Ă�����c�B
��������Ɋ�������C�̉����A���̂Ȃ��A���̌����Ȃ��A�S�����Ђ�����߂āA���ՕǂƂ��������͈�Ԃ��肻���Ȃ��̂ł��������A����������c�c

���Ԃ�g�V�䗠�h����˔j�o����ȁB
���Ղɂ�鋐��Ȋ��I�̎R�́A�{���̓V��̍����߂��܂Ő���オ���Ă������A���Ղ̍ۓV��ɊJ�����匊���A�ʍs�̂��߂̋�ԂɂȂ��Ă���B
�s�������Ȃ��I�I

18�F06�@�i����9����j
�Ƃ����킯�ŁA���y�̎R�ɏ㗤�B
�����̌��畂�シ�邱�Ƃ��o�������A�G�ꂽ���͂��͂�A��C�̒��ł��Ɋo�̉�݂����ɂȂ��Ă��܂��Ă����B
��������͎d�����Ȃ��B�͂₭詓���˔j���āA�@�����B�@�������~���̓��͂Ȃ��B
�S���S���悶�o���āA���Ƃ̓V��̍����ɂ�����y�̎R�̓V�ӂցB
�i�`�F���W��̉摜�́A���Ւn�_����̐U��Ԃ�B�����܂œ�������ڑ�60m���炢�j

���������I
���Ւn�_�̉��ɍB���p�����m�F�I
����������̌������A���������Ă��邼�I�I

18�F07�@�i����10����j�@�s���ݒn�t
�ēx�̓����ցB
�������A���҂����o���̌��́A�Ȃ��i�s�����Ɍ��ʂ��Ȃ������B
�܂��A�ĂуR���N���[�g�������ė̈悪�����Ă���B
�傫�ȗ��Ղ�ڂ̓�����ɂ��Ă���̂ł͂����蕪���邪�A����詓��͒n���ɂ͌b�܂�Ȃ������悤���B
�����܂œ�������70m���炢�i�Ƃ͎v�����A�S���ɑ��Ă͔��������Ă��Ȃ��Ƃ����̂��������B
�����ĕ���n���z�������ƂŁA�i�`�F���W��̉摜�j�U��Ԃ��Ă��O�͌����Ȃ��Ȃ����B
�S�ׂ�����i�Ɖ�����Ă���B
�����X詓��̍U���́A��͂��ؓ�ł͍s���Ȃ��炵���B
�����������܂ŗ�����A�����g�R�g���܂ōs���o�傾�I
�@���Ղ̉��A��捂̐��E�A�@�����āc�c

2024/2/27 18�F08�@�i����11����j
�V��̍����܂Őςݏオ�������Փy���̕ǂ����z����ƁA���̉��ɂ͋��낵����捂ȋ�Ԃ��B����Ă����B
���������ɓ����߂Ă����������S�Ɉ����Ă���A����ɃR���N���[�g�ݑ��炵������ȘH�ʂ��I�o���Ă���B
�H�ʂɂ͔G�ꂽ�D���͐ς��Ă��邩��A��r�I�ŋ߂����v���Ă����悤���B詓����̐��ʂɂ́A���Ȃ�傫���������ϓ�������炵���B
���������łȂ��A���ǂ��R���N���[�g�Ŋ������Ă��Ă���A���ꂪ�v���̂ق��Y��ȏ�Ԃ�ۂ��Ă����B
�Ђъ����n�����̘R�o���Ȃ��A�܂�Ō����̃g���l���̂悤�B
90�N�߂����O�ɒa�����A60�N���O�ɔp�~���ꂽ�g���l���Ƃ��ẮA��ՓI�ȕۑ���Ԃ̂悤�Ɍ������B
�c�c�����Ƃ��A���Ղ��z��������ɂ�������Ă���̂ł��邩��A�����̏ɋ���ȃM���b�v������Ƃ���������m���������ŁA�ۑ���ԂɌb�܂ꂽ�g���l���ȂǂƂ͎v��Ȃ��B
��킭�́A���̕������Ō�܂ő����܂��悤�Ɂc�c�B

18�F09�@�i����12����j
�ނނށB
���̐�A�Ăёf�@��ɖ߂�悤���B
�B�����߂������H����Ă��āA�����͑f�@��Ƃ����̂́A�Â��g���l���ł悭����{�H�p�^�[�������A���̂悤�ɓ������őf�@��ƕ��H�����݂Ɍ�����̂͒������B
���ꂪ�J�ʓ�������p�ł������̂��A��N�̉��ǂɂ����̂��A�ǂ��炾�낤�B
�c�O�Ȃ���m�肳����ޗ��͂Ȃ����A�������Ă������Y��Ȃ̂Ō�҂��ۂ�����������B
������ɂ��Ă��A�I��I�ɕ��H����Ă��镔���́A�O����n�����������Ղ̊댯�ӏ��ƔF������Ă����͂����B
�Ȃ��A�����ǂ̏��X�Ɍ����鍕���_�̓R�E�����ł���B
�������������Ă������A�O�A�m�̎R���Ȃ��A����詓��͂��܂�D�݂ł͂Ȃ��悤���B

����30�`40m�̕��H��Ԃ��I���A�Ăёf�@��ցB�����炭��������100m���炢�͐i��ł���B
�O�ɂ���ɂ��O�̌��������Ȃ��̂ŁA�i�����͂����܂ł����o�I�Ȑ��������B
���������͈����Ă���̂ŁA����@���ČC�𗚂����������Ƃ��v�������A�O�֏o��܂ł͖��f���܂��ƁA���̂܂܂Ői��ł���B�������ő����ɂ��B
�f�@��ɂȂ�ƁA��R�̊��I�������ɎU����Ă����B
���H�����ʂ����Ă������Ƃ��悭�����邪�A���̐�̃`�F���W��̉摜�ɓ_���ň͂����́A�ŏ������f�@�肾�Ǝv�������̂́A�߂Â��Ă悭����Ɓ\�\
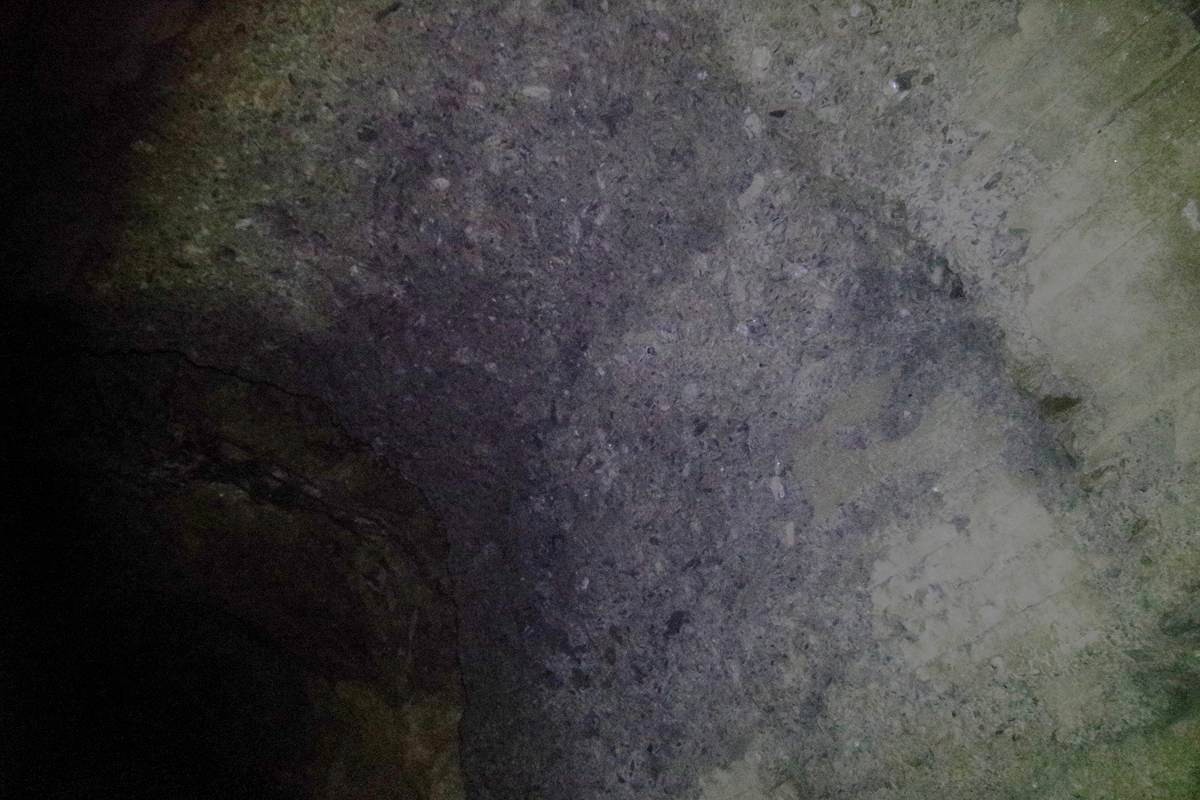
�\�\�������܂��A�R���N���[�g�ɂ�镢�H���s��ꂽ��Ԃł������B
�����A���x�̕��H�́A��قǂ̕��H�Ɣ�r���āA����詓����Ƃ͎v���Ȃ��قǃ{���{���ɏ���ł����B
�{�H�Z�p�◧�n�����ɗD�Ȃ��Ɖ��肷��A���炩�ɍ��x�̕��H�͌Â��������B
�ŏ��̉摜�͓V�䕔������i�s���������̕ǂ̗l�q�ŁA�`�F���W��̉摜�͐i�s�����E���̕ǁA���ǂ̕������B
�R���N���[�g���ɖ��ߎE����Ă����ؔ��I�o���Ă���̂��A�\�ʂ���K�͂ɔj���������ʂł���B
�B�����߂ł́A�X���̂����ł��̂悤�ɍ����j�ꂽ���H�����邱�Ƃ����\���邪�A�����ł͒������B
��͂�A�����̕��H�͏ꏊ�ɂ���Ď{�H�������傫���قȂ�C�������B

���̉摜�́A�{���{���ɂȂ��Ă��镢�H������U��Ԃ��ĎB�e�����B
�_���̕����ɃR���N���[�g�̊������Ă�����B
�V��Ɋ������Ă��Ȃ����������邪�A������ė������̂�������Ȃ��B�����ɏ����ȃR���N���[�g�Ђ���ʂɎU����Ă����B

18�F11�@�i����14����j�@�s���茻�ݒn�t�@
�Ăѓ��������v��ԂɂȂ����I
�ēx�̐��v�͐h�������ł��������A����ɂ��詓����̌��z�̃J�^�`���������Ă����B
�����炭����詓��A�T�^�I���q���z�ɂȂ��Ă���B�����ɕW���̃s�[�N�i�T�~�b�g�j�������āA���B���������ĉ����Ă������̂�q���z�Ƃ����B
��U�͈����Ă������ʂ��Ăь���ꂽ�̂́A���������̃T�~�b�g���z���āA�o���ւ̉����֓��������Ƃ��������Ă����B
�T�~�b�g���S���̒����ɂ���m�͂Ȃ����A�������肷��A�c���120�`150m���x�ł��낤�B���ς�炸�o���������Ȃ����c�B
�����āA���̏̑傫�ȕs���Ƃ��āA�c��̌��z�@���ɂ���āA�o���֒H�蒅���O�ɐ��ʂ������Ȃ��[���ɂ܂Ŋg�傷��댯���������B
�c�c�����������͋F�邵���Ȃ����c�c�B

18�F12�@�i����15����j
�K���ɂ��āA���ʂ̏㏸�͊ɂ₩�ł������B
���̃y�[�X�ł���A��ɏo�����������ȋC�����邪�A�����S���o���̌��������Ȃ��i������ɂȂ��Ă��܂�������H�j�̂��A�ƂĂ��s�����B
�W���u�W���u�W���u�W���u�Ɠ��₩�ȉ��������ɔ������Ă��邪�A�ʂ����Ă��̉��͏o��������o����Ă���̂��낤���c�c�B
�i�`�F���W��̉摜�j�₪��3�x�ڂƂȂ銪�����Ă�����ꂽ�B�i���̃{���{���̕�����������4�x�ځj
�������Ă̑��݂��A�Ȃ�Ƃ����������B
�����O�̌������Ĉ��S�������C�����ƁA���̗₽�����瓦�ꂽ���C��������A����Ƀy�[�X�𑁂߂ăo�V���o�V�������B
18�F13�@�i����16����j
�����ŏ��߂ē�����B�e�B
���R�Ɗ������Ă�ꂽ��Ԃ�Ƀo�V���o�V�����A�ђʂɑ���s������҂����ɂ��Ă���B
���̉����������s�ł������������ԐL���A�����炭��������200m���z���āc�c�B

18�F14�@�i����17����j
�����c
�c�c�c�c�����ǂ��c�c
�܂�ŐΒY�̉n���̈ł��ÏW�����悤�ȍ������̂��A�B���̍s������ǂ��ł���̂��������B
�����ŊO�������Ȃ������킯�ł���c�c�B

����́A�u�ϔO�v���c�c�c�B
�Ȃ�Ƃ�����Ȃ��ƂɁA詓��̓��ǂ���镢�H�����邹���ŁA���Ղ�����]�I�ȕǂɌ��т��Ă���B
�O�̗��Ռ���͑f�@�肾�����̂ŁA����Ȃ�g�V�䗠�̋�ԁh����A���Α��֍s�����̂����c�B
���H������詓��́A�����˂��j�闎�Ղ��N���Ă��܂��ƁA�f�@��̏ꍇ�ȏ�ɒʂ蔲���Â炭�Ȃ邱�Ƃ������Ƃ����A���Ԃ�I�u���[�_�[�����m��Ȃ��悤�Ȍo���������݂���B
���悢�搅�[���[���Ȃ��Ă��Ă��āA�o�����߂��悤�ȋC�������̂����A�����܂ł��c�c�B
�c�c
�c�c�c�c ��H
���͔����Ă���B
�ꌩ����ƌ��Ԃ̂Ȃ������ȁg�����y���̕ǁh���������A�ǂɋ߂Â��ɂ�A�j�ł镗���������B

���������ȁc�c�B
���̈ʒu�ɁA���̔����錄�Ԃ�����悤���B
���S�ɕǂ͂��Ă��Ȃ��悤�ł���B
���y�̎R�ցg�㗤�h���A�K���K������₷���ǂ����Ԃ܂ł悶�o��B
18�F15�@�i����18����j�@�s���茻�ݒn�t�@
�u�߂����Ⴑ���������Ă���I�v
�u�ђʎ��̂͂��Ă�I�v
�u�����������Ēʂ�Ȃ��I�@�c�O�I�v

18�F16�@�i����19����j
�V�䂷�ꂷ��ɕ����������������錄�Ԃ�����A���̉��ɋ������Ă���C�z���������B
�����炭�o�����߂��͂��B
�����A����͐l�Ԃ��ʂ蔲�����錄�Ԃł͂Ȃ������B
�܂��P���ɋ������A���̐����n����������o�Ă��邵�A�����ׂ͔j�ꂽ�R���N���[�g�̓V��ŁA��ʂ̊��I��s����ɐςݏd�˂Ă��邵�B
�N���A����Ȃ����Ĉ������邩���������V��ɁA�i��ŋ��܂낤�Ǝv�����낤���B
�u�c�O�I�v�Ɠf���̂Ă�悤�Ɍ������̂��A������[�������邽�߂̔��j�ɂ������ł������B

18�F18�@�i����21����j
�������́A
�[���Ɏ��s���Ă��܂����I
�����Ȃ��o���Ƃ������邵�A���̌o�������ɉ\�������������Ƃ��������B
���ʁA�l���œ���������K�̌��܂ő�ʂ̐����Ɋт���Ȃ��痼������A���Ԃ����߂Ă������I�̗���I��ŋ̉��֕�������A��O�֗������肵�āA���Ȃ̐l�ԊђʒʘH�̍쐬�ɋ���ł��܂����B
���I�������Ƃ͒v���I���Ղ̈������������\�����͂��Ȃ��炠�������A�o����A����ɂ���R���N���[�g�̕ǂ͌ł��B�����ɐ����ԁA����a���錈�f�������B
�������Ė�2����ɁA���̎ʐ^�̂悤���Œ���̐l�ԊђʒʘH���o�����������B

���ׂĂ̊����������Ƃ����B
���܂���30�b�Ԃ����ʘH��ۂ��Ă���B
�l�ԓ˓��I
�@�˔j�Ȃ邩�I�@�嗎�Ղ̏���詓�

2024/2/2 18�F20�@�i����23����j
�����͂�2�`3���̎��ƂōL�����g�l�ԊђʒʘH�h�́A���̐g�̂��ʂ蔲������ŏ����x�̃T�C�Y�ł������B
������ɂ��A�r���Őg�̂������|�����Đg�������Ƃ�Ȃ��Ȃ邱�Ƃ������Ă͂Ȃ�Ȃ����A����K�v�ȏ�ɑ傫�����邱�Ƃ́A�R���őS�g�т���G��ɂȂ�Ȃ���̌@���ƂɎ��Ԃ������邾���łȂ��A�������s����ɂ��郊�X�N������������A�����̐g�̂��ǂ̃T�C�Y�̌���ʂ蔲�����邩�Ƃ������Ƃ����n�Ől��{�ɏn�m�����A���Ȃ�ł̖͂{���ɃM���M���̃T�C�Y���U�߂��g�ʂ��̂킴�h�ł������B
�����Ď��ۂ́g�ʉ߁h�ɂ������ẮA�w�����Ă���U�b�N�ƁA���ɕt�����E�G�X�g�o�b�O�A������t�J������3�_���������ׂĊO���A���̓����Ɏc������ԂŁA�l�̂����Ŋђʂ��邱�Ƃ����݂��B�����ђʏo�����甽�Α�������L���Ă����3�_���������̂ł���B���ꂪ�ł���ʒu�Ɋe�ו���u�����Ƃ��d�v�������B�i���̂Ƃ��A�Ԉ���Ă���ɉו����ђʌ��ɒʂ��Ă͂����Ȃ��B�����������ǂ��Ȃ��Ă��邩������Ȃ���Ԃł́A��������\�����[���ł͂Ȃ��B�j
�[�ċz�����Ă���A���j���̎p���ŁA�㔼�g���猊���荞�B
�g�̂ň�ԑ����͍̂����̈ʒu�Ȃ̂ŁA�������ʂ蔲������Ηǂ��̂����A�r������W�ŋ��̕ӂ���������炢��������A�����ʂ������ʂ��̂���{���B�t�ɁA����������̂ɖ�����˓�����ƃ}�W���o���B
�܂��A�ђʌ��͋|�Ȃ�̌��z�ɂȂ��Ă���̂ŁA�㔼�g�����̌��������ɏo��ƁA���R�Ɠ������ɂ��Đi�ނ悤�ɂȂ�B
���̎p���͋ꂵ�����A���������o�������ďł邪�A��Âɓ����悤�ɓw�߂��B�����ŕςɑ����o�^�����ĉE�̊��I���ςݏd�Ȃ��Ă��镔���ɂԂ���ƁA�����댯���������B�����Ɗђʌ������܂郊�X�N������B
�͂��߂͌��Ԃ̌������Ɍ����邾�����������A�ǂ̂悤�ȍL����������Ă��āA���̐�͒ʂ��Ă���̂��B
���̍ł��d�v�Ȗ₢�̓������A���̓J�����������Ȃ���ԂŒN���������m�o�����B
���̓����́A�K�b�c�|�[�Y�������I�I�I
�S�ɃK�b�c�|�[�Y��������܂܁A�w�߂đ��₩�ɁA���T�d�ɁA�l�ԊђʒʘH�����S�ɒʉ߂����I
�ʉߌ�A�܂��̓J��������������B
�������������B��B
�p�V���I

18�F22�@�i����25����j
�o���ł���!!!
�����X詓��́A�����ɒv���I���x����2�����̑嗎�Ղ��Ă������A����ł��Ȃ��A�l���R�n���z���镗�ƁA���Ǝ��̐l�̂�ʂ��������I�I�I
����͌����I�ɁA�����l�ނōŌ�̏����X詓��ʉߎ҂ɂȂ邩���m��Ȃ����낤�B
�N���c���͂��Ă��Ȃ����ԈႢ�Ȃ����Ƃ��Ă͑��݂���A���̃g���l�������܂�Ă��������܂ł̑��ʉߐl���c�c�A���̐����ɓ������g�L�O�ԁh�������l�������\��������I
�����łȂ��Ă��A����̎��ԓI�ɂ��肬�肾�����T���̒��ŁA�ǂ��߂�ꂽ�����詓��̊ђʐ����́A��C�ɃS�[���ɑ���������t�@�C���v���C����������A���������g����C�ɉ����Ă����I
������������������I�I�I�I

���ꂪ�U��Ԃ��Č����ђʒʘH���B
�V��̍L���͈͂��j��Ă��āA��������c��ȗʂ̍����������ꍞ��ł���B
������łȂ��A��ʂ̐����ǂ̎��鏊���痬��o�Ă���A�����炭�n�������ɂ������Ă���B�n�������Ɉ����j�ӑт̂悤�ȏꏊ�Ȃ̂��낤�B����ꍞ��ł����������n���ɖ���ׂ��ꂽ�悤�ȕ��������Ă��邵�A���{�I�ɒn�����������ł������B
�����炭�A�R���N���[�g�̕��H�̊O���ɂ͗��Ղ����y���̗e�ςɑ���������o���Ă��邾�낤���A���H�����r���[�Ɏc�����������ŁA���̋��ђʒʘH�Ƃ��Ă͎g���Ȃ������B�������Ŕ��ɋ����ʉ߂�]�V�Ȃ����ꂽ�킯�ł���B

���ɂƂ��Ă̗D�揇�ʂɏ]���āA�J�����A�E�G�X�g�o�b�O�A�U�b�N�̏��Ԃʼnו�����������B
�ʐ^�́A�Ō�ɉ�����ꂽ�U�b�N���B
�y���~��̒n�����V�����[�̉��Ɉ�Ԓ������u���ꂽ���ʁA�[���̌�݂����ȔG����ɂȂ��Ă���A�����֗���O�Ɋ��ɐ��v�ł�����G�ꂾ�������̉����g�ƁA���̒ʉߒ��ɂ��������G�ꂽ�㔼�g�ƁA�ǂ������낢�ɂȂ����B�i�摜�͈◯�i�̂悤�����c�j

18�F23�@�i����26����j
�߂�����[���I
�����ԋ߂Ɍ����Ă���o���Ɍ������āA�����͍Ō�܂ʼn�����z�������Ă���B
���̂��ߍŌ�܂Ő��[�������Ă����悤���B
�c�肨���悻20m�ŁA���݂̐��[�͌҂̏�A�ҊԂɔ��낤�Ƃ����Ƃ���B
�E�G�X�g�o�b�O�ɂ̓E�H�[�^�[�o�b�O�𗘗p���Ă���̂Ő��v���Ă��ꉞ���C�Ȃ͂������A�O�̂��ߌ��|���ɕύX����B
�����܂ŔG�ꂽ��A�����ČҊԂ̊��������炷�闝�R���Ȃ����A���������������p���Ȃ��̂ŁA�ň���܂ŐZ����o��őO�i����B
����20m�Ȃ̂��I�@

�����Ԃ��Ȃ�Ă��蓾�Ȃ��I
�����ђʌ��̉c�Ƃ͏I�����܂����B�X�ł��B

18�F24�@�i����27����j
���ӂ��ӂ��ӂӂӂӁc�c
�X���݂����ȗ₽���n����`�܂ŐZ���������́A���ĂȂ��̂ɏ��Ă���݂����ȑ����ċz�ɂȂ�Ȃ���A�ł�����ς���S�����ď��Ă����C�����邪�A�n��ƒn��̋��ڂ̖���܂��Ȃ����낤�Ƃ��Ă���B
���ݎ������݂�Γ��R���������A�O�͂�������邾�����B
�C�ۑ䔭�\�̓��v�������30���߂��o�߂��Ă����B
�Ȃ���詓�����30���߂��������̂ł���B����ȂɊ|����Ȃ�Ďv�������Ȃ������I�@
�ǂ��Ă��Ĉ����Ԃ��Ă��A����ȂɊ|�����敁�ʂȂ�B
��������������B
�����n����痤�ɏオ���Ă���p�������l�Ɍ����Ă�����A����͊ԈႢ�Ȃ����̐��̂��̂Ǝv���ʋC�F�̈����������낤�B

18�F25�@�i����28����j�@
�����X詓��A�����B���I
�������A�O�֏o���̂ɁA���|�[�g�́g�w�i�F�h�𖾂邭�͏o���Ȃ��ȁi��j�B
�n���̈ł��O�֘A��o���Ă��܂����݂����Ȗ��邳���B
�U��Ԃ�B���ł��邪�A�����Â����āA�������ɓ��H�̎������L�^�����Ƃ͌p���s�\���Ɣ��f�����B
���������̃G���A�ł̒T���𑱂���v��Ȃ̂ŁA�����܂����Ԃ�����āA���̐�͖��邢���ԂɍĖK�E�ă��|�[�g���邱�Ƃ�S�Ɍ��߂��B
�����炱�̌�̓��e�́A�����̗\���I�Ȑ�s�T���ł���B�L�^�͍Œ���ŁA�������S�ɎԂ֖߂邱�Ƃ�D�悷��B�i���̂��ƊX�֍~��ĐH���B���A�Ԓ����̐Q���֍s���āA�ȂǏ��X���l����ƁA�ƂĂ����Ԃ������Ă���j
���ɏオ�������́A�����ɃU�b�N�����낵�A詓��˓�����Ɏd�������o�R�C�����o���āA�o�X�^�I���ő���@�����B
�ꍏ����������G��Ɨ₽������~���o�����������̂����A�`���牺�̒��߂����ׂĐ��ɐZ�����Ă����̂ŁA����@���Ă����܂�Ӗ��͂Ȃ������B����ł��A�����������������銣�����C���c�����̂́A�傫�Ȑ��ʂł͂��������B
���̈�A�̐g�x�x�ɖ�10�����₵�A18�F34�ɑO�i�ĊJ�̏������������B

詓����̏��܂Ƃ߂��ȒP�Ȓf�ʐ}���쐬���Ă݂��B
�S����300m�̓����́A���H�̂��镔���Ƒf�@��̕��������X���x�ŁA�����炭�����ɃT�~�b�g�����q���z�ł������B
���B���ɑ͐ς����y���ɂ���Ēn�����������~�߂��A���B���t�߂����v���Ă���ق��A����2�����ɋK�͂̑傫�ȗ��Ղ�����A���ɐ������̗��Ղ͒ʉߍ���ȏɂȂ��Ă����B

�g�x�x�����Ă��邤���ɁAGPS���@�\���āA���ݒn�����������B
���ݒn�ł��鏉��詓������i�{�쑤�B���j�́A���O�̗\�z�ʂ�A2��ڃg���l�������̂���J��50m���荂���n�_�ŁA����������150m�قǗ���Ă����B
�`�F���W��̉摜�ł��鏺�a32(1957)�N�Œn�`�}���ƁA詓����o�����́A�֍s���Ȃ��獂�x�������đ�X��̐�ׂ�߂Â��Ă����悤�ɕ`����Ă���B���̋�������H���āA�Ƃ肠�����u�ԃf�|�v�n�_�֑��}�Ɍ��������Ƃɂ������B
�����܂Ō��������Ă��Ȃ������C�����邪�A���͂��̃��|�[�g�̃X�^�[�g�n�_����قNj߂�������ɎԂ��f�|���Ă����B
�Ȃ��A�������_�ł��鎩�]�Ԃ��A�g���l���̔��Α��ɒu������ɂ��Ă��邱�Ƃ��Y��Ă͂��Ȃ��I
�����̒T���̂��߂ɂ��A���Ӓ��ɃA���͉�����ɍs���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�i�ʓ|�ő��炵���������A���]�Ԗ������Ă��̒Z���Ԃł̒T���͓K��Ȃ��������A�܂��ǂ��撣���Ă�����詓������]�ԓ����Œʉ߂��邱�Ƃ͏o���Ȃ������̂ŁA���]�Ԃ͐ӂ߂��Ȃ��B�j

18�F35�@�O�i�ĊJ�I
���C�g���Ȃ���ΑO�������Ȃ������A��قǂ��������Ƃ���A���������͖������߂Ė��邢���ԂɍĖK���悤�Ǝv���Ă���B
�Ȃ̂ō��ׂ͍����ώ@�͔����ŁA�ő��ŒE�o���悤�Ǝv���B
�Ƃ肠�������܌��Ă���͍̂B���O�̋������̗l�q�����A����o�������H���G�炵�Ă���B
��R�̊��I��|���U����Ă��āA���S�ɔp���̏�Ԃ��B��k���̍B���O�Ɠ����悤�ȘH�ʏ�Ԃł���B
�n�}���������A�Ԃ��f�|���Ă���n�_�܂Œ��������Ŗ�300m�A���x�����}�C�i�X��60m���炢�ł���B���Ȃ�߂����A�������ɓ������čs���̂͊댯���낤�B

18�F37
�B�����班�������ƁA���ɎR�A�E�ɒJ�̍��R�E�J�ƂȂ����B
����͗\�z�ʂ�̓W�J�ŁA�E�̒J�̉�50m�̈ʒu�ɂ�2��ڃg���l���̐����������J���Ă���͂����B�Â��Č����Ȃ����B
�������͂��Ȃ�r��Ă��邪�A���`�͑N�����B

18�F40
��ꂪ�I�o����悤�Ȍ�������Ԃ͂��܂葱�����A�l�H�тł���X�M�̐X�ɓ������B
�����Ȃ�ƂȂ����їp��Ɠ��H���ۂ����͋C�ɂȂ������A���̂Ƃ��닌������H��Ă���͂����B
�܂������ɐ��̋�ɂ͎c�Ƃ�����A���̃V���G�b�g�����z�I�ɕ����яオ�点�Ă����B�����������߂Ċӏ܂���C���͂Ȃ��A�e�ڂ�U�炸�ɐi��ł������B

18�F41�@�s���ݒn�t
�B������300m�قǁA���邳������ז��������M����i�ނƁA��قǂ���̃X�M�A�ђn���\���ł��������̂悤�ɁA1�{�̗ѓ��A���邢�͍�Ɠ��ƌ��������B
���̓��͉E�������}��ŁA�������ȒP�ȃ`�F�[���Q�[�g�ɂ���čǂ���Ă����B
�܂�ŋ����������K���[�g�ŁA���E�̓��͎}�̍�Ɠ����ƌ������������A�����ɂ͋������ɂ͂Ȃ��^�V�����Q������A���炩�ɉ��E�ƌq�����Ă���悤�������B�����I�ɂ����炩�ɁA�E�̓����s�������������Ԃ̂���ꏊ�։��R�ł������������B�������͊�{�I�Ɍ��z���ɂ₩�ŁA�Ȃ��Ȃ��Ԃ�������։����Ă����l�q�������Ȃ������̂ł���B
�������̒T���͖����Ɏ����z�����ƂƂ��āA���͖��킸�E�̍�Ɠ��i�ނ��Ƃɂ����B
���������痣�E�B

18�F44
�^�V�����������~���ꂽ�������́A�}��&�Â�܂�ň�C�ɍ��x�������Ă����B
���炩�ɋ������ł͂Ȃ����`���������A�����ɉ������B
�����Ă�����x�`�F�[���Q�[�g�݉z���Ă܂��Ȃ��c�c

18�F47�@
��X�쉈���̉E�ݒ�����ʂ�������X�������i�ѓ��������j�ɉ��蒅�����B
�����͎Ԃ��f�|�����n�_����100m���炸�̋Ɏ��ߋ����ł������B

�������ۂɕ����Ċm���߂悤�Ǝv�����A�����炭�{���̋������̃��[�g�́A���̒n�}���Ԃ��_���Ŏ������悤�Ȍo�H�ł������Ǝv���B
������X�������i�ѓ��������j�̈ꕔ�́A��X�g���l���̋��������ė��p���Ă���̂��Ǝv���B
�܂��A�s���N�̎����̈ʒu�ɂ͂悭�������ꂽ��ƘH������A���͂�����g�����ƂŁA�啝�ɉ��R���[�g��Z�k�ł����̂ł������B

19�F36�@�s���ݒn�t
���ꂩ���50����A���͎R���ɒu������ɂ��Ă������]�Ԃ���������B
���̃��|�[�g���̒T���̏��H�����x�͎ԂłȂ���悤�ɑ������̂ł���B
2��ڃg���l��������Ď��]�Ԃ����ɍs���I���������������A�����ɍ����t�F���X�����莩�]�Ԃ��z��������̂��ʓ|���Ǝv�����̂ƁA�P���ɕ����̂ɔ��Ă����̂ŁA�Ԃ𗘗p�����B�i���̍ہA�y�����̗��Βn�_�z ���Â����ŃG�N�X�g���C����ʉ߂�����̂͊̂��₦���j
���Â����ŃG�N�X�g���C����ʉ߂�����̂͊̂��₦���j
�������āA�T���J�n���_�ł����������Y���Ă�����X�g���l���̋������T���́A�Ă̒�I�ՂɎ��Ԑ���}�����A�Ƃ肠�������̍ő�֖̊�ł���œ_�ł�����詓��{�̂ɂ��ẮA�ǂ��ɂ������ɂ��A���̐g�̂�P�����ނ��Ƃɐ��������̂ł������B
�����֑����܂��B