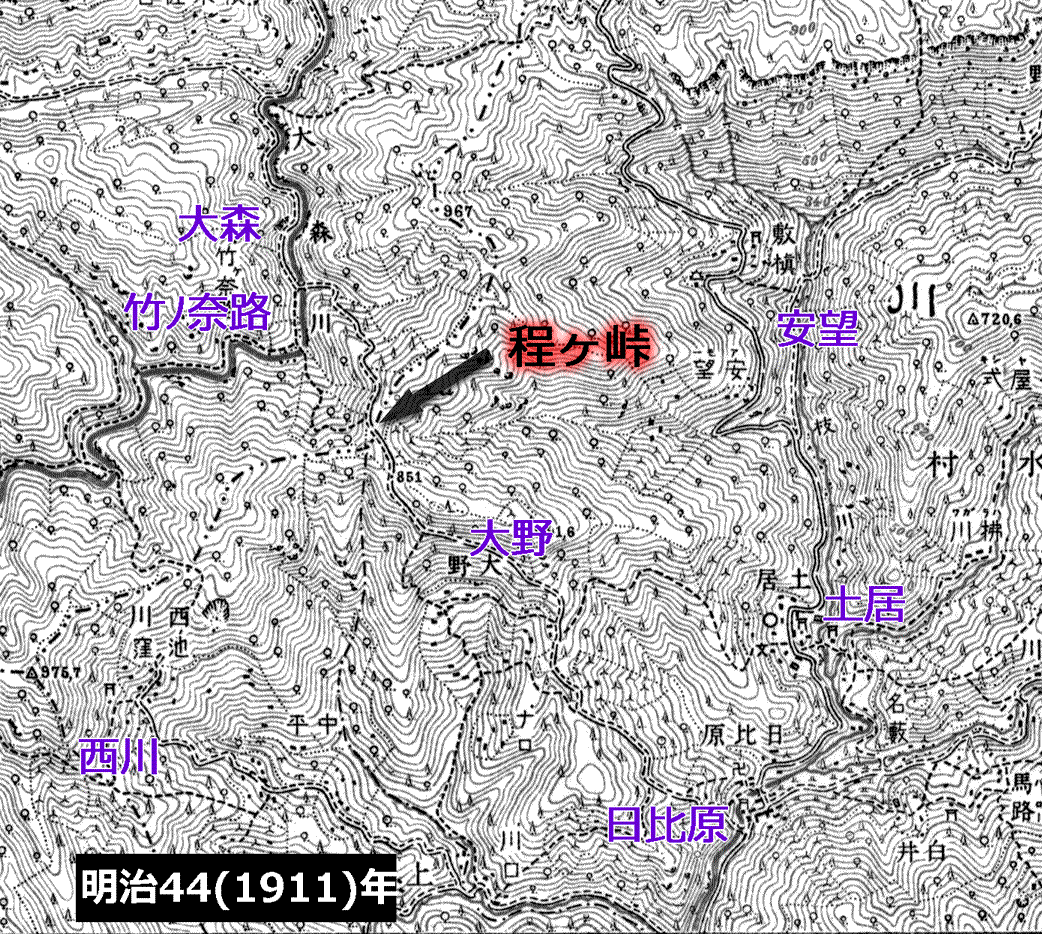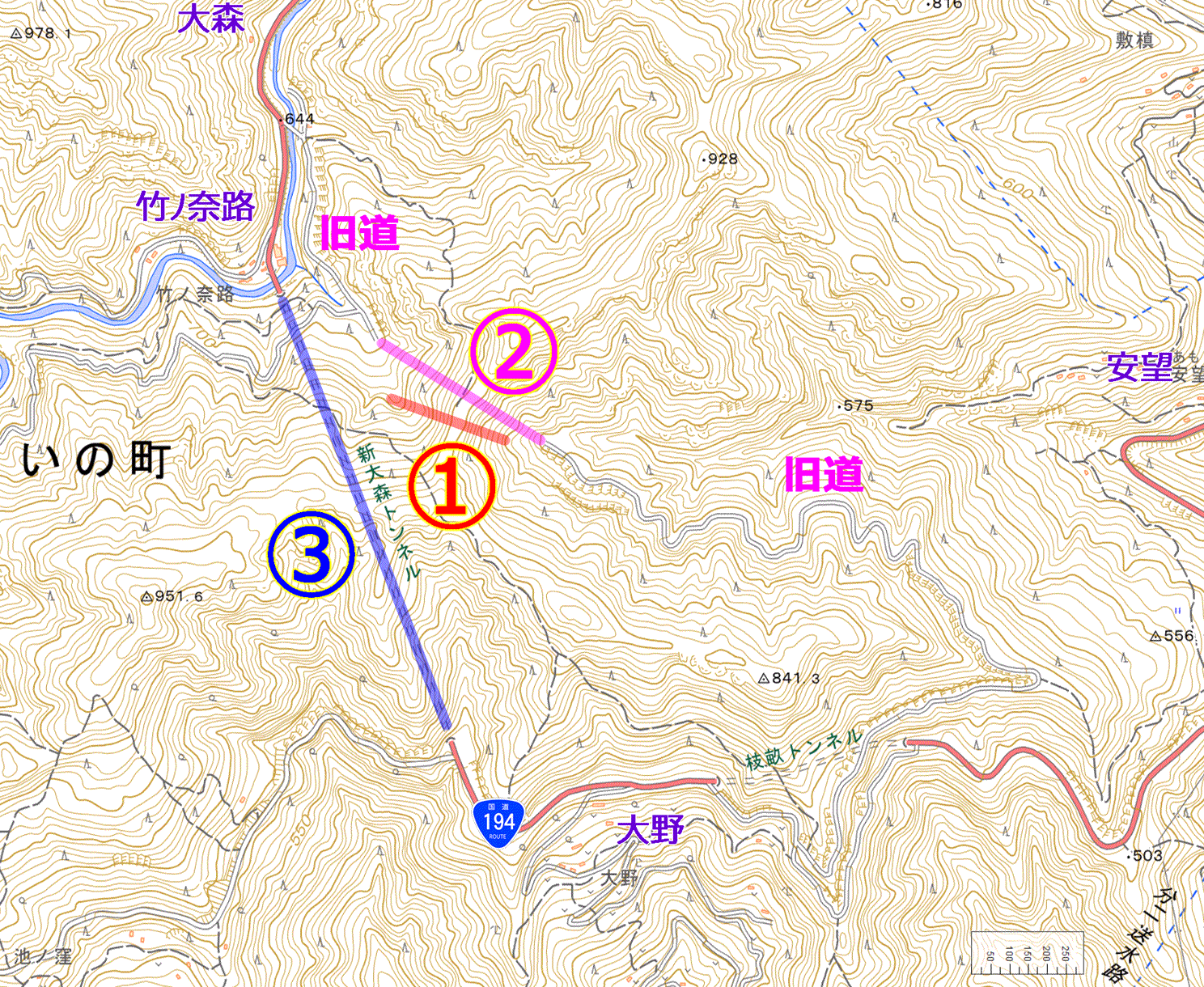国道194号は、四国の中央部を横断し、太平洋岸の高知県高知市と瀬戸内海に面する愛媛県西条市を連絡する全長約89km(実延長77km)の一般国道である。
起伏に富んだ四国山地を正面から横断する山岳路線であり、県境の石鎚山脈を越える寒風山トンネルが昭和39(1964)年に開通したことで、土佐中央部と東予地方が初めて車道によって結ばれた。
現在ではよく整備され交通量も多い路線であるが、開通までは長い産みの苦しみがあり、四国中央産業開発道路や土予(予土)連絡道路といった多くの異名は、古い苦闘の証しだ。
今回のテーマは、同路線の中では寒風山トンネルに次ぐ難所として、やはり長い苦難の歴史を歩んだ「大森トンネル」の旧道群である。
国道194号のうち高知県内の実延長は全て吾川郡いの町に所在している。
いの町は平成16(2004)年に吾川郡伊野町(いのちょう)、同郡吾北村(ごほくむら)、土佐郡本川村(ほんがわむら)の1町2村の合併により誕生したものであるが、大森トンネルが貫く峠は、このうち吾北村と本川村を隔てたもので、伝統的な吾川郡と土佐郡の境であり、地形としては紀伊水道に注ぐ四国最大水系である吉野川水系と、土佐湾に注ぐ仁淀川水系を隔てる規模の大きな分水界である。
前述した寒風山のトンネルが貫通して東予地方とも結ばれるまで、本川村は吉野川水系の最も奥の袋小路に閉じ込められた終点であり、県内においても特に交通不便な地域であった。
それゆえ最初の大森トンネルによって車の出入りが可能になるまで、この標高850mほどの峠の名は、生来のものよりも、本川村の僻性を象徴する“異名”を以て知られていた。
辞職峠。
また出た〜〜〜!!
ってなった人もいるかも知れない。全国各地に辞職峠、あるいは辞職坂のような異名の峠がある。
いずれも由来は単純で、その先にある土地への赴任を命じられた役人(教師の場合もある)が、余りの道の険しさに怖じ気付き、職を辞して逃げ帰ったという物語に由来する。
良くある異名ではあるが、昔の人たちほど役人を軽々しく扱いはしなかったから、これは決して易い名付けではない“信頼の置ける難所地名”である。
私はいつか、全国の辞職峠、辞職坂をマッピングし、どれが真に一番辞職したくなるかを検証したいと思っている(笑)。
四国から遠く離れた秋田にいる私が、この峠のことを知ったのは、趣味と実益を兼ねる全国の“峠の本”集めの成果であった。
平成3(1991)年に高知新聞社が刊行した『土佐の峠風土記』(山崎清憲著)を数年前にネット通販で手に入れて読んでいると、「程ヶ峠(ほどがとう)」のページに、この辞職峠のことが書いてあった。
吾北村日比原から、本川村大森に越す境界鞍部に「程ヶ峠」という峠がある。峠の下方を大森トンネルが貫通しているので、大森峠とも呼ばれているが、“辞職峠”の異名もあり、この方がポプュラーな峠名として、一般に知られている。
辞職峠の由来については、高知から本川村に赴任するお役人が、つづら折りの山道と、峠の高さに驚いて「このようなきつい峠を上り下りするのは大変だ、やめたがまし」と、いわれるようになったので、その名がある。山(田舎)での勤め人といえば、学校の先生、警察の駐在さん、営林署の主任さんあたりだが、本川村長沢に小林区署(営林署)が置かれて以来、署員が峠越えのつらさを表現して、呼びはじめたのではないか、ともいわれている。
『土佐の峠風土記』より
……と、このようにずいぶん具体的に、辞職峠の異名の由来を解説してくれている。
また、『角川日本地名辞典』の本川村の項にもわざわざこのエピソードが登場しており……
大森地区の開発につれて戸中道に代わって整備されてきた大森から程ヶ峠を経て日比原に至る牛馬道は、営林署の役人があまりの険路に職を辞して帰ったということから辞職峠といわれたが、同年(昭和10年)大森トンネルが開通するなど改修され、同37年には国道194号に昇格した。
『角川日本地名辞典 高知県』より
……と、やはり営林署の役人が命名した異名であるという説を採りつつ、昭和10(1935)年に大森トンネルが建設されたことも述べている。
ここで再び『土佐の峠風土記』の記述に戻るが、この程ヶ峠の近代化を実現した大森トンネルについて、次のような記述がある。
大森トンネルの変遷は、昭和10年に“初代”のトンネルが抜け、第2次トンネルは、昭和39年に貫通。現在の新トンネル(1184m)は、昭和53年に完工している。
『土佐の峠風土記』より
このように、昭和時代に3世代のトンネルが掘られたことが出ており、土地鑑のない私を大いにそそった。
それゆえ、いつか四国へ行くときには探索をしようと心に決め、その後、私の生涯2度目となる2024年2月の四国遠征中に探索を試みた。
今回報告するのは、その模様である。
探索の動機が出来たあと、実際にどのような行程で探索するかの検討を、歴代の地形図を入手して行った。
皆さまにも歴代の地形図に描かれた3世代の大森トンネルの変遷を見ていたきたい。
I
明治44(1911)年
| 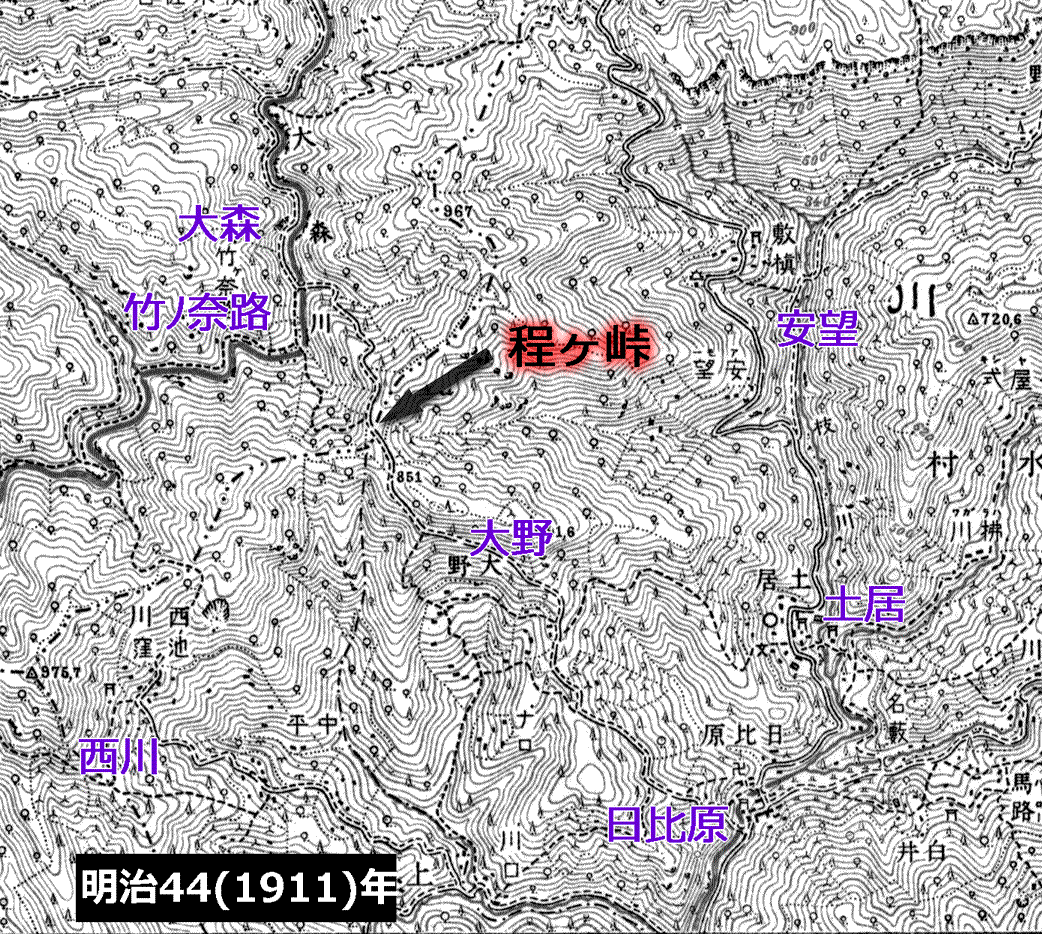
|
|---|
II
昭和32(1957)年
|
|---|
III
昭和43(1968)年
|
|---|
IV
昭和53(1978)年
|
|---|
V
地理院地図(現在)
|
|---|
5枚の地形図を古い方から見較べてみよう。まずは最も古いI,明治44(1911)年版から。
地図に峠名の注記はないが、図の中央を通る「荷車の通ぜざる里道(連路)」の記号が、辞職峠の異名を持つ「程ヶ峠」である。
右下の「日比原」から尾根伝いに高度を上げ、「大野」の在所を経て頂上へ。越えると短距離で吉野川源流の一つである大森川沿いの本川村「竹ノ奈路」集落へ達する一連の峠道だ。
峠の表裏で河床までの高低差が大きく異なる典型的な片峠と見え、それだけに外から本川村へ入ることは、思わず職を投げ出したくなるほどキツかったのだろう。
II,昭和32(1957)年版には、「府県道」を意味する太い二重線の道路が大きく迂曲しながら峠へと伸びている。鞍部の直下をトンネルで越えているが、これが昭和10(1935)年竣工と伝わる第①代の「大森隧道」である。
III,昭和43(1968)年版には早くも②代目のトンネルが登場する。昭和39(1964)年竣功の「大森隧道」で初めて名前の注記もある。またこの図には①の隧道も描かれているので、位置関係が分かりやすい。
IV,昭和53(1978)年版では矢継ぎ早に③代目にして現行であるトンネルが出現。昭和53(1978)年竣工とされる「新大森トンネル」だ。この図には②の旧隧道や前後の旧道は描かれているが、①の旧旧隧道は消えている。
V,最新の地理院地図には現行である③代目のトンネルしか描かれていないが、各図から引き継いだ②旧隧道、①旧旧隧道の位置もハイライトで示した。
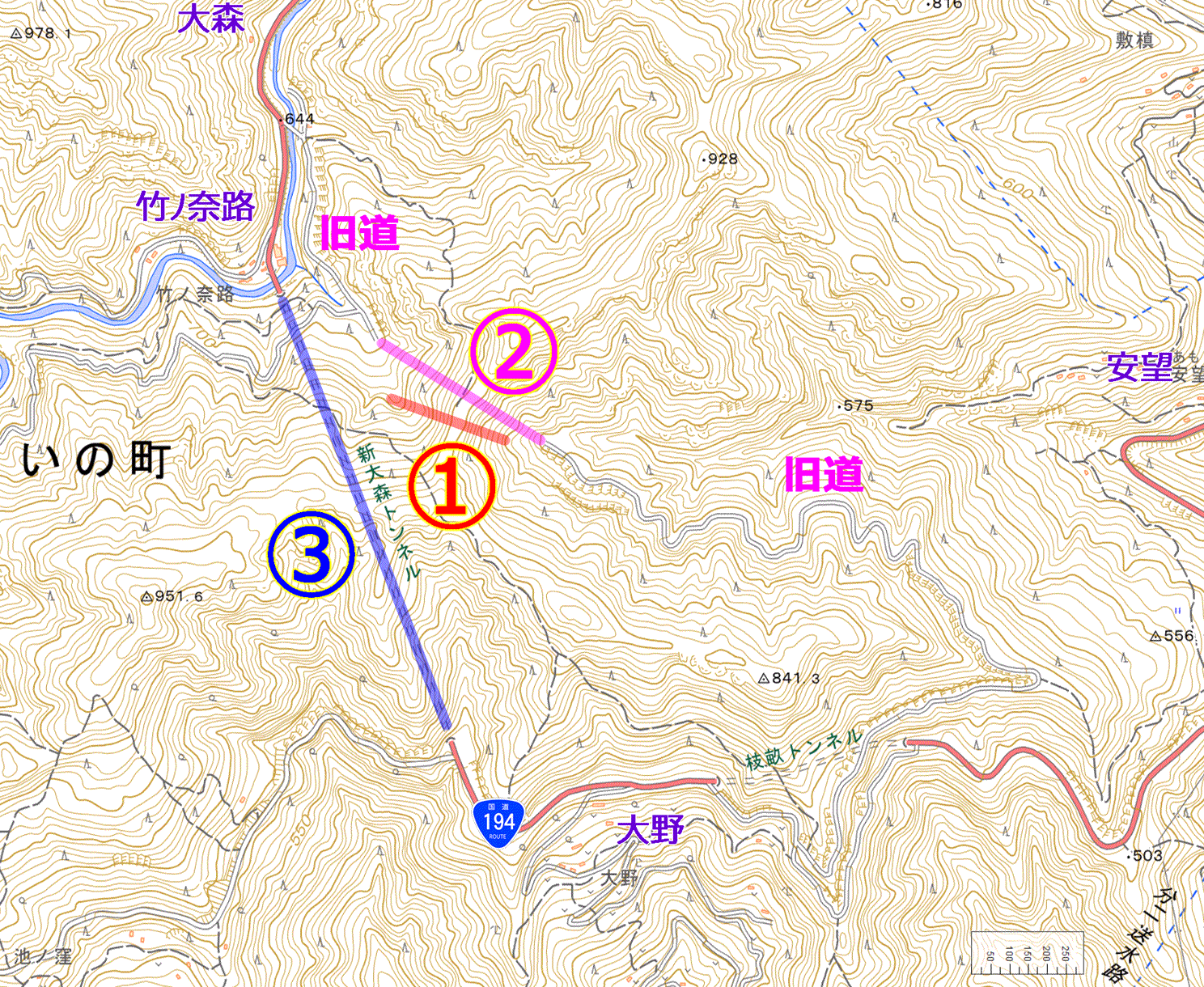
今回の探索のターゲットは大森トンネルの旧道および旧旧道(もちろん各隧道を含む)である。
探索の流れとしては、現道と旧道が分れる地点から自転車で「スタート」して旧道を約3.8km辿ると、最新の地図では消えているが、②代目トンネルの東口に辿り着くはずだ。
辿り着いたら、周辺の第①代トンネルも捜索・探索を行いたい。
①か②のどちらかを通り抜けられれば、そのままトンネル西側の旧道も探索しよう。
以上のような大まかなプランを以て……
辞職回避への旧道探索開始!
序章: 新大森トンネルを潜って旧道を目指す

2024/2/27 16:23 海抜630m
2世代分の旧トンネルを目指す前に、実際の探索の時系列に沿って、3世代目となる現トンネルの風景を軽く紹介しておこう。
旧道探索をすべく、私が車から自転車を下ろし出発したのは、上の図の「現在地」の位置、すなわち現国道と旧国道の西側(本川側)分岐地点である。
ここから現トンネルを潜って旧道の東口を目指す。
ところで、上記の時刻表示は、これから2世代もの旧道探索を始めようというには遅すぎるように見えるかも知れないが、
マッタクソノ通リデアリマス……。
遅すぎるかもしれないなと内心でも思っていたが、遠征中毎日いろいろな探索を強行軍に詰込んだ結果、たまたまこの時刻になった。
これでも、明るいうちに探索を終えられる勝算が全く無かったわけではなく、克服すべき高低差の総量や、グーグルアース(航空写真)でおおよそ見ることができた旧道の路面状況などから、自転車を上手く駆使できればイケル可能性は高いと判断していた。
というわけで、探索が全般的に駆け足気味になることを予めお断りしつつ、スタート!

これが出発地点の風景だ。
絵に描いたような峠前の新旧道分岐地点の風景で、左の橋を渡る道が旧道だ。が、ここではまず右の現道へ行く。
旧道が峠を越す旧トンネルは、写真正面の奥まって見える谷の中に旧旧トンネルと共にあるはず。今回は、背撃作戦をとる。
また、この段階では特に旧道に封鎖されている様子は見られないが、これは旧道の行先が峠の他にもあるせいだろう。大森川の上流にある大森川ダムは、この道が進入路である。
なお、左端に見える標柱は大森橋バス停で、県交北部交通の路線バスが、旧本川村役場があった長沢と高知駅バスターミナル間の60km近い距離を毎日2往復(他に区間運転もある)している。ここは長沢のターミナルから3kmの地点である。旧道時代は旧道を、旧旧道時代は旧旧道を、やはり高知駅行きのバスが通った。峠にトンネルが通ったことで、初めて本川村は「四国のチベット」のあだ名を過去にものにすることが出来たそうだ。

大森川を挟んで、現道と旧道は少しの間並走するが、次第に旧道は高くなり、遠くなった。
そして、分岐から約300m、大森橋の次のバス停「奈路路」のある地点が……

16:27 《現在地》 海抜640m
現代における本川地区の表玄関口、国道194号新大森トンネルの坑口に面した、竹ノ奈路集落である。
大森川沿い最奥の集落で、奈路(なろ)というのは土佐地方に広く分布する特徴的な地名の一つ、平らを意味する「ナル」という古語に由来する説が濃厚だ。
これまで無数の峠を自転車や車で越えてきた私だが、この新大森トンネルの現れ方はとても特徴的で印象的だった。
間もなく見ていただく出口側の風景と対比することで、程ヶ峠の強烈な“片峠ぶり”(峠の両方で地平までの高低差が大きく異なること)が感じられる。
なにせここは村の中心から約3kmしか離れておらず、しかも川沿いの坦々とした道だから、全く峠を登っている気分がなかった。
そして小さな集落の軒を掠めたと思った途端、大森川を渡り、そこから直ちに長い峠のトンネルが始まっている。

この場所が本川地区の玄関口である証しというべき、今日では少々懐かしい道路上の構造物が残っていた。
これは“安全門”と呼ばれるもので、一昔前は各地で良く見られたが、老朽化と共に撤去が進み、減ってきている。
ミドリ十字のお馴染みのマークと共に「本川 交通安全」の標語が掲げられ、支柱にも【これ】「今日も無事故で幸せ家族・幸せ家庭」や【あれ】「あせらず 急がず 安全運転」など懐かしい感じの文言が並んでいた。
村外へ働きに出る村民の多くが朝な夕なと潜った門だ。村の顔といっても良いだろう。
チェンジ後の画像は、門をくぐると、新大森橋(昭和50(1975)年竣工)から……

直ちに、新大森トンネル(昭和53(1978)年竣工)へ。
この年代のトンネルに特に多い、扁額以外の装飾要素を全く持たないシンプルなコンクリート坑門だ。
2車線の車道は充分な幅があるが、歩道を持たないことも、この年代までの山岳トンネルらしい。
チェンジ後の画像は坑門に備え付けられた銘板だ。
「新大森トンネル」を名乗っている。
単純に旧トンネルを置き換える場合(同時に利用することを考えない場合)は「新」を付けない命名になる傾向がある。
この場合は「新」があるので、旧トンネルをすぐに廃止するつもりはなかった可能性が高い(実際しばらく使われていた)。

全長1184mと決して短くない新大森トンネルだが、本川側から吾北側へ自転車で通り抜けるのは時間が掛からない。
なぜなら、全長の7割くらいが下り坂だから。
入ってすぐになだらかなサミットがあり、そこを過ぎると下り坂になる。
平面的な線形は直線だが、出入口を見通せないのは勾配が変化するためだ。
入洞から2分、風を切りながら颯爽と出口へ!

16:30 《現在地》 海抜630m
脱出!
四国島の北東に河口を有する吉野川水系から、南に河口を有する仁淀川水系へ抜け出した。
旧郡名も旧村名も変わったが、現行の地名としては、吾川郡いの町内の隣の大字へ移っただけだ。
しかし風景は全く違う。反対は【これ】 だった。
だった。
まずそこに人家がないし、川がない。そして代わりに空がある。
「急な下り坂」を、「急カーブ」を、予告する標識群がある。
長い長い下り坂が、ここから始まる!
写真中央の角辺りから、路肩の向こうが覗けるので、見てみよう……。

高い!
展望台から見る風景ではないから手前の障害物が少し邪魔だが、ここが高いことはすごく分かる。
海抜630mという標高は、反対側と10mしか違わないが、こちらには確かに600m下にある地平を遙か遠くに見透かすような空の広がりがあった。
現に国道194号は、ここから旧伊野町の中心部まで約40kmにわたって、ひたすら繋がる谷に沿って下り続ける。
ある意味、程ヶ峠や大森トンネルの登程は、この40kmすべてである。
1本のトンネルを挟んだ風景の劇的ギャップ、片峠ならではの面白さが、ここにあった。

振り返る吾北側坑口。
傍らの砂利敷きの広場に、「新大森トンネル」のバス停がある。
背後の稜線との高低差は250m内外といったところで、旧来の程ヶ峠も同じ並びにあるが、地形として見える感じはしない。
植林地ではない雑木の山で、かつ急峻な地形であることが見てとれた。
なお、この坑口前は丁字路になっていて、国道から西へ立派な2車線舗装路が分岐している。
入口に道路名の案内はないが、当サイトではお馴染みの存在である“大規模林道(=緑資源幹線林道)”の一線だ。
四国に計画された5本のうちの1本、吾北池川線(計画全長43.3km)の起点はここである。
が、緑資源機構が廃止され、残事業が県に引き継がれた平成20(2008)年時点でも5kmほどしか完成しておらず、その後も停滞しているようだ。私が生きているうちに全通することはまずないだろう道である。

16:33
既に述べた通り時間に余裕がないので、自転車に跨がり直してすぐに先へ進む。
新大森トンネルを出た国道は、堰を切ったように勢いよく下って行く。
この下りに完全に身を任せてしまうと、約4km先の安望(あもう)集落がある枝川川(←誤記ではない)河床の標高350m近くまであっという間に連れて行かれてしまうが、旧道探索が目的なら完全に行き過ぎだ。

16:35 《現在地》 海抜600m
トンネルから900m進むと、次の「枋谷(とちだに)」バス停があり、その直後にトンネルがある。
枝畝(えだうね)トンネル、全長516mである。【銘板画像】
その入口の脇に、いかにも旧道らしい入口がある。
実際にこれも国道の旧道だが、国道であった期間が非常に短い。
先ほどの新大森トンネルが開通した昭和53(1978)年から、枝畝トンネルが開通した昭和55(1980)年まで、最長でも3年間だけの国道である。というか、枝畝トンネル開通までの仮国道といった方が正しいかも知れない。
この旧道を行くと、私が探索したい旧道への近道になるが、まあ大きく差が付くほどではないので、ここは華麗にスルーして、より伝統あるコースで旧道探索を始めたい。直進して、トンネルへ。

圧倒的片勾配の枝畝トンネルを爆走し、再び地上へ!
ここまではまだ下り方に多少の遠慮というか、現代らしさがあったが、このトンネルを出たところからは、線形こそ今風に整っているものの、勾配はやや年代を感じさせる厳しさとなる。
この変化の理由はもちろん……

16:36 《現在地》 海抜580m
この枝畝トンネル以下は、昭和10年頃に開通した最初の車道を原形として改良した現道だからだ。
すなわち、ここが目指していたもう一つの新旧分岐地点となる。
坑口脇の目立たぬ道こそ、旧道の吾北側入口である!
“さくらでんや”があった枝畝を回って……

16:36 《現在地》 海抜580m
新大森トンネルの吾北側坑口から1.5km下った枝畝トンネルの吾北側坑口前から、反転して旧道へ進入した。
旧道の入口には特に封鎖や通行止の告知はなかったが、車の出入りは多くなさそうに見える。
そもそも、交通量が少ないことを前提とした交差点の造りだ。
交通量多く、かつ流れも早い国道のトンネル出口に完全なブラインドで旧道は接続しており、カーブミラーもないので、旧道側から国道へ車で合流するのには、よほど注意しないと危険である。
旧道へ入ると、巨大なコンクリートの箱のような坑門工に沿って進む。
道幅はそんなに狭くないし、舗装もあるが、車1台分を除いた路面は冬枯れの草や灌木に覆われていて、外観的に廃道一歩手前のような印象だ。

16:36
坑門工が途切れると、いよいよ旧国道当時からの本来の道となるが、案の定、とても狭い。
いわゆる“酷道”と呼べるような道である。
こういう道に慣れてはいるが、今回は時間がないので、自転車ですんなり峠の旧トンネルまで辿り着きたい気持ちが強いだけに焦る。そこで旧旧トンネルを探すことを最大の目的と考えている。
地図読みで、この旧道入口から旧トンネルまで約3.4kmある。結構長いが高低差はさほどでもなく、せいぜい150mほどだ。したがって、道さえ悪くなければかなり短時間で辿り着けるというのが、私の“期待”であった。

16:43 《現在地》 海抜590m
入口から500mほど等高線に沿って進むと、尾根の先端が見えてきた。
枝畝トンネルが貫いてショートカットしている尾根である。
ここまでは西日に対して完全な日陰になっていて薄暗かったが、尾根の先は一転して眩しそうだ。
なお、この尾根こそは、車道化される前の古道“程ヶ峠”の通路であり、実際に尾根沿いを下って行く登山道程度の歩道があったが(地形図にも徒歩道として現存)、意識しただけで(写真は撮らず)通り過ぎた。普段なら写真の1枚くらいは撮ったと思うのだが――

――森の隙間から垣間見えた山並みに目を奪われたことで、忘れてしまったのだ。
前回も述べたように、この大森トンネルがある峠は強烈な“片峠”で、本川側にはほとんどアップダウンがないが、吾北側には標高の数字通りの高さがある。
今回私が辿る旧道の高低差がさほどでもないのは、峠の上の方のトンネル周りだけで何度も道の切り替えが行われて来たせいである。
チェンジ後の画像は、写真の中央付近をズームしたもので、谷底へ降りていく現国道が見える。
新大森トンネルや枝畝トンネルの開通と共に、この峠の全線が2車線化したのは昭和50年代である。
それ以前の本川村は、自動車で辿り着けるとは言ってもやはり、大半のドライバーにとって覚悟を要する行先であったろう。
そのようなことを想像させる眺めであった。
尾根を回ると西日を正面から受けるようになり、前が見えにくいほど眩しくなった。
相変わらず道は狭いが、陽当たりがよいだけで印象は変わる。
路傍に点々と手作りのハニーボックスが並んでいるのも長閑である。
ところで、この全天球画像には1ヶ所に赤い○印で囲んだ部分があるが、次の写真は、その周りをズームして撮影したものだ。

そこには、陽当たりのよいところで丸まって眠る猫のような集落があった。
雄大な景色の中にあるせいで、ずいぶん遠くにも見えるが、実際は数百メートルの至近距離にある大野という集落だ。
いまでは無人化して“跡”になってしまったところも多いが、この辺りの山の中腹には、ずいぶんと多くの集落があった。いまでも多くの地名や小道が山のそこかしこに描かれている。
車道という特別に便利な道路が完成し、誰もがそこを通るようになるまでは、山の方々まで毛細血管のような小道に血が通い、ちょっとした陽当りにも穏やかな暮らしが営まれていたのであろう。
現地では時間がなく、ここも駆け足で通り抜けたことは正直に告白しなければならないが、良い景色だと思ったのは本当だ。

16:47 《現在地》 海抜600m
狭かった道が急に広くなり、その先に分岐地点が見えてきた。
入口から約800mの地点である。
チェンジ後の画像は、同地点からの眼下の眺め。
大野集落のはずれにあたる人家がすぐ近くに建っていた。
規模の大きな石垣や広い段畑もあり、暮らしの永さが窺えた。
ここ大野は険しい程ヶ峠の沿道にある最奥の人里で、多くの旅人が一息を付ける場所であった。
今回の探索のきっかけとなった、冒頭でも紹介した『土佐の峠風土記』には、次のような記述がある。
「枝畝」と称する支尾根の道を上ると、標高600メートルの旧県道に出る。すぐ上の台地には、昭和10年ごろまで茶屋が建っていたという。桜の大木があったので、“さくらでんや”と呼ばれ、旅人はここで酒を飲んだり、あめや餅を買って一服したという。
トンネルが抜け、車道が開通しても、安望を遠回りする羊腸の道は長く、バスを利用しても随分と時間がかかったので、登山帰りの私たちは、枝畝でバスから降ろしてもらい、旧坂道1.7キロを日比原まで駆け下り、茶屋でうどんを食って小休しているところへ、バスがやってくるといった、のどかなころのあったことを思い出す。
『土佐の峠風土記』より
前段の話は、最初の車道が開通するまでこの辺りに“さくらでんや”という茶店があり(漢字で書けば「桜店屋」だろう)、旅人に酒や甘味を提供していたこと。
後段の話は、筆者自身の体験談として、車道が開通してからもバスは(道が悪かったから)遅く、むしろこの場所から古い峠道を駆け下る方が早かったことが述べられている。
どちらも往年の峠道の風景を情感たっぷりに想像させてくれるエピソードだ。
またこれは読者から教えてもらったのだが、昭和35(1960)年に作成された記録映画『日本風土記』には、当時の国道194号の走行風景が収録されている。(→動画リンク)
まさにこの辺りの風景であり、確かにこれなら走った方がバスよりも早く着ける状況もあったと思う。
私がいま見ている風景も長閑であることに変わりはない。
だが、昔の旅人が見たものとはやはり違うのだろう。
昔はこんなにスギの森は広くなかっただろうし、一方で山の家はもっと沢山見えたろうと思う。
①
地理院地図(最新)
| 
|
|---|
②
昭和53(1978)年
|
|---|
③
昭和43(1968)年
|
|---|
④
昭和32(1957)年
|
|---|
⑤
明治44(1911)年
|
|---|
古道と旧道の接点であったこの「枝畝」の地図風景から、道の変化を辿ってみよう。
①は最新の地理院地図で、変化を見るための起点。
②は昭和53(1978)年版で、新大森トンネルは開通したが枝畝トンネルは未開通という短い期間(3年間ほど)の状況を描いている。着色されている道が国道だが、当時は現在地よりも下はまだ1車線の旧態依然とした車道であったことが分かる。
③は昭和43(1968)年版で、当時の国道はここで180度大きく切り返して、旧トンネルがある峠へ向かっていたことが分かる。
④は昭和32(1957)年版で、車道の位置は③と変わらないが、国道194号が昭和37(1962)年に指定される以前の「県道」であった時代を描いている。
⑤は明治44(1911)年板で、まだ車道はなく、程ヶ峠が歩かれていた。確かにこの当時は「現在地」の尾根に2軒ばかり建物が描かれており、これが“さくらでんや”と呼ばれた茶屋なのだろう。
これらの建物は、④になると道路によって消えている。
残念ながら名物だったという桜の大木も、いまでは見られないようだ。
さて、現地レポートに戻ろう。
この交差点の進み方は、もう分かっているね。
画像の黄色い線のように、ぐるりと180度切り返すのが、旧トンネルへの経路である。
敢えて、狭い道から狭い道へと、狭い道ばかり選んでいるのが、いかにも旧道っぽいと思った。
私もくしゃみが出そうな激しい逆光から解放されて、今度こそ行き止まりの旧道へ。
ここまでは順調。このまま暗くなる前に攻略したい!!

しかし、ここで遂に先行きへの悪い告知がなされてしまう。
「 旧大森トンネル 通行不能 これより3.4km先 高知県 」
これは旧トンネルのことだろう。
旧大森トンネルについては、ごく最近と言っても良かろう平成26(2014)年に発行された地形図でも普通に通れそうに描かれていて、その次の更新で紙の地形図からデジタルの「地理院地図」になった時に削除された。
そのことを知っていたから、封鎖もごく最近だと思っていたが、この看板のそれなりに古ぼけた感じからすると、意外に時間が経っているのか……?
でも本当を言うと、旧トンネルの坑口が塞がれていないことだけは事前に調べて知っていた。
だから、車は駄目でも自転車なら通り抜けられるとの算段だった。
旧トンネルは、通れて当然という前提。
私の本当のターゲットは、ずっと早くに廃止されてしまった初代の大森隧道である。
それがどうなっているかを、私は知りたい!