集落のすぐ後にダムがあり、ダムのすぐ後から……
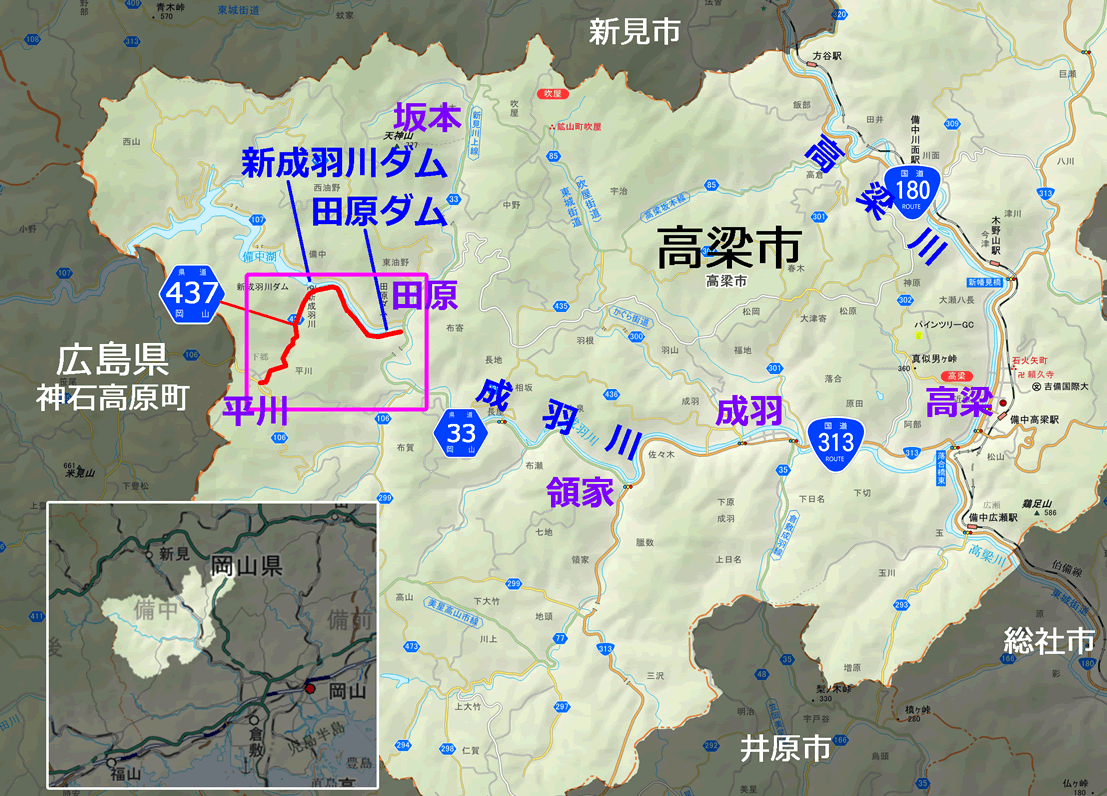
岡山県中西部の広い範囲を占める高梁(たかはし)市の西部、広島県と接する平成の合併までは川上郡備中町(びっちゅうちょう)と呼ばれていた地域に、一般県道である岡山県道437号下郷惣田線はある。
路線名に含まれる2つの地名とも市町村名はおろか大字名でさえない(おそらく字名)小地名であるから、よほど土地鑑がなければ、路線名から所在が分からないと思う。
この路線の特筆すべき点は……(↓)
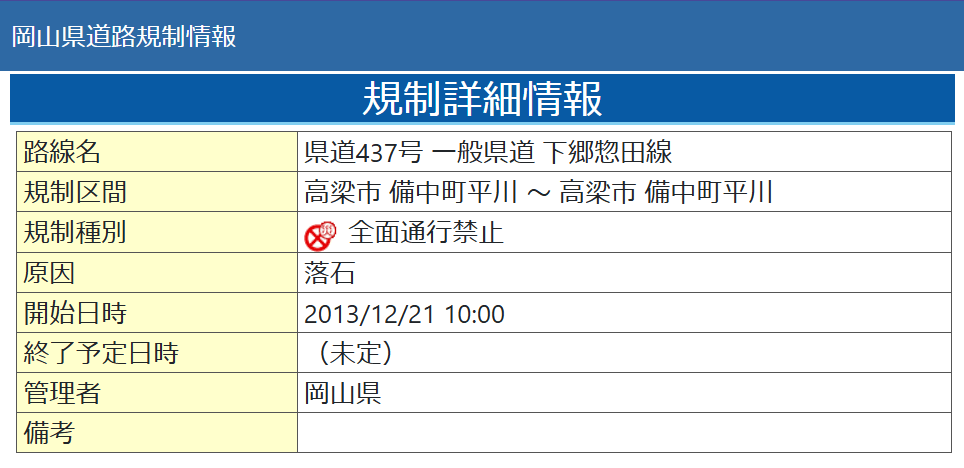
「岡山県道路規制情報」より
10年以上にわたって、「落石」を原因とした「全面通行禁止」の規制が継続していることである。
県内の交通規制を網羅している岡山県道路規制情報において、現時点で災害による規制が10年以上継続している県道は、ここと、以前紹介した「岡山県道50号北房井倉哲西線 無明谷」の2路線だけである。
しかも、10年以上も全面通行止であるにもかかわらず、Wikipediaにある同路線のページ上では、このことへの言及が全くない。
……なんというか、あまりにも注目されていなさそうで気の毒だったので、現地を確認しに行ってみることにしたのが今回のレポートだ。まあ、探索時点では規制からまだ10年は経ってなかったけど。現状についての事前情報もほとんどなかったし、気になったのである。

で、これが路線全体が収まるくらいまで拡大した最近の道路地図(2023年版のスーパーマップルデジタルver.24=SMD24)の画像だ。
県道437号下郷惣田線は、高梁市の備中町平川という大字の中で完結している。この大字の原形は川上郡平川村といい、昭和31(1956)年に周辺の村と合併して備中町となった経緯がある(さらに平成16年に合併で高梁市の備中町平川となった)。かつての平川村の中心集落の一角である「下郷」の起点で県道106号から分岐し、下郷川の谷を下って成羽川沿いに出ると、同川を堰き止めた田原ダムの湖畔を経由し、県道33号との交点である惣田(そうだ)の終点に達する。全長は約7.4kmである。
そして、「岡山県道路規制情報」によれば、平成25(2013)年12月21日以来今日まで、このうち成羽川沿いの区間の大半となる約3kmが、落石を理由に、通行止のままになっている。
地図を見る限り、通行止区間の対岸に別の県道が平行しており、おそらく迂回路として機能していることが想像された。
湖を挟んで両岸に県道があって片岸の道が長期通行止になっているパターンは、かの有名な廃県道である大嵐佐久間線を彷彿とさせる。こちらは遙かに規模が小さいし、通行止の継続期間もまだ短いが…。
ただ、このパターンはね……、
やっぱり、いろいろと整備の優先度を競っていく中だと、不利になりがちなんだとは思うよな。
実際、どんな状況になっているのか、長期通行止区間の実情を、見にいってみた。

2022/2/21 12:55 《現在地》
ここが、岡山県道437号下郷惣田線の終点である、田原橋袂の惣田の交差点だ。
田原橋の右岸と左岸でそれぞれ分岐する県道の行先をまとめて案内する青看をはじめ、1つの標識柱にいくつもの案内標識が取り付けられているせいで、交差点は信号のないシンプルなものだが、なんだかちょっと賑々しい。
しかしそれだけに、県道437号に欲しい案内は、ちゃんと揃っている。
行先が「下郷」と案内されているし、いわゆる卒塔婆標識の“ヘキサ”もある。
さらに、通常の青看ではない水色の(おそらく自治体が設置したオリジナル)案内標識もあり、道路地図には載っていない可能性がある小地名「下郷」が分かりづらい人のために、「平川」というもう少し大きな地名を案内する親切までしてくれていた。

だが、いざ県道437号へ左折しようとする私の目に、インコーナーに設置された“赤モノ達”が、早速飛び込んで来た。
青看が道路の案内をする役割なら、これら赤色を主体とした看板は、反対に通行の規制や制限に関する内容であることがほとんどだ。“危険信号”である。
具体的には、事前情報通り、「全面通行止この先下郷惣田線落石のため通行できません 岡山県」と書かれた全面通行止の予告と、あとは、「この先大型車通行困難 最小幅員2.5M 岡山県」という、そもそも通行止になる前から“険道”であったことを窺わせる看板である。
完全に、私を挑発しにきていて(←していない)、アタマに血が上った。

迷わず突入。
これが突入直後の風景で、左右に点在しているのが惣田集落の家々である。
ただ、地図をよく見ると察せられるかと思うが、いま見えている道路は、はじめから県道437号として生誕したものではない。
元来は、今分岐した県道33号新見川上線がここを通っていた。だから、旧県道沿いの街並みである。

12:56 《現在地》
起点から100mほどの地点で、前触れなく丁字路が現れた。
あまり目立っていないが、角のカーブミラーに黄色い案内標識(“黄看”?)があって、「平川←」とある。
というわけで、県道437号はここを左折するのが正解。
ちなみに直進は50mほど先で成羽川にぶつかって終わっているが、以前は県道33号の田原橋がここに架かっていた。
昭和56(1981)年に冒頭1枚目の写真の位置へ架け替えられた際に、県道437号の終点は、「現在地」から冒頭の交差点へ移動したのである。
左折する。

ここからが純粋な意味で県道437号として整備された区間であるが、左折直後の道幅は1.5車線で、まあ良くあるローカル県道の佇まいだ。
ただ、最初から人家が沿道にほとんどない。これは道自体が比較的新しいのか、集落の拡張には寄与していない雰囲気だった。
そして行く手へ目を向けると、なんか、いきなり別の地方と思うくらい雪が多く見えていて、ちょっと動揺した。
日当りの影響だろうか、最初からこれはさすがに不安だ。これから山へ入っていく一方なのに。
(ちなみに、SMD24では冬季閉鎖が行われる道路が区別されるが、本路線にそのような表示はない)

今日、朝から半日自転車を漕いできた中では、圧倒的にここが一番雪があるな。
路上でも3cmくらいの積雪があった。
幸い、轍の部分には路面が出ているので、自転車で漕ぎ進むのに苦労はないが、結構な上り坂だし、轍がなかったらタイヤを取られて面倒くさかったと思う。
あと3kmくらいは進んでみるつもりなので、この轍にはぜひ頑張って貰いたい。
そして、なんかまた赤っぽい色彩の看板が見えてきた。

なんだこれは。
珍しい組み合わせだ。
そもそもが珍しい「その他の危険」の道路標識と、事前通行規制区間の看板が、組み合わされている。
これが岡山県の標準的な告知方法なのだろうか。まだ同県内の経験が足りないので判断できないが……。
それに、「その他の危険」の標識の背中合わせに、別の道路標識が反対向きに設置されている。しかし白い幌で隠されていた。隠された標識が分からないので、意図を図りかねる。
なお、事前通行規制の内容自体は特筆するような極端なものではなかったが、通行の可否を表示する可変部分の表示は、しっかり「通行止」になっていた。

12:57 《現在地》
雪の轍が、県道へ行ってない!(涙)
ここには2回目となる「全面通行止この先下郷惣田線落石のため通行できません 岡山県」の看板が設置されているが、それでもまだ予告だ。なのに誰も行っていない! (←何も不思議じゃないだろそれは…)
というわけで、探索開始から僅か2分、たった300mを前進した地点で、雪道へ突入。
秋田県人なので自転車で雪道を走るのは慣れているが、ただただ疲れるので嫌でしかない。
今のところはまだ浅いが、わざわざ岡山まで来て雪道探索になるとは…。

雪道である。
雪は積もったばかりで柔らかく、下の舗装もまだ凍っていないので、多少抵抗が増えるだけで普通に漕ぎ進められている。
それは良いとして、風景の変化の早さに驚いている。
2分前までは人家の傍を走っていたと思うのだが、今ではもう、深山の雰囲気を持った峡谷を相手に、終わりの見えない入山を始めたような風景である。
実際、ここから先の谷――成羽川の峡谷は、広島県境も越えて20km以上も先まで激しく蛇行しながら、広大な吉備高原を深く抉り抜くように続いている。
幸いにして、県道437号がそれに付き合うのは最初の3kmに過ぎず、残りは対岸の県道107号の独擅場となるが。
そして、この長く途切れない峡谷の大半は、連続する大小2つの人造湖である。
下流にある“小さな方”の主であるダムが、既に行く手に見え始めている。
この田原ダムは、高さは41mとほどほどだが、直下の惣田集落から500mの至近距離にそそり立っている点が珍しい。

ほぼ一定勾配でほぼ直線という淡々たる登りで41mの堤高を稼いだ県道は、平坦になった。
ダムの管理施設の一部である建物が路傍に現れ、道幅を狭めた。
路肩に目を向けると、眼下には無骨な姿の田原ダムと、その建設の目的となった発電施設が展開していた。
ちなみに、【最後の分岐】 で轍が向かっていたのが、この田原発電所である。
で轍が向かっていたのが、この田原発電所である。

13:01 《現在地》
これが、本編冒頭1枚目の写真を撮影した「6分後」に、「自転車で」辿り着いた場所の風景である。
同じ自転車乗りなら、この景色の変化の大きさに、私と一緒に感心するのではないだろうか。
田原ダム、到達。
しかし、轍も足跡もない新雪の道を辿って大きなダムの上まで辿り着いたのは、なんだか新鮮な体験だった。
ここでは、ダムが流す放流の瀑音だけが、ひとけの無い路上を満たす唯一の音だった。
そういえば、ダム脇の道路には付き物となっている、ダム建設以前の旧道の分岐が見当らなかった。
そこで、この県道はそもそもダムの建設によって初めて誕生した道ではないかと思った。
田原ダムは、この上流にある“大きな方”のダムのパートナーであり、建設された経緯も、使用の実態も、全く切り離せない。
そしてともに昭和43(1968)年に完成している。

13:01 《現在地》
せっまいな!
田原ダムの堤上路は、地形図などでは道路として解放しているようには描かれていないが、実際は車止めも規制もなく、解放されていた。
ただ、ちょっとマイカーで突入するには勇気が要る狭さである。
堤長も201mあるそうなので、途中で嫌になっても大変だよ(笑)。
でも、それなのに新雪を踏んだ車の轍がついていて、四輪車には余裕のないその狭さを分かりやすくしていた。
つうか、そんなに県道437号を通りたくないのかよ。通って良かったんだぞ、ここまでの区間は別に。
なお、対岸で接続しているのは県道107号である。対岸には全く雪らしいものが見えないので、これが南向き斜面と北向き斜面の積雪の差であった。
県道437号には、最初から冬期間のハンデがあったわけだ…。

せっまい。
ダムの上よりはマシだけど、ダム関連の建屋のせいで県道が圧迫されている。
いきなりだけど、ここのことなんじゃないか? 大型車通行困難の幅2.5mって。
まだ分からないけど、前後の道に比べて必要以上に狭いぞここ。
まあそれはいい。
堤上路のお陰で轍が復活したし、こいつと一緒に通行止区間を攻略しようと思います。
田原ダムを越えて、前進続行!

あ…。

13:02
これ、復旧させる気 なくなくなくない?
長期化した規制期間中に設置したのが、この恒久感あるバリケードって……。