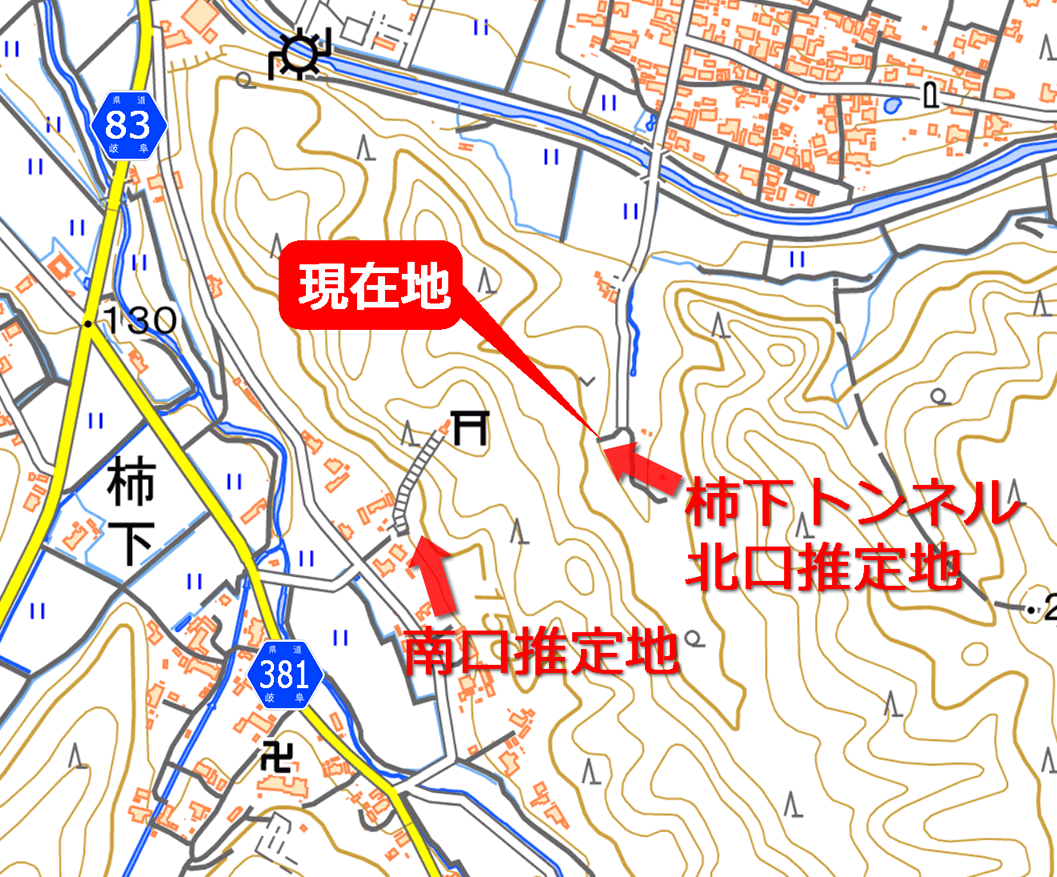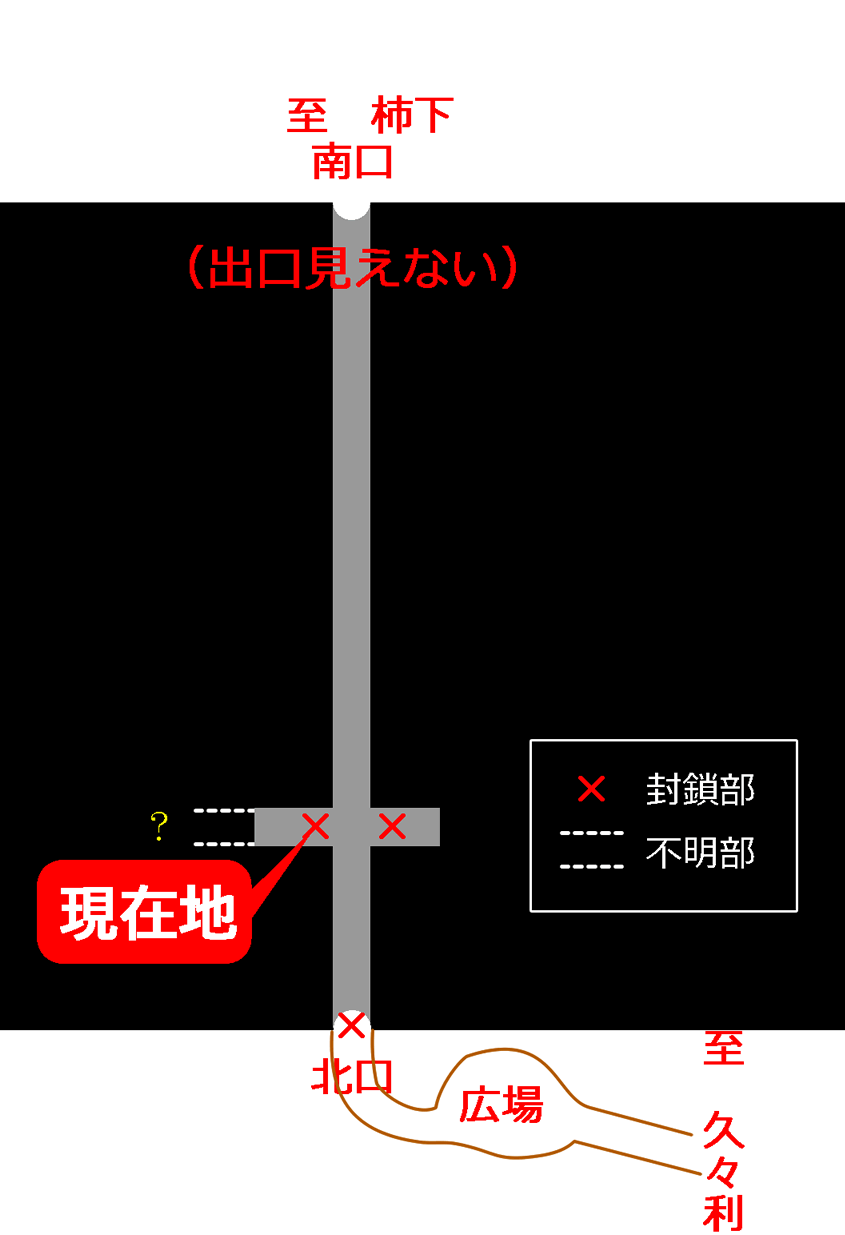《周辺地図(マピオン)》
名古屋駅から北東へ約30km、濃尾平野の外縁から尾張丘陵にかけた地域に岐阜県可児(かに)市がある。東部の丘陵地帯で広く良質の粘土を産出することから、古くより「美濃焼」をはじめとする窯業が発達し、近年ではそこからさらに発展したセラミック工業地帯や、交通に恵まれた名古屋市のベットタウン、あるいは近郊行楽地としても開発が進んでいる。
古い窯跡が多くあり、一説には「美濃焼」発祥の地といわれる市内の久々利(くくり)地区と、隣接する柿下(かきした)地区を繋ぐ1本のトンネルが、私が長年愛用している電子地図帳「スーパーマップルデジタル」(画像は2024年版のVer.24から引用)に描かれている。
チェンジ後の画像の“赤矢印”の位置を見て欲しい。
国道でも県道でもない無色の道に、「柿下トンネル」という注記を持つ、それなりに長いトンネルが描かれているのが分かると思う。
この「柿下トンネル」は、当サイトでもお馴染みのトンネルリストである『平成16年度道路施設現況調査』には次のように記載されている。
| トンネル名 | 道路種別 | 建設年次 | 延長 | 幅員 | 有効高 | 壁面 | 路面
|
| カキシタトンネル | 市町村道 | 昭和35(1960)年 | 205m | 3.0m | 2.5m | 素掘り | 未舗装
|
|---|
『平成16年度道路施設現況調査』より抜粋
こうしてデータを見ると、飛び抜けた数字はないものの、ほどほどに古く、ほどほどに長く、ほどよく狭い、素掘りで未舗装の、ほどよく怪しい隧道という印象だ。
そして、グーグルのストリートビューが近くまで行きながらなぜか引き返していて坑口を確認できないことや、全国Q地図の「2018年度全国トンネルマップ」に記載が見られないこと、そして最新の地理院地図にも記載がされていないことなどから、最近廃止された廃隧道である可能性が高いと判断した。
ならば現状を確認すべしということで、ちょっとした寄り道探索の気軽さでアタックしたのが今回の探索である。
それではさっそくスタート!

2023/4/8 14:40 《現在地》
ここは久々利の街の中にある古い辻の一つだ。
久々利は室町時代に美濃守護土岐一族によって整備された久々利城の城下町であり、東西南北の道が通じる交通の要衝だった。現在では集落外れの田園を貫く県道たちも、かつては家並みの間で忙しなく交わっていたのであって、そんな旧県道から柿下トンネルへ向かう道が分れる角が、この交差点だった。
何かトンネルにまつわる道標や記念物がありやしないかという期待を持って角を眺めたが、そこには確かに古い(紀年のない)道標石があった。ただ、「左 御嵩」「右 多治見」と二面に刻まれたそれは、多治見と御嵩(みたけ)を結ぶ旧県道がここを通っていた時代か、あるいはさらに古い由来を持つものらしく、昭和35年竣功とされる柿下トンネルに関するものではないようだ。
行先に対する案内や目印を見つけないまま、交差点を直進。もちろん自転車に跨がって。

上記の辻から柿下トンネルまで地図上約450mの距離で、途中にある分岐は基本的に全て直進で良さそうだ。
スタート時点で真っ正面に小高い丘が見えているが、そこに柿下トンネルがある。
なんともシンプルで、話の早い、アプローチである。

14:44 《現在地》
約150m進むと、川とそれを渡る橋に突き当たる。
川は久々利川、橋は久々利橋、銘板によると、平成28(2016)年竣功の真新しい橋だった。以前の橋は見当らないから、架け替えられたのだろう。
なお、可児市管理橋梁一覧によると、この久々利橋は市道1052号線に属している。
ホタルが棲んでいそうな綺麗な小川を渡って、トンネルがあるとされる左岸の丘陵地帯へ分け入って行く。

橋を渡ると道が狭くなり、登り坂が始まる。
写真は沿道最後の人家の前で撮影した。
狭い道だが舗装はされており、荒れている様子もない。電柱もある。
まだ奥に墓地があるようだ。
チェンジ後の画像は、同じ場所から久々利の町を振り返って撮影。
遠目にはそう見えなかったが、近くの山がずいぶんと岩山がちだ。採石場でもあったのか、緩やかな地形に反して岩肌の露出が目立つ。

14:58 《現在地》
久々利橋から200m足らずで、道は広場になっていた。登り坂もここまでのようだ。
地図上の道の行き止まりはもうすぐで、その行き止まりが、柿下トンネルの擬定地である。
ちなみにここまで、トンネルの存在を予感させるような看板や規制などの表示は全くない。
(チェンジ後の画像)広場の向こう側に道は続いているが、鋪装がなくなり、泥濘んでいる。
泥濘みに轍がはっきりと刻まれていて、奥はカーブしている。
ストビューはここまでしか来ていないが、カーブの途中に道路標識が見える! それもいかにもトンネル前にありそうな規制標識だ。
間違いない! この先にトンネルがありそうだ。

15:00
発見! 柿下トンネル!
最大高1.8mという、トンネルの高さ制限としては稀に見る厳しい規制を表示しているが、残念ながら(?)案の定にも、トンネルは封鎖されていた。
予想していた通り、道路トンネルとしては最近廃止になったのだと思う。
ただ、閉じたゲートにもお構いなしという感じに、真新しい轍がトンネルへ入り込んでいるように見えるのが気になる。
完全封鎖ではなく、何らかの“関係者”の通行は可能な状態で維持されているのだろうか?
そして、坑門の主張がなんとも乏しいトンネルである。
素掘りなのは情報通りだが、坑口としての岩肌の露出が少なく、緑のジャングルへ直に刺さるような姿だ。
ジャングルにぽっかり黒い口が開いているという印象。
たぶんこれは現役時代も大きく違わなかったと思う。
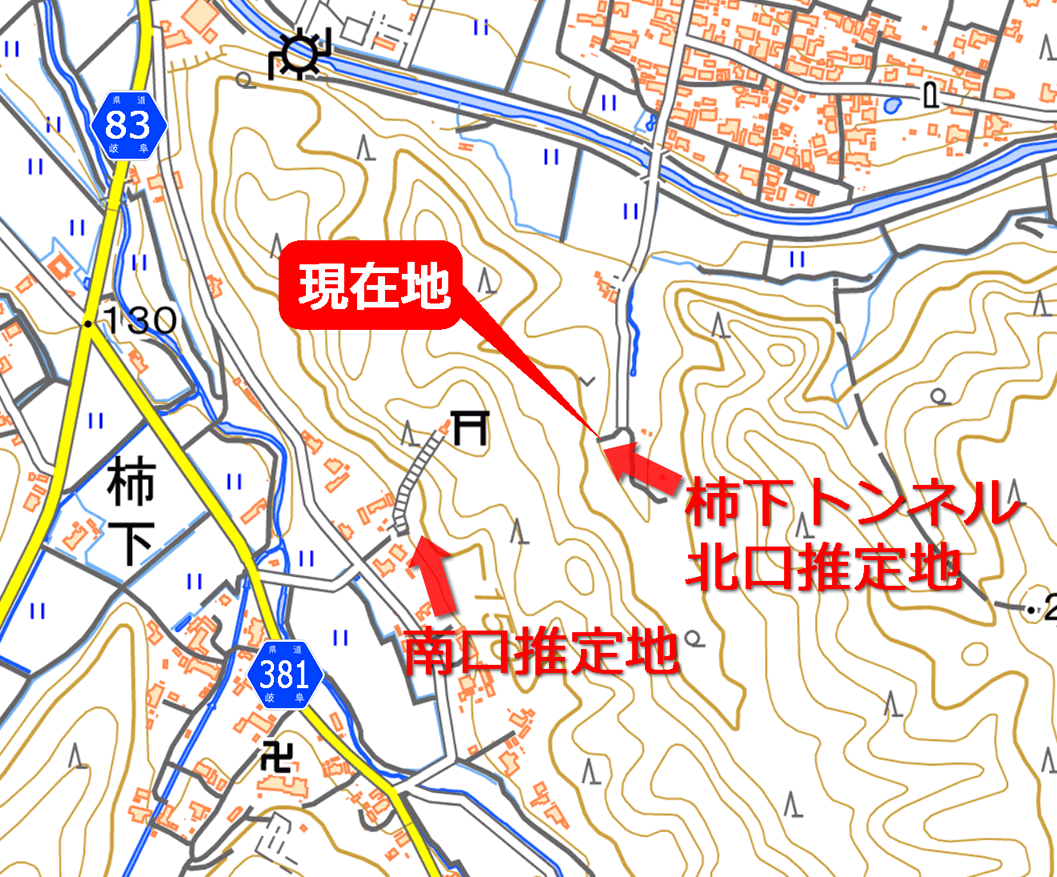
改めて、最新の地理院地図と、SMD24の描き方の違いを比較してみる。
前者にトンネルは描かれていないが、後者では現役さながらである。
トンネルの廃止がごく最近の出来事であったことを伺わせる事象だ。
実際、後者の地図を頼りに通れることを期待してここへ来て、引き返さざるを得なかったドライバーも少なからず居ると思う。

柿下トンネル久々利側坑口(北口)近景。
昭和35(1960)年竣功の記録があるが、もっと古いと言われても疑わない、野趣溢れる坑口だ。
そして、道路標識の規制が示すように、天井が低い。また規制はないが、幅も相応に狭い(3.0m)。
天井高は2.5mとなっていたが、マージンを取って最大高1.8m規制としていたのだろう。
基本的に普通乗用車以下の車だけが通れる規制で、ハイエースのような大きなワゴン車は通さなかったろう。
トンネルの全長は205mあるらしいが、ゲートの奥に出口の光を見通すことは出来なかった。
ただ、風通しを僅かに感じるので、完全に閉塞していることはなさそうだ。
ゲートが完全に閉じているが、通行規制のような表示物はない。その代わり……

「行き止まり」
と書かれたラミネ加工紙が1枚、頼りのないお札のようにぺらりんと天井からぶら下げられていた。
深い意味はないかもだが、「立入禁止」ではなく、「行き止まり」……。
…………どうにも、得体の知れない感じがする入口だ……。
こんな姿なのに、なぜか真新しい轍が入り込んでいるように見えるのも怪しく思える。
正直、禁断のアソコをちょっと思い出したのはナイショだ…。
しかも……
お水が、めっちゃ滴っている!
坑口から垂れた大量の水が、路面をしとどに濡らして泥濘みとしているのである。
水溜まりにこそなっていないが、洞内状況への不安を煽る坑口だった。

とはいえ、ここまで来て開口を確認し、なお立ち入らないと選択肢はない。
ニャンコの出番だ。
わるにゃん。

15:02 にゃああん。
なお、自転車には坑口前でお留守番をして貰うことにした。
むりやり入れることも出来そうだったが、自転車同伴でトンネルを通り抜けて先へ進むことは今回の行程上重要でないので、まずは身軽な状態で突入することにした。
しかしこれ、本当にトンネル内にまで新しい轍が来ている。
ゲートを開けての車の通行が、比較的最近に行われたことを物語っている。
そして、進行方向は、

深い闇の世界。
車1台分の狭い素掘りの坑道が、見通せない闇の奥へと真っ直ぐに消えていく。
だが、まだ見えない出口まで通じているに違いない、新しい轍がある。
その存在は、私の心の頼りになるものだった。
土の匂いが濃い洞内へ、歩きの速度で潜入していく。

15:03 (入洞1分後)
なんだこれは?!
坑口から30〜40mばかり進んだ地点で、左右同時に大きな横穴状の空洞が出現した!
どちらの横穴にも瓦礫が山と積まれており、故意に塞がれている様子だが……、異様な感じがする。

これは、右側の横穴の様子だ。
天井すれすれまで大量の瓦礫や産廃らしき機材が詰込まれている。
天井自体は崩れていないので、明らかに外から持ち込まれた土砂だと思う。
天井の隙間を見通すと、10mくらい奥に掘られていない行き止まりの壁(トンネルとしての切羽)があるようだ。
おそらくだが、この横穴はもともと10mくらいの奥行きしかなかったと思われる。
行き止まりの横坑を土捨場として利用したように見えるが、そもそも、道路のトンネルにこのような行き止まりの横穴があるのは珍しい。
しかもそれが……

左右両側にある。
直進する本坑に対して、左右とも直角に分岐しており、全体として一つの“トンネル内十字路”を形成している。
直角十字路がある道路トンネルなんて、初めて見るような…。

このような洞内十字路の存在は、道路トンネルというよりも、まるで防空壕のよう?
いや、それよりもさらに坑道の規模が大きい感じがするので、大戦中の地下工場跡のような気がする。
柿下トンネルは、戦時中の地下工場跡を再利用して作られた道路トンネルだったの可能性が?!
(昔探索した隧道に、そのような経緯を持つものがあったが、いずれにしても珍しいものだと思う)
なお、この左の横穴は積み上げられた土砂の量が天井に迫るほどではないうえに、乗り越えた先に奥行きがありそうだった。
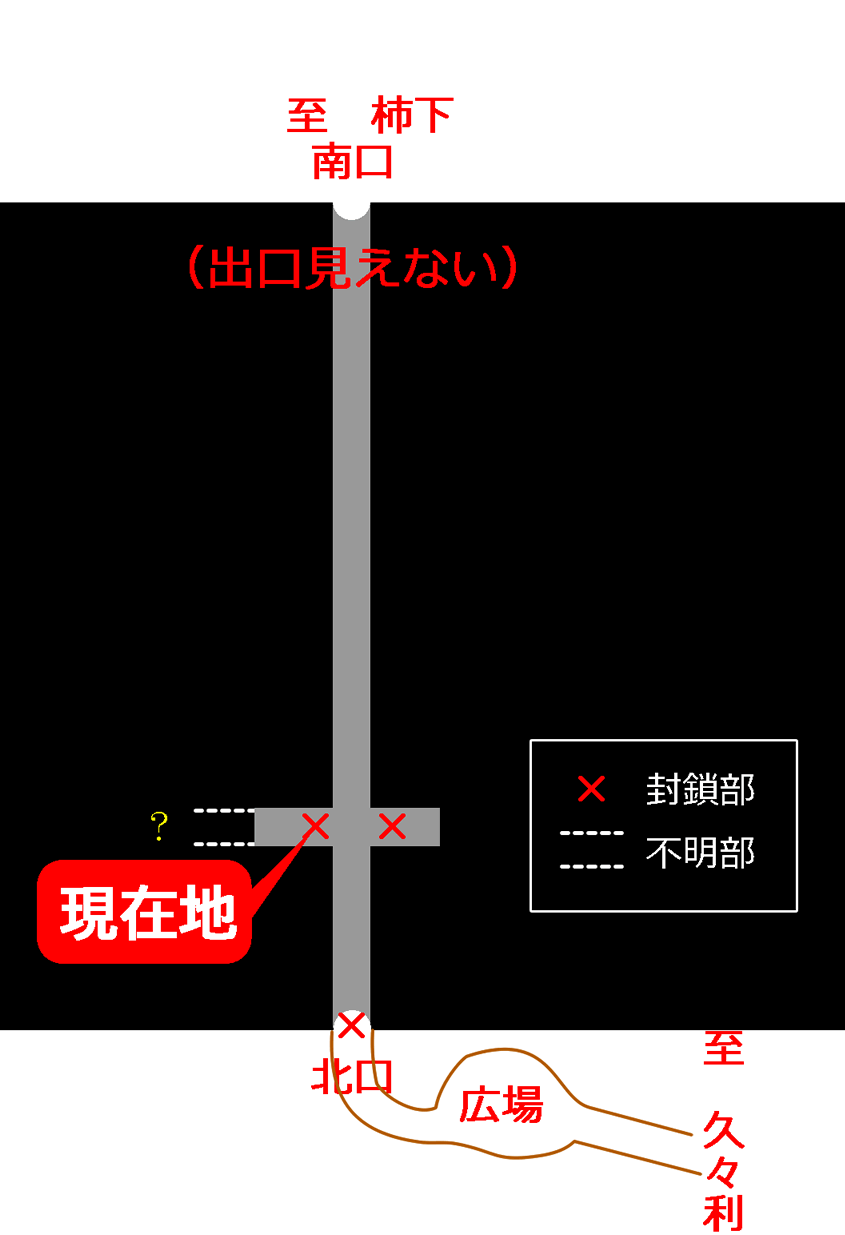
ここまでの洞内の様子を図に描いてみた。
もはや横坑部分は柿下トンネルの一部とは言えない気がするが……。少なくとも、205mの全長には計上されていない区間だろうし…。