���q詓��`�P�싴

2010/5/18�@17�F06�@�s���ݒn�t
�������̕��q�g���l���e���狌��������ƁA���̕��q詓��ɒ����B
���݂͑����Ƃ��Ďg���Ă��邪�A������g�������悤�ȝG���Ȓf�ʌ`�́A���č����̒ʍs�ʂ�L���Ă������c��Ƃ����邾�낤�B
�܂��A���̉��L�����ȊO�͓��ǂɉ��ʂ�����A�f�x�ɃR���N���[�g�����t���̎d�グ�炵���B��������������������B
���q詓�
�S���F210���@�ԓ������F�T���@���E���F4.7m�@�v���N�x�F�L�ږ����i���ۂ́c��q�c�j�@���H����A�H�ʃR���N���ܑ����u���H�g���l����Ӂv�i詓��f�[�^�x�[�X�j���]��
�{詓��̓�͏v�H�N�x�ł���B
���X�g�ɋL�ڂ��Ȃ����A��̂����o�����̂��낤���B
�ł��A�Ƃ肠����������͌�ɂ��āA�������Ă݂悤�B

��������o�������ʂ��Ȃ��������A��������̂͂��ŁA�����t�߂��E�ɑ傫���Ȃ����Ă����B
���������̋Ȃ����Ă��鏊�́u�Ҕ����v�ɂȂ��Ă���A�O��20m�قǂ̋�Ԃ��A�܂�Łg���̂��h�̂悤�ɖc���ł����B
��^�ԓ��m������Ⴆ��L���g���l���͗\�Z�I�ɍ��Ȃ����A�J�[�u�̂����Ō��ʂ��������̂ŁA�����ɑҔ�����������̂��낤�B
�����Ƃ��A�����ƂȂ������݂͂��̖c��݂����p�����悤�Ȍ�ʗʂ͖����悤�ŁA�������y���͐ς��Ă����B
�܂��A�Ȃ����Ҕ������ӂ̏Ɩ��̂ݏ������Ă���A�������L�����Ƃ������āA�w�b�h���C�g���x���ƕs����������قLjÂ������B
�T���C���͐���オ�邪�A�l�I�ɍL���g���l���̕����������d��ꂻ���ȋ��|�������ċ��B

�����[�̓�������B
���̂��Ҕ����B
������210m��詓������A���ꂾ���ł͏I���Ȃ������B
�Ȃ�ƁA���y���̏o���t�߂ɂ��܂������������J���Ă����̂ł���B
��̂���͂Ȃ�̂��߂̌����H
���R�����B

�Ȃ�قǁB
�����͒Z���ʘH����Ă����ɒn��Ɍq�����Ă������A���̐�ɂ͕P���O�_�����������B
�ǂ���炻�̊Ǘ��p�ʘH�炵���B
���̂܂܊O�ɏo�Ă݂�B

�����ɂ͖�����̒ʘH�̑��ɁA�l��l�������Ȃ��ׂ��ᒆ�ʘH���������B
���������݂͎g���Ă��Ȃ��炵���A�{�����ꂽ�S�i�q�ɉ����ăh�����J�����������ǂ��A���̏�œ���̒K�̒u�����u�����֎~����v�ƌ�������Ɏ���グ�Ă����B
����͖��S����������B
���̎����A�����́g�ɂ�h���A�������o���Ȃ��B

�����d�͂��Ǘ�����P���O�_���B
������8.6m�Ƒ傫���Ȃ����A�����̕P���O���d���ɑ������邽�߂̎搅�p�_���ł���B
�����͏��a30�N�Ƃ��Ȃ�Â��B
�����Ă����炭�A���q詓������̃_���ƃZ�b�g�ō��ꂽ�̂��Ǝv����B
�_�����o����܂ł́A�����������Ă��邱�̏ꏊ�������ŁA�R������Ĕ��ɉ�荞��ł����̂��낤�B
���a28�N�̒n�`�}��詓����`����Ă��Ȃ����Ƃ�A詓��̒f�ʂ����a�����̓d���J���ɔ����t���ւ��g���l���ɋ��ʂ���X�^�C���ł��������Ƃ��A������x������B
���̐�͒��d�̊Ǘ��p�n�ŗ�������Ȃ������ʂ����������ɉ������������Ȃ̂ŁA�����Ԃ����B

���q詓��̓���ɂ́A詓��Ɠ����T�C�Y�̓��傪�ڑ�����Ă���B
���̕����̔z�u�ɗV�ѐS��������i�u���v�u�q�v�u�݁v�u�فv���ĉ����ȁj���A�u���J�����i�Љ�ҁj�v�ɂ��Əv���͏��a55�N�ƈӊO�ɐV���������B
���q詓��̒T���͂���ŏI���B
����ɋ�����쉺����ƁA������ �P���O��т��ے����镗�i �������B

�Ζʂ��ׂ��Q�{�̋��B
��O�̋��ɂ͖����������O�͕�����Ȃ����A�P��x���̒��J���n���Ă���B
�����Ėڂ������͉̂��̋��ŁA�P��̖{����n���Ă��邻�̖����u�P�싴�v���B
���E�ŏ����̌�������gRC���[�[�����h�Ƃ��āA����14�N�Ɂu�����y�؈�Y�v�̎w������������B
�c�Ȃɂ��H�����̂悤�����c�B
���������݂̋������̏��a14�N�����̋��ł��邩�͕�����Ȃ��B
�����ڂ����m�肽���l�̂��߂̕⑫�������@������Ă�OK��I
�@�����J�썇���n�_�̓��H�̕ϑJ��
�P��ƒ��J�삪��������n�_�̗��n�`�}�����ɕ��ׂĂ݂��B
���ꂼ��ɍׂ��ȕω�������ʔ����̂Ō��r�ׂė~�����B�ȒP�ɉ�������ꂽ�B
 �吳���N�� | ���@�吳���N�łł́A ���a�T�N�łł́@�� |
 ���a�T�N�� |
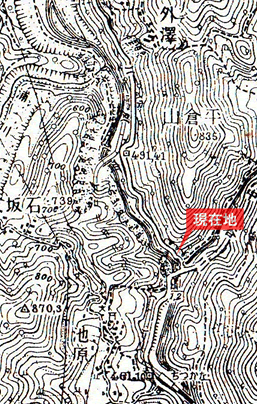 ���a28�N�� |
���@���a28�N�łł� �Ō�Ɍ��݂̔łł́A�@�� |
 ���� |

���J��͌����ɉ˂��鋌���̋�����A�㗬���Ɍ������̋�������B
���͌������č��ɂ��镽�q�g���l���ƈ�A�̃X�m�[�V�F���^�[�ɕ����Ă���A�h���C�o�[�ɂ͋��̑��݂��F������Ȃ������m��Ȃ��B
�܂��悭����Ɨ��݂̋���ɂ͋�����A�ʘH�̂悤�ɂȂ��Ă���B
�P���O�_���Ő��ʂ��㏸����ȑO�̓��͂��̍����ɗL�����\�������邪�A����I�ɂ͗���Ă���֘A���͕s�����B

17�F10�@�s���ݒn�t
���J��̋���n��ƁA���́g���G�Ȍ����_�h�ɓ˂�������B
�������͉E�܂��ĕP�싴��n�邪�A������Ƃ������֊�蓹���Ă݂悤�B
��蓹�F�@����114�����@�R�Z�g���l���̋���

���܂���Ƃ����Ɍ������Ƃ̌����_������B
���͎�����A�E�͑咬���ʂł���B
�����Ē��i���铹�́A���J���̉����~�I�ȉ���n�ł��鏬�J����֑����������B
���쌧��114���u��K���J��������v�Ƃ����H�����̒ʂ�A�I�_�͎�����s�����A�r���ɒ���ȕs�ʋ�Ԃ������Čq�����Ă͂��Ȃ��B
���̓����ɂ͐^�V�����g���l���������J���Ă��邪
�i�����_�̎O�����g���l���j�A
�B��̔w��ɉ���������c�B

���́B
����͑�_�ȏ��ɍB�����������̂��B
�����͐V���ȃg���l���̍B�傻�̂��̂ɂ���āA�Ԃ������Ă���B
���ꋌ���B

�V�g���l���́u�R�Z�g���l���v�Ƃ������O�ŁA���͐����ƋÂ������ɂȂ��Ă���B
�܂����̂������Ă��邵�A���̏�ɏ������u���J���v�Ɠ�����Ă���̂́A���J�쉈���̈�т����Ē��J���ƌĂ�ŏ��J���Ƌ�ʂ��Ă������ƂɗR������̂��낤�B
���̃g���l���͂��傤�ǒ��J�여��̌����Ȃ̂ŁA���������悤�Ɏv����B
���Ƃ�����ƋC�ɂȂ����̂́A�u���J���v�́u���v�̎��Ɂg�J�M�h�̂悤�ȏo�����肪�Q�t�����Ă��邱�Ƃ��B
�����炭�����������̂�����̂��Ǝv���B
�茳�ɂ��閾���̋��n�`�}�u����v�̑莚�ɂ���u���v�̎����A�S���������̂ɂȂ��Ă���̂ŁB

��������̓I�}�P�Ȃ̂ŁA������ƍs���B
���͂܂������̎R�Z�g���l�����������āA���Α��։�荞�B
�g���l���̒�����401���ŁA�v���͕���18�N�Ƃ����V�����B
�����ăg���l���̒��͂��̂̌����ɕЌ��z�ŁA���R�̂悤�ɃI�[�����B�n�[�h�B�i400���̍��፷��40����j
�~�j�g���g���l���h�̋�a�𖡂�������A���܂苤���͓����Ȃ����Ȃ̂ŁA�������ƐU��Ԃ��ċ����ցB
������������͉��z�Ȋ����ɐ�l�߂��Ă���B
���g���l���̃G���������Ă��āA�߂����炾�Ƌ����̑��݂ɂ��C�t���Ȃ��B

400���̌����ɑΉ����鋌���̒����͖�400���B
���g���l���͒n�\�̍ЊQ������邽�߂ɒn����ʂ��Ă��邾���Ȃ̂ŁA�����͂قƂ�Ǖς��Ȃ��B
�����ċ����̂قƂ�ǂ͈�A�̒�������i�X�m�[�V�F�b�h�j�ɕ����Ă���B
�x���������ׂ��ؚ������Ɍ����邱�̃X�m�[�V�F�b�h�ɂ͖��O������A�u���J�����i�Љ�ҁj�v�ɂ��ƁA�u�R�Z�v�Ɓu�R�Z2���v�Ƃ����炵���B
���̏㗬���ɂ���̂��R�Z�X�m�[�V�F�b�h�i�S��251���j�ŁA���a37�N�ɏ��J���ōŏ��̃X�m�[�V�F�b�h�Ƃ������݂��ꂽ�������B
����������ɐ������ꂽ�ӂ�A�����ɂ��̒n�_������̓�ł���A�܂��I��̗����Ȃ������̓����ł����������f����B

���g���l���Ƃ́A�����̃V�`���G�[�V�������ƂĂ��悭���Ă���B
���������ƈ��삪����Ă����Ƃ���ɁA�����x�̋K�͂̒��J�삪����A�܂��傫�ȍ��h�_������𗎂Ƃ��Ă���Ƃ������������B
�������̂���������ŁA�����≄�X�Ɖ����Ă����Ƃ���A�X�m�[�V�F�b�h�̕��͋C�Ȃǂ���v����B
�������A���̎R�Z�̋����ɂ̓g���l���͂Ȃ��B
���̓_�ł͒n�������A�����Ƃ̖����x�Ƃ����Ӗ��ł͂��d�v�Ȗ����������Ă����̂��A���́u���J���v�̓��������R�Z�X�m�[�V�F�b�h�������B

�R�Z�X�m�[�V�F�b�h�́A���̂܂܍|�S���́u�R�Z2���v�X�m�[�V�F�b�h�ɐڑ����Ă���B
������͑S����84���ŁA���a61�N�Ɋ������Ă���B
�V�������������āA�����������炩�]�T����������Ă���悤�������B

�X�m�[�V�F�b�h����ƁA�����͂������o���̂���ꏊ���B
��́A�Ԃ�ɂ���Ă��܂��������ł���B
�����炩�猩��ƁA�Ԃ����肳�ꂽ�����͂�����ƕ�����B
�����̘H�ʂ͐���y�ɓۂݍ��܂�Ă��܂����A���̐���y�̒��ɎR�Z�g���l���̍B��������̂��B
�����炭��������Ă����ڍB��܂œ͂��Ȃ��悤���L�����̂��낤���A���A�ŋ����͎S�߂ȏ�ԂɂȂ����B
����ɂĊ�蓹�͏I�����B
���J���ŌẪX�m�[�V�F�b�h�́A�Â��ɋ�����̂�҂��Ă����B
|
�X�|���T�[�����N |
������Ƃ����I���b�L���̐�`�B
|
�P�싴�@�`�@���y�w

17�F24�@�s���ݒn�t
���āA����̍���148���̋�������́A���ԓI�ɂ��s���I�ɂ�����ōŌ�̃t�F�[�Y���B
���݉s�Ӂg��t�h�H�����̕P�싴��n���āA�P������̒��y�w��ڎw���B
�����_�ɂ́A�܂���������̐ł��c���Ă����B
�������B��̍s�����������Ă��܂��A�S�����p�̒����Ɂc�B
�撣���ď����ꂽ���������ʂ���ǂݎ�낤�Ƃ������A��i�́u������v�Ƃ����傫�ȕ������������炸�B
���i�͕s�����B�P�Ƀ��[�}�����ȁH

���a12�N�����i���J�����͏��a14�N�Ƃ��Ă���Q���L��悤���j�̂R�A�q�b���[�[�����ł���P�싴�́A���̌`���̌������Ƃ��ČÂ������łȂ��A�����̓��{���u����Ă����S�s���Ƃ����ŁA�������ȋ����˂��邽�߂̐�i�I�ȋZ�p�����ł��������ƂƁA�v�ҁi�������j�����쌧���ɓ��l�̋����ː݂��Ă���n�搫���F�߂���ȂǁA�F�X�ȗ��R�œy�؈�Y�Ƃ��Ă̍����]�����Ă���B
�m���ɃR���N���[�g���̃��[�[���̋��͂��܂茩�Ȃ����A�����������̂œƓ��̏d�����������ăJ�b�R�C�C�B
�܂��A�����Ƃ��Č���ƁA�O��Ƃ����p�J�[�u�ɂȂ��Ă���ȂǁA���Ȃ��Ȃ����ł͂���̂����c�B


�T�����͂��܂��܃R���N���[�g�����ĕ�C����H���̍Œ��ł���A�q�b�i��Reinforced-Concrete�i�⋭���ꂽ�R���N���[�g�j�j�\���̍����ƂȂ�S���A�R���N���[�g�������悤�ɖ��ߍ��܂�Ă���M�d�ȗl�q�����邱�Ƃ��o�����B
�f�l�ڂɂ͓S�̕\�ʂɎK���Ȃ��Y��Ȃ悤�Ɍ��������A��X�I�ȕ�C���K�v�Ȃ��炢���Ă����̂��낤�B

�u���J�����i�Љ�ҁj�v�́A���a�̏����ɑ������ŏ��J���̌������i�����͂܂������������j���i�v�������ꂽ�������̂悤�ɏ����Ă���B
���a�ɂ͂���Ǝ����Ԃ�o�X�����X�ɕ��y�����߁A����������ɂ��킹�ĉ��ǂ�]�V�Ȃ����ꂽ���a�̕s�i�C�Əd�Ȃ������߁A����͂͂��������Ȃ��������A���J����ł͏��a7�N�ɏ��J���A12�N�ɐe�A14�N�ɐ�K�̕P�싴�Ɠ������R���N���[�g�̉i�v���ɂȂ�Ȃǐi�W������ꂽ�B
���̂����A���J���͖{���|�[�g�̖`���œn�������ł��낤���A�e�͍����Ԃł͂Ȃ����A�P�싴�Ɠ��������������v�����q�b���[�[�����Ƃ��Č����A�y�؈�Y�Ɏw�肳��Ă���B
���āA�H���̂��߂ɗ]�v�����Ȃ��Ă��鋴�i���̂��ߑ�^�Ԓʍs�~�߂������j��n��ƁA���p�J�[�u�ɂȂ��Ă���A�����ɓ��傪�n�܂�B
���a58�N�Ɋ���������K����ł���B

��K����͒Z���A�������Ƃ������ɐ�����̖������ԂƂȂ�B
�����Ă����ɁA���w�ɂ����D�܂����傫���̈ԗ�肪����B
�ԗ��Ƃ������Ƃ͒����ɑ傫���u�얳����ɕ��v�ƉA������Ă��邱�Ƃŕ����邪�A�����̏����ȕ�����ǂނƁA���ꂪ�u���a�Z�N�܌����O���v�Ɂu�����ؔn�V���o��v�Ƃ����l���́u����V�n�v�ł��邱�Ƃ����炩�ƂȂ����B
�����I�ɂ͏t�̒��J�ő���������ɗ������̂��A�w��ɐ삪�����Ă��邹���ŗ]�v���������z���������B
�Ȃ������ؔn�́A���݂̑咬�s���i������j�ɂ���ؔn�i����܁j�n��̎����낤���B
���ݒn�����25km���炢����Ă��邪�A����������X���Ō���Ă���B

����ɐi�ނƁA�����g���l������o�ė����厅���̐��H����������悤�ɂȂ�B
����������������͑������A���ꂼ�ꂪ�g���l���Ɠ���ɓۂݍ��܂��B
�������̓���͖��O�����܂����A�������܂����̂���肭�����ł��Ȃ����A�Ƃɂ����������́i���O���ˁj�B
���̖����A������т�����
�O�O�b�Ă݂Ă����̂������Ⴂ�A�Ӗ��s���B
�������̐l�������狳���ė~�����B

���厩�̂����\�C�P�C�P�Łi�����H�j�A�R���N���[�g�̗��̕\�ʂɓS��\��t���ċ��x�𑝂₵�Ă���ӂ�A�g�V���ɕڑł��h���悭�o�Ă���B
�S�̓I�ɍ�肪�S�c�S�c���Ă��āA�����������ɃN�C�b�N�ȃJ�[�u�������A��������ɂ��������Ƃ��v���Ώ\���ɖG���镨�����B
���x�u���J�����i�Љ�ҁj�v�ɂ��ƁA�S����146���A�v���͏��a60�N�c�c�c�H
���āA�ق�ƁH
�ӊO�ɐV�����ȁB�@�ƂĂ������͌����Ȃ����c�B

���˂铴��̓r������́A�P��̗Y��ȃJ�[�u�Ƃ��̌������̎R�ɋ��܂ꂽ�A�r�����̏W���������Ă����B
���ۂɌ�����g���l���́A���d���̔r���H���낤���B
�厅���̒��y�w�͂��̏W���ɂ���B
���̖ړI�n�ւ̐ڋ߂��A�܂��ꔏ�u���ĉ��]�������Ƃ����̂́A�D���ȃV�`���G�[�V�������B

�����ē�����o��Ȃ�A���̂����Ⴒ���Ⴕ�����̌����B
���������o�[�ɍ��������W���ɏ��s�̕W���ɒn���̕W���ɂx�j�j�G�N�X�e���A�̊ŔɁA����炪�w�i�Ζʂɂւ�t���悤�Ɍ��ƕ��݂Ɠ����Ɍ��ꂽ������A�u�˔@�X�ɏo���v�Ƃ��������������B
���܂��I

17�F37�@�s���ݒn�t
�����Ė����ɒ��y�w�ɓ����B
�w�O�ɂ͍��������o�[�����˂�i�Ǝv����j�A�[�`������A�u����v�u����v�u��v�u���v�u���v�u���J���v�̕������f�����Ă���B
���ܗ��s�i�H�j�́u������肵�Ă����Ăˁv����肵�Ă���B
�����A�u�䂱���v�Ɏ����������B
�����A���͂�����肵�Ă͂����Ȃ��B
����Ƃ����Č�錾�t�̎v�����Ȃ��w�O�Ɖw�ɂ���˂������́A�����ɗ�������߂�͂��߂��B
�������A�S���͂ɋ߂����炢�̐����ŁB
���n��I�ɂ́A�u�ԊO���v�ɑ����܂����A
���|�[�g�Ƃ��Ă͂���ŁA�����ł��B