洞内の断面変化から読み解く、本隧道の“工法”
本隧道が未成であるがゆえに見ることが出来る、様々な断面。
平たく言ってしまえば、掘っている最中の様々な形ということになるのだが、決して闇雲に掘り進めていたわけではないからこそ、下図のように第1〜第8断面に区間に分ける事が出来たのである。
闇雲ではない、ルールに従った掘り進め方を、“工法”という。
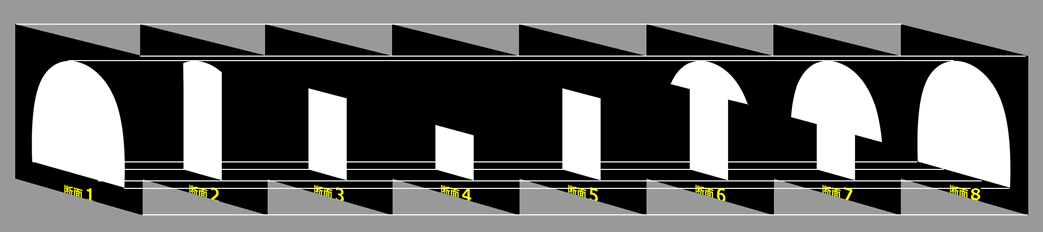
上図の左側が、私の侵入した西側の坑口で、東側は閉塞していたが、以前は貫通していたと考えて、断面8を右端(東口)に置いた。
この図を眺めれば、この隧道が東西の坑口から同時に建造されていたということが、自然に理解されるだろう。
(ただし、導坑がどちらか一方から掘られたか、両方から同時に掘られたかは不明である)
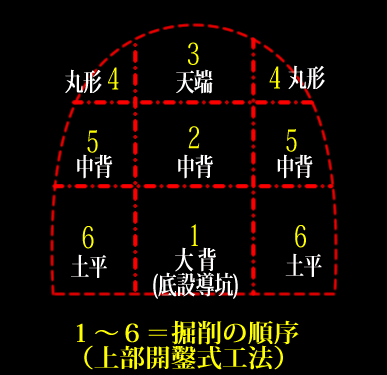
上部開鑿式工法。
それがこの隧道の工法の名称である。
その事は何か文書や証言として見たわけではないが、先ほどの図から分かる事である。
左図は、上部開鑿式工法の掘削順序の一例を示したものだ。
隧道の古典的な工法の多くでは、このように完成形の断面を9つに分け、その掘削順序によって区別された。
1番(大背)を底設導坑として掘り始める方法は、上部開鑿式工法や新オーストリア式工法などがあった。
3番(天端)を頂設導坑として掘り始める方法は、ベンチ式工法や日本式工法などがあった。
地質が極めて良い場合や、最終的な断面が小さな隧道では、導坑を用いず全断面を一気に掘り進める全断面工法が選ばれる事があった。
他にも様々な工法があって、地質の良し悪し、工費、工期、巻き立ての有無、地域性など、様々な条件から選択された。
これらは古代から改良されて受け継がれてきた伝統的な掘削方法だが、現代ではあまり用いられていない。現代では隧道の周囲の地山に鉄柱を打ち込んで補強しながら全断面を掘るNATM工法や、円筒形のシールドマシンで全断面を掘りながら巻き立ても自動で行うシールド工法が主流である。
なお、本隧道には掘削途中の隧道を補強するための、支保工とよばれる支え木が一切見られなかった。
このことは、隧道の地質が比較的良好であると判断されていたことを意味している。
そして、半世紀以上を経た現在でも目立った崩れがないという事実は、当時の技術者の見立ての正確さを示しているのである。
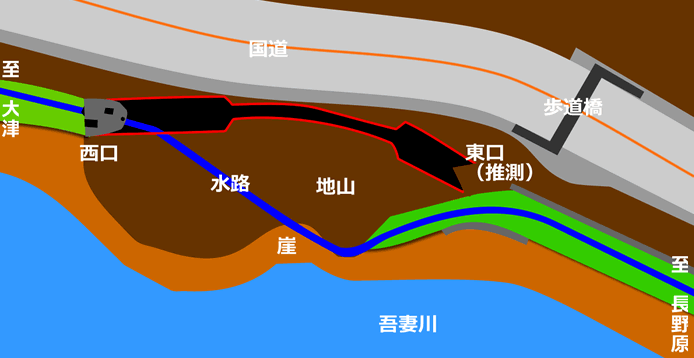
断面の変化にばかり着目していたが、地中で分岐する隧道と水路の関係も、この隧道の興味深い特徴であった。
なぜ、水路は素直に未成隧道を利用しなかったのだろう。
この疑問の答えとして考えられる可能性はいくつかあるが、水路の方が古かったと考えるのが最も自然だろうか。解明するには、大津用水の歴史を調べねばなるまい。
左図は、未成隧道と地下水路の位置関係を模式的に示したものだ。
縮尺などは適当というか、そこまで凝って作っていないので、まあ大体の繋がりを表現しただけだ。
現地の探索では解明できなかったことに、東口の所在地がある。
だが、相当高確率で跡地は次の画像の場所だったと思う。

こうして外から見ても、隧道があった痕跡は少しも残っていないが、上部に国道があるので、その拡幅とか歩道の整備といった何らかの事情で、一度は貫通していた坑口が崩され、また埋め戻されたのだと思う。
その後に大津用水が整備されたのではないだろうか。
以上、未成隧道が教えようとしてくれることを、私なりに少しでも多く理解しようと努力した。
でも、まだ分からないことが多すぎるので、続いてはいつもの… ↓↓↓










