
�ߋ��̎��̒T���̒��ł��A�����炭�����Ƃ��d���I�ɍs��ꂽ����̒T���ł��������A���Ԃ����̋��͂������āA�听�����ɖ�������B
���̊�т����܂�ɑ傫�����������ŁA�A���ɂ������|�[�g�������n�߂����A�V���Ȋ��㒲���̋@��Ȃ��܂܂ɏ����I���悤�Ƃ��Ă���B
���q�g���l���̐V���R����ɂ킽�闈���ɂ́A�T�����I�������܂ł��������̓䂪�������c���Ă���B
�Ȃ��ł� �ő�̓�́A����̃��C���^�[�Q�b�g�ƂȂ�������詓����A�����ꂽ�̂� ���낤�B
����ɂ��ẮA���m�ȏ�S���Ȃ��B
�����_�Ŕc�����Ă���A����詓��Ɋւ���B��̕����I���́A�{�ґ�P���ŏЉ���i�����Ă��̒T���̂��������ƂȂ����j�A�w����k�����y�j�����i��ҁj�x�i���a49�N���j�ɂ��鎟�̋L�q�ł���B
���a23�N�ɂQ��ڂ̃g���l�����@��ꂽ�Ə�����Ă��邪�A����ȑO�Ɏg���Ă�������g���l���������ꂽ�̂��́A�G����Ă��Ȃ��B
����A����̌��n�T�����ɉ�ǂ����u���ΔV��v�ɂ́A��L�����炩�ɖ���������e���܂܂�Ă����B��������Ǝ��̂悤�ȕ��͂��B
����̒���80�ԁA�����̍���8�ځA��9�ځA�����̐؊�40�ԁA�������H���a27�N9���A��28�N5���v�H�����B
���l��A����l��A�����̕�z�̂����̘H�~�͉����s�\�ȎR����z�����Ă݂܂��B���a27�N�A�c��̕�ɗ����āA�悵�����ɓ�����@�낤�ƈ�O���N������l�̒j�������B���̐l�̖��͍��X�ؘZ�Y48�ˁA��Ђ̓s��瓦�ꋽ���ɋA���ĊԂ��Ȃ��ނ̊�ɁA���y�̔��W�͌�ʂ̊m�ۂ����Ȃ��Ǝʂ����ɈႢ�Ȃ��c�c
�����́A�Q��ڃg���l���̊����N�Ɋւ��镔���ɂ���B
�ʂ����āA�����N�͏��a23�N�Ȃ̂��i���y�j�����j�H�@���a28�N�Ȃ̂��i���ΔV��j�H
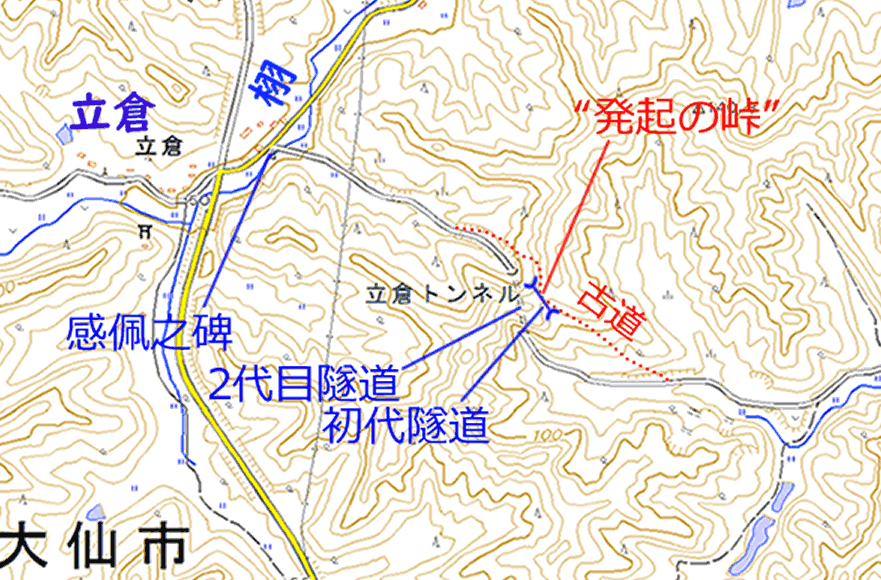
�Ȃ����̂悤�Ȗ������������̂��s�v�c�����A�����Ƃ����ƁA�Ȃ��u���ΔV��v�͏���詓��̑��݂ɂ��đS���G��Ă��Ȃ��̂��낤���B
��X�͌��n�T���̂Ȃ��ŁA�蕶�ō��X�ؘZ�Y�����������狽����詓����݂N�������ƂɂȂ��Ă���A�u��z�̂����̘H�v������Ă���B
�����Ă��̒���ł����g���N�̓��h���A����詓��̎��߂Ȓ����ł��邱�Ƃ�m���Ă��܂��Ă���I
�c�c���������������Ƃ����A���̔蕶�̋L�q�͏��X�s���R�Ȃ̂��B
�u���a27�N�A�c��̕�ɗ����āA�悵�����ɓ�����@�낤�ƈ�O���N�v�������̑����ɁA���ɏ����詓������݂��Ă����Ƃ�����A�s���R����Ȃ����B
���̏�ʂ��^������тт�ɂ́A���a27�N�̎��_�ŏ���詓��������Ă͂Ȃ炸�A�Z�Y�������̓��Ŕ��N����詓������A����詓��łȂ���Ȃ�Ȃ��B
�������A�蕶���ō���Ă���詓��̒����i80�ԁ�145���j�́A�����̏���詓��Ƃ͕������Ȃ��B����詓��́A��������20�`30�Ԃ̒��������Ȃ��B
�c�����Ƃ��A���̔蕶��^�ʖڂɍl�@����̂́A���N�̏�ʂ��n��łȂ��Ƃ����O��̘b�ɂȂ�̂����c�B
������������A�w���y�j�����x�Ɓu���ΔV��v�̂����̋L�q�́A����詓��ƂQ���詓��̌��݂Ɋւ��āA���G�ɗ��ݍ����悤�ȍ��������Ă��āA���ۂɂ́\�\
���a23�N�ɁA��Ђ̓s���ċ����ɖ߂����Z�Y���̔��N�ɂ���āA�����̓��̒����ɂ͂��߂Č��݂��ꂽ�̂��A����T����������詓��ł����āA���ꂪ�s�ւ��������߂ɁA���a27�N����28�N�ɂ����āA���߂Č��݂̗��q�g���l���̈ʒu�Ɍ��݂��ꂽ�̂��A�Q��ڃg���l���Ȃ̂�������Ȃ��B�@
�\�\�Ȃ�Ă��Ƃ��A�l���Ă���B
������A�V���Ȑ��ʂ���������A�NjL�������B
����詓��̏v���N�𖾂����V�������������ꂽ�I�@�@2019/3/9�NjL
�{�҂ōŌ�܂Łg��h�������A�g����詓��h�̏v���N�B
����A�ǎҗl�̐s�͂ɂ��A�������������������I�Ȏ������������ꂽ�B
���킹�āA���X�ؘZ�Y�������݂N����詓����A����ƂQ��ڂ̂�����ł������̂��Ƃ�����ƁA��̐������݂��Ă����Q���詓��̏v���N�ɂ��Ă��A�M�ߐ��������Ǝv��������A�{詓��Ɋւ����͂قڊ��S�ɉ𖾂����Ɏ������B
�ȉ��A���̓��e�ɂ��ĒNjL����B
���҂́A���s�ݏZ���c�����ł���B
���́A�H�c�����s���^�c���Ă������s�A�[�J�C�u�Y�i�p�������Ȃ���A���݂�c�����Ă��Ȃ������j�ɓƎ��ɖ₢���킹���s���A�����̒����ɂ���āA����Љ�镶���̑��݂����炩�ɂȂ����Ƃ����B
�����̃^�C�g���́A���a53(1978)�N2���ɐ���k�������掺�����s�����w���̐̂������˂��x�ŁA�u�L��ɂ�����ڂ��v�Ɍf�ڂ���Ă����u���̐̂������˂āv�Ƃ����R�[�i�[���W�����e�ł���Ƃ����B�����Ă��̂Ȃ��ɁA����u���q�̓���v�Ƃ����^�C�g���̉��^����Ă����̂��B
�ȉ��A���������Ȃ邪�A�ɂ߂Ċj�S�I�Ȃ��̓��e�̑S����]�ڂ���B
�܂��́A����詓��Ɋւ��O����������B
�@��͖��̂悤�ɁA�傫�Ȃ����čL���n��ł��邪�A���ɂ͗��q�̂悤�ɁA�������܂����Ƃ���ɂ��镔��������B���̐̂̓��H�̊J���Ȃ�����̘b�ł��邪�A�u�H�̒��̗��t���A�G�̂�����܂ő����ŕ��������̂��v�ƁA�����\���z�����k���A�����ɂ����S�[�����Ɍ��̂����B
�@����Ȗ�ŁA�̂͂ƂĂ��s�ւȏ��̂悤�ł��������u������Βʂ���v�̌��̒ʂ�ŁA���͕֗��ɂȂ����B����͎R��z���A��O���̗����ɋ߂��A�����ɍs���Δ������̂ł��Ȃ�ł��ł���B����ł͂��߂́A�����z���ĉ����������̂����A�R�͑S�̓D��ł���Ƃ��납��\�y���͂��Ēꂪ�o��ƁA���ׂ��ĕ����Ȃ��B�J�̓��Ȃǂ͎�ɂЂǂ��B�����ŒN�����ƂȂ��u�D��̎R������A�����ʂ�����悢�v�Ƃ������ƂɂȂ�A���q�A����A�z���̐l�B�ŁA�吳�\��N�̏H����~�ɂ����Č@�葱���A���ɗ��\��N�̏t�A�ђʂ����̂ł���B�������\�ԗ]�𗼕��̌�����l�ܐl���Ō@�����Ƃ������Ƃł���B
���̓䂪�A����Ō����I
����詓��̏v���́A�吳12(1923)�N2���I
�����ɁA�S���̐������o�ė����B70�Ԃ́A�����悻127���ɑ�������B
�����A����͉�X���T���ł���詓��̒��������{���炢�������悤�Ɋ�������B
��������̊�30���قǂ̈ʒu�ɕǂ�����̂����A���̐�̕s���B��Ԃ͎��̍l���Ă���ȏ�ɒ����̂�������Ȃ��B�܂��A�ȑO�T���������ː�詓��i���́j�ŋN���Ă����悤�ɁA������̕����ɂ���čB������ނ��āA���݂̑S���͒Z�k����Ă���\�������邾�낤�B
��ې[���̂́A�{�����Ɂu�D��v�Ƃ������X���I�ȗp�ꂪ�o�Ă��邱�Ƃ��B
�D��i�ł���j�́A�����ł͎�ɕŊ�i������j�ƌĂ��͐ϊ�̈��ŁA���̖��̒ʂ��ɔ������₷������������B
�y����詓��̕Ǖ��z ���y2���詓��̗��Օ��z
���y2���詓��̗��Օ��z �ɁA���̓����I�Ȕ�̕���������ʂɑ��݂��Ă����B
�ɁA���̓����I�Ȕ�̕���������ʂɑ��݂��Ă����B
�吳����̑������n���𐳊m�Ɍ������Ă������ƂɊ��S���邪�A���̂��Ƃ͖���34(1901)�N�Ƒ吳3(1914)�N�ɑ������ōs��ꂽ������ł̉͐�詓��H���ɂ���āA���l�̊ԂɌo�����~�ς���Ă����\�����f�킹��B���ɑ吳3�N�̌���ƂȂ����z���̒n���́A詓��@�w�̓����҂Ƃ��Ă����ɂ��o�ꂵ�Ă���̂ł���B
�������āA�ߗׂ�3�̏W���̐l�X�̗͂Ō@�蔲���ꂽ�Ƃ�������詓��̃G�s�\�[�h�ɁA���X�؉��͓o�ꂵ�Ȃ��B
��͂�ނ̓o��́A2��ڂ̂��Ƃł������B
�ȉ��A�㔼������]�ڂ���B
�@����ŗ����Ƃ̌�ʂ͔��Ɋy�ɂȂ�A�F�X���тł��������A�������Ă��邤���ɐ��̒��́A�O���O���i�����āA���]�ԁA�����Ԃ̉^�s�ƕς���ė����B�����Ȃ�Ƃ��̓����ʂ�ɂ́A��������̎R��o��Ȃ���Ȃ�ʂ��ƁA�����܂ł̓��H�͂ƂĂ��Ԃ̒ʂ����̂ł͂Ȃ����ƂȂǂ���A�ǂ����Ă����������������ʂ��āA�����ɂ����܂ł̓��H���悭���Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂɂȂ����B
�@���̎��ɁA�������a��\�N�㌎�_�ސ쌧�ߌ��̃j�b�T�������Ԃɂ����A���X�ؘZ�Y�������̗��q�ɋA���ė��āA���̌�ʂ̂��܂�ɕs�ւȂ̂�Ɋ��������J���̂��߂ɁA�V�����֗��ȓ����ʂ��A�����ɓ��H�����C���Ȃ���Ȃ�ʂƌ��S�����̂ł������B
�@��U�v���������Z�Y�͐��ɐ^���Ŏ��瑼��������āA������O�����ʂɂ������̂��āA�����̊��W�߂�ȂNj�S���d�ˑQ���ɂ��ē���\���N�\�ꌎ���Z�����֓��Γ�i�Z�Y�̌Z���O�̓�j�j�����ʂ��͂��߂�Ɏ������̂ł���B
�@���ꂩ��͈ĊO�����i��ŁA����\���N�O���A�ђʗ������邱�Ƃ��ł����̂ł���B����̊Ԍ��͋�ځA�����͔��ځA�����\�ԑS�̂ɗ��������킽�����B�����ɓ���܂ł̓��H�́u���P�ѓ��v�Ƃ��ĉ��C����A���ł͈����x�̑�^�Ԃ��y�X�ƒʂ��Ă���B
�@���������Ɛr���y�X�ƌv�悳��H�����i�悤�Ɏv���邪�A������݂�A�Z�Y���ߌ�����A���ė��āA���̂��Ƃ��l���o���Ă�����ɁA���N�̔N�����o�߂��Ă�����̂ŁA���̊Ԃ̋�J�͌����ď��Ȃ��Ȃ��̂ł���B
�@���͂Ƃ�����A����͊W�҈ꓯ�̈�v�����w�͂ƁA����̋��͌㉇�������Ă͂��߂āA���̑�Ƃ͐��A�����̂��Ƃ͌����A�܂����������̏���O�A����ƂƂ��Ɋт��ʂ����Z�Y�́A���E�s���̈ӎv�́A���ɋM�����̂Ƃ��ׂ��ł���B��������A���q�����ł͂��̌��ɂނ���邽�߁A�R�јZ���l���i�����뒬���]�j�����̂ł���B�@
�Q���詓��̏v���́A���a28(1953)�N3���I
������������v���N�́A�u���ΔV��v�̋L�q�������������悤�����A���܂Ō���ƁA�蕶�ł�5���ƂȂ��Ă���A2�����̂��ꂪ����B
�܂��A詓��̒����⍂���E���Ȃǂ̐������A�蕶�ƈ�v���Ă��邪�A�u�S�̂ɗ��������킽�����v�Ƃ����̂͏����̏�B
���݂���|�S���̃Z���g���ł͂Ȃ��A�����炭�͖ؑ��̎x�ۍH�������Ă����̂��낤�B����詓�������₷�����Ƃ��A��������\������Ă����̂ɈႢ�Ȃ��B
��L�̕��͂ɂ���āA����܂ŕ�����Ȃ��������X�؉��̂����u��Ђ̓s��v�i�蕶�j���ǂ��ł������̂��i���l�s�ߌ��j�Ƃ������Ƃ�A�����ɖ߂��Ă��������i���a20�N9���j�����������B
�����āA�蕶�ɂ͂Ȃ������ނ̉��̋��͂�A�����ɑ���ɂ��Ă�������Ă���A��A�̍H�����ɂ߂ĉ~���ɏI���������Ƃ��f������e�ƂȂ��Ă���B
�Ȃ��A���̂Q���詓��́A���X�؉��ɂ��J��Ɓu���P�ѓ��v�i���P�Ǝ��ƂŐ�������閯�L�їѓ��j�̐�������20�N��̏��a48(1973)�N�Ɏ����āA�O��̓��ƂƂ��ɑ�K�͂Ȋg���Ɖ��C���A�u���q�g���l���v�Ɓu�劲���ѓ��v�ւƐ��܂�ς�����B���ꂪ����ɔ����I���o�����݂ǂ̂悤�ɂȂ��Ă���̂��́A�{�҂Ō����Ƃ���ł���B
���͍͂Ō�A���M�҂̑̌��L�ɂ���Ē��ߊ����Ă���B
�@���͈�U�Ԃœ�O���̓�������܂Œʂ�ʂ��A�A��͎Ԃ�����Ĉ������A�����ė��q�̓����܂Ŗ߂��Č������A�����͋@�B�ɂ����͂ɂ�����炸�A�{�c���A�{�c���߂͂��꒚�Ō@��i�l�B�́A�O�͂̋����A�O�ꂵ���C���̂����܂����A���̉���̂��o�����̂ł������B�����̑��̊�ǂɍ��Ȃ��c���Ă���߂͂��̐ՂɁA�J������̂������A�^���^���Ɗ��̂悤�Ȑ��H�̂Ȃ��ꂩ�����Ă���̂�������u�A�����m��Ȃ��������ɑł��ꂽ�̂ł������B
�@�@���a�l�\�O�N����

�Ō�ɖ������ꂽ�A���ɂƂ��ẴT�v���C�Y�B
���a43(1968)�N7���̎��_�ł́A���̏���詓��͒ʂ蔲�����\�������̂��낤���B
���͖{�Ғ��ŁA����詓��̓V�䂪�ɒ[�ɒႢ���R�ɂ��āA�O������c�y���������܂ꂽ�\�������������B
�����Ă��̋@��������Ƃ�����A����͏��a48�N�̗��q�g���l���Đ����̎��ł͂Ȃ��������Ə������B
�}�炸���A��L�̋L�q�́A���̎��̐��������삵�Ă���B���a43�N�ɒʂ蔲����ꂽ���㓴��̓V�䂪�A
�������炱���܂ŒႯ��A���̂��ƂɑS���G��Ă��Ȃ��͕̂s���R�Ɏv����̂��B
�Ȃ��A�{�҂ŐG��Ȃ������Ǝv�����A�m���ɏ���詓��̓����t�߂̓��ǂɂ͋͂��Ȃ����@��̍��ՂƂ݂����w�̍����c��ǖʂ��������B
�����炭�Ŋ�̓����ɂ���đ唼���������Ď���ꂽ�Ȃ��ŁA�S�苭���c�����B��̕��������A���M�҂͂����ڂɂ��Ċ������q�ׂĂ����B
���̂��Ƃ́A���M�҂��ԈႢ�Ȃ�����詓��ɗ��������ł���悤�ɂ��v����B�܂��{���̒f�ʂ�L���Ă�������詓���O�ɂ����̂��낤�B
�i�����܂����j
�ȏ�ɂ��A���q�̂R��ɂ킽��詓��̕ϑJ�́A���̑S�e���𖾂��ꂽ�Ƃ����邾�낤�B
���҂̓c��������сA���������ɂ�����ꂽ���s�A�[�J�C�u�Y�E���Ɋ��ӂ��܂��B





























