最終試練?! “スパルタ谷”の死闘

2008/7/31 14:01 14.6km 《現在地》
突破出来ないなんてことが、もう許されない状況で、戦慄すべき展開が待ち受けていた。
ここしばらくは正面突破に窮する難所が現れておらず、実際、地形的に最も険しいとみられる領域は通り抜けていたし、少し前には“石垣”といういう分かりやすい“褒美”を得たことで、私の中でなんとなく、もうこれ以上の難所は現れないのだろうという予断が生じていた中での、突然の反旗であった。
この時の私は決して油断していたわけではなく、というか、油断していてもいなくても、この展開は変わらなかった。
出発から9時間をほぼ歩き通した今なお、3km近い峠までの残距離があり、かつその峠は生還のゴールではない。しかも、降って湧いたような雷雨の恐怖や、常にあるダニ害と熊害の恐怖があり、重石をつけて歩いているような両足の強い疲労感もあった。加えて、もう撤退が許されがたい地点に達しているという状況が与える大きなプレッシャーもずっしりと重石のように感じられた中で、私が、予断という名の希望に縋っていたまでのことだった。
端的に言って私に不備はなく、ただただ神か三島か誰の差配かは知らないが、踏破者にさらなる試練が与えられたことだけが真実だった。
これぞまさに“スパルタの谷”であると、私は咄嗟に名付けていた。

地形としては序盤で突破した“若見薙”とよく似た大型ガリー、常には水が流れていない涸れ谷である。
山肌の浸蝕に弱い部分が雨水などで集中的に削られた結果、表土が失われて地肌が露出し、岩盤にも浸蝕が進んでいる。
山肌を横断していたはずの道は見事に寸断され、もともと橋があったやも知れないが、両岸とも著しく険悪であるため痕跡は無さそうだ。
まだ目前に達していないが、ここから見ても既に凶悪さが際立っており、正面突破は無理だと察する。
明るさから見るに、上もますます険しい感じであるから、突破口は、“若見薙”の時と同じく、下方に求めるよりないだろう。
が、その迂回も容易ではなさそうだ。
こちら岸もシダが疎らに生えているだけの急斜面で、前半戦で私がうっかり尻に孔を食らった場面を彷彿とさせる。
だが対岸は輪をかけて険しく、ほとんど岩崖の鋭さとなって、その上に見える道の続きを遠ざけていた。

正面突破は無理だと分かっていたが、突破ルートを俯瞰で探る意図もあって、道が切れている先端まで迫った。
そして、覗き込む。
……落ちたら、助からない。
両岸とも、絶望的に切り立っている。“スパルタの谷”は、甘くはない。
そして、この危機的な場面で、スポットライトみたいな日光が久々に射し込んだ。
これは、励まされていると解釈して良いのか。
それは分からないが、この時点で強い雨が降っていたら、前進に窮する場面であったろうことは想像に難くない。
ありがたく、このうちに突破してしまいたい。
突破した先がどうなっているかは、とりあえず考えず、ここに全力を投入しよう!

すぐさまガリー底への下降ルートを探し出した。
突端から20mほど戻って、土のシダ付き斜面が谷底近くまで続いている部分を発見し、そこを下りる。
このままガリー底を伝ってずっと下まで下りてしまえば、地形はもっと緩やかそうに見えたが、それをすると今度は対岸の道へ復帰するのが大変そうだった。
それでも時間に余裕があるのなら、ここを安全に突破するルートを遠方に捜索することは出来そうな感じがした。
あくまでも狭い範囲内で解決しようとするから、対岸の岩場と格闘することを余儀なくされる感じだ。
しかし現実的に、今の私は急がば回れを信じてばかりもいられない状態だ。
具体的には、今から5時間以内に男鹿高原駅まで辿り着けないと、帰り道がなくなる……は大袈裟かもしれないが、今日中には帰宅できない。その場合、栃木市辺りでもう一泊しなければならなくなるだろう。最悪それを受け入れるにしても、もう4時間もすれば日が暮れる。その前に下山できないと本格的にマズイのは変わりなく、どんな難所が待ち受けているかも分からない距離がまだ3km近くある以上、ここで貴重な時間を余計に費やすのは問題だった。

スパルタ!!!
スパルタ谷の底の様子がこれだ。
先ほど崖の突端から見下ろしたのも、この辺りである。
もし水が流れていれば確実に滝となるような傾斜であった。
いま一滴の流れておらず、かつ苔などで滑りやすくもなっていないことは、幸運であった。
そのお陰で、傍目にはいささか無謀にも見えるかも知れない、この先の綱渡り的突破ルートに挑戦することができた。
動画も撮ってみた。
周囲の様子を見渡すだけのとても短い動画だが、見上げた両岸の険しさと、登るべき高さを見て欲しい。
ここはもし探索の序盤で遭遇していたら、まず間違いなく大規模な迂回を選択して、こんな直接的に踏み込むことはしなかっただろうと思える、とても危険度の高い場所だった。
だが今は時間がない!

ガリー底に下りはしたが、最大の難関は、ここから対岸の路盤へどうやってよじ登るかだ。
真下からよじ登ろうとすると、この写真のような崖が待っている。
上半分のポヨポヨとした草付き斜面ならまだしも、手の届く範囲にある鼠返しのような最初の落差5mほどは、さすがに登りようがない。
なんとかしてこの最初の5mだけでも迂回しないと、無理である。

そこで、幸いにして水がなく、ゴツゴツとした険悪な険しさが逆に豊富な手掛りと足掛りを提供してくれているガリー底を、このまま少し上流まで登ることで、対岸との高度差を埋めようという作戦を選んだ。
5mほど登ったところから、対岸の草付きを斜めに路盤まで登っていこうという算段である。

こんな感じにな!

目標とする高度まで、徒手空拳でよじ登った。
足がかり、手掛りは豊富だと書いたが、危険な浮き石もあり、万が一バランスを崩して転落すればただでは済まない落差と傾斜があった。
股の間に見下ろされる高度感も物凄く、怖気るものがあった。
写真はスパルタ谷上部の様子を撮影。
これ以上は登らないが、谷はますます険しく細くなって、黄昏を帯びたガスの中に消えていた。
今度はここから斜め右方向へ振り返って……

この草付きをよじ登るのだ!
草というか、痩せた笹が岩場に付いた浅い土にこびり付いたような斜面である。
ここも濡れていればどうなったか分からないが、私は無事にここを攀じ上がることに成功する。
例によって、登っている最中の写真は撮っていない。

14:08
“スパルタ谷”の突破に成功!
出来るだけ時間を使わないため、最小限度の迂回による突破を目指した結果、少しばかりリスキーな突破方法を選んだが、何度も言うように、もし谷が濡れていたらこのルートは選べなかった気がする。

は ぁ は ぁ … …
息を整える時間くらいは許して欲しい。
息を整え、すぐさま、前進を再開しようと強く思ったが、なかなか動き出せない……。
はぁはぁ……。
…峠まであと2.6kmくらいだろう。
ほんと、今みたいなのはもういらないぞ。
探索中のドキドキは楽しいが、度が過ぎれば身を滅ぼす。
真面目な話、もう足が重くて堪らないんだ。
急にスイッチが切れて、1時間くらい座り込んじゃいそうな不安がするんだよ。厳しく自分を律さないと、勝手に休もうとする。
歩き続けた時間と距離を考えると、これまでの私が体験したことのない体力消耗の領域に入っている可能性があった。
夢幻に眠る工事の褥(しとね)

14:08
久々の“大難所”であった“スパルタの谷”は、多少無理をしたことで、7分という短い時間で横断することに成功した。
大事をとって大きく迂回すれば、この数倍の時間はかかったと思う。
そうして谷の先を歩き出した1分後、タラッと冷や汗。
ここもあともう少し大きく削れてしまえば、すんなりは通れず、面倒な迂回をしなければならなくなる感じだ。
今はまだ、ギリ地続き。
助かった。

その先も、仄かに断絶の予感を感じさせる、危うい雰囲気の道が続く。
全体的に地形が険しく、崩壊も進んでいる。
またいつ大きな崩れが現れても不思議がないと思うと、恐い。
もう何事もなく、私を峠へ連れて行って欲しい。 本当に、何事もなく……。
遺構が見たいとかそういう贅沢も言わないよ。背に腹は代えられぬのだから。

14:18
が、そんな薄氷のような道を10分ほど耐えて進むと、どうにか危機を脱したらしかった。平穏な森に道が入っていくのである。
と、同時に、ここで急に正面からぶつかってくる風が強く感じられるようになった。
それはきっと、正面にあるとみられる桃の木峠の鞍部を抜けて吹き下ろしてくる風だと思った。
汗みどろの全身に染み渡るような心地の良い風だった。それが目的地から来ていると思えば、なおのことだった。
三島よ、いい加減に峠をよこせ。
本当にくたくたなんだ。時間が不安だから、ずっと休憩したいのに我慢して歩いているんだぞ。限界が来てしまう前に……!

わーーっ!(歓喜)
ふと見下ろせば、善知鳥沢の本流と見られる水のせせらぎが、あんなにも近くに!
7時間以上前に“大旗高橋”で渡って以来の本流だ。
この間、ずっとこの谷の中にいはしたが、簡単に行き来の出来ない高所の通過を余儀なくされ、こんな近づいたことはなかった。
このかつてない景色の変化に、GPSという現在地を確実に知る手立てを持っていなかった私でも、峠への接近を心底信じられた。
これは本当に、あともう少しなんだな!(歓喜!!!)

14:23 15.0km 《現在地》
な! なんだこれは?
道が、もう1本ある?!
左へ分れて登っていく道があるように見えるんだが、目の錯覚だろうか……?
思えば、これまで、当たり前のように、ずっと一本道だった。
塩原新道から分かれる脇道がないことは、この道が実用としてほとんど生きなかった証といえるだろう。
二つの地点を結ぶ用途で作られたきり全く発展しなかったから、分岐がなかったと考えられる。
が、いまはじめて例外が現れたのかもしれない。
これは、事前情報からは全く予期しない遭遇だった。
今回探索における唯一の先行する探索情報と言うべき、日光森林管理所OB作成の“三島街道(通称)位置図”にも、一切の分岐は描かれていなかったのである。
……もしかしたら、新発見なんだろうか……。
嬉し ……くない。
というか、有り難くない。
なぜなら、今の私には脇道の行先をチェックしている時間がないんだよッ!(涙)
……まあ、生還さえすれば、不可能なことではないだろうから、これは再訪するしかないのか…。
もう当分は来たくなかったのに……。
ったく、なんなんだよこの道はよぅっ!
この場所で撮影したボイスメモ代わりの動画。
低解像度のこの動画でも、広い本線とみられる正面の道と、狭い支線のような左の道があることが見て取れると思う。
あと、先ほども言及した峠から吹き下ろしてきているとみられる強い逆風の存在が、さざめきとしても、木の枝葉の動きとしても、現れている。
そして、私の抱えた強い疲労は、ろれつと抑揚が弱くなった語り口に露見している。

泣き言を呟きながらも、「3分だけ」という、我ながら何かを解明するにはあまりに少なすぎるタイムリミットを宣言することを免罪符として、その脇道へ立寄り始める私がいた。
この写真は、少しでも寄り道の距離を省略しようとして、メイン道から脇道が登っていこうとしている斜面上へ強引によじ登ろうとしているところだ。
すぐ先に、石垣と呼べるかは微妙だが丸い川石が雑に積まれているところが見える。そこが脇道の路肩だった。
地味だが、やはり人工の作為が加えられていると思う。

脇道側から分岐地点を振り返って撮影した。
両者の道としての規格の差は明らかで、同じ時代の道ではあるのだろうが、幅が2倍は違う。もちろん、下の本道が広い。さすがは、国道級の使命を与えられた道である。
一方の脇道は、普段の探索でも良く目にする、荷車がぎりぎり通れる程度の軽車道らしい感じ。これはこれで親しみは覚えるが…、今は余力が……。

14:25
ここは、広場……?
脇道は、本道からいくらも離れないうちに、だだっ広い場所に着いた。
それは明らかに人工的とみえる広場で、中央にひときわ大きな広葉樹が一本生えているほかは、笹と下草が繁る空間だ。
奥まで行くと笹が濃くなり見通しが利かないが、広場としての全体の広さは30m四方以上ありそう。
全体に一様な高さにあるこの広場は、本道から3mほど高い山側にあって、脇道によって到達するようになっていた。
この広場の正体は、なんだろう?
もしここが林道であったのなら、広場は作業員宿舎とか造林作業所とかを想定するだろう。

峠直下に存在する、この“謎の広場”の正体は、飯場跡 であると見る。
根拠は、探索前から内容を把握していた文献『土木県令三島通庸』(昭和54(1979)年/丸山光太郎 著)にある次の記述だ。
古町から四里ばかりの善知鳥沢に少し広い平地があったので、ここに土木吏員や土方達も飯場を建てて宿泊した。多いときには一日五千人も働いた。
三島通庸の県政については多くの一次資料(三島通庸関連文書)が存在し、それらを典拠として編纂された人物伝的な書籍も多くある。
上記の『土木県令三島通庸』は、中でも名著とされるものであり、土木工事についても他の文献に見られない多くの内容を含んでいる。
塩原新道の建設にまつわる内容も、この書が一番詳しいと思う。(本作の机上調査でも最大の情報源となっている)
そんな本に、古町(塩原)から約4里(約16km)の善知鳥沢にある少し広い平地に、工事を監督する県の吏員や工事にあたる人夫(土方)達が宿泊する飯場があったと書いてあったのだ。
同書には他にこのような飯場の記述はなく、これは塩原新道工事に関係する付帯施設として唯一無二の記録である。(一次資料にはさらに多くの記録がある可能性はある)
そして肝心なこととして、「現在地」は塩原から実測約15km前後のところであって、これは記述と合致する範囲内であると思う。
約123年前に、全く人家も集落も存在しない奥山にて繰り広げられた、異常に工期が短い人海戦術的突貫工事。
その実現のために用意された秘密の工事拠点の跡――これまで文献の中だけに知られていた施設が実在した痕跡を――私は探り当てたのではないだろうか。
だとしたら、これは大きな成果であると自惚れたい。

そしてこの飯場跡らしき広場であるが、その入ってきたのとは反対側の端から、今度は下り坂の小径が出ていた。
それを落差にしてほんの3m、坂道の長さにして20mほど下っていくと、これがまたもとの本道へ綺麗に戻ったのである。
この戻ってきた地点は、本道側から見ると最初の分岐からカーブを一つ回った先で、両者が離れていた長さは50〜60mだった。
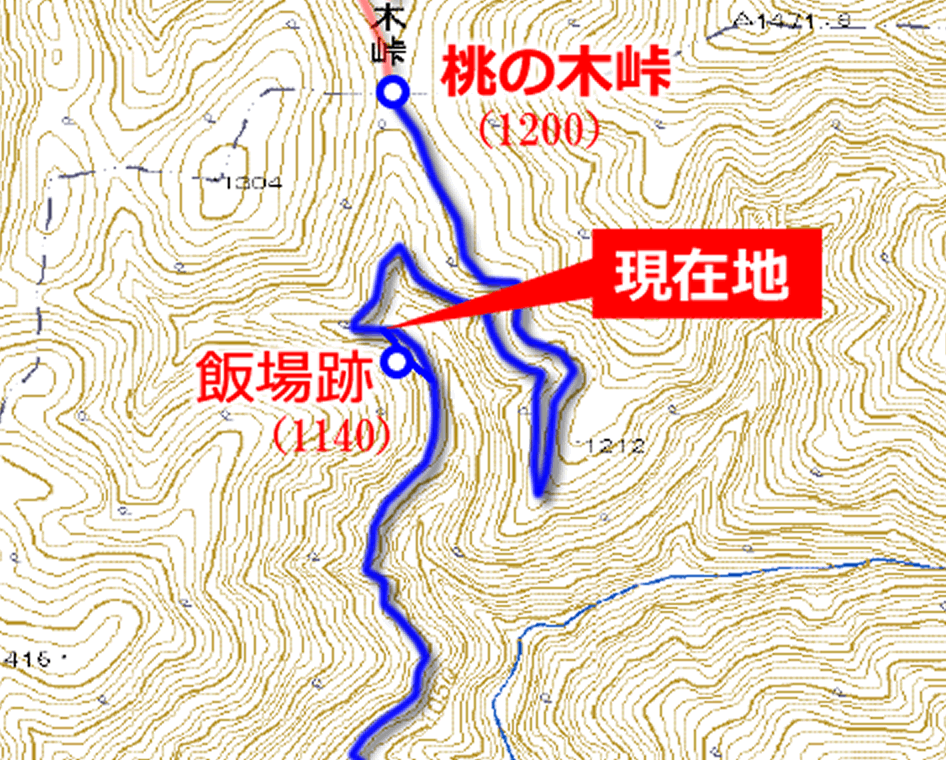
これを地図上に表現してみると上のようになる。
まるで、現代の高速道路の本線とSAPAを思わせる線形である。
このように飯場跡が行き止まりではなく、通過可能なピット方式だったことに私は驚いた。
わが国としては最初の近代交通といえる馬車の時代から、こういう現代の高速道路にもよく見られる線形が既に採用されていたものかと。冷静に考えれば、川の流れにも似た極めて普遍的な線形に過ぎないとも思うが。
ところで、かの万世大路の工事中には、県令である三島通庸本人が飯場に泊まって工事を督励したことがあった。
このことは、彼がどれほど万世大路に熱心であったかという語り草になっているのだが、塩原新道でもそのようなことが行われたかは伝わっていない。
それはともかく、工事の完了後に飯場は撤去されたとして、同時に塩原新道の長大すぎる人家のない山岳区間の途中には何らかの休憩施設が必要で、この峠下の広場は、旅人の休憩施設を設置するにもうってつけの場所であると想像できる。
したがって、この場所では開通パレードに臨んだ三条ご一行や、記録のために往復をした高橋由一が、足を止めている可能性がある。(後者に至っては宿泊した可能性もある)
今はただ笹深い広場であるが、かつて幾千幾万の人々が、この地を褥に三島の夢の手足となったものか。
夢見がちな私の瞼は、またしても熱を帯びるのであった。
もう完全に思い残すことはない。あとは、峠を越えるだけだ。
桃の木峠まで あと2.2km
| 当サイトは、皆様からの情報提供、資料提供をお待ちしております。 →情報・資料提供窓口 | |
|
このレポートの最終回ないし最新の回の「この位置」に、レポートへのご感想など自由にコメントを入力していただける欄と、いただいたコメントの紹介ページを用意しております。あなたの評価、感想、体験談など、ぜひお寄せください。 【トップページに戻る】 |
|