�@���̖ؓ����RRTA�@�i�������ꂪ��ԑ����Ǝv���܂��j

2008/7/31�@15�F30�@17.3km�@�s���ݒn�t
�����V���Ƃ̌����������B
���10���Ԕ��A��������17km���z���钷�r�z���A���ɍō��n�_�ł������̖ؓ��ɒH������̂ł���B
�����V���ƌĂ��p�����A�R�������牖������܂Ŋm���Ɍq�����Ă��邱�Ƃ��A�����ɂ��m���߂邱�Ƃɐ��������B
�V�R�̈ƕ��ɐ[�����݂��܂ꂽ���ٓI�ɒ�����ʂ��́A2�����O�ɔ��Α�����H�蒅�����Ƃ��ƕς��Ȃ��p�Ŏ����}�����B
�ƕ��𐁂������鋭���k�������݂ł���B
�������O��ƈႢ�A�J�ɍ~���邱�Ƃ͂Ȃ������B�r���̗��J�\��Ƀq���q���������A�����܂ŕۂĂA�������v���낤�B
���т̓��������B
�Ȃ�Ƃ������A�b���ɁA���e���Ȃ��c�c�i��j�B
�����ʂƂ����̂��������Ǝv�����A�Ȃɂ���ꂷ���������Ǝv���B��������ĂȂ��B

�O��i����Ɂj���t�����g�O���̖h���A������݁B
����������ǁA�u�݂��܁[�I�v�̐⋩�͂������Ȃ��B����͍��̋��т�����A�����|���|���o����̂ł͂Ȃ��̂��B
�܂��Ƃɂ����������������B
�Z�p�I�ȓ���g�ጩ��h�Ƃ��g�X�p���^�̒J�h�Ƃ����������������A��͂肱�̉����V���i�������j�̓���́A�q��Ȃ炴�鋗���̒����ƁA��������ĒT�������Ȃ��G�X�P�[�v���[�g�̖R�����ɂ���Ǝv���B
10���Ԉȏォ�����Ă悤�₭���ɒH�蒅�������A����ł܂����Ƃ����̂����낵���B
���͂�������ȏ�t������Ȃ����A���̓����z�肷�闷�l�̓����Ƃ��ẮA��������O��T���������[�g���t�ɐi���12km��̌����u�R�����v���z���A�����3km�قǕ������։������ʒu�ɂ���u�R�������v�܂ŁA��������1���ŕ����ʂ��K�v����������������Ȃ��B
��������R�������܂Ŗ�35km���邪�A�����V���͂��̖��O�̒ʂ�A�S���V���ɐ�J���ꂽ���ł��������߁A�����ɏW���͑��݂��Ȃ������̂ł���B

��ʂ��̏ڍׂ͑O��Ń��|�[�g���Ă��邪�A����200m�͂��낤���Ƃ����ُ�Ȓ����������A�����炵�Ƃ��Δ�ł���Ƃ��A�h��ɖڂ��䂭���̂͂Ȃ������B
�����A���̍ۂ����������́A��x����ΖY���قǂ̋�����ۂ�����B
�����āA���j���A�Ȃ��B
�����͓��{�ɂ�����n�Ԍ�ʎ���̍����I���H�Ƃ��āA�ق�̈�N�قǂ̊Ԃ́A�c�_�̏œ_�ł������Ǝv���B
�����炭�A���א��疜�l���ʍs���邱�Ƃ����҂��ꂽ�A����Ȑ�ʂ��������Ǝv����B
�������A�^���͂��̓��ɗ₽���A���߂�100�N�ł�10�l�������ƎR�����̊Ԃ�����Ă��Ȃ���������Ȃ��B
�Ƃ���ŁA��ʂ��̖k�����̌��ɂ����镔���ɁA���ɕ���ȏꏊ������B
���̑��݂͑O��C�t���Ă��āA�����炭�x�e���̐Ղƍl�������A�o���Ă͊m���߂Ȃ������Ƃ���ł���B
����A�Ō�̗͂�U��i���āA�o���Ă݂��B

����ɂ́A���̑�Q�������B
��l�ɃJ��������������A��ĂɃ^�[�U���̂悤�Ȑg�y���ŎU���Ă��������A����������ł��悭����j�z���U���̌Q�ꂾ�����B
���ܐl�ނ����Ԃ����A���̕���B
��͂�ԈႢ�Ȃ��l�H�I�ɐ��n����Ă���B
�L����10���l�����炢�B�O�Ɍ����g�я�Ձh���͋����B�����A������S�̓I�ɂȂ��炩�Ȃ̂ŁA���ɂ����n����Ă���y�n������̂����m��Ȃ��B

���ɕ��ꂩ�猩���낵����ʂ��B
�ʍs��������ɂ͂��傤�Ǘǂ��ꏊ�����A�֏��ł�����܂����A��͂�x�e���i�����j�ł��ݒu���悤�Ƃ��Ă����̂��B
���ۂ̂Ƃ���́A�S����Ȃ�������Ȃ����B
�����V���Ƃ������ɂƂ��āA���̓��̖ؓ��Ƃ����ꏊ�̑��݊��͂ƂĂ��傫�������͂������A�s�v�c�Ȃ��ƂɁA���̓��ɂ������{�݂ł���Ƃ��A�����ł̏o�����ł���Ƃ��A�����������Ƃ�`����G�s�\�[�h�͑S���������Ă���B����ɁA�R������j���싴���̃A���O������`���������R����A�Ȃ���������`���Ȃ��������A����������B�e���Ă���e�n�V�w���A�B�e���Ă��Ȃ��B�S���s���ł���B

15�F40�@�s���ݒn�t
������ʂ����������A���Ȃ���̖k���ցB
�O�q��������ւ̏����Ȋ�蓹���܂߁A���ɑ؍݂������Ԃ͖�10���B
�ЂƂƂ������~�߂͂������A�x�e�Ƃ�����قǂɋx�ނ��Ƃ͂��Ȃ������B���ԓI�ȃv���b�V���[����A���̋C�ɂȂ�Ȃ������B
��ʂ��ւ̓��B�́A����̒T���̖ړI���������A1���̍s���̒��ł́A�ʉ߂��ׂ��n�_�ɉ߂��Ȃ��B
��ʂ������̂ŁA��͑��₩�ɐ��ʂ𓌋��֎����A�邽�߂̋A�H�ֈڂ�B
���̌v�惋�[�g�͎��̒ʂ�ł������B
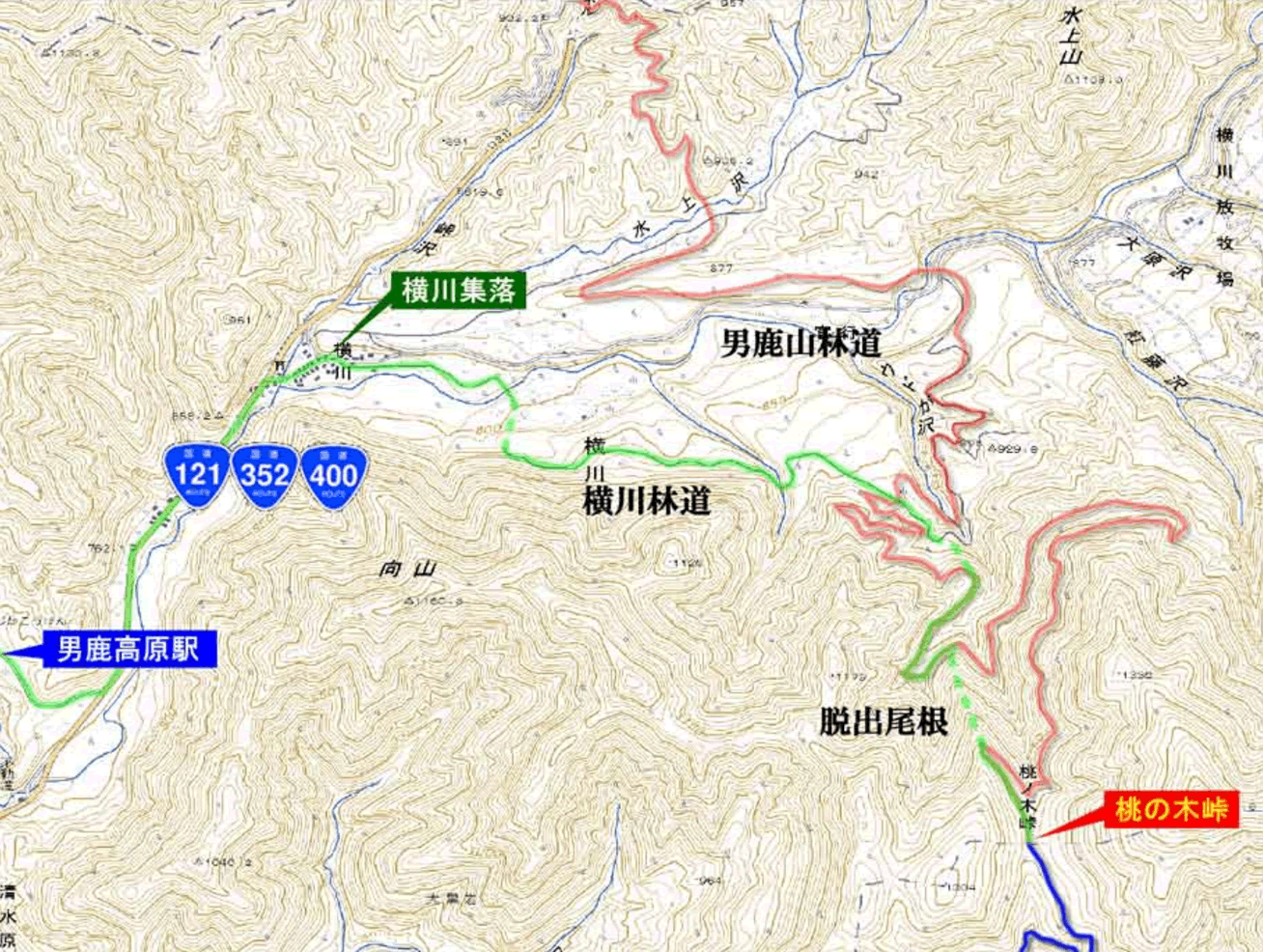
�����A�����o���������B
�Ԑ����A2�����O�ɓo�������B
�������̐����A����\�肵�Ă���ő��̉��R�R�[�X�ł���B
����́A�O��I�Ɏ��ԓI�ŒZ��ڎw�������[�g���B
���̂��߁A�r���ɂ͒n�}��ɓ��̂Ȃ���Ԃ�3�ӏ����邪�A�k���̋��݂��������čŒZ�œ˔j���Ă��������B
���̗\�胋�[�g��H�肫�����ꍇ�̑z�苗���́A���ݒn����ŏI�ړI�n�̒j�������w�܂Ŗ�7km�B���፷�̓}�C�i�X450m�B
���A�{�����ɓd�Ԃ̏��p���ɂ���ē���s����܂ŋA�蒅����^�C�����~�b�g�́A�j�������w18�F37�i������2����57����j�ł���B
�_���_���ȑ��ڂɁA������̃p���`���������Ă���c�c
15:40�@���̖ؓ�����̉��RRTA�A�J�n�I

15�F51
���̖k���ŏ��̐�Ԃ��J�[�u�i��ʂ��o�������400m�j�ł��邱�����A�ŒZ�E�o���[�g�̓������B
���K���[�g�͂������E�ɐ܂�Ԃ��Ă���A���������Ŗ�400m�A�����ɂ���160m�������Ăђʉ߂���܂ŁA���X4km���I�邪�A�������L400m�Ɍ���Ȃ��߂������ŏI��点�Ă��܂����Ƃ����̂��A���̔������g�����V���[�g�J�b�g���B
�Ȃ��A����͖`���ł͂Ȃ��B
�O��̒T���̋A�H�́A���̃V���[�g�J�b�g���\�ł��邱�Ƃ̊m�F�����˂Ă����B�@�˓��I

�������}�Ȕ����ł���A�����̐g����4�{�ɂ�5�{�ɂ��Ȃ����悤�Ɏv����قǂ̍��x���ɁA��u����␂ށB
�����A�ΖʑS�̂ɎႢ�q�o�������C���ɐA�т���Ă��邽�߁A�p�`���R�Ֆʂ̓B�̐X�̒ʂ�A�������藎���悤�Ƃ��Ă������܂ł͗������Ȃ��B����������āA�e�i�K�U�������`�[�t�ɃK�V�K�V�������B���������̓��肪�����Ȃ����A��Ŋ撣��B

16�F03�@�s���ݒn�t
�]����悤�ɉ���I����I���������ʁA12���Łg4km��ł���͂��̓��h�ւƓ]���o���I
���̎O���ɏ|�˂��V���[�g�J�b�g�̓}�W�ŋC�������ǂ��I�@�A�h���i�����o���I�I

���蒅�����n�_�����700m�́A�����V���ɏ]���ĕ����B
�{���Ȃ�{���U�X�ꂵ�߂�ꂽ�悤�ȋ}�Ζʂ��g���o�[�X���Ă�������Ǝv�����A���̕ӂ�́u�O���X���������v�̐l�X�̓w�͂ɂ���Č����ɕ�������Ă���̂ŁA123�N�O�̗��l�Ɠ������K���ŕ������Ƃ��o����̂��B
�i�Ȃ��A�������ꂽ�������݂ǂ��Ȃ��Ă��邩�͖��m�F�j

16�F20�@�s���ݒn�t
2�x�ڂ̃V���[�g�J�b�g�����ցB
�����́u���������v�̐l�B�����������V���[�g�J�b�g�Ȃ̂ŁA�Ȃ�̐S�z���v��Ȃ��B������₷�����A�����₷���B

�ł������V�_���n�ʂ��s�����Ă������e�L�p�L�Ɖ����čs���ƁA��4���Ŋቺ�ɍ������������Ă����B
�͂��I�@�������c�c
������݂��b

�_�[�[�[!!!!!!

16�F26�@�s���ݒn�t
���S�B
���ꂵ�ڂ��B
�������āA�n�ʂɐg�̂��߂荞�B

16�F33�@�i�܂����S���j
�ѓ��ɒ������u�ԁA���̐^�ɑ�̎��ŐQ�]�B
�܂��N���}�����Ȃ����낤���Ƃ�ǂ����ƂɁA���ꂩ��7�����o�߂��������܂��|�ꂽ�܂܁A�r�Ǝ������āA�����銴���ɂނ��ёς��Ă���B
���ł͂܂���@���������ďo���Ȃ��������т̕\�����A�����Ĕ�J�̕\�����A���܂����ő����ɔ�I���Ă���B
�������̂�15�F40������A�Ȃ��50�����炸�Ř[�̗ѓ��܂ʼn��������ƂɂȂ�B
�܂��ɗ����̂悤�ȓd�����R�B
���S�ɁA�����Ƃ������̑O��T�����������������B
�������ŁA�^�C�����~�b�g�܂ł͂���2���Ԃ���B�c��̋����͖�5km�����A�R�n�̑唼�͏I�����B
�c�c���������A�o�����邩�B
���̂ɁA�䖝�Ȃ��قǃA�u���W���Ă����B

16�F35
��������́A�O��̉��R�Ƃ͔��̕����ցA�����̉���ѓ�������čs���B
�O��͑f���ɓ��ɉ����ĉ��R�����̂����A�n�`�}���������A2km�قǐ�ɂ��邱�̗ѓ��̏I�_�܂ōs���Ă���A�n�}�ɂȂ��Ƃ�������傿�傢�ƃV���[�g�J�b�g����ƁA��葁������W���֒H�蒅�������������B����������B

16�F49
�������s���~�܂�̗ѓ����������āA�i��ł����ƖڂɌ����Ă���ڂ���Ă����B
�ł��A�p���Ƃ��Ă͑S�R�C�[�W�[�B
��肪����Ƃ�����A�߂��u���L�Ɍ������ꂽ�̂��Ǝv���قǃM�R�M�R�ƒɂޗ����̏�Ԃ��B
�����̎��]�Ԃ��~���߂��ă^�}���i�C�B

17�F05�@�s���ݒn�t
�c�c���A�@�H�蒅�����B
�����炭�������A�n�`�}�ɂ���ѓ��̏I�_���낤�B
GPS�Ȃ�����S�p�[�̎��M�͎��ĂȂ����ǁA���͂��đ��ƐX�Ɉ͂܂ꂽ�L��ŁA����ȏ�ǂ��ɂ��������тĂ���l�q�͂Ȃ��B
�����āA��̉��������ɕ�������B
�ŁA����Ȃ�c�c

�I�_����A��̉���������ցA�����O��ĉ����čs���B
���ݐՂ̂悤�Ȃ��̂͂Ȃ����A�ǂ���Ɋɂ₩���B
��i����ƃX�X�L�̌����ς�����A�x�k�n���ۂ��B
������˂����Ă�����x�X�̎Ζʂ�����ƁA�ڂ̑O�����ς��ɐ^�������͌����L�����Ă����B

17�F09�@�s���ݒn�t
�j����̗��ꂾ�B
�_���ʂ�A���������ɂ����n��R���N���[�g��������A�V���[�g�J�b�g�͍�����听���ł���I
����ŃS�[���ł���w�܂ŁA�s����̕s���v�f�͂Ȃ��Ȃ����B
���Ƃ�3.2km�A���m�ܑ̕��H����������B�c�莞�Ԃ́c�c�c�c��1���Ԕ��B
�c�c�悵�I�@�@��邩�I

17�F13
�ӂ킟�[�[�[�[�[���[�[�[�c�c�c�c
���A�������Ɠ��R�Ɋ��������A���̒��ɉ����u�E�l�E�l�v�Ɠ����Ԃ��~�~�Y�݂����ȏ����Ȑ���������R���邱�Ƃ��B�Ԓ����H�I
������オ��A�����b�N�̒��ɔ鑠���̔鑠�ł������Y��ȃY�{���ƃp���c�ƃV���c�ɒ��ւ����B���ՂŔj��ĐK�}���_�V���O�ƂȂ��Ă����Y�{���́A�O�`���b�ƃ����b�N�ɉB�����B
17�F24�@�o���I

17�F34�@�s���ݒn�t
�����V���͂킴�킴�R����I�đf�ʂ肵�����A��Ð��X������̏h�꒬�ŁA���܂͍���121�������蔲���Ă��鉡��W���ցB12���ԂԂ�ɐl�Ƃ������B���₻����肩�A���l�������B�Ăт����āA�u���̖ؓ����z���ĉ������痈�܂����I�v���Ď����������Փ��ɋ��ꂽ���A���肬��ʼn䖝�����B

�W�����̋��������o�R���āA����121���֏o��B���̎��_�ʼnw�܂Ŏc��2km�B�߂��悤�ʼn����B����ȗǂ��������]�ԂŐi�߂Ȃ��̂́A���ɂƂ��Ă͍���ɋ߂��B�����ܑ��H�̂����ŁA�����ɗ����̍����U�N�U�N�h����悤�Ȍ��������݂��o�ė����B�����܂ō��������ɂ̂́A�T�������߂āB�R�̒��ł����Ȃ�����A��������ȁB���̂܂ܒɂ܂�������Ƃǂ��Ȃ邾�낤���B
�Ƃɂ�������̍s���́A�̗͓I�ɂ��A���ԓI�ɂ��A���̎�������ł�����E�������悤���B
�O�����߂̍Ō�̓��́A���𑪂邽�߂ɂ������̂��B

18�F04�@�s���ݒn�t
�j�������w�A�����B
�o������13���Ԃ�4���B
���x�����A�S�[�����B
��͐Q�Ă��Ă��Ƃɒ����B�i�Ǝv������A��芷����4����������j
���Ԃ̎����܂ōŌ�ɗ]�������Ԃ�33���B
����܂Ŕ����t���́u�w�m�[�g�v���߂����ĉ߂������B
�����āA�Ō�̃y�[�W�Ɏ�����������BURL���Y���āA���̖����Ȑ�`�����B�N�����Ă��ꂽ���ȁH

�O���ʗf���߂̍�����Ō�̓��A�U�������B
����18(1885)�N�B
�����V���̉X�����J�ʎ��T�̗��N�ł���A�Ȗ،���p�������̗\�Z���s���~�����A������̔p�~�̔N�B
�n���s�����ł���Ȗ،��߂���A�����̓y�؋ǒ��i����̍��y��ʏȂɂ����鎖���������j�ƂȂ����O���́A�S���̍����ɗ��j�㏉�߂āg�H���ԍ��h��^����u�����\�v���z�Ƃ������v���s�������A�����V���������ɂ͂��Ă��Ȃ��B
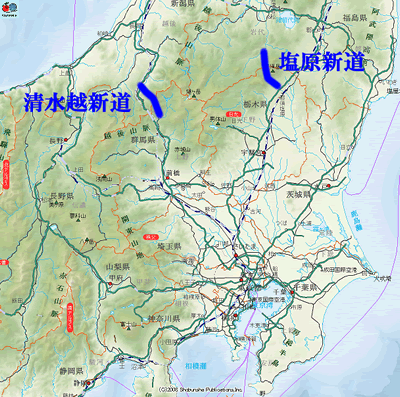
���N9���A�ނ͖k����{�\�v�e����������Q�c�R�p�L����ƂƂ��ɁA�ނ��ԍ���U��������u�����v�̊J�ʎ��T�ɎQ���B
����́A�����ƐV���`���ŒZ�����Ō��ԁA�����B��̓����Ȓ��c�y�؍H���ɂ��A�����z�V���ł���B
�C��1448m�Ƃ��������̍����ō��n�_���ђʂ���Y��ȎR�x���H�̌v��ɁA�ނ͊֗^���Ă��Ȃ��B
�������A���̔��Ď҂ł����v�ۗ��ʂ́A�O�����ł��Ă��o�p�������M�̈�l�ŁA����7(1874)�N�ɔނ���c���߂֑���o���A���̗��r�ɓ��k�̊J����a�����l�ł�����B
1�N��O�サ�ĊJ�ʂ��������V���Ɛ����z�V���B
�����̓��ɂ́A�����m���Ɠ��{�C�������Ԑҗ��R���z���̔n�ԓ��H�Ƃ������m�ȋ��ʓ_������B
�����āA�ǂ�����܂Ƃ��ɋ@�\�ł����A�����Z���Ԃōr�p�ɋA�����Ƃ������ʓ_���c�c�B
�����ɂ́u���R�̈�v�v���z�����A�Z�p�I���E���������悤�Ɏv���ĂȂ�Ȃ��B
�����͂����Ƃ����݂͏o�����Ƃ��Ă��A�Ƃ��Ă��u�����s�\�ȓ��H�v�������̂ł͂Ȃ����낤���B
�킪���̐[���������җ��R�n�ɒʔN���p�ł�����肵����ʘH����J�����̂́A�����̌㔼�ȍ~�A�S����Ƃ����g���l���Z�p�̐i�W��҂��˂Ȃ�Ȃ������B
�������ɁA���̂Ƃ��g�b�v�ɂ����O�����v�ۂ��A�S���ɂ��Ă̐挩�̖��������Ă�����A�����̓��͑����Ȃ������̂����m��Ȃ��B�������{�I�ɂ͐��x�̕s���ł������Ǝv���B
���������邻�ꂼ��̒n��̓�����[�������������̓y�؋Z�p�҂��A�v��̒i�K����[���֗^���Ȃ�����A�����s�\�ȓ��H�𒆎~���锻�f�͏o���Ȃ������Ǝv���B���������̉Ǔ��I�g�b�v�_�E���^�s���V�X�e���̖��n�����A�����ُ̈�ɑs��ȋZ�p�I���s�ƌ��Ȃ��铹�H���A�e�n�ɒa���������̂��Ǝ��͎v���B
�\�\���s����w�Ԃ��Ƃ̕����A��������w�Ԃ��Ƃ��������\�\
����̓��{�̐��E�Ɍւ�ׂ���ʖԂ��A���������Č����Ă����������肪�A���ɂ͂�������B