置き去りにしたヒジ曲リ沢の隧道を求め逆走する

14:06 《現在地》
約1時間ぶりに軌道跡の探索を再開した。
今いるのは、前回撤退したヒジ曲リ沢の滝がある地点から推定250mほど軌道跡を前進した地点であり、この250mの間には最低でも1本の隧道が存在しているはずだ。
その未発見である西口(上流側坑口)を目指して、探索の流れからは逆走する形で一旦下流方向へ向かう。
長く見積もったとしても、200mも進めば西口の擬定地に差し掛かるはず。
なお、この探索当日の14:00から「ポケモンGO」の「コミュニティデイ」というイベントがスタートし、17:00まで「チルット」が大量発生するうえ、通常は出現率が極めて低い「色違い」の個体も高確率で出現する状態になっていた。熱心なポケGOのトレーナーである私は、「コミュデイ」に参加し是非とも「イロチ」の「チルット」をゲットしたかったが、あいにくこの場所には電波がなく、参加できる状況ではなかった。イベント終了時刻までには是非電波がある場所へ辿り着かねば!

14:09
再会した軌道跡の状況は、悪劣であった。
撤退したヒジ曲リ沢の末端附近と感じが似ているのである。
全体的に路盤は著しく風化し、斜面化が進んでいたし、石垣や枕木など、これまで所々で見ることができた遺構や遺物も皆無であった。
ケモノ道を含む踏み跡も感じられなかった。
しかも、軌道跡は白砂川に落ち込む険しい岩崖の縁をなぞるように付いており、所々に死のボッシュートを誘う危険なスリットが開いていた。
うっかり木の根に蹴躓いただけで命を落としかねない、そんな緊迫感が疲れた身体に堪えたし、降り続く雨は斜面を歩き続ける気力を萎えさせた。

14:17
遺構と呼べるものは何もないが、地形の起伏から読み取れる微かな痕跡を頼りに進んで……
というよりも、この軌道跡に由来すると考えられる僅かな緩斜面の他は上も下も通りようがない感じだ。
この直前には面倒な位置に大きな倒木があって、時間を食わされたが、それでもこの軌道跡のラインから外れることは出来ない。ここだけが頼りだ。
そういう状況だから、ずっと不安である。
もしこのラインが スパッ と切れるようなことになったら、迂回して先へ進めるイメージが湧かないのだ。
ついさっき白砂川から無理矢理上ろうとして一度敗退を経験しているから、これはもう漠然とではない確固たる不安だった。

14:19
何もないのでテンションの上げようもないが、探索者としての貪欲さと、あとは私が探索中に課している“決め事”に則って、黙って進んでいる。
ちなみにこの“決め事”とは、「探索中は心を殺せ、つまらなさに克て」、みたいな内容だ(笑)。
好きでやっていることでなければ、こんな意志を蔑ろにするような決め事は秒で破棄したいが、廃道では出来るだけ、つまらないことを引き返す理由にはしない。
探して何も見つからないのは、探すことを止めるよりは遙かに上等な成果である。
心中は鬱々としながらも、想定の目的地へ確実ににじり寄っていた。

14:19
………………うん。
……残念だけど、おそらくここが……
このなんの面白みもない土斜面が、
待望していた「隧道6(仮称)」の西口擬定地と思う。
最大の根拠は、地形だ。
この前方に見える崖のように急な尾根の向こうは、もうヒジ曲リ沢である。
そして、ここまで仄かに残っていた軌道跡に由来する緩斜面が、この尾根を前に完全になくなっている。
尾根を回り込む部分に切り通しなども見えず、やはり想定通り隧道がなければならない地形だった。
残念ながら、坑口は現存していなかった。
はっきり隧道跡と分かるような地形でないことも、残念だった。
とはいえ、可能性としてはここが一番大きいというような弱性の擬定地ではなく、ほぼ確信レベルでここしかないというのが私の実感。
残念ではあるが、辿り着けたから、納得感はあった。
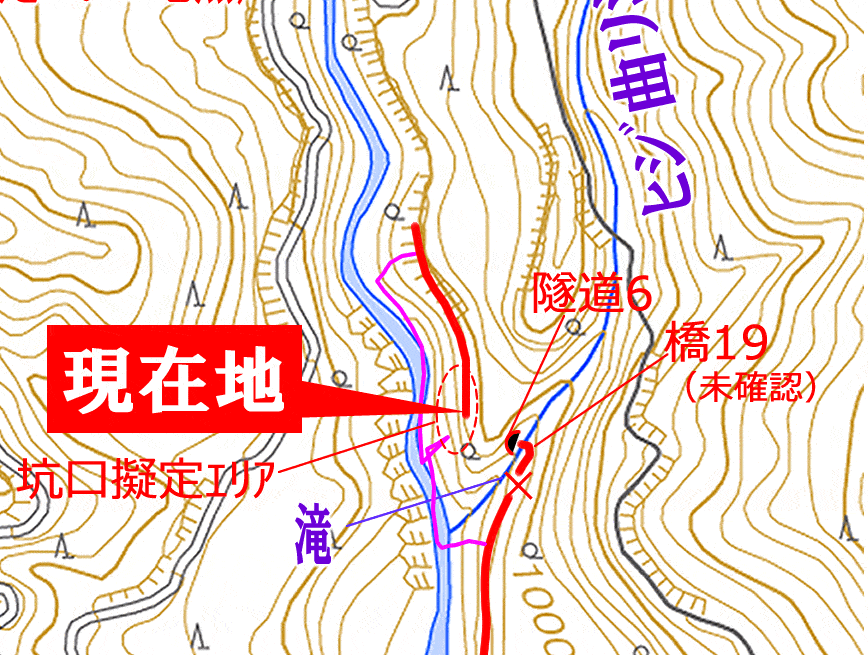
GPSによってすぐに現在地が明らかになった。
調べるべき地点を全うしていることが判然として安堵した。
この位置で軌道跡が途絶えていることと、先に見つけている坑口の存在を合わせれば、「隧道6」の現状は、片開口の閉塞状態と断定できる。
(なお、この坑口埋没現場付近は、下手に歩き回って滑り落ちたら目も当てられない悪地形なので、雨が降り続けていることもあり、擬定地の斜面内を詳細に見て回る気にはなれなかった。それでも、開口していないことだけは確かだろう。)
さて、次はどうしようか。
来たところを引き返すか、それともここから尾根を乗り越えて、ヒジ曲リ沢に残してしまった隧道の東口を目指すか。
もちろん、後者の方が成果を期待できる積極的な選択肢であり、後顧の憂いを断つためにも出来るだけ選びたいところだったが、いかんせん、地形の条件が目に見えて悪い……。
ここから尾根を越すか、回り込むかするのは、どちらも簡単ではないだろう。それが簡単ならわざわざ隧道を掘ったりはしない。
地形図だとそれほど急な尾根に見えないが、実際はとても厳しい尾根だった。
それでも尾根を越せる可能性を考えるなら、この全天球画像に“赤矢印”を付けた辺りまで登ってみて、上部がより緩やかであることに期待するしかないと思う。
さあ……、どうする。

14:24
約5分後、私は尾根の上にいた。
地形図でも緩やかそうに描かれている尾根上は、両側の斜面の険しさとは対照的に緩やかだった。
が、本当に純粋な自然地形なのかと疑いを覚える歪な緩やかさであった。
この写真でも分かると思うが、尾根と交わる方向に細長く伸びる完全な平坦地があった。
まるで幅の広い林道跡のようであり、一瞬そんな期待を持ったのであるが、実際は完全に孤立した平場で、前後のどこにも道は通じていなかった。
だから自然地形なのかもしれないし、あるいはまだ知られていない索道がかつてあって、そのために尾根を削平した名残……なんて可能性もあると思った。
自然か人工かの切り分けすら出来なかった正体不明の“擬平場”だが、これがある尾根の下を隧道で潜る軌道と直接通じる存在ではなかったと思う。明確な落差がある。

14:26
謎の平場のおかげで、尾根の上をヒジ曲リ沢に臨む位置まで移動するのは容易だった。
ただそれはあくまで尾根の上にいる限りである。
ヒジ曲リ沢に臨む端に立ち、谷底を覗き込んだのが、この写真だ。
ぶっちゃけ、何かを決めるには、決め手を欠ける写真だ。
谷底まで見通せないし、地形について確信を持てる何かも見えない。
はっきりしているのは、相当の急斜面であるということだけ。
そして、写真からは伝わらない私が感じている感覚もあり、それは雨の音と少し遠い滝の音、あとはざわざわする風の肌寒さだった。
下の状況がはっきり分からないのに降りて行って大丈夫か。
これが究極の選択となった。
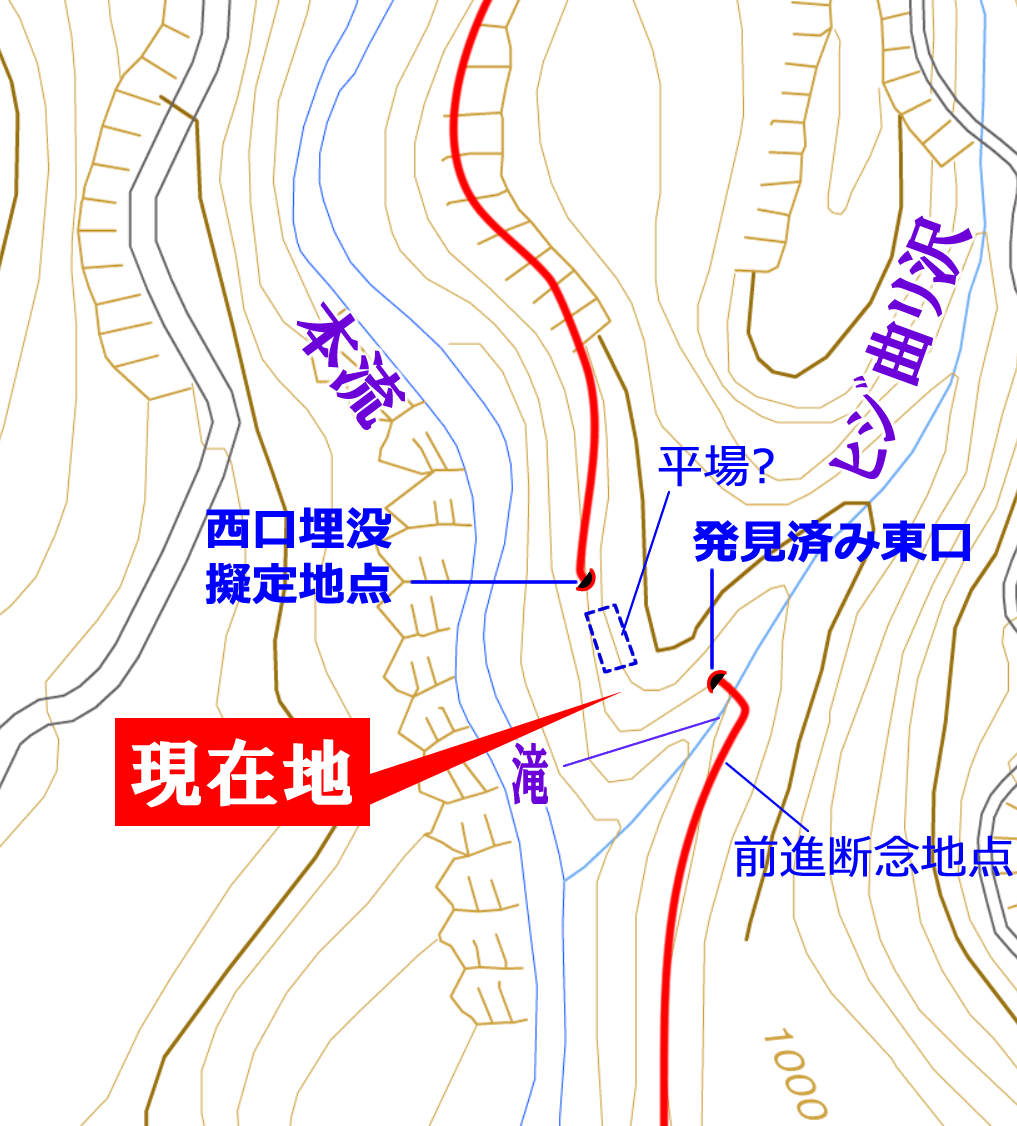
唐突だが、拡大した地形図に探索で得た諸々の情報を書き加えたものをみて欲しい。
私を既に1時間半にわたって束縛し続けているヒジ曲リ沢の軌道跡は、この図のような経路であったと思われる。
零から身体で情報を集めて、ここまで識った。
もはやこの界隈の残された“未知”は、開口しているように見えた隧道の東口と、閉塞が確定しているその内部である。
それがこの足元の直下から近いところにあるのは確実で、辿り着きたいと誰よりも願っている。
チェンジ後の画像は、この日に記録されたGPSのログ(赤線)である。
谷底であることや、機器の性能の限界から、多少のブレはあるが、1時間半分の私の頑張りが全て記録されている。
登ろうとして果たせなかった失敗の軌跡まで見える。
GPSのログが、私の選択の答えである。
私は、この尾根から先へは進まなかった。
理由の第一は雨だ。本降りとなって止む気配のない雨が、これ以上リスクを取る選択を選ばせなかった。
第二は地形だ。私がいる地点は、厳密には目指したい隧道東口の直上ではなく、ズレている。ここから降りると、例の滝の上に出てしまう可能性が高かった。滝の周囲が全方位的に崖であることを既に見ているので、ここから降りていくのはリスクが大きいと判断した。
が、もしも雨でなければ、ある程度は試しに降りて判断したと思うので、やはり第一の理由が一番大きい。
(東口への接近は本稿執筆時点も果たせていないが、上流の林道から沢沿いを降りられないかを試したいと思っている。実行したら追記します)
次回は、間近となったゴールを目指します。
万沢林道と軌道跡の知られざる接続地点

14:39 《現在地》
「隧道6」の尾根を引き返して12分後、前章冒頭の地点(迂回から軌道跡へと復帰した地点)まで無事戻り、そのまま今度は上流方向へ軌道跡を進み始めた。
そして、新たな区間を約1分進んだところが、この写真だ。
緩やかなカーブで回り込む尾根の突端になっていて、上流を見渡せたが、V字に切れ込んだ谷の両岸が淡い新緑に彩られている景色があるだけで、特に人工物も変わった地形も見えなかった。そもそも、雨のせいで煙っており、あまり遠くまでは見えなかった。
今回の探索のゴールとして早朝に自転車をデポした白砂川大橋は、この500mほど上流にあり、あと200〜300mも歩けば橋に通じる林道と遭遇するはずだった。
もう10分で探索開始から10時間が経過するが、ようやくゴールは目前だ。
ところで、チェンジ後の“赤矢印”の位置に注目。
なんか、見えるでしょ?

“赤矢印”の位置にあったのは、おそらく井桁状に並べられた枕木の残骸だった。
林鉄が廃止されると、転用可能なレールの撤去が最優先で行われたが、枕木も撤去されることがあった。
撤去した枕木は邪魔にならないところに井桁に組んで放置されることがしばしばあったようで、軌道跡にこのような枕木の山の跡をよく見る。
ただ、この辺りは廃止が昭和24(1949)年と早かったせいで、枕木はほとんど土に還ってしまって、井桁としての高さは残っていなかった。
そしてさらに発見が続く。
この写真は来た方向を振り返っているが、奥の“黄矢印”の位置に、通った時に気付かなかったものを見つけた。

危うく素通りされかけた、小さな小さな橋の跡。探索中に見つけた橋の順番的に、「橋20」である。
この橋は路盤の一部が切れ落ちている部分を渡っており、小さなコンクリート&石組みの橋台が残されていた。
一見、廃線後の小欠壊地のように見えて、現役当時からあった地形ということが分かる。
おそらくだが、この他にも似たような小規模橋は沢山あったはずだ。
私が番号を振った場所は、明確に橋の痕跡を見つけたり、そうでなくても橋の存在が明らかに想定できる場所だけである。
久々に小さいながらも明確な林鉄の遺物と遺構を発見し、「隧道6」の撤退で大きく消沈した気分を少しだけ回復させた私が前進を再開すると、またすぐに――

まるで「橋20」は尖兵であったとでも言うように、同じシチュエーションだが、遙かに規模の大きな橋跡が出現した!!
「橋21」である!

14:42
やはり両岸に橋台としての痕跡があるが、ここから前面が見えている対岸のそれは、垂直に切り立った自然の岩盤だった。
自然岩盤の突端部分に丸太を敷き、そこに橋桁を乗せていたようである。
ここからだと全貌が見えない此岸も、おそらく同じ様な自然岩盤を利用した“疑似橋台”である。
地形でも岩でも使えるものはなんでも使って少しでも安く早く線路を奥地へ延ばす。
そんな設計の理念が強く込められていそうな橋跡だった。
本林鉄の開設時期は昭和13(1938)年から16年までの4年間で、我が国が戦争状態にあった時期に建設されている。戦争遂行の資源となる木材の増産に向けた緊急の開設事業だった可能性は高い。
(だからこそ、戦後間もない昭和24(1949)年に、採算性が低い奥地の区間を一挙に廃止したのではないだろうか)

「橋21」の跡地は、間違いなく正面突破の出来ない地形だったが、ここは高巻きによって越えた。
路盤は険しい崖の中腹を横断しているが、そこから急斜面を頑張って20mくらい登ると、そこには思いのほか平坦な笹原が広がっていた。
あとはこの平坦地を使ってトラバースしてから、再び路盤へ降りることが出来た。
写真は、高巻き中に撮影した風景だ。
「橋21」が、クレバスのように狭く切り立った岩の隙間を跨ぐ橋であったことがよく分かる眺めだ。
短い割に橋の高さは物凄い。たぶん20mくらいあっただろう。

14:47
「橋21」の対岸の路盤から、5分前にいた場所を振り返っている。
やはり最初に辿り着いた側にも橋台らしい橋台はなく、切り立った岩盤の突端に、枕木より太い丸太を横に置いただけの“疑似橋台”だった。
あの丸太の上に木桁を乗せていたのだろう。
あくまでも仕事のための道として、一般の通行を想定しなかった林鉄は、安全性に関する設計の取り決めも公道などとは大きく異なっており、普通人なら足が竦んで通れないような橋が当然として存在していた。

14:50
地形が山側から緩み始め、路盤も緊張の絶えない崖の縁から漸く解放されていく。
この地形の辺から、林道の接近を察したが、まだ気配は感じられない。
というか、本当に林道が間近にあるのか不安になるくらい、未だ全然踏み跡がない。
上流側から軌道跡へ踏み込んだ人の痕跡が、少しくらいはあっても良いと思うが、全然だ。
釣り人ならさっさと川へ入渓するだろうし、林業関係者も入り込んでいないとしたら、一度も地形図に描かれたことがないこの廃線跡は、我々のような林鉄ファンでさえいままで訪れていなかったのかもしれない。そんな愉快な想像を楽しんだ。

14:54
見える範囲から谷が完全に消え、緩やかに傾斜したカラマツ林に包まれた。
人工林だと思うが、それでもまだ踏み跡やピンクテープは現われない。
路盤の痕跡は仄かな地形の凹凸として残されているが、カラマツはそれを無視して植えられていた。
廃止が早い林鉄であることは知っていたが、林鉄の廃止後に、歩道や牛馬道として継続的に使われるようなこともなかったのかもしれない。
感覚的な話になるが、道としての影の薄さを感じた。

14:55
キタッ! 林道だっ!!
15mくらい下に、切り返しのヘアピンカーブを描く舗装路が見えた!
出発からちょうど10時間というタイミングで、初めて軌道跡から他の道路を間近に見た。
そして間もなく軌道跡は、この万沢林道とぶつかる。
その地点を以て、今日の白砂川林鉄探索は終了である。

単調な雑木林を水平に進んでいく軌道跡に対し、眼下に現われた林道は、同じ方向へ進みつつ、強い勾配でどんどん迫ってきている。間もなく接続するに違いない。
いったいどんな接続をするのか。それを見るのが今日の最後の楽しみだろう。
結局は2時間以上も降り続いている雨により、森は底までぐしょ濡れだ、
私も気付けば全身が汗と雫でぐっしょりと濡れていた。
濡れと疲れのダブルパンチで重い足に鞭打って、最後の軌道跡を歩ききった。

15:02 《現在地》
林道へ脱出!
この道路は国道405号と国道353号を山越えに結ぶ万沢林道という国有林林道で、私は通り抜けたことはないが、ネットの口コミだと通り抜けが出来そうな感じである。
早朝に自転車をデポした白砂川大橋から約400m東へ進んだ位置が、軌道跡と林道の接点だった。
現地は、ぱっと見で分かるような“分岐”ではなく、軌道跡は林道の法面で無造作に切り取られていた。
探そうとしなければ、ここに軌道跡の存在は見いだせないだろう。
もちろん目印のピンクテープなどもない。
そして、ここは白砂川林鉄としては起点から推定7.1kmの位置である。
今日歩いたのは起点から推定0.8km地点からだったから、軌道跡を6.3km確かめたことになる。
また、ここの海抜は約1010mあり、歩き出した地点が約900mであったから、6.3kmでわずか110mしか標高を上げていないことになる(平均勾配1.6%)。
これは林鉄の中でもかなり勾配が緩い部類に入ると思うが、意図的に勾配を減らそうとしたわけではなく、白砂川の河川勾配に準じた結果だろう。
一見して険しい山峡が、必ずしも急流というわけではないのだった。だがその分、注ぐ支流に落差の負担を強いて、多くの滝を作らせていたことが、軌道跡の難しさに繋がっていたと思う。支流の沢を越える部分が悉く難所であったから。
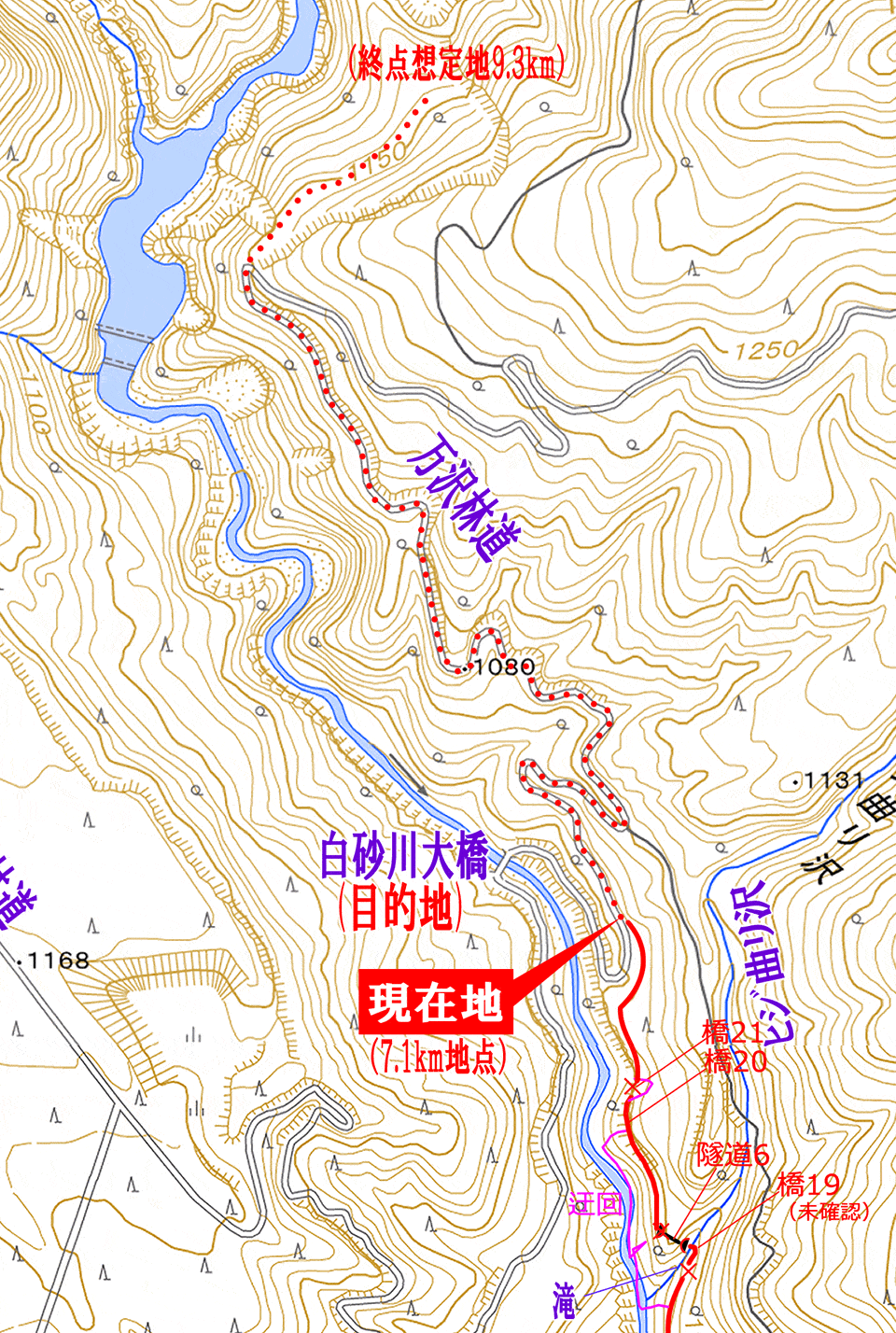
今日は十分よく歩いたが、まだ白砂川林鉄の終点は遠い。
冒頭で資料を示して述べた通り、この路線の全長は9337mと記録されている。
したがって、現在地が7.1kmであるとすれば、さらに2km以上は続いていたことになる。
では、残りの部分はどこにあったのか。
これはまだ分かっていない。
昭和16年に完成し、同24年に早々と廃止された最も短命な2412mの区間がこれに相当すると思われるが、万沢林道の元になったのか、あるいは別のルートが存在したのか。
この問題については、本編ラストの机上調査にて、新たに入手している資料も用いながら検討してみたい。

というわけで、ここは林鉄の終点ではないが、今回の探索は予定通り、ここまでとする。
人知れず軌道跡を呑み込んでいた林道の素知らぬ素振りを目に焼き付けてから、まだ見ぬ終点への思いを断ち切って、下山を開始した。
辿り着けなかった「隧道6」の存在と共に、この林鉄はまた私を誘うつもりらしい。

15:13 《現在地》
林道を400m歩いて白砂川大橋へ。
今朝4時過ぎに真っ暗闇のなかでデポした自転車が律儀に待っていた。ただ、雨よけをしなかったサドルがぐっちょり水を吸ってしまい、この後数日にわたって、乗る度に尻が濡れる後遺症に悩まされることになった。
チェンジ後の画像は、橋の上から眺めた白砂川の下流方向。
今朝は闇の中に姿が見えず、轟々たる瀬の音に不安ばかりを募らせていたが、実際に見てきたいまなら言える。
この自然の川は、人工物のなれの果てとしての軌道跡よりも、よほど優しい存在だったと。探索のピンチを何度もこの川の歩きやすさに助けられた。
途中で出会った釣り人は、もう無事戻ってきたのだろう。近くに車などが見当らなかった。
冷たい自転車に跨がったら、今度こそ“下山”である。
ただし、この“下山”は実際のところ、万沢林道で350mという高度差を登ってから、国道405号で450mを下るという、むしろ峠越えに近い高度推移をたどる必要がある、脚力的に大きな仕事を要するものだった。
したがって、今朝の出発地点へ戻るために、さらに2時間を費やした。
最後まで雨は止まずに私を萎えさせたが、探していた色違いのチルットは15:26に【1匹目】 を確保。さらにイベント終了直前の16:54には【2匹目】
を確保。さらにイベント終了直前の16:54には【2匹目】 もゲットし、探索だけでなくポケ活にも滑り込みで成功した1日となった。
もゲットし、探索だけでなくポケ活にも滑り込みで成功した1日となった。
| 当サイトは、皆様からの情報提供、資料提供をお待ちしております。 →情報・資料提供窓口 | |
|
このレポートの最終回ないし最新の回の「この位置」に、レポートへのご感想など自由にコメントを入力していただける欄と、いただいたコメントの紹介ページを用意しております。あなたの評価、感想、体験談など、ぜひお寄せください。 【トップページに戻る】 |
|